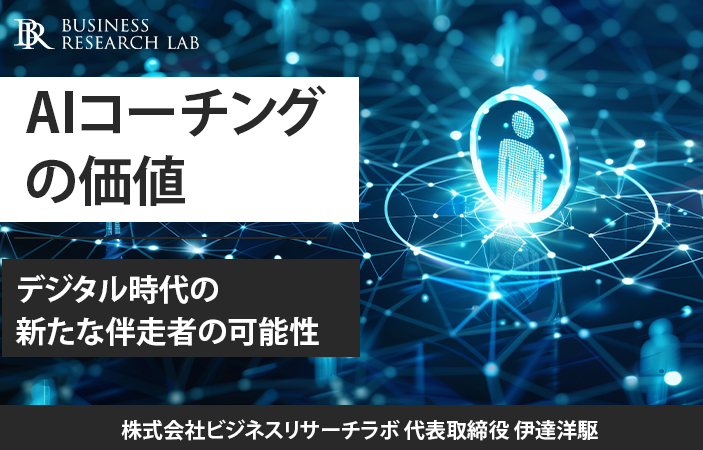2025年8月6日
AIコーチングの価値:デジタル時代の新たな伴走者の可能性
急速に進化するテクノロジーの波が私たちの生活の様々な側面に押し寄せる中、AIを活用したコーチングが新たな可能性として広がりを見せています。従来のコーチングと言えば、専門的なトレーニングを受けた人間のコーチが対面やオンラインで一対一の関係を築きながら行うものでした。しかし、デジタル技術の発展に伴い、AIが対話を通じて目標設定や振り返り、行動計画の立案をサポートする「AIコーチング」が登場しています。
AIコーチングの魅力は、時間や場所の制約を受けず、必要なときにいつでもアクセスできる手軽さにあるかもしれません。人間のコーチングと比較して費用が抑えられる場合もあり、これまでコーチングを受ける機会がなかった多くの人々に門戸を開く可能性もあります。
しかし、AIによるコーチングは本当に効果があるのでしょうか。AIは人間のコーチが持つ共感性や直感、臨機応変な対応力を備えているのでしょうか。それとも、AIコーチングには人間のコーチングにはない独自の価値があるのでしょうか。
本コラムでは、AIコーチングの効果に関する研究知見を紹介します。AIコーチングが初心者レベルのコーチングとどのように比較されるのか、人間のコーチングとの効果の違い、身体活動の促進における有効性、そして職場における新入社員の適応支援など、いくつかの観点からAIコーチングの可能性と課題を探ります。
初心者並みの効果を持つ
AIコーチングとは、人間のコーチの役割を機械が代替し、目標設定や課題探索、自己内省、行動促進を対話形式で支援するものです。このAIコーチングが実際にどのような効果をもたらすのかを検証する動きが広がっています。
2025年に発表された研究では、コーチング分野におけるAIの応用に関する体系的な文献調査が行われました[1]。この研究では1990年から2024年3月までに発表された英語の査読付き論文から、コーチングとAIに関連する16本の研究が選ばれました。
調査対象となった研究では、学生やビジネスパーソン、がん患者など、多様な参加者に対してAIコーチングが実施されていました。コーチングの形態もテキストベース、音声ベース、対話ベースなど様々でした。また、理論的な基盤としては認知行動療法や目標理論、解決志向コーチングなど、多岐にわたるアプローチが採用されていました。
この調査から見えてきたのは、AIコーチの有用性です。AIコーチは目標達成、自己開示の促進、自己責任感の向上に役立つことが確認されました。特にAIチャットボットは心理的安全性を高める効果があることも分かりました。人は時に、他者からの評価を気にせず、自分の弱みや悩みを打ち明けられる相手を求めることがあります。匿名性が保たれたAIチャットボットは、そのような安全な空間を提供できる可能性があります。
もちろん、AIコーチにも限界はあります。例えば、ストレス軽減においては人間のコーチの方が優れる場合もあることが示されています。これは、人間のコーチがもつ共感性や感情の機微を読み取る能力が、ストレス軽減においては意味を持つためかもしれません。
この研究では、AIコーチングの具体的な効果についても調査されました。特定の目的に特化したAIコーチング、例えば目標達成や健康行動促進などに焦点を当てたAIコーチングは、何も介入を行わない対照群と比べても有意な効果があることが確認されました。
そして興味深いことに、この調査ではAIコーチが人間の初心者レベルのコーチと同等の効果を持つ可能性があることも示されました。初心者のコーチは基本的なコーチング技術を用いることが多く、このような基本的なコーチングプロセスであればAIでも再現できるかもしれないということなのでしょう。
しかし、AIコーチングには倫理的な課題も存在します。例えば、プライバシーの問題や、AIのアルゴリズムに含まれる可能性のある偏見やバイアス、そして倫理的な判断能力の不足などが指摘されています。AIが収集する個人情報の取り扱いや、AIが提供するアドバイスの倫理的な妥当性などについては、今後さらなる検討が必要です。
また、AIコーチングを実践するためには、技術の受容性が非常に大事であることも指摘されています。これは従来のコーチングにおける「作業同盟」(コーチとクライアントの間の信頼関係や協力関係)とは異なる変数であり、AIコーチングの成功に影響を与える可能性があります。ユーザーがAIコーチをどれだけ信頼し、その助言を受け入れるかが、AIコーチングの効果を左右するということです。
人間と同程度の効果がある
AIコーチングが初心者レベルのコーチングと同等の効果を持つ可能性があることが分かりましたが、実際に人間のコーチングとAIコーチングを直接比較した場合、どのような結果が得られるのでしょうか。
ある研究では、AIによるコーチングと人間によるコーチングの効果を、目標達成という観点から直接比較しました[2]。この研究は、AIがコーチングにおいて実際にどの程度効果的であるかを検証した数少ない研究の一つです。
研究者たちは「AIによるコーチングは、人間のコーチングと比較して、クライアントの目標達成にどの程度有効なのか」という問いを設定し、これを検証するために2つの並行したランダム化比較試験(RCT)を実施しました。
第1の研究では、英国のビジネススクールの学生210名を対象に、10ヶ月間にわたって毎月1回(計6回)、人間のコーチによる1時間のオンラインコーチングセッションを行いました。コーチは全員、専門的なトレーニングを受けた経験豊富な人材でした。
第2の研究では、同じビジネススクールの学生268名を対象に、10ヶ月間、AIチャットボット「Vici(ヴィッキー)」を使用したコーチングを実施しました。このViciは目標理論に基づいて開発され、Telegramというチャットアプリ上でテキストベースの対話を行いました。Viciは具体的な目標設定、進捗確認、行動計画支援など、基本的なコーチングプロセスを実施しました。
それぞれの研究には、コーチングを受けない対照群も設定されました。目標達成の評価は参加者自身が行い、「目標達成度」(0〜100%)と「目標の難易度」(7段階の評価)を組み合わせて、各時点の「総合目標達成スコア」を算出しました。
研究の結果、人間のコーチ群もAIコーチ群も、コーチングを受けなかった対照群よりも有意に高い目標達成スコアを示しました。これはコーチングが目標達成に有効であることを裏付けるものです。
驚くべきは、10ヶ月後には、AIコーチは人間のコーチとほぼ同等の効果を示したことです。さらに、AIコーチを頻繁に利用した参加者ほど、目標達成度が高まることも分かりました。
なぜAIコーチと人間のコーチがほぼ同等の効果を示したのでしょうか。研究者たちはその理由として、AIコーチが「目標理論」を厳密に実施したことを挙げています。AIコーチは常に目標設定と振り返りを正確に行い、一貫性を保っていました。この厳密さが、人間のコーチが持つ柔軟性や共感性とは異なる形で、効果的なコーチングを提供したのかもしれません。
また、AIコーチは常時利用可能であったことも効果を高めた要因と考えられます。参加者は自分にとって最も適切なタイミングでAIコーチにアクセスすることができました。人間のコーチングでは予約した時間に合わせる必要がありますが、AIコーチは時間の制約がなく、必要なときにいつでも利用できるという利点があります。
このように、AIコーチと人間のコーチはそれぞれ異なる強みを持ちながらも、目標達成という観点では同程度の効果を発揮することが分かりました。
AIコーチングは運動意欲を高める
AIコーチングは目標達成において人間のコーチングと同等の効果を持ちうることが確認しましたが、具体的な健康行動の促進においてはどのような効果があるのでしょうか。特に、健康格差が存在する社会的マイノリティにとって、AIコーチングはどのような価値を提供できるのでしょうか。
スペイン語と英語を話す低所得層の女性を対象に、運動促進を目的とした対話型(チャットボット)コーチングのプロトタイプを開発し、その有用性や受容性を調査した研究があります[3]。
低所得者層、女性、特にヒスパニック系やラテン系などの少数民族は、十分な身体活動を行えていない傾向があります。また、既存の健康促進用チャットボットの多くは英語版のみであり、スペイン語話者や社会的に不利な状況にある女性を考慮した開発はあまり行われていませんでした。
研究者たちは、低所得の英語・スペイン語話者の女性がチャットボットを健康増進に活用したいと考えるのか、彼女たちの健康上の優先事項やニーズは何か、そしてチャットボットをどのようにデザインすれば彼女たちのニーズを満たせるのかを明らかにしようとしました。
研究はカリフォルニア州とテネシー州の低所得女性18名(スペイン語話者10名、英語話者8名)を対象に行われました。参加者の年齢は27〜41歳で、大半はヒスパニック系でした。技術的には、SMSを利用したインターフェースにIBM Watson Assistantというシステムを組み合わせたチャットボットが開発されました。チャットボットの対話設計には、行動活性化、動機づけ面接法、受容・コミットメント療法、解決志向短期療法といった理論的基盤が用いられ、150以上の会話要素、1,000万通り以上の対話経路を含む複雑な構造が作られました。
調査は4つのフェーズで行われました。初めに健康状態や技術リテラシー、チャットボットに対する認識を評価するインタビュー、続いて人間がチャットボットを模倣して応答する「Wizard of Oz法」によるテスト、そして自動応答チャットボットのテスト、最後にスペイン語による共創ワークショップです。
研究の結果、英語話者とスペイン語話者の間には、テクノロジーに対する親和性に違いがあることが分かりました。英語話者はスマホアプリに馴染みがあり、健康管理アプリをよく活用していましたが、スペイン語話者は健康情報を主にYouTubeやFacebookなどのSNSから得ており、健康管理アプリはあまり使っていませんでした。
プライバシーとセキュリティへの懸念も明らかになりました。英語話者は個人情報、特に位置情報の共有に強い抵抗感を示しました。一方、スペイン語話者はチャットボット技術への理解が不足しており、情報の扱いに対する不安が大きい傾向がありました。
チャットボットの使いやすさと満足度については、多くの参加者がチャットボットの応答スピードと簡便さを評価していました。ただし、スペイン語話者の中には文字入力が難しい参加者もおり、音声入力を希望する声もありました。
人間らしさに関しては、英語話者は「Wizard of Oz法」による人間の応答の方が会話的で人間らしく感じ、自動応答チャットボットの人間らしさを低く評価する傾向がありました。一方で興味深いことに、スペイン語話者は自動応答チャットボットにも人間的なつながりや支援を感じる人が多く見られました。
継続的な利用意向については、英語話者はチャットボットの反復的な応答に飽きる懸念を示し、頻繁に新しいコンテンツが追加される必要があると指摘しました。スペイン語話者は家族と一緒に利用したいという希望が強く、家族の健康も一緒に考えたいという文化的背景が垣間見えました。
研究者たちは、機械的なチャットボットであっても、参加者は感情的な支援を受けられると感じることができたという点を考察しています。また、言語や文化、デジタルリテラシーの違いを考慮した設計が必要であることも指摘しています。シンプルで分かりやすいテキストを用い、必要に応じて音声入力など多様なインターフェースを提供することが望ましいとしています。
新卒の職場適応を促進する
AIコーチングの効果は健康行動の促進だけにとどまりません。職場における課題、特に新入社員の職場適応という文脈でもAIコーチングの可能性が探られています。
具体的には、初めて職場に入る大卒新入社員を支援するためのAIチャットボットコーチの活用可能性が調査されました[4]。大卒新入社員は職場環境への適応、業務量の管理、仕事とプライベートのバランス、人間関係の構築、そして目標設定と達成において多くの困難に直面しています。高等教育機関は主に認知的スキルの開発に焦点を当てているため、卒業生が職場に入ると実務的なスキルのギャップが生じることがあります。
多くの企業は新入社員のために研修やオンボーディングに投資していますが、これらのプログラムは高額であり、その効果が疑問視されることもあります。他方で、個別コーチングは効果が実証されている人材開発手法ですが、コストが高く、一般的に新入社員には提供されていないという現状があります。
この研究では、AIチャットボットコーチが大卒新入社員の職場への移行を支援できるかを検討しました。研究者たちはAIコーチングを「機械支援による体系的なプロセスで、クライアントが専門的な目標を設定し、それを効率的に達成するための解決策を構築するのを支援するもの」と定義しています。
研究は南アフリカの銀行で行われ、9名の大卒新入社員(全員が3〜4年の大学教育を修了)が参加しました。参加者は4週間にわたり、目標達成を支援するAIチャットボットコーチ「Vici」を使用しました。このViciは、前述の通り、ルールベース(非生成型)のチャットボットで、メッセージングアプリを通じてアクセスすることができます。
参加者とのインタビューは4週間後に実施され、チャットボットの使用経験について質問されました。インタビューデータは主題分析という手法を用いて分析され、チャットボットに記録された目標データも併せて分析されました。
分析の結果、4つの主要なテーマが浮かび上がりました。
- 1つ目は「利便性とアクセシビリティ」です。参加者は24時間365日いつでもコーチングを受けられることを高く評価しました。また、ユーザーフレンドリーなインターフェースと、適切な質問が好評でした。
- 2つ目のテーマは「限界」です。一部の参加者はチャットボットが機械的で個人的でないと感じました。より柔軟でパーソナライズされた目標設定を望む声もありました。AIチャットボットは事前にプログラムされた範囲内でしか対応できないため、個々の状況に合わせた柔軟な対応には限界があったようです。
- 3つ目のテーマは「キャリア開発における有効性」です。チャットボットは具体的な行動ステップと測定可能な成果に焦点を当て、キャリア目標の達成に効果的でした。参加者は小さなマイルストーンに目標を分解できることを評価しました。大きな目標を小さな達成可能なステップに分けることで、進捗が見えやすくなり、モチベーションの維持につながったと考えられます。
- 4つ目のテーマは「内省と自己認識」です。チャットボットが目標に対する責任を持たせ、進捗を追跡する機能が価値あるものとされました。チャットボットは参加者が自分の弱点に向き合い、個人の成長を振り返り、改善すべき分野を特定するのを助けました。
研究結果は主に2つの理論的枠組みを用いて解釈されました。1つ目は「技術受容モデル」です。この理論によれば、利便性とアクセシビリティはテクノロジーの受容に直接関連しています。常に利用可能でユーザーフレンドリーなシステムは使いやすいと認識され、技術の意図的および実際の使用を促進するとされています。AIチャットボットが24時間利用可能で簡単に使えるという特性は、参加者の継続的な利用を促進する要因になったと考えられます。
2つ目の理論的枠組みは「自己決定理論」です。この理論は自律性、有能感、関係性という3つの心理的欲求が人間の動機づけに重要であるとします。研究結果では、AIチャットボットは自律性と有能感の促進に貢献していました。自律性については、チャットボットは参加者が現実的で詳細な目標を設定し、行動を起こすことで自分の日常生活と将来のキャリアをより自分でコントロールできるように支援しました。有能感については、チャットボットを通じた自己認識の向上により、参加者は自分の能力に合った目標を設定し、職場の複雑さにより効果的に対処できるようになりました。
ただし、関係性の面ではAIチャットボットに不足が見られました。参加者は人間的な触れ合いとより個人化された経験を望んでいました。これは、AIチャットボットの限界の一つであると言えるでしょう。
AIコーチングは人間のコーチングを完全に置き換えるものではありませんが、特に関係性の面では限界があるものの、大卒新入社員にとって自律性と有能感を促進する効果的なツールとなる可能性があります。このようなテクノロジーは、より多くの従業員にコーチングの恩恵を広げる方法を提供し、通常はコストの問題でコーチングが提供されない従業員層に価値があると考えられます。
脚注
[1] Passmore, J., Olafsson, B., and Tee, D. (2025). A systematic literature review of artificial intelligence (AI) in coaching: Insights for future research and product development. Journal of Work-Applied Management. Advance online publication.
[2] Terblanche, N., Molyn, J., de Haan, E., and Nilsson, V. O. (2022). Comparing artificial intelligence and human coaching goal attainment efficacy. PLOS ONE, 17(6), e0270255.
[3] Figueroa, C. A., Luo, T. C., Jacobo, A., Munoz, A., Manuel, M., Chan, D., Canny, J., and Aguilera, A. (2021). Conversational physical activity coaches for Spanish and English speaking women: A user design study. Frontiers in Digital Health, 3, 747153.
[4] Terblanche, N. H. D., and Tau, T. (2024). Exploring the use of a goal-attainment, artificial intelligence (AI) chatbot coach to support first-time graduate employees. Industry and Higher Education. Advance online publication.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。