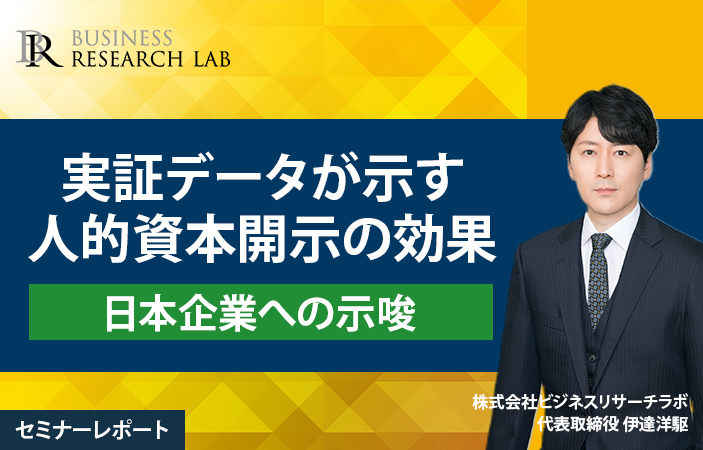2025年8月5日
実証データが示す人的資本開示の効果:日本企業への示唆(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年7月にセミナー「実証データが示す人的資本開示の効果:日本企業への示唆」を開催しました。
企業の競争力の源泉として「人的資本」の重要性が高まる中、その情報開示に対する関心が拡大しています。人的資本情報の開示は、企業の市場評価を高め、透明性や信頼性の向上に寄与するとともに、株価にもポジティブな影響をもたらすことが明らかになっています。
本セミナーでは、ビジネスリサーチラボ代表取締役の伊達洋駆が、人的資本開示に関する研究知見をもとに、企業価値向上への影響について解説しました。国内外の先進事例を踏まえながら、業種や企業規模に応じた効果的な開示方法、投資家や市場からの評価を高めるポイントについてお話ししました。
また、人的資本開示が情報提供の枠を超え、企業の戦略的行動として機能している側面にも焦点を当て、人事部門が経営層と連携して取り組むべき課題についても考察しています。人的資本の価値を可視化し、それを企業競争力の向上につなげるための知識を得る内容です。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
企業経営における「人」の価値に改めて注目が集まっています。従業員が持つ知識やスキル、経験といった「人的資本」は、単なるコストではなく、企業の持続的な成長と競争力を支える資産であるという認識が広がってきています。この流れを受け、日本でも2023年3月期決算から、有価証券報告書において人的資本に関する情報開示が義務化されました。
多くの人事担当者の皆さんが、どのような情報を、どのように開示すべきか、試行錯誤されていることと存じます。情報開示は、規制に対応するための義務にすぎないのでしょうか。本講演では、世界各国の研究成果を紐解きながら、人的資本開示が企業価値や採用競争力、さらには従業員の意識にまで及ぼす多面的な影響を考察し、これからの情報開示戦略を考える上でのヒントを提供します。
人的資本開示と企業価値の向上
人的資本に関する情報を積極的に開示することは、企業の市場における評価を高める上でどのような効果を持つのでしょうか。この問いに答える研究が世界中で進められています。
例えば、米国の企業を対象とした調査では、労働コストといった人的資本に関する情報を自主的に公開している企業は、そうでない企業に比べて市場でのパフォーマンスが高い傾向にあることが示されました[1]。この研究では、労働投入量に対する収益の増加分を示す「労働の限界生産性」や、そこから賃金コストを差し引いた「労働効率性」といった指標を用いて分析が行われました。
その結果、これらの指標が高い、要するに人的資本への投資効率が良い企業ほど、市場から優れた評価を得ていました。興味深いのは、この効果が比較的小さな企業でより顕著に見られた点です。大企業に比べて情報が不足しやすい小規模企業にとって、人的資本の開示が投資家との情報の非対称性を埋め、自社の魅力を伝える上で重要な役割を果たすことを物語っています。
同様の傾向は、他の地域でも確認されています。ヨーロッパ32カ国の企業を対象とした大規模な調査では、人的資本に関する自主的な情報開示が、企業の株価や株式リターンに対して統計的に有意なプラスの影響を与えていることが明らかになりました[2]。
この結果が意味するのは、市場の投資家たちが、会計上は「費用」として計上される人件費や教育研修費を、将来の価値を創造する「資産」への投資として評価しているということです。人的資本に関する情報は、企業の将来的な収益性を予測するための手がかりとなり、投資家が抱える不確実性を低減させる効果があります。
さらに、ナイジェリアの保険企業を対象とした調査では、具体的な開示項目と市場価値との関連が分析されています[3]。保険業界のように、従業員の専門性や顧客との信頼関係が事業の根幹をなすセクターでは、人的資本の質が企業価値に結びつきます。
分析の結果、従業員のトレーニングやキャリア開発、あるいは健康と安全への配慮といった、従業員の能力向上や労働環境の改善に直結する項目を開示している企業ほど、市場価値が高いという正の関連が見られました。これは、投資家が人的資本への投資を、企業の競争力を高め、持続的な成長を実現するための打ち手として評価していることの証左と言えます。
一方で、従業員の退職計画に関する開示は、市場価値との明確な関連が見られなかったことも報告されており、どのような情報を開示するかが重要であることを示唆しています。これらの研究は、積極的かつ戦略的な情報開示が、企業の価値を市場に正しく伝え、評価を高める上で有望であることを教えてくれます。
信頼と採用競争力を高める情報開示
人的資本の開示がもたらす恩恵は、投資家からの市場評価向上だけに留まりません。それは、顧客や地域社会、そして未来の従業員候補者といった、より幅広いステークホルダーからの信頼を獲得し、企業のブランド価値を高める力を持っています。
スペインの大企業を対象に行われた研究は、この点を示しています[4]。この研究では、企業の年次報告書などを分析し、人的資本に関する情報開示の状況を評価したところ、従業員の教育や報酬、労働安全といった情報を詳細に開示している企業ほど、市場からの透明性評価が格段に高いことが判明しました。
人的資本への真摯な取り組みを示すことは、企業が社会的責任(CSR)を果たそうとする姿勢の表れと見なされ、ステークホルダーからの信頼醸成につながるのです。この観点に立てば、人的資本開示は、単なる報告義務の遵守ではなく、企業全体の評判を高めるための広報・ブランディング活動の一環として捉えることができます。
そして、この信頼獲得という効果は、人材獲得競争が激化する現代において、人事担当者が活用すべき武器となり得ます。アメリカの求職者を対象として行われた大規模なフィールド実験があります[5]。
この実験では、十数万人の求職者を対象に、推薦される求人情報に企業の「多様性スコア」を提示するという試みが行われました。このスコアは、従業員の人種構成や男女比、学歴の多様性などを総合的に評価したものです。結果、多様性スコアを提示された求職者たちは、そうでない求職者に比べ、より多様性の高い企業の求人情報をクリックする傾向が有意に高まりました。
分析を進めると、求職者にとって企業の多様性の高さは、金銭的な報酬、すなわち給与とある程度置き換えが可能なほど魅力的な要素として認識されていることが明らかになりました。たとえ給与が少し低くても、多様性に富んだ魅力的な職場環境で働きたいと考える求職者が少なからず存在することを示唆しています。
実際に、求職者が多様性を重視する傾向にある産業ほど、企業側も多様性に関する情報を積極的に開示しているという相関関係も確認されました。これは、企業が採用市場のニーズを理解し、情報開示を活用していることの表れでしょう。
この研究結果は、労働人口の減少という構造的な課題を抱える日本の人事担当者にとっても、重要な示唆を含んでいます。これからの採用活動においては、給与や福利厚生といった条件だけでなく、自社が持つ職場環境の魅力を、具体的なデータをもって求職者に伝えることが不可欠になります。
多様性に関する情報はその一例に過ぎません。従業員の働きがい、キャリア開発の機会、健康への配慮など、求職者が「この会社で働きたい」と思えるような情報を(採用の文脈だけではなく人的資本開示の文脈でも)積極的に開示できる企業が、これからの人材獲得競争を優位に進めていくことができるでしょう。
開示レベルを左右する要因と戦略
人的資本開示の重要性が認識される一方で、その開示レベルはすべての企業で一様というわけではありません。企業の置かれた環境によって、開示の積極性や内容には違いが生まれます。その違いはどのような要因によってもたらされるのでしょうか。
この問いを探るため、経済的な成熟度が異なるポーランドとドイツの上場企業を比較した調査があります[6]。ポーランドが市場経済へ移行中の国であるのに対し、ドイツは長い歴史を持つ経済大国です。分析の結果、両国に共通して、時価総額や従業員数といった企業規模が大きいほど、人的資本の開示内容が充実している傾向が見られました。大企業ほど多くのステークホルダーから注目され、情報開示に対する社会的な要請が強まるためと考えられます。
また、開示状況は各国の産業構造を反映していました。ドイツでは製造業やサービス業が積極的だったのに対し、ポーランドではエネルギー・鉱業といった分野の開示が進んでいました。国全体の経済状況も影響しており、経済的に成熟したドイツの企業は、ポーランド企業に比べて全体的に開示水準が高く、特に従業員の満足度調査や人材育成プログラムといった、より踏み込んだ内容の開示が活発でした。
新興国に目を向けると、異なる実態が見えてきます。トルコの製造業を対象とした調査では、人的資本開示が十分に進んでいない状況が明らかになりました[7]。従業員数のような基本的な情報は多くの企業が開示しているものの、従業員一人当たりの付加価値といった、企業の業績と直結するような指標の開示は極めて限定的でした。
ここでも、人的資本開示の水準に影響を与える要因として、業種や上場してからの年数、そして大手監査法人を利用しているかどうかに加え、やはり企業規模が最も強く関連していました。大企業であるほど、社会的な説明責任を果たさなければならないという意識が強く働くことが、その背景にあると考察されています。
これらの研究結果から、人事担当者が自社の開示戦略を立てる上で得られる含意は二つあります。第一に、他社比較、すなわちベンチマーキングが戦略の第一歩となるということです。開示のレベルは国や業種、そして何より企業規模によって異なります。やみくもに国内外の先進事例を模倣するのではなく、まずは自社と同じ業界や同程度の規模の企業が、どのような情報を、どの程度の具体性で開示しているのかを調べることが、現実的で効果的な戦略を立てる上で有効です。
第二に、自社の規模に応じた「説明責任」を自覚することの重要性です。研究が一貫して示すように、企業規模が大きいほど、社会が企業に向ける視線は厳しくなり、より高いレベルの透明性が求められます。自社が、特に上場企業や業界を代表するような大企業である場合、人事担当者は、人的資本の開示を任意の活動ではなく、多様なステークホルダーに対する当然の責務であると認識する必要があるでしょう。
開示に映る企業文化と戦略的意図
企業が発信する人的資本情報はデータの羅列ではありません。そこには、その企業が何を大切にし、どのような価値観を持っているのかという、企業文化や国民性が映し出されます。スリランカの上場企業を対象とした調査は、この点を示しています[8]。
この調査によると、スリランカの企業は「従業員一人当たりの付加価値」といった、成果を示す結果指標を頻繁に開示する傾向がありました。研究者たちは、これはプロセスよりも結果を重んじるスリランカの企業文化が反映されたものだと考察しています。
また、年次報告書に従業員の写真や名前を掲載する企業も多く、これは集団主義的な価値観が強い社会の中で、従業員の会社への帰属意識や一体感を高める効果を狙ったものと考えられます。実際、プロセスを重視する傾向のあるオーストラリア企業と比較すると、その違いは鮮明であり、人的資本開示が文化的な文脈に深く根差していることが分かります。
このことは、日本の人事担当者にとって、欧米の開示基準をそのまま導入するだけでなく、日本企業ならではの価値観、例えばチームワークや長期的な視点といった要素を反映させた開示に、意味があり得ることを示唆しています。
人的資本開示の裏側には、より計算された戦略的な意図が隠されている場合もあります。企業は、必ずしも中立的・客観的な情報提供だけを目的としているわけではありません。同じくスリランカの企業の年次報告書を分析し、さらに人事担当役員らへのインタビューを行った別の研究では、企業が社会的・政治的な動機から、開示する情報を巧みに選択している実態が明らかになりました[9]。
調査対象となった企業の多くは、当時、技術革新に伴う人員削減を進めていました。その一方で、報告書では従業員との良好な関係性を強調する情報を開示することで、人員削減に対する社会的な批判を和らげようとしていたのです。対照的に、公平性(例えば、民族間の雇用比率など)や安全管理といった、社会的に敏感で企業の弱点となりうるテーマに関する情報の開示は少ないことも分かりました。
この事例が示すのは、人的資本開示が、企業イメージの向上や社会的批判の回避を目的とした「守り」の企業防衛戦略としても機能する、という事実です。自社の開示情報を検討する際、また、他社の開示情報を読み解く際にも、その情報の背後にある「意図」や「文脈」を批判的に考察する必要があります。
「なぜこの企業は、この指標を特に強調しているのか」「なぜ、あのトピックには一切触れられていないのか」。このように、開示される情報と、あえて開示されない情報の両方に目を向けることで、数値の比較に留まらない、より本質的な企業の姿を理解することができるでしょう。
開示と社内実態の乖離がもたらすリスク
企業が社外に向けて発信する華やかな報告書。しかし、その内容と、社内の従業員が日々感じている現実との間には、時に隔たりが存在します。スウェーデンの上場企業を対象とした研究は、この「開示と実態の乖離」という問題に光を当てました[10]。
この研究では、企業の年次報告書で開示されている人的資本情報と、CFO(最高財務責任者)へのアンケートを通じて把握した、企業内部で実際に重要視されている管理活動とを比較しました。その結果、両者の間には必ずしも強い相関関係が見られず、企業が内部で重要だと認識している項目が、必ずしも社外への開示に反映されていないことが明らかになりました。
なぜこのような乖離が生まれるのでしょうか。研究者たちは、いくつかの理由を挙げています。一つは、競争優位に関わる情報が競合他社に漏れるリスクを避けるためです。独自の人材育成プログラムなど、企業の強みそのものである情報を詳細に開示することは、模倣のリスクを伴います。加えて、人的資本の価値を測定し、報告するための統一された基準が確立されていないことも、企業による情報の選択的な開示、つまり「良いとこ取り」を可能にし、乖離を生む一因となっています。
この「開示と実態の乖離」は、報告書の信頼性を損なうだけでなく、深刻なリスクを企業にもたらす可能性があります。日本の上場企業を対象とした研究は、衝撃的な結果を突きつけます[11]。その研究では、人的資本に関する情報の開示スコアが高い企業ほど、従業員のエンゲージメントスコアが有意に低いという、逆説的な関係が見出されたのです。情報開示が進めば進むほど、従業員の働く意欲や会社への帰属意識がむしろ低下してしまうというのです。
この現象の背景には何があるのでしょうか。研究者は、開示された「理想」と、従業員が肌で感じる「現実」との間に存在するギャップが、かえって従業員の不満やシニカルな反応を引き起こしている可能性を指摘しています。
報告書で「従業員は最も重要な資産です」「多様性を尊重し、成長を支援します」といった美辞麗句が並べられていても、現場の従業員が日常業務の中でそれを実感できていなければ、それらの言葉は空虚な「建前」にしか聞こえません。むしろ、「会社は私たちのことを全く見ていない」「また綺麗事を言っている」といった冷笑的な態度を生み、組織全体の士気を削いでしまう危険性すらあるのです。経営層が良かれと思って進めた情報開示が、意図せずして従業員の心を離反させてしまうという皮肉な状況が起こり得ます。
これらの研究から導き出される教訓は、人事担当者が警戒すべきリスクは「社外への発信」と「社内の実態」の乖離である、ということに尽きます。そして、これまで情報開示の受け手として主に想定されてきた投資家以上に、従業員こそが手厳しく、そして重要な情報の受け手であり批評家である、という視点を持つ必要があるでしょう。外部向けの報告書を作成する際、「この内容を、現場で働く従業員が読んだらどう感じるだろうか」という問いを意識しなくてはなりません。
人的資本開示の成功は、社外向けのアピールを先行させることではなく、まず従業員が納得し、誇りに思えるような職場環境や制度を地道に構築することから始まります。社内改革と、従業員との誠実な対話。この順番を間違えれば、従業員の信頼を失い、組織の活力を削ぐという事態を招きかねません。開示を、実態を糊塗するための「化粧」ではなく、組織の健全な成長を映し出す「鏡」と捉え、その鏡に映る姿そのものを磨き上げることが求められます。
おわりに
本講演では、人的資本開示をめぐる世界の研究動向を概観し、その多面的な可能性と潜在的なリスクについて考察してきました。見てきたように、人的資本開示は、定められた項目を報告するだけの受動的な義務ではありません。それは、市場からの評価を高めて企業価値向上につなげ、優秀な人材を惹きつける採用競争の武器となり、さらには自社の企業文化や価値観を社内外に発信する戦略的なコミュニケーションツールでもあります。
しかし、その一方で、開示される「理想」と従業員が感じる「現実」との間に乖離が生じた時、従業員の信頼を損ない、組織の活力を奪いかねないというリスクも内包しています。結局のところ、最も重要なのは、開示内容と社内の実態との一貫性です。人的資本開示を組織のあり方を映す「鏡」と捉え、その鏡に映る姿、すなわち従業員一人ひとりが働きがいを感じられる組織を磨き上げることが期待されます。
Q&A
Q:人的資本の情報開示は、実態を美化する「化粧」ではなく、ありのままを映し出す「鏡」であるべきだというお話に共感しました。「鏡」を作り上げていくプロセスにおいて、従業員をどのように巻き込んでいけばよいでしょうか。
大前提として、このプロセスに従業員を巻き込むという姿勢そのものが重要です。経営層や人事部だけで完結させるのではなく、従業員と共に作り上げるという意識を持つことが出発点となります。
では、具体的にどう巻き込むか。例えば、企業がどのような情報を開示するかを検討する初期段階から、従業員の声を反映させる機会を設けることが考えられます。いきなり最終決定案を示すのではなく、素案やドラフトの段階で、「私たちはこのような情報を開示しようと考えています」と共有します。具体的には、従業員代表や、部門横断のメンバーで構成されるプロジェクトチームを立ち上げ、意見交換会を実施するといった方法があります。また、匿名アンケートで開示案へのフィードバックを募る方法もあります。
いずれにせよ重要なのは、意思決定に従業員の声を反映させるプロセスを経ること、そしてそのプロセス自体を「皆さんの声を参考にしました」と社内に発信し、透明性を確保することです。これによって開示情報への当事者意識と納得感が高まり、より精度の高い「鏡」となるでしょう。
Q:開示のためのデータ収集に多くの時間と労力がかかり、本来注力すべき人事業務がおろそかになっています。情報開示そのものが目的化してしまう「開示疲れ」をどう防げばよいでしょうか。
切実な問題ですね。情報開示が本来の人事業務を圧迫するのは本末転倒です。この問題を防ぐ鍵は、開示する情報を、普段の人事業務の中で目標管理に使っている重要な指標(KPIなど)と連動させることです。
「開示のために、特別なデータをわざわざ集める」という発想から、「普段から業務で活用しているデータを、開示にも活用する」という発想へと転換することが求められます。理想は、日常的に計測している複数のKPIを組み合わせることで、そのまま開示指標として使える仕組みを構築することです。
このように、開示を日常業務の延長と位置づけることで、年に一度の「大規模イベント」ではなく、日々の人事活動の「成果発表会」のような健全な形となり、現場の負担も軽減されるでしょう。
Q:「企業文化」や「従業員の働きがい」といった、数値化しにくい質的な情報を、どうすれば説得力を持って開示できるでしょうか。
「企業文化」や「働きがい」も、従業員サーベイなどを活用することで、ある程度は数値化(定量化)することが可能です。
とはいえ、人々の共感を呼ぶ上では、数値だけでは伝わらないストーリーや背景もまた重要です。説得力を高めるには、具体的なエピソードや従業員の生の声を引用することが効果的です。例えば、自社の強みとして「チームワークの良さ」を伝えたい場合、サーベイのスコアを示すだけでなく、「ある困難なプロジェクトで、部署の壁を越えて社員が協力し、目標を大幅に上回る成果を上げた」といった成功事例を紹介します。こうした生の声やエピソードが、データに血を通わせ、ストーリーに深みを与えてくれます。
Q:情報開示を進めるほど、かえって従業員のエンゲージメントが下がってしまうという日本企業の事例は衝撃的でした。このリスクを回避するために、開示前に確認すべきチェックポイントはありますか。
このリスクを回避するチェックポイントは、開示予定の内容が「従業員の現場感覚と乖離していないか」という点です。これを確かめるには、開示案を従業員に見せ、「この内容は、皆さんの実感と合っていますか」と率直に意見を求めるのがベターです。特にエンゲージメントが低い部署など、乖離が生まれそうな層に意図的に話を聞きに行きましょう。
もし大きな乖離があると判断された場合、重要なのは開示の「順番」です。まず先に「現状をこのように改善していきます」という計画を社内でしっかりと共有し、従業員の理解と納得を得た上で、情報開示に踏み切ります。このステップを踏むことで、開示される内容は「絵に描いた餅」ではなく、「これから目指すべき目標」として前向きに捉えられ、会社の変革に向けた意思が伝わります。
Q:人的資本の情報開示で「ストーリーを語ることの重要性」がよく指摘されますが、人を惹きつけるストーリーを作るコツはありますか。
ストーリー作りと聞くと難しく感じられるかもしれませんが、優れたストーリーには「型」が存在します。例えば、古典的な型の一つに、「挑戦と克服」の物語があります。これは「課題→挑戦→克服→展望」という流れで構成されます。
初めに、会社が人的資本に関して直面している「課題」を率直に示します。その課題を乗り越えるための「挑戦」(具体的な人事施策など)を語り、その結果としての「克服」を伝えます。最後に、これらの経験を踏まえた「展望」を描いて締めくくります。この型に沿って情報を整理・構築すれば、散発的な情報の羅列が、一貫性のあるストーリーへと昇華されます。
ただし、一つ注意点があります。ストーリーをあまりにきれいに作り込みすぎると、かえって従業員に「現実と違う」という白々しさを感じさせ、実態との乖離という問題を生む危険性があります。ストーリーテリングは強力な武器ですが、誠実さとのバランスが求められます。
脚注
[1] Lajili, K., and Zeghal, D. (2006). Market performance impacts of human capital disclosures. Journal of Accounting and Public Policy, 25(2), 171-194.
[2] Elbannan, M. A., and Farooq, O. (2016). Value relevance of voluntary human capital disclosure: European evidence. Journal of Applied Business Research, 32(6), 1555-1560.
[3] Tom, I. M., Okpo, S. A., and Simeon, U. (2025). Human resource factor disclosures and market value of insurance firms in Nigeria. Journal of Accounting and Financial Management, 11(2), 206-226.
[4] Dominguez, A. A. (2011). Transparency, social responsibility and corporate governance: Human capital of companies. International Journal of Human Resources Development and Management, 11(1), 29-48.
[5] Choi, J. H., Pacelli, J., Rennekamp, K. M., and Tomar, S. (2023). Do jobseekers value diversity information? Evidence from a field experiment and human capital disclosures. Journal of Accounting Research, 61(3), 695-735.
[6] Bryl, L., and Truskolaski, S. (2017). Human capital reporting and its determinants by Polish and German publicly listed companies. Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(2), 191-206.
[7] Uyar, A., and Kilic, M. (2013). Discovering the nature and extent of human capital disclosure, and investigating the drivers of reporting: evidence from an emerging market. International Journal of Accounting and Finance, 4(1), 63-85.
[8] Abeysekera, I., and Guthrie, J. (2004). Human capital reporting in a developing nation. The British Accounting Review, 36(3), 251-268.
[9] Abeysekera, I. (2008). Motivations behind human capital disclosure in annual reports. Accounting Forum, 32(1), 16-29.
[10] Ax, C., and Marton, J. (2008). Human capital disclosures and management practices. Journal of Intellectual Capital, 9(3), 433-455.
[11] Elamer, A. A., and Kato, M. (2024). Governance dynamics and the human capital disclosure-engagement paradox: A Japanese perspective. Competitiveness Review: An International Business Journal, 35(1), 76-99.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。