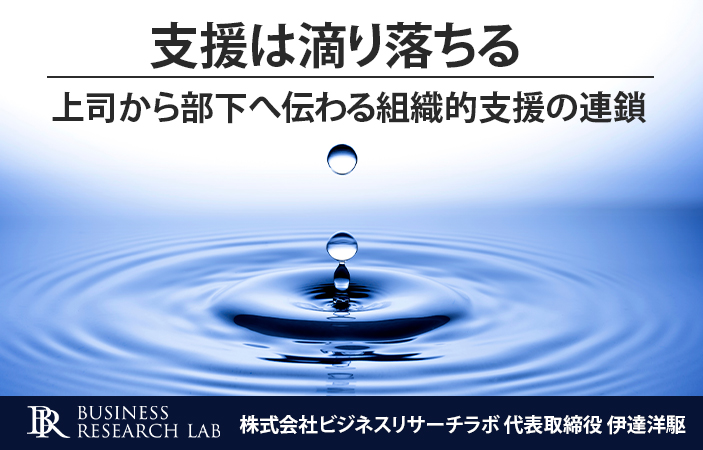2025年8月5日
支援は滴り落ちる:上司から部下へ伝わる組織的支援の連鎖
組織と従業員の関係性は企業の成功を左右する要素の一つとなっています。特に「組織的支援」という概念は、従業員が組織からどのように大切にされ、評価されているかという認識を表すものであり、職場における行動や意欲に関わっています。従業員は単純な業務の執行者ではなく、組織との相互作用を通じて様々な心理的変化を経験します。組織が従業員を支援し、その貢献を評価すると、従業員はどのような反応を示すのでしょうか。また、その心理的メカニズムはどのようなものなのでしょうか。
本コラムでは、組織的支援の性質について掘り下げていきます。組織的支援が従業員の組織への愛着や帰属意識よりも実際の行動にどう結びつくのかを見ていきます。そして、個人の持つ情緒的な欲求の強さによって、組織的支援の効果がどのように異なるのかを検証します。さらに、組織的支援が上司から部下へと連鎖的に伝わっていくというダイナミックな現象についても考察します。
これらの理解は、より良い職場環境の構築や人材マネジメントの向上に役立つかもしれません。組織的支援の性質を理解することで、従業員と組織の間に好循環を生み出し、双方にとって価値ある関係を築くための洞察が得られるでしょう。
組織的支援は組織コミットメントより組織市民行動を促す
私たちは給料のためだけに働いているわけではありません。職場における人間関係や組織からの評価、支援なども私たちの行動や意欲に意味を持っています。とりわけ「組織的支援」と呼ばれる概念は、従業員の行動を理解する上で鍵となります。
組織的支援とは、「組織が従業員の貢献をどれだけ評価し、その幸福を気にかけているか」という従業員の認識を指します。例えば、「会社は私の仕事ぶりを正当に評価してくれている」「この組織は私の幸福に関心を持っている」といった感覚です。この組織的支援の認識は、従業員が組織に対して抱く感情や行動に関わっています。
アメリカの多国籍企業で行われた研究では、組織的支援の認識が従業員の行動パターンにどのように影響するかが調査されました[1]。この調査では、従業員の心理的要素として組織的支援の認識に加え、情緒的コミットメント(組織への感情的な愛着や所属感)と存続的コミットメント(組織を離れることのコストが高いために留まる必要性)が測定されました。
調査は2段階で実施され、まず従業員自身の心理状態が測定され、次に上司から見た従業員の行動が評価されました。焦点が当てられたのは「組織市民行動」と呼ばれる、職務記述書には明記されていないけれども組織のために行う自発的な行動です。これには、同僚を手助けする「利他的行動」や、組織のルールや規範を守る「遵守行動」などが含まれます。
調査結果から見えてきたのは、組織的支援の認識が情緒的コミットメントや存続的コミットメントよりも、組織市民行動をより強く予測するという事実でした。組織から支援されていると感じる従業員ほど、職務範囲を超えて同僚を助けたり、組織のために自発的に行動したりする傾向が強かったのです。
一方で、存続的コミットメント(組織を離れることの損失が大きいために残る意識)は、むしろ組織市民行動を抑制する効果があることも判明しました。言い換えれば、「辞めると損をするから仕方なく働いている」という意識が強い従業員は、積極的に組織のために行動することが少ないという結果です。
この研究は、社会的交換理論という考え方を支持しています。この理論によれば、人は自分が受け取ったものに対して返報する義務感を持つとされています。組織から支援されていると感じる従業員は、その支援に対する「お返し」として組織市民行動を行うということです。単純な取引関係ではなく、感情的な要素を含む社会的な交換関係だと考えられます。
もう一つ、「印象管理行動」と呼ばれる、上司に良い印象を与えるための行動についての発見も紹介しましょう。当初の予想では、組織的支援の認識が高い従業員は印象操作的な行動をあまりしないだろうと考えられていました。しかし実際には、組織的支援の認識が高い従業員は上司に対する「好意的行動」(例えば上司の個人的な用事を手伝うなど)を多く行っていました。これは、表面的な印象操作というよりも、組織への肯定的な感情が上司への好意的行動として表れていると解釈できます。
この研究の意義は、従業員の行動を予測する際に、従来重視されてきた組織コミットメントだけでなく、組織的支援という要素を考慮することの重要性を明らかにした点にあります。組織が従業員を支援し、その貢献を評価する雰囲気を作ることで、従業員は義務として働くだけでなく、自発的に組織のために行動するようになるのです。
組織的支援は情緒的欲求が強い人ほど効果が高い
組織的支援が従業員の自発的な貢献行動を促すことを見てきました。しかし、この効果は全ての人に同じように現れるのでしょうか。個人が持つ特性によって、組織的支援の効果は異なることが分かっています。
アメリカの州警察を対象とした研究では、組織的支援の効果が個人の「社会情緒的欲求」の強さによって調整されることが明らかになりました[2]。社会情緒的欲求とは、自己評価欲求(自分の価値を認められたい欲求)、親和欲求(他者と親密な関係を持ちたい欲求)、情緒的支援欲求(困った時に助けてもらいたい欲求)、社会的承認欲求(社会から認められたい欲求)などの感情的・社会的ニーズを指します。
この研究では、308名の警察官を対象に、組織的支援の認識と社会情緒的欲求を測定し、それらが実際の職務パフォーマンス(具体的には飲酒運転の逮捕件数やスピード違反の取締り件数)とどのように関連するかを調査しました。
調査の結果、組織的支援が職務パフォーマンスに及ぼす効果は、社会情緒的欲求の強さによって異なることが分かりました。社会情緒的欲求が強い警察官では、組織的支援が高いほど職務パフォーマンスも高くなりました。要するに、自分の価値を認められたい、人との関係を大切にしたい、周囲からの支援を求めたいという欲求が強い人ほど、組織からの支援を受けると、その「お返し」として高いパフォーマンスを発揮するということです。
一方で、社会情緒的欲求が弱い警察官では、組織的支援と職務パフォーマンスの間に明確な関係は見られませんでした。驚くことに、情緒的支援欲求が特に低い一部の警察官では、組織的支援の認識が高いほど逆にパフォーマンスが低下するという結果も出ました。
この結果をどのように解釈すれば良いのでしょうか。社会的交換理論から考えると、社会情緒的欲求が強い人は、組織からの支援をより価値のあるものとして認識し、その見返りとして高いパフォーマンスで応えようとすると考えられます。言い換えれば、情緒的な欲求が強い人にとって、組織からの支援や承認は「貴重な資源」となり、それに対する返報義務を強く感じるのです。
反対に、社会情緒的欲求が弱い人にとっては、組織からの支援はそれほど価値のあるものとして認識されないため、返報義務もあまり感じられないのかもしれません。一部の人では、組織からの過度な支援が逆に「監視されている」「期待に応えなければならない」というプレッシャーとなり、パフォーマンスを低下させる可能性も考えられます。
この研究では「社会的怠惰」の可能性も指摘されています。社会的怠惰とは、集団の中で個人の貢献が見えにくくなると努力が低下する現象を指します。情緒的欲求が弱い従業員は、組織からの支援を「当然のこと」とみなし、特別な見返りを提供する必要性を感じず、むしろ怠けてしまう傾向があるのかもしれません。
組織的支援の効果は一律ではなく、個人特性によって異なります。組織が従業員を支援する取り組みを行う際には、個人の特性や欲求の違いを考慮することが重要だということが分かります。
社会情緒的欲求が強い従業員に対しては、組織からの支援を明確に示すことでモチベーションを高め、パフォーマンスを向上させることができるでしょう。一方、社会情緒的欲求が弱い従業員に対しては、支援を提供するだけでなく、その支援と職務上の目標や期待を明確に結びつけるコミュニケーションが有効かもしれません。
組織と従業員の関係は「支援すれば応えてくれる」という図式ではなく、個人の心理的特性や欲求によって異なる複雑な相互作用があるということです。職場のマネジメントにおいては、こうした個人差を理解し、それぞれの従業員に合った関わり方を考えることが求められるでしょう。
組織的支援は上司から部下へと連鎖的に伝わる
組織的支援が従業員の行動に及ぼす効果や、その効果が個人の特性によって異なることを見てきました。しかし、組織的支援はどのようにして従業員に届くのでしょうか。階層的な組織構造の中で、組織的支援はどのように伝わっていくのでしょうか。
アメリカの大型家電量販店チェーンで行われた研究では、組織的支援が「上司から部下へと連鎖的に伝わる」という現象が明らかになりました[3]。この研究では、上司が自分自身が組織から支援されていると感じる度合い(上司の組織的支援の認識)と、部下が上司から支援されていると感じる度合い(上司支援の認識)、そして部下自身の組織的支援の認識とパフォーマンスの関係が調査されました。
研究結果から見えてきたのは、上司が組織から支援されていると感じるほど、部下は上司から支援されていると感じるということです。さらに、部下が上司から支援されていると感じるほど、部下自身も組織全体から支援されていると感じるようになり、その結果、職務パフォーマンスや自発的な貢献行動が向上するというメカニズムが確認されました。
この現象は「トリクルダウン効果」と呼ばれます。組織からの支援が上司に与えられると、それが「滴り落ちる」ように部下にも伝わっていくのです。組織から支援されていると感じる上司は、その見返りとして組織に貢献しようとする意欲が高まります。その一環として、部下への支援行動も増加します。部下は上司からの支援を感じることで、それを組織全体からの支援と認識し、さらにその見返りとして高いパフォーマンスで応えるという連鎖が生まれます。
実際の分析では、上司の組織的支援の認識が部下の上司支援の認識を通じて、部下の組織的支援の認識や職務パフォーマンス、さらには自発的な組織貢献行動に影響を及ぼすという「媒介効果」が確認されました。上司が組織から支援されているという認識は、直接部下のパフォーマンスに影響するわけではなく、上司から部下への支援行動を通じて間接的に影響しています。
組織における支援の「流れ」を明らかにした点が、この研究の有益なところです。組織は従業員一人ひとりと直接的な関係を持っているわけではなく、多くの場合、上司を介して関係が構築されます。したがって、組織が上司を支援することは、最終的に部下のパフォーマンス向上につながるという視点を提供しています。
経営層や人事部が直接全従業員と関わることには限界がありますが、管理職層への支援を充実させることで、その効果を組織全体に波及させることができるかもしれません。例えば、上司に対して自律性を付与したり、意思決定への参加機会を増やしたりすることで、上司の組織的支援の認識を高めることができます。そうした上司は部下への支援行動を増やし、部下のパフォーマンスや組織への貢献意欲が向上するという好循環が期待できます。
組織的支援は「会社が従業員を大切にする」という抽象的な概念ではなく、階層的な組織構造の中で連鎖的に伝わっていく動的なプロセスだということです。上司は組織の方針や価値観を伝える「伝達者」であり、上司自身が組織から支援されていると感じることが、部下への適切な支援行動につながります。
管理職の育成や支援は、管理スキルを向上させるだけでなく、組織全体としての支援文化を浸透させるための戦略と言えるでしょう。上司と部下の良好な関係構築は、組織全体の効果的な機能につながる基盤となります。
脚注
[1] Shore, L. M., and Wayne, S. J. (1993). Commitment and employee behavior: Comparison of affective commitment and continuance commitment with perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 78(5), 774-780.
[2] Armeli, S., Eisenberger, R., Fasolo, P., and Lynch, P. (1998). Perceived organizational support and police performance: The moderating influence of socioemotional needs. Journal of Applied Psychology, 83(2), 288-297.
[3] Rhoades Shanock, L., and Eisenberger, R. (2006). When supervisors feel supported: Relationships with subordinates’ perceived supervisor support, perceived organizational support, and performance. Journal of Applied Psychology, 91(3), 689-695.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。