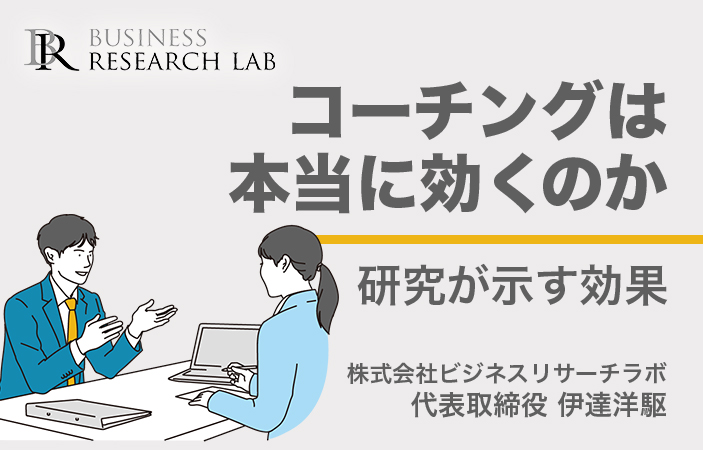2025年8月4日
コーチングは本当に効くのか:研究が示す効果
ビジネスの世界で「コーチング」が浸透してきています。企業研修やリーダーシップ開発、人材育成の文脈で取り入れられる、この手法は、上司が部下に指示を出すという従来の関係性とは一線を画しています。コーチングにおいては、相手の潜在能力を引き出し、自ら考え行動できるよう支援することを主眼としています。
かつては例えばスポーツの世界で用いられていたコーチングですが、近年、ビジネス分野でも普及してきました。経営環境の変化が激しくなる中、従業員一人ひとりが自律的に考え、行動することの価値が高まっています。このような背景から、組織の中でコーチングを取り入れる動きが世界的に広がっているのです。
しかし、コーチングは実際に効果があるのでしょうか。少なからぬ企業がコーチングを導入していますが、その投資に見合う成果が得られているのでしょうか。
本コラムでは、コーチングの効果について検討します。学術研究の知見を基に、コーチングが自己効力感、自己調整能力、生産性、目標達成能力などに与える効果について見ていきます。これらの研究は、コーチングが単なる流行ではなく、個人と組織の成長に貢献をしていることを示唆しています。
コーチングは自己効力感を高める
仕事の場面で「自分にはこの課題を成し遂げる力がある」と感じることは、実際のパフォーマンスに関わってきます。この「自分にはできる」という自信を専門的には「自己効力感」と呼びます。自己効力感が高い人ほど、困難な課題にも前向きに取り組み、粘り強く努力することが分かっています。コーチングはこの自己効力感にどのような影響を与えるのでしょうか。
オランダの連邦政府に勤務するマネジャーを対象とした調査では、コーチングが自己効力感の向上に寄与することが明らかになりました[1]。この調査では、60名のマネジャーを二つのグループに分け、一方のグループ(30名)には4か月間のコーチングを実施し、もう一方のグループ(30名)にはコーチングを行いませんでした。
コーチングの内容は、目標設定の明確化を支援するG(Goal)、現状を認識し実現可能性を評価するR(Reality)、目標達成のための選択肢を探索するO(Options)、実際の行動へと導くための意志を強化するW(Will)という「GROW」モデルに基づいて行われました。各マネジャーは自分の関心やニーズに応じて、ロールプレイやブレインストーミングなどの手法を選択しました。
調査では特に3つの領域に焦点を当てました。「自己目標設定能力」「バランスのとれた行動能力」「注意深くマインドフルな生活と仕事」です。これらの領域における自己効力感(自分にはその能力があるという信念)と成果期待(その行動が望ましい結果をもたらすという期待)を測定しました。
4ヶ月後の測定の結果、コーチングを受けたグループでは、「自己目標設定能力に対する自己効力感」と「バランスのとれた行動をとることに対する成果期待」が顕著に向上しました。特に自己目標設定能力については、自己効力感のみが向上し、成果期待には変化がありませんでした。コーチングによって明確な目標設定を行う機会が増え、成功体験を積み重ねたことで、「自分にはできる」という自信が高まったと考えられます。
一方、バランスのとれた行動能力については、成果期待のみが向上し、自己効力感には変化がありませんでした。研究者たちは、行動の変化が自己効力感の実際の改善にまで至るにはさらに時間を要するためではないかと考察しています。
「注意深くマインドフルな生活と仕事」については、自己効力感も成果期待も有意な変化は見られませんでした。今回のコーチングが主に目標設定や行動変容に焦点を当てていたからでしょう。
この研究から、コーチングは特に「自己目標設定能力」に関する自己効力感を高める効果があることが分かります。目標を自分で設定する力は、自律的なキャリア開発や職場での主体的な行動の基盤となるものです。コーチングによってこの能力の自己効力感が高まることは、長期的な職業生活においても意味を持つでしょう。
コーチングは自己調整能力を高める
自己調整能力とは、自分自身の思考や感情、行動をコントロールし、目標達成に向けて調整していく力のことです。この能力は職場での成功に有効であり、変化の激しいビジネス環境ではますます求められるようになっています。コーチングが自己調整能力と関連することを示した研究があります。
組織内におけるコーチングの効果を総合的に検証したメタ分析(複数の研究結果を統合して分析する手法)の結果を見てみましょう[2]。このメタ分析では、コーチングが個人レベルの様々な成果に与える効果を体系的に検証しました。
研究者たちは、「組織内で提供されるプロフェッショナルなコーチングは本当に効果があるのか」という問いを立て、5つの成果領域に焦点を当てました。具体的には、パフォーマンスとスキル、ウェルビーイング(心身の健康状態)、コーピング(ストレス対処能力)、仕事に関する態度、目標志向型の自己調整能力です。
18本の研究をもとに分析した結果、コーチングはすべての領域で肯定的な効果を示しました。その中でも、「自己調整能力」に対する効果が最も大きいことが分かりました。コーチングは特に自己調整能力の向上に強く寄与するということです。なぜコーチングが自己調整能力に対して強い効果を持つのでしょうか。
コーチングのプロセスでは、コーチとクライアントが共に目標を設定し、その達成に向けた計画を立て、進捗を振り返り調整していきます。このプロセス自体が自己調整の練習になっています。また、コーチは質問を通じてクライアントの思考を促し、自己認識を深め、行動の選択肢を広げる支援をします。こうした関わりがクライアントの自己調整能力を高めていくものと考えられます。
メタ分析で明らかになったもう一つの興味深い点は、コーチングセッションの回数と効果の関係です。セッション数が多いほど効果が高くなると想定されるかもしれませんが、研究結果はそうではありませんでした。実際には、少数(5回以下)のセッションでも十分な効果が見られたのです。これは、コーチングが必ずしも長期間にわたって行う必要はなく、短期間の集中的なセッションでも効果を上げられる可能性を示唆しています。
自己調整能力の向上は、職場における多くの前向きな変化につながります。例えば、目標に向かって自分の行動を調整できる人は、効率的に業務を遂行し、困難な状況でも踏みとどまることができるでしょう。また、感情のコントロールも自己調整の一部であり、職場での良好な人間関係構築にも貢献します。
コーチングで研修後の生産性が高まる
職場での研修は多くの組織で実施されていますが、研修で学んだことが実際の業務に活かされるかどうかは別問題です。研修内容の「職場への転移」が十分に行われないというのは、人材開発の分野での長年の課題です。この課題に対して、コーチングがどのように貢献できるのかを検証した研究を見てみましょう。
アメリカの公衆衛生関連機関で実施された研究では、管理職トレーニング後にコーチングを追加することで、生産性がどのように変化するかを調査しました[3]。対象となったのは同機関の管理職者31名で、研究は2つの段階に分けて行われました。
第1段階では、全員が3日間のマネジメント能力強化の集合研修を受けました。研修の前後に知識テストも実施されました。研修前の正答率が71.1%だったのに対し、研修後は88.0%に上昇していました。参加者の満足度評価も高く、5点満点中平均4.87点という結果でした。
しかし、ここで重要なのは、研修後に生産性の向上を定量的に示した参加者がいなかったという点です。知識は増えても、実際の業務パフォーマンスの変化は出てこなかったのです。
そこで第2段階として、約8週間にわたるコーチングが実施されました。8名の内部マネジャーがコーチングスキルを習得し、残りの23名に毎週1時間の1対1のコーチングを提供しました。各参加者は職場で具体的な改善プロジェクトを実施し、その結果を公開プレゼンすることが求められました。
コーチングは7つの要素で構成され、目標設定、協働的問題解決、実践、フィードバック、上司の関与、結果評価、公開プレゼンが含まれていました。とりわけ、経営幹部の前での公開プレゼンは、成果を高める動機づけとなりました。
コーチング後の結果は印象的です。生産性が向上し、トレーニングのみの場合の平均的な生産性向上が22.4%だったのに対し、コーチングを追加した場合の生産性向上は88.0%に達しました。これはトレーニングのみの場合の約4倍という差です。
この生産性向上に寄与した要因として、研究者たちは2つの点を挙げています。一つは「明確な目標設定」です。明確で測定可能な目標設定により、参加者の自己効力感が高まり、業務への転移が促進されたと考えられます。もう一つは「公開プレゼン」です。経営幹部の前で成果を発表するという機会が、大きなインセンティブとして働いたのでしょう。
この研究は、トレーニングとコーチングがそれぞれ質的に異なる学習を提供することも示唆しています。トレーニングは知識の抽象的な学習を促すのに対し、コーチングは具体的な職務プロジェクトを通じた実践的な学習を促します。この二つを組み合わせることで、知識の獲得と実践への応用という両方の学習が強化され、結果として高い生産性向上につながったと考えられます。
この研究から得られる実践的な示唆は、研修を設計する際には、知識提供の場だけでなく、その後の実践を支援するコーチングも組み込むことが効果的だということです。研修で得た知識を実際の業務に活かすためには、個別の支援やフィードバック、具体的な目標設定が重要であり、それらはコーチングによって提供できます。
コーチングは目標達成と回復力を高める
組織変革や厳しい競争環境の中で、管理職には高いストレス耐性と目標達成能力が求められます。コーチングはこれらの能力向上にどのように貢献するのでしょうか。オーストラリアの公的医療機関で実施された研究を見てみましょう[4]。
この研究の特徴は、ランダム化比較試験(RCT)という厳密な方法を用いたことです。RCTとは、参加者をランダムに「介入群」と「対照群」に分け、介入の効果を測定する方法です。外部の専門コーチによるエグゼクティブ・コーチングの効果をRCTによって検証しました。
対象となったのは、組織再編などの変化に直面していた公的医療機関の管理職41名でした。彼ら彼女らは2群にランダムに割り当てられ、介入群は10週間で4回のコーチングを受けました。研究期間中、全ての参加者は360度評価(上司、同僚、部下などからの多角的評価)と半日のリーダーシップ研修を受講していました。
コーチングでは、認知行動療法と解決志向アプローチを組み合わせ、参加者自身の強みを活用して具体的な目標達成をサポートしました。また、GROWモデル(Goal, Reality, Options, Way Forward)を活用し、セッションごとに目標設定とアクションプランを促しました。
その結果、コーチング群は目標達成において有意な向上を示し、レジリエンスも有意に向上しました。また、抑うつが有意に低下し、職場ウェルビーイングも改善しました。短期間のコーチングでも、仕事のパフォーマンスと心理的健康の両面で顕著な効果が見られたのです。
参加者からの自由記述を分析すると、具体的な変化が見えてきました。多くの参加者が「自信の向上」を報告し、自己理解が深まり自信がついたと感じていました。「マネジメントスキルの向上」では、実践的なマネジメントスキルが高まったと報告されました。
変化やストレスをより良く管理できるようになったという声も多く聞かれました。これは、コーチングがレジリエンス(回復力・耐性)を高める効果を持つという定量的な測定結果を裏付けるものです。
さらに、「個人的・職業的な洞察の獲得」や「キャリア開発支援」も重要なテーマとして浮かび上がりました。多くの参加者が、自己や職業的方向性について洞察を得たり、自身のキャリア形成に役立ったりしたと感じていました。
研究者たちは、目標選定に自由度を持たせたことが参加者の意欲やコミットメントを高め、良い成果につながったと解釈しています。コーチングセッションで自ら設定した目標に取り組むことで、参加者は主体性を持って行動できるようになり、それが目標達成とレジリエンスの向上に寄与したということです。
この研究からは、短期的なコーチングでも十分な効果が得られることが示されました。4回のセッションで目標達成やレジリエンスの向上が見られたことは、組織にとっても導入しやすいという実務的な価値があります。組織変化の時期における心理的なサポートツールとして、コーチングが有用であることが確認されました。
脚注
[1] Evers, W. J. G., Brouwers, A., and Tomic, W. (2006). A quasi-experimental study on management coaching effectiveness. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 58(3), 174-182.
[2] Theeboom, T., Beersma, B., and van Vianen, A. E. M. (2014). Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context. The Journal of Positive Psychology, 9(1), 1-18.
[3] Olivero, G., Bane, K. D., and Kopelman, R. E. (1997). Executive coaching as a transfer of training tool: Effects on productivity in a public agency. Public Personnel Management, 26(4), 461-469.
[4] Grant, A. M., Curtayne, L., and Burton, G. (2009). Executive coaching enhances goal attainment, resilience and workplace well-being: A randomized controlled study. The Journal of Positive Psychology, 4(5), 396-407.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。