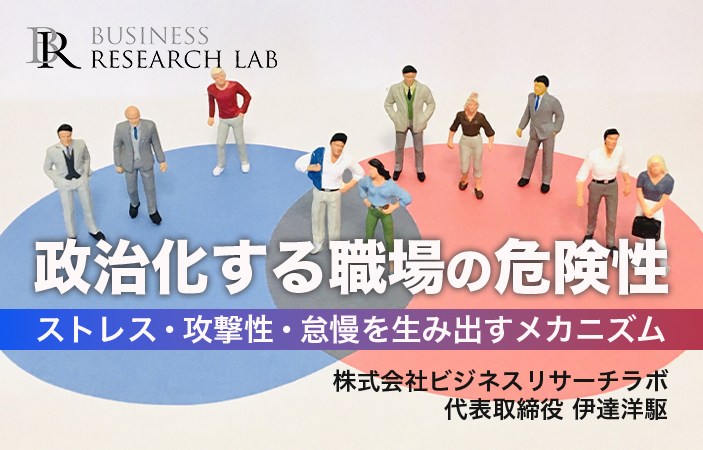2025年8月1日
政治化する職場の危険性:ストレス、攻撃性、怠慢を生み出すメカニズム
「職場の政治」という言葉を聞いて、どのようなイメージを持つでしょうか。同僚が上司に取り入っている姿、自分の評価を上げるために他者の足を引っ張る行為、あるいは派閥争いなど、多くの人が何らかのネガティブな光景を思い浮かべるのではないでしょうか。
組織内政治とは、組織の中で自分の利益を最大化するための行動や影響力の行使を指します。例えば、昇進や報酬を得るために自分の業績を誇張したり、他者の失敗を利用したりするといった行動が含まれます。
このような組織内政治は、多くの職場で見られる現象かもしれません。しかし、それが組織や従業員にどのような影響を与えるのでしょうか。とりわけ、組織内政治が蔓延した環境では、従業員の心理状態や行動にどのような変化が生じるのでしょうか。
本コラムでは、組織内政治が職場にもたらす影響について、実証研究の知見をもとに考察します。組織内政治が攻撃的行動を引き起こすメカニズム、政治的な職場環境が敵対的行動を高める理由、組織内政治の知覚が階層によってどのように異なるのか、そして公務員の怠慢行動との関連性について見ていきます。
組織内政治はある意味で避けられない現象かもしれませんが、その影響を理解することで、健全な職場を目指すための第一歩となるでしょう。
職場の政治は攻撃的行動を引き起こす
職場の中で「政治的な駆け引き」が日常的に行われていると感じたことはありませんか。組織内政治が従業員にどのような影響を与えるのかを調べた研究があります。イスラエルで行われたこの調査では、公共、民間、非営利セクターの従業員540名以上を対象に、組織内政治とそれに伴う職場での行動について分析しました[1]。
組織内政治とは何でしょうか。職場内で自己利益を追求するために影響力や権力を利用する行動です。例えば、上司に取り入ったり、自分の評価を上げるために他者の功績を自分のものにしたり、あるいは情報を独占したりする行為が含まれます。
この研究では、組織内政治が従業員に与える影響として、「ストレス反応」と「攻撃的行動」に焦点を当てました。攻撃的行動とは、同僚や上司に対する言葉による攻撃や、場合によっては物理的な攻撃も含む行動を指します。
研究者たちは3つの仮説を立てました。一つ目は、組織内政治の知覚が職務ストレスやバーンアウト(燃え尽き)と関連しているというもの。二つ目は、組織内政治の知覚が職場での攻撃的行動と関連しているというもの。そして三つ目は、職務ストレスとバーンアウトが、組織内政治の知覚と攻撃的行動の間の関係を媒介しているというものです。
調査の結果、いずれの仮説も支持されました。組織内政治の知覚はすべてのサンプルにおいて職務ストレスと有意な関連があり、それは職場での攻撃的行動とも直接的な関連があることが分かりました。職務ストレスは組織内政治と攻撃的行動の関係を部分的に媒介していることも明らかになりました。
なぜこのような結果が得られたのでしょうか。研究者たちは、政治的な職場環境が従業員に不公平感や心理的な緊張をもたらし、それがストレス反応を引き起こすと説明しています。ストレスを感じた従業員は、それを攻撃的な行動という形で表出させます。例えば、同僚への批判や皮肉、あるいは無視といった行動が見られるようになります。
組織内政治は直接的にも攻撃的行動を促進します。職場が政治化されていると感じる従業員は、自分を守るために、あるいは自分の地位を確保するために、攻撃的な行動を取るようになります。
この研究が教えてくれるのは、組織内政治が蔓延する職場では、従業員のストレスレベルが上昇し、それが攻撃的な行動として表出されやすくなるということです。職場の雰囲気を悪化させるだけでなく、従業員間の協力関係や信頼関係を損なうでしょう。
職場の政治は人間関係の問題ではなく、従業員の精神的健康や行動、ひいては組織全体の機能に関わる問題です。政治的な駆け引きが当たり前になっている職場では、知らず知らずのうちに攻撃的な行動が増え、職場環境が悪化していく危険性があります。
政治的な職場は敵対的行動を高める
組織内政治が従業員のストレスを高め、攻撃的行動を引き起こすことを見てきました。組織内政治の影響はそれだけではありません。政治的な職場は、より広範な「敵対的行動」も促進することが分かっています。ここでは、組織内政治と敵対的行動の関係について、別の角度から検討した研究を紹介します[2]。
この研究では、「政治的環境」と「支援的環境」の二つを区別し、それぞれが従業員の行動や態度にどのような影響を与えるのかを調査しました。政治的環境とは、競争的で自己利益を追求する雰囲気が支配的な環境を指します。一方、支援的環境とは、協力的で互いに助け合う雰囲気が強い環境を指します。
研究者たちは、製造業に勤めるフルタイム従業員69名と、大学生のパートタイム従業員185名を対象に調査を行いました。調査では、政治的環境と支援的環境の認識、職務満足度や組織への忠誠心、離職意図のほか、パートタイム従業員については「敵対的行動」や「心理的離脱」も測定しました。
敵対的行動とは、同僚との衝突や悪口、嫌がらせなど、他者に害を与える行動を指します。心理的離脱とは、仕事から精神的に離れてしまい、無関心や無気力になる状態を指します。
調査の結果、政治的環境と支援的環境は別々の要素であり、それぞれが従業員の行動や態度に異なる影響を与えることが明らかになりました。政治的な環境は、離職意図、心理的離脱、敵対的行動、そして様々な職務ストレス(仕事の緊張、身体的緊張、一般的疲労、バーンアウト)と強い関連があることが分かりました。
例えば、政治的な環境だと感じている従業員は、同僚との関係が悪化しやすく、口論やいざこざが増えるということです。また、仕事に対する無関心さが高まり、「何をしても無駄だ」と感じる従業員も増えます。
政治的環境が敵対的行動を促進する理由は「投資モデル」という考え方で説明されています。政治的環境は、従業員にとって「リスクの高い市場」のように感じられます。どれだけ頑張っても、それが正当に評価されるかどうかが不確かな環境です。このような環境では、従業員は将来の報酬を期待できず、「自分だけが損をしている」と感じます。
そのため、政治的環境では、従業員は自己防衛のために敵対的な行動を取りやすくなります。例えば、他者を批判したり、情報を共有しなかったり、あるいは協力を拒否したりする行動が増えるのです。心理的に仕事から離脱し、最低限の努力だけで仕事を済ませようとする傾向も強まります。
一方、支援的環境では、従業員は安定的で予測可能な報酬を期待できます。このような環境では、協力することで全員が利益を得られると感じるため、敵対的行動は減少し、職務満足度や組織への忠誠心が高まります。
この研究が示しているのは、職場の政治的環境は敵対的行動や心理的離脱という形で、従業員の行動に悪影響を与えるということです。組織内政治が蔓延すると、従業員は互いに協力するよりも敵対することを選び、組織全体の機能が低下し得ます。
組織内政治の知覚は中間管理職で最も高い
組織内政治が職場での攻撃的行動や敵対的行動を引き起こすことを見てきましたが、組織内のすべての人が同じように政治を認識するわけではありません。組織内の立場によって、政治の認識度は異なることが分かっています。中間管理職は他の階層よりも組織内政治を強く認識する傾向があります。
アメリカの政府系研究開発機関に勤務する従業員1641名を対象にした調査では、組織内政治の知覚に影響を与える要因や、政治認識がもたらす結果について分析されています[3]。この研究では、組織的要因(意思決定への関与、役割の明確性など)、個人的要因(年齢、性別、学歴など)、職場環境要因(キャリア開発の機会、報酬の公平性など)が政治認識にどう影響するかが調べられました。
興味深い発見の一つは、組織内の階層と政治認識の関係でした。調査では、従業員を「一般職員」「中間管理職」「上級管理職」の3つのグループに分け、それぞれの政治認識を比較しました。すると、中間管理職が最も強く組織内政治を認識していることが明らかになりました。
なぜ中間管理職は政治をより強く認識するのでしょうか。研究者たちはこれを「サンドイッチ状態」と説明しています。中間管理職は上からの圧力と下からの要求の間で板挟みになりやすい立場にあります。彼ら彼女らは上級管理職の方針を実行する責任がある一方で、一般職員の要望や不満にも対応しなければなりません。
また、中間管理職は組織の意思決定プロセスに部分的にしか関われないことが多いかもしれません。重要な決定に関与はできても、最終決定権は持っていないということです。このような「限定的な影響力」が政治的駆け引きの必要性を感じさせます。
中間管理職の中には、昇進競争の渦中にあることも多く、限られたポストを巡って互いに競争する状況に置かれている人もいます。このような競争環境は政治的行動を促す要因となります。
研究では、組織内政治の知覚を低減させる要因も明らかになりました。例えば、役割と責任が明確であること、意思決定プロセスに参加できること、部門間の協力が良好であること、報酬や評価が公平であることなどが、政治認識を弱める効果を持っていました。
「部門間の協力」と「役割の明確化」は政治認識に大きな影響を与えていました。部門同士が協力的な関係にある職場では、政治的な駆け引きが少なくなります。また、自分の役割や責任が明確に定義されている場合も、政治を認識する度合いが低くなります。
一方で、組織的要因の中で唯一「アファーマティブ・アクションの強調」だけは、政治認識を高める方向に作用していました。こうした施策が組織内の公平性に関する疑問を引き起こす可能性があるためと考えられています。
個人要因では、マイノリティの従業員は、非マイノリティよりも組織内政治を強く認識していました。少数派が職場で不平等な扱いを受けやすいという現実を反映しているのかもしれません。
組織内政治の知覚がもたらす結果としては、イノベーションへの支持の低下が確認されました。政治的な環境だと感じている従業員は、新しいアイデアや変化に対して消極的になります。政治的な環境では失敗のリスクが高く評価される可能性があるため、従業員が保守的な行動を選びやすくなります。
この研究から言えるのは、組織内政治の知覚は従業員の立場によって異なり、特に中間管理職が敏感に政治を認識するということです。また、部門間の協力や役割の明確化など、職場環境の要素が政治認識に影響することも分かりました。
組織内政治は公務員の怠慢を招く
組織内政治は職場での攻撃的行動や敵対的行動を引き起こし、特に中間管理職がその影響を受けやすいことが分かりました。しかし、組織内政治の影響はそれだけではありません。特に公的セクター(公務員)においては、組織内政治が「怠慢行動」という問題を引き起こすことが研究によって明らかになっています。
イスラエルの自治体で働く公務員303名を対象にした調査では、組織内政治の知覚が従業員の態度や行動にどのような影響を与えるかが調べられました[4]。この研究の特徴は、従業員の自己報告だけでなく、6ヶ月後にその上司による業績評価も収集した点にあります。これによって、政治認識と実際の業績との関係も分析することができました。
調査の結果、組織内政治の知覚は予想通り、職務満足度や組織への忠誠心(組織コミットメント)と負の関係があり、離職意図とは正の関係があることが確認されました。職場が政治的だと感じている公務員ほど、仕事に満足せず、組織への忠誠心も低く、辞めたいと思う傾向が強かったのです。
注目すべき発見は、組織内政治の知覚と「怠慢行動」との強い関連性でした。怠慢行動とは、仕事への努力を減らし、問題から逃げ出したり、無視したりする行動を指します。例えば、締め切りを守らない、会議に遅刻や欠席をする、仕事の質を落とす、問題を放置するといった行動が含まれます。
研究では、組織内政治の知覚が高い公務員ほど、このような怠慢行動を取ることが示されました。しかも、組織内政治の知覚は、個人属性や他の仕事態度を考慮した後でも、怠慢行動を予測する独自の力を持っていました。この結果は、組織内政治が公務員の行動に直接的かつ強い影響を与えることを意味しています。
なぜ公務員は組織内政治に対して怠慢行動で反応するのでしょうか。研究者たちは、これを職場の安定性と関連づけて説明しています。公的セクターの仕事は一般的に安定しており、簡単に解雇されることはありません。そのため、公務員は政治的な環境に不満を感じても、積極的に職場を離れる(離職する)よりも、消極的に怠慢行動を取る傾向があります。
公的セクターでは昇進や報酬の機会が限られていることも、怠慢行動を促進する要因となっているのかもしれません。政治的な環境で自分の努力が正当に評価されないと感じた公務員は、「どうせ頑張っても報われない」と考え、仕事への努力を減らす選択をします。
研究では、組織内政治の知覚と業績との関係も調査されました。予想通り、組織内政治の知覚が高い公務員ほど、上司による業績評価が低い傾向が見られました。政治的な環境が実際の業績にも悪影響を与えるということです。
脚注
[1] Vigoda, E. (2002). Stress-related aftermaths to workplace politics: The relationships among politics, job distress, and aggressive behavior in organizations. Journal of Organizational Behavior, 23(5), 571-591.
[2] Cropanzano, R., Howes, J. C., Grandey, A. A., and Toth, P. (1997). The relationship of organizational politics and support to work behaviors, attitudes, and stress. Journal of Organizational Behavior, 18(2), 159-180.
[3] Parker, C. P., Dipboye, R. L., and Jackson, S. L. (1995). Perceptions of organizational politics: An investigation of antecedents and consequences. Journal of Management, 21(5), 891-912.
[4] Vigoda, E. (2000). Organizational politics, job attitudes, and work outcomes: Exploration and implications for the public sector. Journal of Vocational Behavior, 57(3), 326-347.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。