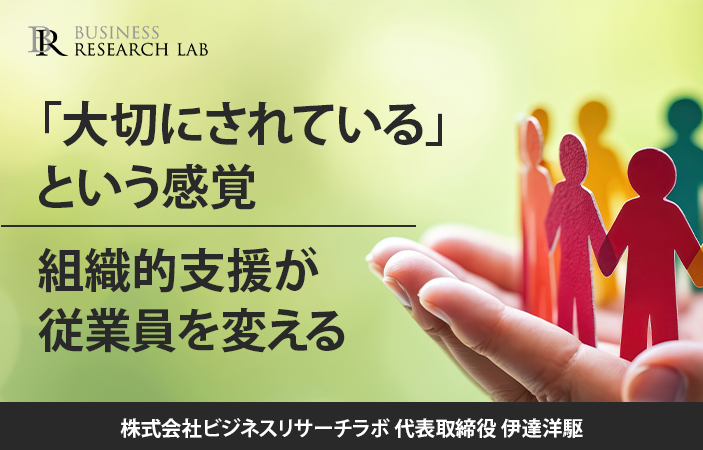2025年7月29日
「大切にされている」という感覚:組織的支援が従業員を変える
職場で働く人にとって、自分が所属する組織からどれほど大切にされているかという感覚は、日々の業務や長期的なキャリアに関わります。組織が皆さんの貢献を評価し、皆さんの幸福に配慮していると感じられるとき、どのような気持ちになるでしょうか。おそらく多くの人は、そのような組織に対してより強い愛着を抱くことでしょう。
このような「組織が自分を支援してくれている」という従業員の認識は、学術的には「知覚された組織的支援(Perceived Organizational Support:POS)」と呼ばれ、活発に研究されてきました(以降、組織的支援)。組織的支援は、好感度や満足度とは異なる独自の概念であり、従業員の行動や態度に多面的な作用をもたらします。
本コラムでは、組織的支援という概念がどのように形成され、従業員の心理や行動にどのような変化をもたらすのかについて、これまでの学術研究の知見を基に解説します。組織的支援が従業員の満足度、欠勤率、組織への愛着、そして離職に至るまでどのように関わっているのかを明らかにしていきます。
組織的支援は満足度と強く関連するが独立概念
あなたの貢献は組織に評価されていますか。組織はあなたの福祉を考えていると感じますか。このような問いかけに対する従業員の認識が、組織的支援です。この組織的支援という概念は、職場における他の心理的要素とどのように区別されるのでしょうか。
組織的支援を測定する尺度「知覚された組織的支援調査票(SPOS)」の妥当性を検証する研究が行われています[1]。この研究では、多国籍企業に勤める330名の従業員を対象に、組織的支援と他の関連概念との弁別性を調査しています。
調査に参加した従業員の平均年齢は47歳、組織での平均勤続年数は22年以上と、豊富な職場経験を持つ人々でした。研究者たちは、組織的支援の測定尺度が本当に独自の概念を捉えているのか、それとも職務満足度や組織コミットメントといった既存の概念と区別できないものなのかを統計的手法で検討しました。
分析の結果、組織的支援は「情緒的コミットメント」(組織への感情的な愛着)や「存続的コミットメント」(組織を辞めることで生じる損失を避けるための理性的な判断)とは明確に区別できる概念であることが確認されました。特に、組織的支援と存続的コミットメントとの関連性は低く、両者は全く異なる概念であることが分かりました。
一方で、組織的支援と職務満足度の間には強い関連性が見られました。特に「上司への満足度」との関連が強かったのです。このことから、組織的支援と満足度は互いに密接に関わり合っていると言えます。しかし、概念的には区別できるものだと考えられています。
その理由として、研究者たちは次のような違いを指摘しています。組織的支援は、組織を一つの人格のように捉え、「その組織が自分にどのような態度を示しているか」という認知的な判断です。これに対して、満足度は職務や職場環境に対する感情的な反応です。例えば、「この仕事は楽しい」という感情と、「組織は私の貢献を評価している」という認識は、関連はしていても別の心理現象です。
この研究が明らかにしたことは、従業員が組織からの支援をどう感じているかという要素が、満足感とは異なる独自の心理的要因であるということです。職場の人間関係や業務内容に満足していても、組織全体として自分が大切にされていると感じられなければ、その従業員の行動や態度は異なるものになる可能性があります。
組織的支援という概念を理解することの価値は、それが従業員の行動や態度に独自の作用をもたらす可能性がある点です。職場での満足度を高めることも確かに大切ですが、それだけでは捉えきれない「組織と従業員の関係性」を考える上で、組織的支援という視点は洞察を提供してくれます。
組織的支援は欠勤を減らし、返報意識を高める
自分が組織から大切にされていると感じると、従業員はどう反応するのでしょうか。この問いに対する実証的な答えを探究した先駆的研究があります。組織的支援の概念を学術的に定義し、それが従業員の行動にどのような変化をもたらすかを調査しました[2]。
この研究では、社会的交換理論という理論枠組みが用いられています。これは、人間関係において互恵性の原理が働くという考え方です。「誰かから良くしてもらったら、それに応えて何か返したいと感じる」という心理です。研究者たちは、これが組織と従業員の関係にも当てはまると考えました。
研究は二つの部分から構成されています。最初の調査では、9つの異なる組織に所属する361名の従業員を対象に、組織的支援を測定する36項目の尺度を開発しました。分析の結果、従業員は組織からの支援を一貫した全体的な認識として形成していることが確認されました。「組織は自分の貢献を評価している」「組織は自分の福祉を気にかけている」といった様々な側面に対する認識が、一つの「組織的支援」という全体像を形作っているのです。
二つ目の調査では、私立高校の教師97名を対象に、組織的支援が実際の行動にどう影響するかを検証しました。教師たちの組織的支援を測定し、年間の欠勤データと照らし合わせました。加えて、「交換イデオロギー」という考え方も調査しました。これは「自分の仕事への努力は、組織からの待遇に応じて変わるべきだ」と考える強さを表す概念です。
分析の結果、組織的支援を強く感じている教師ほど欠勤が少ないという関連が見られました。そして、この関連は「交換イデオロギー」の強さによって変化しました。交換イデオロギーが強い教師(「組織からの待遇に応じて自分の努力も変わるべきだ」と強く考える人)ほど、組織的支援と欠勤の負の関連が強く現れました。
このことは、組織的支援が欠勤を減らす効果は、従業員がどれほど「組織との関係を交換的に捉えているか」によって変わることを表しています。言い換えれば、「組織が自分に良くしてくれたから、自分も組織に応えたい」という返報意識の強い従業員ほど、組織的支援を感じると欠勤が減少する傾向があるのです。
この発見は、組織的支援が従業員の満足感を高めるだけでなく、実際の行動(この場合は欠勤の減少)にも変化をもたらすことを示した点で意義深いでしょう。組織の視点から見れば、従業員が支援されていると感じられる環境を整えることで、欠勤率の低下という実質的なメリットが得られることが実証されたのです。
またこの研究は、個人差(交換イデオロギーの強さ)が組織的支援の効果に関わることも意味しています。すべての従業員が同じように反応するわけではなく、個人の価値観や考え方によって組織的支援の受け止め方や、それに応えようとする意識の強さが異なります。
組織的支援は組織への愛着を高め、上司支援とは異なる
職場における人間関係は多層的です。従業員は組織全体との関係と同時に、直属の上司との関係も形成しています。これらの異なる関係性は、従業員の行動や態度にどのような差異をもたらすのでしょうか。
従業員が形成する二種類の社会的交換関係に着目した研究を取り上げましょう[3]。一つは、これまで議論してきた「組織的支援」で、これは従業員と組織全体との関係です。もう一つは「LMX(Leader-member exchange)」で、これは従業員と直属の上司との関係を指します。これら二つの関係性が、従業員のどのような行動や態度と結びつくのかを検証しました。
調査は米国南部の病院で行われ、102名の非管理職従業員とその直属の上司26名が参加しました。従業員自身が組織的支援、LMX、組織コミットメントを評価し、直属の上司が従業員の組織市民行動(職務上の要求を超えた自発的な貢献行動)と役割内行動(正規の職務として求められる行動)を評価する形で実施されました。
分析の結果、組織的支援とLMXが従業員の異なる側面に作用することが明らかになりました。組織的支援は組織への情緒的コミットメント(感情的な愛着)と強く関連していましたが、LMXは上司や同僚に向けた組織市民行動や、役割内行動と強く関連していました。組織全体からの支援を感じると「組織への愛着」が高まり、上司との良好な関係は「職場での行動の質」に反映されるということです。
この研究の興味深いのは、従業員が「恩返し」をする相手が異なる点です。組織から支援されていると感じた従業員は、その恩返しとして組織への愛着を深めます。一方、上司との良好な関係を持つ従業員は、その恩返しとして上司が評価するような行動(組織市民行動や役割内の優れたパフォーマンス)を示します。
例えば、組織が従業員の福利厚生に力を入れていると感じた従業員は「この組織で長く働きたい」という組織コミットメントを高めるでしょう。一方、上司が自分を信頼し、支援してくれると感じた従業員は「上司の期待に応えたい」と考え、職務を超えた自発的な貢献をしたり、与えられた仕事をより良く遂行したりする可能性が高まります。
このように、組織的支援と上司支援は、似ているようで異なる効果をもたらします。組織の階層構造が強い職場では、役割内行動(日常の業務パフォーマンス)は上司との関係性に強く影響されるかもしれません。上司が直接的な評価者であり、日々の業務の指示者であることを考えれば、これは理解できる結果でしょう。
ここで強調すべきは、組織的支援とLMXが互いに排他的ではないということです。理想的には、両方を高めることで従業員の多面的な態度や行動にプラスの作用をもたらすことができます。しかし、限られたリソースの中でどこに重点を置くかを考える際には、こうした異なる効果の理解が役立つでしょう。
組織的支援は人事施策を通じて離職を防ぐ
人材の確保は多くの組織にとって永続的な課題です。優秀な従業員の離職は、知識やスキルの喪失、採用・育成コストの増加など、組織にとって損失となります。どのようにして従業員の離職を防ぐことができるのでしょうか。ある研究が、この問いに対して組織的支援の視点から知見を提供しています[4]。
この研究では、支援的な人事施策が従業員の離職にどのように関わるのかを、組織的支援を媒介とするモデルで説明しました。「意思決定への参加」「報酬の公正性」「成長機会」といった支援的な人事施策が組織的支援を高め、組織的支援が組織コミットメントと職務満足度を向上させ、それによって離職意図が減少し、最終的には実際の離職行動が抑制されると考えました。
この仮説を検証するため、彼らは二つの異なる職業集団を対象とした調査を実施しました。一つ目のサンプルは米国南東部のデパートに勤務する販売員215名、二つ目のサンプルは全国規模の保険会社の保険エージェント197名でした。両グループともに時間をおいて複数回の調査を行い、実際の離職データを収集しています。
調査の結果、支援的な人事施策(意思決定への参加、報酬の公正性、成長機会)は組織的支援を高め、組織的支援は組織コミットメントと職務満足度を向上させ、それらは離職意図を減少させ、離職意図は実際の離職行動を予測するという仮説モデル全体が支持されました。支援的な人事施策は直接的に離職を防ぐのではなく、組織的支援を通じて間接的に作用することが明らかになったのです。
デパートの販売員と保険エージェントという異なる職業集団で同様の結果が得られたことは重要です。両者は職種や労働環境、さらには離職率も異なります。それにもかかわらず、支援的人事施策→組織的支援→組織コミットメント・職務満足度→離職意図→離職行動という一連のプロセスがともに確認されました。
この結果は、組織的支援が離職防止において一貫して機能する可能性を示唆しています。職場環境や離職率の高低にかかわらず、従業員が組織から支援されていると感じることが、離職を防ぐ鍵となるのです。
もう一つ重要なのは、人事施策が「支援的である」と従業員に認識されることの重要性です。組織がいくら支援的だと自負する人事施策を実施しても、従業員がそれを本当に支援的だと感じなければ組織的支援は高まらず、離職防止の効果も限定的となります。例えば、成長機会を提供するための研修制度を整えても、それが従業員のニーズや希望に合っていなかったり、参加するための時間的配慮がなされていなかったりすれば、従業員は支援とは感じないかもしれません。
離職率を低減させたい組織は、人事施策を整備するだけでなく、それらの施策が従業員に「支援的である」と認識されるための工夫が必要になります。それには、従業員の意見を取り入れた制度設計や、施策の背景にある組織の意図を伝えることなどが含まれるでしょう。
脚注
[1] Shore, L. M., and Tetrick, L. E. (1991). A construct validity study of the Survey of Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 76(5), 637-643.
[2] Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., and Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 71(3), 500-507.
[3] Settoon, R. P., Bennett, N., and Liden, R. C. (1996). Social exchange in organizations: Perceived organizational support, leader-member exchange, and employee reciprocity. Journal of Applied Psychology, 81(3), 219-227.
[4] Allen, D. G., Shore, L. M., and Griffeth, R. W. (2003). The role of perceived organizational support and supportive human resource practices in the turnover process. Journal of Management, 29(1), 99-118.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。