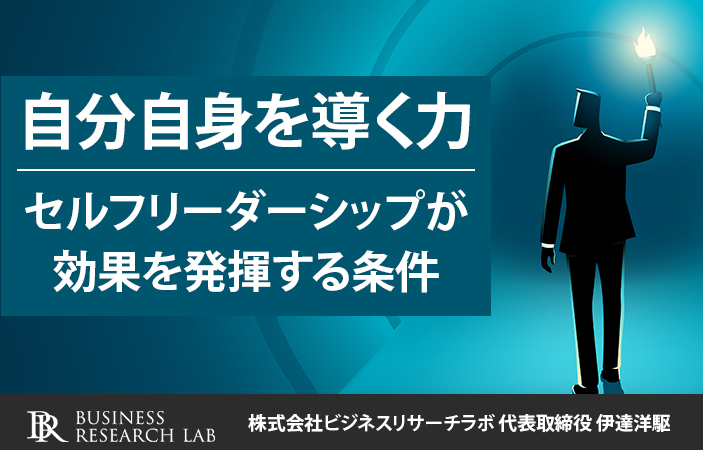2025年7月28日
自分自身を導く力:セルフリーダーシップが効果を発揮する条件
組織の成功には多様なリーダーシップの形が必要です。そのような中、近年、「セルフリーダーシップ」という概念が着目されています。セルフリーダーシップとは、自分自身を動機づけ、自らの行動や思考を管理することで目標達成に向かう一連の戦略を指します。具体的には、自己目標設定、自己観察、自己報酬といった「行動に焦点を当てた戦略」、仕事自体の楽しさや満足感に集中する「自然報酬戦略」、そしてポジティブな自己対話や成功イメージを描く「建設的思考パターン戦略」などが含まれます。
セルフリーダーシップは従来の管理手法を補完する要素として認識されています。多くの研究が示すように、セルフリーダーシップは個人の生産性向上や職務満足度の増加、パフォーマンスの改善など、様々な良い効果をもたらすことができます。しかし、セルフリーダーシップが常に同じように機能するわけではなく、その効果は状況や個人特性によって変わることも分かってきました。
本コラムでは、セルフリーダーシップが効果を発揮する条件について探ります。個人主義文化との親和性、職務自律性との関係、個人の自律性欲求の影響、そしてバーチャル環境での有効性について、研究知見をもとに解説します。
セルフリーダーシップは個人主義文化で効果が高い
セルフリーダーシップという概念は、過去20年以上にわたって研究されてきました。個人が自らを動機づけ、自己管理を行うための戦略ですが、その効果は文化的背景によって異なることが分かってきました。
2021年に発表された大規模なメタ分析の研究では、セルフリーダーシップの効果が文化的要因によってどのように変わるかが検討されています[1]。この研究では、2020年までに発表された58の独立した研究データを集め、合計22,406名の参加者から得られた結果を統合・分析しました。その結果、セルフリーダーシップは全体として職務成果に肯定的な関連があることが確認されましたが、その効果の大きさは文化によって差があることが明らかになりました。
とりわけ個人主義的な文化圏(北米や西ヨーロッパなど)において、セルフリーダーシップはより高い効果を示しました。個人主義文化では、自律性や個人の選択、自己表現が尊重されます。そのため、「自分で自分を導く」というセルフリーダーシップの基本理念が文化的価値観と合致しやすいのです。
一方、集団主義的な文化圏(アジアの多くの国々など)では、セルフリーダーシップの効果は相対的に小さいことが分かりました。集団主義文化では、集団の調和や上下関係が重んじられます。そのような環境では、個人が自立的に行動することよりも、集団の決定に従うことが期待される場合が多いため、セルフリーダーシップの実践が文化的規範と衝突する可能性があります。
この研究では、セルフリーダーシップの各戦略ごとに異なる効果も確認されました。「行動に焦点を当てた戦略」は特に職務パフォーマンスや生産性に関連していました。例えば、自分で目標を設定し、その達成度を自己監視するといった行動は、具体的な業務遂行能力の向上につながりやすいようです。
「自然報酬戦略」は仕事満足度や内発的動機づけといった感情的・動機づけ的成果と強く結びついていました。仕事自体の楽しさや魅力に意識を向ける戦略は、仕事へのポジティブな感情を育むのに効果的だと言えます。
「建設的な思考パターン戦略」は自己効力感やストレス管理といった心理的成果との関連が強く見られました。自分自身に対するポジティブな対話や、成功のイメージを描くなどの認知戦略が、心理的な強さやレジリエンスを高めるのに役立つことが示されています。
セルフリーダーシップは職務自律性が高いと有効
セルフリーダーシップの効果を左右する条件として、「職務自律性」が挙げられます。職務自律性とは、仕事の進め方や意思決定において、個人がどれだけ自由裁量を持っているかを表します。この職務自律性とセルフリーダーシップの関係について、中国の組織環境を対象とした研究が行われました[2]。
この研究では、香港と中国本土の企業9社から407組の上司と部下のペアを対象にデータが収集されました。調査では、セルフリーダーシップと職務自律性、そして職務成果の関係が分析されました。職務成果としては、上司によるパフォーマンス評価、客観的な職務パフォーマンス(保険販売員の場合は販売実績)、職務満足度の3つが測定されました。
調査の結果、セルフリーダーシップは上司によるパフォーマンス評価と職務満足度に肯定的な関連があることが分かりました。しかし、これらの関係性は職務自律性のレベルによって変化することが判明しました。職務自律性が高い環境では、セルフリーダーシップと成果の関係が強まり、反対に職務自律性が低い環境では、その関係性が弱まりました。
この結果は、セルフリーダーシップが機能するためには、それを発揮できる環境が重要であることを示しています。どれだけ優れたセルフリーダーシップのスキルを持っていても、仕事の進め方が厳格に決められていたり、細かな指示に従ったりするだけの環境では、その効果を十分に発揮することができません。
一方で、職務自律性が高い環境では、セルフリーダーシップの各種戦略を実践する機会が多く、それが成果につながりやすいと考えられます。例えば、自分でスケジュールを管理したり、仕事の優先順位を決めたりする自由があれば、行動焦点型のセルフリーダーシップ戦略が活きてきます。また、自分の裁量で仕事のやり方を工夫できる環境では、仕事自体を楽しむ「自然報酬戦略」を実践しやすくなります。
この研究で特に価値があるのは、西洋で発展してきたセルフリーダーシップの概念が、中国という非西洋文化圏においても一定の有効性を持つことを示した点です。先ほど見たように、セルフリーダーシップは個人主義文化で効果が高い傾向がありますが、この研究は集団主義的な文化圏でも、適切な条件(職務自律性の高さ)があれば効果を発揮することを実証しています。
職務自律性がセルフリーダーシップの効果を高める理由については、「状況強度理論」によって説明できます。この理論によれば、状況の「強さ」によって個人の特性や行動パターンの発現が左右されます。強い状況(規則やルールが厳格で行動の自由度が低い環境)では、個人の特性による差が出にくく、弱い状況(自由度が高い環境)では個人差が出やすくなります。
職務自律性の高い職場は「弱い状況」に当たり、個人のセルフリーダーシップ能力が発揮される余地が大きくなります。逆に、職務自律性の低い職場は「強い状況」となり、どんなに優れたセルフリーダーシップのスキルを持っていても、それを発揮する機会が制限されてしまいます。
この研究では客観的職務パフォーマンス(保険販売実績)とセルフリーダーシップの直接的な関連は弱いことも分かりました。販売実績には個人がコントロールできない外的要因(市場状況や景気動向など)の影響が大きいためでしょう。しかし、職務自律性が高い場合には、セルフリーダーシップが販売実績にも肯定的な関連を示しました。これは、自律性の高い環境では、セルフリーダーシップを発揮して外部環境の変化に柔軟に対応できるためかもしれません。
セルフリーダーシップの効果を最大化するためには、セルフリーダーシップのトレーニングを提供するだけでなく、職務自律性を高める環境づくりが必要です。例えば、業務のプロセスや手順を細かく規定するのではなく、成果に焦点を当てた評価システムを導入したり、業務の時間や場所に柔軟性を持たせたりすることが考えられます。
セルフリーダーシップは自律性欲求で効果が変わる
セルフリーダーシップの効果を考える上で見逃せないのが「個人の特性」です。同じ環境であっても、人によってセルフリーダーシップの実践度や効果は異なります。その中でも「自律性欲求」という個人特性に注目してみましょう。自律性欲求とは、仕事において自発的に行動し、自分で決定したいという内的な欲求の強さを指します。
米国の防衛関連企業を対象とした研究では、リーダーシップスタイルがフォロワー(部下)のセルフリーダーシップ行動に及ぼす影響において、この自律性欲求が調整機能を果たすことが明らかになりました[3]。この研究は10週間にわたる縦断的調査で、初回調査時は75チーム・404名、2回目の調査では72チーム・313名からデータが収集されました。
研究では、リーダーシップを「エンパワリング型」と「指示型」の2つのタイプに分類しました。エンパワリング型リーダーシップは、部下の自主性や自律性を促し、自ら課題を解決し責任を持つよう促進するスタイルです。一方、指示型リーダーシップは伝統的な指示命令型で、リーダーが指示を与え、部下はそれに従うことが求められるスタイルです。
調査の結果、エンパワリング型リーダーシップは、自律性欲求が高いフォロワーのセルフリーダーシップ行動を促進することが分かりました。自分で決めたい、自律的に行動したいという欲求が強い人ほど、上司からの権限委譲や励ましによってセルフリーダーシップを発揮しやすくなるのです。
反対に、指示型リーダーシップは、自律性欲求が高いフォロワーのセルフリーダーシップ行動を抑制することが判明しました。自律性欲求が強い人は、細かな指示や管理を受けると、むしろセルフリーダーシップを発揮しにくくなります。
この結果から見えてくるのは、「全ての従業員がエンパワメントを望んでいるわけではない」ということです。自律性欲求の低い人にとっては、エンパワリング型リーダーシップが必ずしも効果的とは限りません。むしろ、明確な指示を与える指示型リーダーシップの方が、そうした人々には合っている可能性があります。
自律性欲求とリーダーシップスタイルの相互作用が重要である理由は、心理的な適合性にあります。自律性欲求の高い人は、自分で考え行動する機会を求めています。そのような人に対して上司が過度に細かい指示を与えると、自己決定感が損なわれ、モチベーションや自発的な行動が低下します。逆に、自律性欲求の低い人は、自分で判断するよりも明確な指示に従う方を好みます。そのような人に対して「自分で考えなさい」と言っても、それはかえってストレスになることもあるでしょう。
ただし、自律性欲求は固定的なものではなく、時間とともに変化する可能性もあります。例えば、新入社員や新しい職務に就いたばかりの社員は、まだ不慣れなため自律性欲求が一時的に低下することがあるかもしれません。しかし、経験を積んで自信がついてくれば、より自律的に行動したいという欲求が高まる可能性もあります。
セルフリーダーシップはバーチャル環境で効果を増す
近年、テレワークの普及により、物理的に離れた環境で仕事をする「バーチャルな働き方」が増えてきています。このようなバーチャル環境において、セルフリーダーシップはどのような役割を果たすのでしょうか。
この問いに答えるため、23企業、129チーム、681名の従業員(116名のリーダー含む)を対象とした研究が行われました[4]。この研究では、セルフリーダーシップと変革型リーダーシップの関係性を検討し、さらに「バーチャルな仕事環境」が両者の関係をどのように調整するのかを分析しました。
セルフリーダーシップと変革型リーダーシップの関係について、3つの競合するモデルが比較検討されました。その結果、「変革型リーダーシップ → セルフリーダーシップ → モチベーション → パフォーマンスおよび情緒的コミットメント」というプロセスが最もうまく当てはまることが分かりました。変革型リーダーシップはセルフリーダーシップを高め、それが従業員のモチベーションを媒介し、最終的にパフォーマンスと組織へのコミットメントにつながるというプロセスが実証されたのです。
興味深いのは、バーチャル環境の影響です。研究では「バーチャル性」を、コミュニケーション媒体(対面かデジタルか)と地理的距離の組み合わせで測定しました。例えば、同じオフィスで直接会話するのが最もバーチャル性が低く、異なる国や地域にいてオンラインツールだけでコミュニケーションをとる場合が最もバーチャル性が高いということになります。
分析の結果、次の2つの発見がありました。
- リーダーがバーチャルな環境(物理的に離れた場所)にいるほど、変革型リーダーシップがセルフリーダーシップに与える影響は弱まりました。
- チームメンバーがバーチャル環境で働くほど、セルフリーダーシップがモチベーションに与える影響は強まりました。
これらの結果から読み取れるのは、バーチャル環境ではセルフリーダーシップの重要性が増すということです。物理的に離れた環境では、リーダーの直接的な影響力が弱まりますが、その代わりに個人のセルフリーダーシップがモチベーションに与える影響が強くなります。テレワークなどのバーチャルな環境では、上司の指示や監督に頼るよりも、自分自身でモチベーションを維持し、仕事を管理する能力が成功の鍵を握るのです。
これは直感的にも理解できる結果です。オフィスで対面している状況では、上司は部下の様子を観察し、必要なときに声をかけたり指導したりすることができます。また、同僚との雑談や組織文化の空気感など、非公式なコミュニケーションを通じて動機づけられることも多いでしょう。しかし、在宅勤務などのバーチャル環境では、そうした外部からの刺激や管理が減少します。その分、自分で自分を動機づけ、管理する能力、すなわちセルフリーダーシップの重要性が高まります。
脚注
[1] Harari, M. B., Williams, E. A., Castro, S. L., and Brant, K. K. (2021). Self-leadership: A meta-analysis of over two decades of research. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 94(4), 890-923.
[2] Ho, J., and Nesbit, P. L. (2014). Self-leadership in a Chinese context: Work outcomes and the moderating role of job autonomy. Group & Organization Management, 39(4), 389-415.
[3] Yun, S., Cox, J., and Sims Jr, H. P. (2006). The forgotten follower: A contingency model of leadership and follower self-leadership. Journal of Managerial Psychology, 21(4), 374-388.
[4] Andressen, P., Konradt, U., and Neck, C. P. (2012). The relation between self-leadership and transformational leadership: Competing models and the moderating role of virtuality. *Journal of Leadership & Organizational Studies, 19(1), 68-82.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。