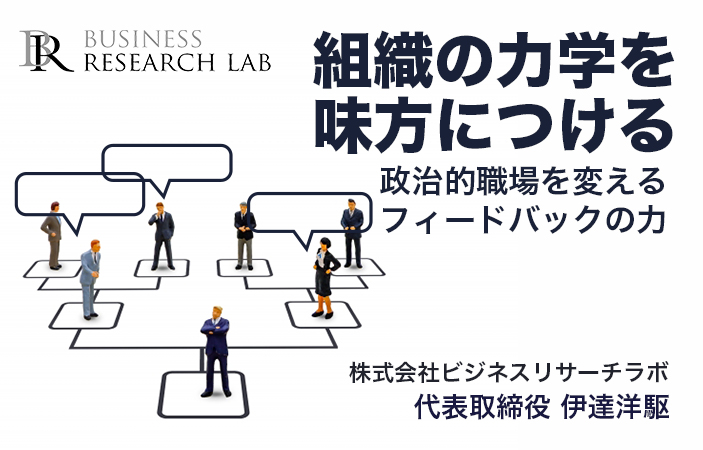2025年7月25日
組織の力学を味方につける:政治的職場を変えるフィードバックの力
組織で働く人は、日々さまざまな人間関係の中で自分の目標を達成しようと努めています。しかし、組織内で目標を達成するためには、自分の仕事をきちんとこなすだけでは不十分な場合があります。組織には公式のルールや手続きだけでは説明できない「政治的な側面」が存在するからです。
組織内政治とは、自分自身や自分のグループの利益を守ったり拡大したりするために行使される非公式な影響力を指します。人によっては「政治」という言葉にネガティブな印象を持つかもしれませんが、組織内政治はある意味で避けて通れない現実です。人間が集まれば、そこには異なる利害関係や権力構造が生まれるからです。
この組織内政治に対する認識や向き合い方が、職場での成功や満足感に関わってくることが、近年の研究で明らかになってきました。ある人は組織内政治に振り回されてストレスを感じる一方で、別の人はそれをうまく活用して自分の仕事を円滑に進めていきます。この違いはどこから生まれるのでしょうか。
本コラムでは、組織内政治と人々の関わりについて、学術研究の知見をもとに検討します。どのような特性を持つ人が政治的な職場でより効果的に働けるのか、地位によって用いられる政治的な戦術はどう変わるのか、政治的スキルとはどのようなものか、そしてフィードバックがどのように組織内政治の知覚に影響するのか。これらの問いを一つずつ紐解きながら、組織内政治という現象への理解を深めていきましょう。
政治的な職場ほど誠実性が効果的
組織内政治が存在する職場では、どのような性格特性を持つ人がより効果的に働くことができるのでしょうか。この疑問に答えるため、「誠実性」という性格特性に焦点を当てた研究を紹介しましょう[1]。
誠実性とは、自制心があり、責任感が強く、勤勉で計画的に行動する傾向を指します。この特性は一般的に職務遂行能力と関連することが知られていますが、組織内政治がこの関係性をどう変えるかを検証しました。
この研究では、4つの異なる業種(流通業、製造業、テレマーケティング業、ソフトウェア開発)から合計813名の従業員を対象に調査を行いました。従業員たちは組織内政治の知覚度と自身の誠実性に関する質問に答え、その直属の上司が職務遂行能力を評価しました。
その結果、誠実性と職務遂行能力の間には予想通り正の相関が見られました。誠実性が高い人ほど、一般的に仕事のパフォーマンスも高い傾向があったのです。しかし、興味深いのは組織内政治の知覚が高い環境における結果です。
組織内政治の知覚が中程度から高い環境においては、誠実性が高い従業員ほど職務遂行能力も高いという関係が強まりました。一方で、組織内政治の知覚が低い環境では、誠実性の高さは職務遂行能力にほとんど影響しませんでした。
この結果は何を意味するのでしょうか。政治的な職場では、誠実性の高い人がより効果的に働けるということです。誠実性の高い人は、計画的で規律正しく、目標に向かって粘り強く取り組む特性があります。こうした特性は、組織内政治が存在する複雑な環境でも、一貫した行動を維持し、混乱に惑わされることなく職務を遂行するのでしょう。
例えば、同じ仕事をする二人の従業員がいるとします。一人は誠実性が高く、もう一人は誠実性が低いとしましょう。政治的でない職場では、両者のパフォーマンスに大きな差は見られないかもしれません。しかし、上司の気まぐれな判断や同僚間の駆け引きが日常的に行われる政治的な職場では、誠実性の高い人は自分の仕事に集中し、計画通りに進めることができます。一方、誠実性の低い人は組織内政治の動向に振り回され、一貫した仕事ぶりを維持するのが難しくなる可能性があります。
地位によって政治的な戦術が変わる
組織の中で人々はどのように他者に影響を与えようとするのでしょうか。また、上司、同僚、部下といった異なる立場の人に対して、私たちは異なる影響戦術を使い分けているのでしょうか。
従来の研究では、主に上司から部下への影響力に焦点が当てられていました。しかし実際の組織では、同僚間の影響力や部下から上司への影響力も行使されています。ある研究が、組織内の様々な方向の影響関係に着目し、人々が実際にどのような戦術を用いているかを明らかにしました[2]。
この研究は二段階で行われました。第一段階では、165名の管理職を対象に、職場で実際に他者に影響を与えようとした経験について記述してもらいました。上司、同僚、部下のそれぞれに対する影響戦術が分析され、370個の具体的な行動が抽出されました。
第二段階では、最初の調査で得られた影響戦術を58項目に整理し、754名のMBA学生を対象に質問紙調査を実施しました。この結果、組織内で用いられる影響戦術として次の8つの因子が特定されました。
- 自己主張:要求や命令、期限設定などの直接的な戦術
- 迎合:謙虚な態度を示したり、相手を褒めたりする戦術
- 合理的説得:論理やデータを用いて説得する戦術
- 制裁:昇給の抑制や昇進の停止などを示唆する戦術
- 交換:互恵的な提案や個人的な援助を申し出る戦術
- 上位への訴え:上層部に公式・非公式に訴える戦術
- 妨害:協力を停止したり、仕事を遅延させたりする戦術
- 連合形成:同僚や部下の支持を得る戦術
これらの戦術の使用は相手の地位によって異なることが分かりました。上司に影響を与える際には、合理的説得や迎合という戦術が多く用いられました。例えば、データや事実に基づいて自分の意見を説明したり、上司に対して敬意を表しながら提案したりするといった方法です。これは上司という立場を尊重しつつ、自分の考えを通そうとする戦略と言えます。
一方、部下に対しては自己主張や制裁といった、より直接的で強制力のある戦術が使われました。例えば、明確な指示を出したり、従わなかった場合の不利益を示唆したりするといった方法です。これは、立場上の権限を活用した影響力の行使と言えます。
同僚に対しては、交換や連合形成といった互恵的な戦術が多く用いられました。例えば、「今回私があなたを手伝うから、次回はあなたが私を手伝って」というような取引や、「一緒に上司に提案しよう」というような協力関係の構築などです。
また、影響を与える目的によっても使用される戦術が異なることも明らかになりました。例えば、個人的な援助を求める場合は迎合戦術が、仕事の割り当てを変えてもらう場合は自己主張戦術が、新しいアイデアを提案する際は合理的説得が多く用いられていました。
この研究は、組織内で行使される影響力が単一の方法ではなく、相手や目的に応じて戦術を使い分ける複雑なプロセスであることを示しています。私たちは、「この相手にはこの方法が効果的だろう」と考えて戦術を選択しているのです。
政治的スキルは職務成果を予測する
これまでに、誠実性が政治的な職場での職務遂行に有利であることや、地位によって異なる影響戦術が用いられることを見てきました。続いて、組織内で他者に効果的に影響を与えることができる能力、すなわち「政治的スキル」に注目してみましょう。
政治的スキルを測定するための尺度「政治的スキル・インベントリー(PSI)」を開発し、その妥当性を検証した研究があります[3]。研究では政治的スキルを「職場において他者を理解し、その知識を活用して、自分自身や組織の目標を促進する方向に他者に影響を及ぼす能力」と定義しています。
その上で、大学生や様々な業種の職業人など、複数のグループを対象に調査を行い、政治的スキルが次の4つの次元から構成されることを明らかにしました。
- 社会的洞察力:他者や社会的状況を鋭く観察・理解し、適切な行動を取る能力。例えば、会議の場で誰が実質的な決定権を持っているか、誰がどのような立場にあるかをすばやく把握できる能力です。
- 対人的影響力:他者に対して説得力を持ち、柔軟に行動を調整して相手から望ましい反応を引き出す能力。言葉遣いや表情、仕草などを状況に応じて調整し、相手に良い印象を与えることができます。
- ネットワーク形成能力:効果的な人間関係や共同関係を築き、組織内で必要な資源を獲得する能力。様々な関係者と良好な関係を維持し、必要な時に協力を得られるネットワークを構築できます。
- 見かけ上の誠実さ:影響力の行使が利己的ではなく、誠実であるように相手に見せる能力。自分の行動が真摯なものであり、隠された意図がないことを相手に信じてもらうことができます。
研究によると、これらの4つの次元を含む政治的スキルは、職場における様々な成果と関連していることが分かりました。特に、上司による職務遂行評価や部下によるリーダー有効性評価を有意に予測しました。要するに、政治的スキルが高い人ほど、職場で高い評価を得るということです。
同じ専門知識や経験を持つ二人のマネージャーがいるとします。政治的スキルが高いマネージャーは、チームメンバーの個性や動機を深く理解し、それぞれに適した対応をします。他部署との連携もスムーズで、組織内の様々な関係者から協力を得ることができます。プロジェクトはより効率的に進み、チームの成果も向上します。
他方で、政治的スキルが低いマネージャーは、チームメンバーの個性を十分に理解せず、一律の対応をしてしまうかもしれません。他部署との連携も不十分で、必要な協力を得られないことがあります。その結果、プロジェクトの進行に支障をきたし、チームの成果も制限されてしまいます。
政治的スキルの中でも「社会的洞察力」が職務遂行評価の予測において最も重要でした。他者の感情や意図、組織内の力関係などを敏感に察知し、理解する能力が、職場における成功に関わっているということです。
政治的スキルは他の能力や特性とも関連していましたが、同一ではありませんでした。例えば、セルフモニタリング(自分の行動を状況に応じて調整する能力)や感情知性(自分と他者の感情を認識し、管理する能力)と正の相関を示しました。一方で、一般的な知能とは関連がなく、政治的スキルが知的能力とは異なる独自の能力であることが示されました。
フィードバックは組織内政治の知覚を下げる
組織内政治の知覚は、職場での満足度やコミットメント、パフォーマンスに悪い影響を与えることが示されています。この組織内政治の知覚を低減させるためには、どのような環境が効果的なのでしょうか。「フィードバック環境」という観点からこの問題に取り組んだ研究があります[4]。
フィードバック環境とは、職場で日常的に提供される非公式なフィードバックの質や頻度、利用可能性、フィードバックを求めることへの支援といった要素を含む広い概念です。従来の研究では、正式な業績評価制度に焦点が当てられることが多かったのですが、この研究では、日々の業務の中で交わされる非公式なフィードバックの重要性に着目しました。
具体的には、様々な業界の組織に勤務する部下とその直属の上司150組(合計300名)を対象に調査を行いました。部下には組織内政治の知覚、フィードバック環境、職務満足度、情緒的コミットメントについて回答してもらい、上司には部下の職務パフォーマンスを評価してもらいました。
調査の結果、質の高いフィードバック環境は組織内政治の知覚を低減させることが明らかになりました。上司からのフィードバック環境が組織内政治の知覚に強く影響していました。同僚からのフィードバックも影響していましたが、その程度は上司からのものほど強くありませんでした。
なぜフィードバック環境が組織内政治の知覚を低減させるのでしょうか。研究者らは、質の高いフィードバック環境がいくつかの効果をもたらすと説明しています。
初めに、適切なフィードバックは、職場での行動や成果に関する基準を提供します。「何が評価されるのか」「どのような行動が期待されているのか」が明確になることで、不確実性が減少し、組織内政治が存在する余地が少なくなります。
続いて、フィードバックは情報の非対称性を減少させます。組織内政治は情報の偏りや不透明さから生じることが多いですが、オープンなフィードバック環境では情報が共有され、透明性が高まります。
そして、質の高いフィードバックは信頼関係を構築します。上司や同僚から誠実で建設的なフィードバックを受けることで、「この職場では実力や成果が正当に評価される」という信頼感が生まれます。その結果、「成功するためには政治的駆け引きが必要だ」という認識が弱まるのです。
研究では、組織内政治の知覚が低下することにより、職務満足度や組織へのコミットメントといった「モラール」が向上し、その結果として職務パフォーマンスも向上することが示されました。フィードバック環境の改善は、政治認知の低減、モラールの向上、パフォーマンスの向上という好循環を生み出す可能性があります。
脚注
[1] Hochwarter, W. A., Witt, L. A., and Kacmar, K. M. (2000). Perceptions of organizational politics as a moderator of the relationship between conscientiousness and job performance. Journal of Applied Psychology, 85(3), 472-478.
[2] Kipnis, D., Schmidt, S. M., and Wilkinson, I. (1980). Intraorganizational influence tactics: Explorations in getting one’s way. Journal of Applied Psychology, 65(4), 440-452.
[3] Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C., and Frink, D. D. (2005). Development and validation of the Political Skill Inventory. Journal of Management, 31(1), 126-152.
[4] Rosen, C. C., Levy, P. E., and Hall, R. J. (2006). Placing perceptions of politics in the context of the feedback environment, employee attitudes, and job performance. Journal of Applied Psychology, 91(1), 211-220.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。