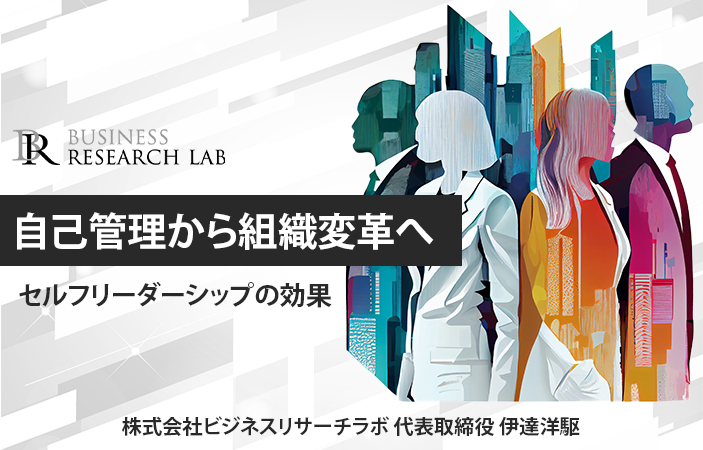2025年7月24日
自己管理から組織変革へ:セルフリーダーシップの効果
変化する環境で効率的に業務を遂行するための方法はないものでしょうか。本コラムでは、そうした課題に対する一つの切り口として、「セルフリーダーシップ」の概念と効果について解説します。セルフリーダーシップとは、自己管理と自己動機づけを通じて、自分自身の行動と思考を効果的に導く能力のことです。
従来のトップダウン型の管理では、急速に変化するビジネス環境における複雑な課題に対応することが困難になっています。市場変化への迅速な対応や革新的なソリューションの開発には、組織全体で主体的に考え行動できる人材の存在が不可欠です。
セルフリーダーシップを実践している社員は、明確な指示がなくても問題を特定し、解決策を実行に移すことができます。目標設定から進捗管理、結果評価まで一連のプロセスを自律的に進めることができます。直接的な監督がない状況でも一定のパフォーマンスを維持できる人材が、組織の生産性を支えます。
本コラムでは、実証研究に基づいてセルフリーダーシップがもたらす効果について紹介します。生産性向上、問題解決能力の強化、職場満足度の上昇、チームパフォーマンスの改善など、セルフリーダーシップが個人と組織にもたらす多様な利点について、データをもとに説明していきます。
セルフリーダーシップは創造性を通じて革新を促す
ビジネスの世界で長期的な競争優位性を確保するためには、組織内での革新が欠かせません。革新とは、新しいアイデアや方法を実践に移し、実際に価値を生み出すことです。革新はどのように生まれるのでしょうか。タイにおける地域特産品を生産する小規模生産者グループを対象とした研究から、革新の源泉について見てみましょう[1]。
タイ東北部の地域特産品生産者グループ138団体、1,526名のメンバーを対象にした調査では、個人の創造性が革新に関連していることが判明しました。創造性とは新しく有用なアイデアを生み出す能力のことで、革新の前提条件となります。この研究では、個人レベルとグループレベルの両方から革新の要因を検討しました。
この調査で興味深いのは、セルフリーダーシップと創造性との関係です。研究者たちは当初、セルフリーダーシップが直接革新に結びつくと予想していました。しかし結果は異なりました。セルフリーダーシップは直接的には革新に影響せず、創造性を媒介して間接的に革新に寄与していました。
セルフリーダーシップが高い人は、自分の行動や思考を効果的に管理できるため、困難な状況でも粘り強く創造的な活動を続けられます。目標設定に明確な方向性を持ち、自己観察によって自分の進捗を把握し、自己修正によって方向修正ができるのです。こうした自己管理能力が創造的思考を促進し、それが革新的な行動につながると考えられます。
グループレベルの要因も革新に関わっていました。例えば「構築的文化」と呼ばれる、リスクテイクや創造的活動を奨励し失敗を許容するグループ文化は、創造性を媒介して革新に影響していました。
また、知識マネジメントも革新の要因でした。地域の伝統知識や暗黙知を含む知識の獲得、共有、活用の活動は、直接的にも創造性を介した間接的にも革新に寄与していました。
この研究から見えてくるのは、セルフリーダーシップが単独で革新を生み出すのではなく、創造性という媒介要因を通じて革新を促進するということです。加えて、組織の文化や知識管理といった環境要因も個人の革新性を引き出す上で重要な役割を果たします。
セルフリーダーシップは職場の支援で創造性を高める
セルフリーダーシップが創造性を経由して革新に結びつくことを見てきました。しかし、セルフリーダーシップを持つ個人が常に創造性を発揮し、革新的な行動を取れるわけではありません。それには職場環境からの支援が必要です。
ある研究では、セルフリーダーシップと創造性・革新性の関係についてモデルが提案されています[2]。このモデルによれば、セルフリーダーシップの強い人は創造性や革新性の「潜在能力」が高いとされます。しかし、この潜在能力が実際の行動として表れるかどうかは、職場環境からのサポートに左右されるのです。
セルフリーダーシップを構成する要素を振り返ってみましょう。一つ目は「行動中心型戦略」で、自己目標設定、自己観察、自己報酬、自己修正、自己訓練といった具体的な行動管理の方法です。二つ目は「自然報酬戦略」で、仕事自体の楽しさや満足感を高め、内発的な動機づけを促進します。三つ目は「建設的思考戦略」で、前向きな思考や自己対話を通じて思考パターンを改善する方法です。
これらの戦略を効果的に実践できる人は、創造性や革新性の潜在能力が高まります。しかし、それを実際の行動に移すためには、職場からの支援が求められます。この研究では、支援の源として「チームからの支援」「上司からの支援」「組織全体からの支援」の三つを挙げています。
例えば、上司からの支援が不足していると、創造性の潜在能力を持つ従業員でも、新しいアイデアを提案することをためらうかもしれません。「このアイデアを上司に話しても理解してもらえないだろう」と思えば、創造的な発想は頭の中にとどまってしまいます。同様に、チームメンバーからの支援がなければ、協力が必要な革新的なプロジェクトは実現しにくくなります。
組織全体の支援も重要です。情報共有の仕組み、失敗を許容する文化、適切な報酬制度、参加型の管理スタイルなど、組織の方針や文化が創造性や革新性の発揮を後押しします。逆に、過度に官僚的で変化を嫌う組織文化であれば、セルフリーダーシップの強い従業員でも革新的な行動を控えるでしょう。
この研究では、「潜在的創造性」と「実践的創造性」という区別を設けています。潜在的創造性は、個人が持つ創造的なアイデアを生み出す能力のことです。一方、実践的創造性は、そのアイデアを表現し、実行に移す行動のことを指します。セルフリーダーシップは潜在的創造性を高めますが、それが実践的創造性になるかどうかは職場環境の支援次第なのです。
職場環境の支援が強ければ強いほど、潜在能力と実践の間のギャップは小さくなります。これは、創造性や革新性を高めたい組織にとって重要な視点です。セルフリーダーシップを持つ人材を育成するだけでなく、その能力を発揮できる環境づくりも同時に進める必要があります。
セルフリーダーシップは上司が評価する革新性を高める
実際の職場において、セルフリーダーシップは従業員の革新的行動にどのような効果をもたらすのでしょうか。イスラエルで行われた研究を見てみましょう[3]。
この研究の特徴は、革新的行動を「自己評価」と「上司評価」の両方から測定した点にあります。多くの研究では自己報告データのみを用いるため、客観性に欠ける場合がありますが、この研究では上司の視点も含めることで、より信頼性の高い結果を得ています。
イスラエルの6つの異なる組織(政府機関、教育機関、民間企業など)から175名の従業員とその上司のペアを対象に調査が行われました。セルフリーダーシップスキルは、行動中心型戦略、自然報酬戦略、建設的思考戦略の3つの側面から測定されました。そして革新的行動は、問題認識とアイデア生成、アイデアの普及とサポート獲得、アイデアの実行という3段階のプロセスとして捉えられています。
調査結果から、セルフリーダーシップスキル全体の指標は、上司評価による革新的行動、および、自己評価による革新的行動と有意な関連があることが明らかになりました。特に、行動中心型戦略と建設的思考戦略は上司評価による革新的行動と強く関連していましたが、自然報酬戦略は上司評価との関連が見られませんでした。
これはどのように解釈できるでしょうか。行動中心型戦略(自己目標設定や自己観察など)を実践する従業員は、目標達成に向けて計画的に行動するため、革新的なアイデアを実行に移す段階でも効果的に進められると考えられます。同様に、建設的思考戦略を持つ従業員は、困難に直面してもポジティブな思考で乗り越えようとするため、革新的なプロジェクトが直面する障害にも粘り強く対処できるでしょう。
一方、自然報酬戦略(仕事自体から楽しさを見出す能力)は自己評価による革新的行動とは関連していましたが、上司評価とは関連していませんでした。これは、自然報酬戦略が個人の内面的な動機づけに関わるものであり、外部から観察しにくいためかもしれません。あるいは、仕事を楽しむことが必ずしも上司から見て革新的な成果に結びつかない可能性も考えられます。
この研究では収入と勤続年数という要因も考慮に入れていますが、それらを統制した後でもセルフリーダーシップスキルは革新的行動に対して有意な効果を持っていました。この結果は、セルフリーダーシップが様々な背景要因を越えて、革新性を高める効果を持つことを示唆しています。
この研究結果から言えることは、セルフリーダーシップが組織における革新的行動を促進する上で重要であるということです。特に、行動中心型戦略と建設的思考戦略は、上司からも認められる革新的行動につながります。組織が革新性を高めたいなら、従業員のセルフリーダーシップスキルを育成することが一つの方法と言えるでしょう。
セルフリーダーシップは自己効力感を通じて成果を高める
セルフリーダーシップはどのようなメカニズムで成果につながるのでしょうか。ある研究では、「自己効力感」がその仲介役としての役割を果たすことが明らかになっています[4]。
自己効力感とは、特定の行動を成功裏に実行できると個人が自信を持つ程度のことです。「自分はこの課題をうまくこなせる」という自信のようなものです。自己効力感が高い人は、困難に直面しても努力を継続し、高いパフォーマンスを達成する傾向があります。
大学生151名を対象とした調査では、セルフリーダーシップが自己効力感を高め、その自己効力感が実際のパフォーマンスを向上させるという連鎖が確かめられました。この研究では、学期の初めにセルフリーダーシップと自己効力感を測定し、学期末にパフォーマンス(試験スコア、レポート評価、授業参加度)を評価するという方法がとられました。
この研究で特徴的なのは、セルフリーダーシップがパフォーマンスに直接的な効果を持たない点です。セルフリーダーシップの効果は自己効力感を通じて間接的に現れていました。セルフリーダーシップ→自己効力感→パフォーマンスという関係が見出されたのです。
このメカニズムは次のように説明できます。セルフリーダーシップの行動中心戦略(目標設定や自己観察など)は、自分の行動をコントロールできているという感覚を強め、それが「自分はできる」という自己効力感につながります。同様に、建設的思考戦略(前向きな自己対話やイメージ)も、困難な課題に対して「自分ならできる」という確信を高めます。そして高まった自己効力感は、実際の場面で粘り強く課題に取り組む原動力となり、良いパフォーマンスをもたらします。
この結果は、セルフリーダーシップトレーニングの方向性に示唆を与えます。セルフリーダーシップのスキルを教えるだけでなく、自己効力感を高めることを意識したトレーニングが効果的だということです。例えば、セルフリーダーシップスキルを身につけた後、徐々に難しくなる課題に挑戦して成功体験を積み重ねることで、自己効力感が強化されるでしょう。
この研究は学生を対象としたものですが、職場環境にも応用可能な知見です。組織が従業員のパフォーマンスを高めたいなら、セルフリーダーシップと自己効力感の両方を強化する取り組みが有効でしょう。例えば、難しいプロジェクトを小さなステップに分け、一つずつ達成感を味わえるようにすることで、自己効力感が高まります。
セルフリーダーシップは職務満足を通じてチームを高める
セルフリーダーシップはチームや組織の成果にはどのように結びつくのでしょうか。オーストラリアの製造企業で行われた研究を紹介します[5]。
この研究では、セルフリーダーシップの中でも特に「行動中心型戦略」に焦点を当て、それがチームのパフォーマンスにどう関連するかを検討しました。そして両者の関係を仲介する要因として「職務満足」に着目しています。
職務満足とは、従業員が自分の仕事に対して抱く態度や感情のことで、内発的満足(仕事の内容や達成感に関するもの)と外発的満足(給与や労働条件に関するもの)の二つの側面があります。この研究では、セルフリーダーシップ→職務満足→チームパフォーマンスという関連性を検証しました。
オーストラリアの製造企業に勤務する304名の従業員を対象に調査を行った結果、自己観察、自己目標設定、自己報酬、自己処罰といった行動中心型のセルフリーダーシップ戦略は、内発的・外発的な職務満足の両方を高めることがわかりました。そして、その職務満足はチームの財務的・非財務的パフォーマンスの両方に好ましい効果をもたらしていました。
メカニズムを詳しく見てみましょう。まず、セルフリーダーシップの行動中心型戦略を実践すると、自分で目標を設定し、進捗を確認し、成果を自ら評価するといった「自律性」が高まります。こうした自律性の感覚は職務満足を増大させます。人は自分でコントロールできるという感覚があると、仕事に対する満足度が高まるのです。
職務満足が高まると、従業員は仕事に対して前向きな態度で取り組み、チームの目標達成に貢献しようとします。また、職務満足は離職意図を低下させ、チームメンバーの安定性を高めます。職務に満足している従業員は同僚との関係も良好になりやすく、チーム内の協力が促進されます。こうした様々な要因が組み合わさって、チーム全体のパフォーマンスが向上するのでしょう。
脚注
[1] Pratoom, K., and Savatsomboon, G. (2012). Explaining factors affecting individual innovation: The case of producer group members in Thailand. Asia Pacific Journal of Management, 29(4), 1063-1087.
[2] DiLiello, T. C., and Houghton, J. D. (2006). Maximizing organizational leadership capacity for the future: Toward a model of self-leadership, innovation and creativity. Journal of Managerial Psychology, 21(4), 319-337.
[3] Carmeli, A., Meitar, R., and Weisberg, J. (2006). Self-leadership skills and innovative behavior at work. International Journal of Manpower, 27(1), 75-90.
[4] Prussia, G. E., Anderson, J. S., and Manz, C. C. (1998). Self-leadership and performance outcomes: The mediating influence of self-efficacy. Journal of Organizational Behavior, 19(5), 523-538.
[5] Politis, J. D. (2006). Self-leadership behavioural-focused strategies and team performance: The mediating influence of job satisfaction. Leadership & Organization Development Journal, 27(3), 203-216.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。