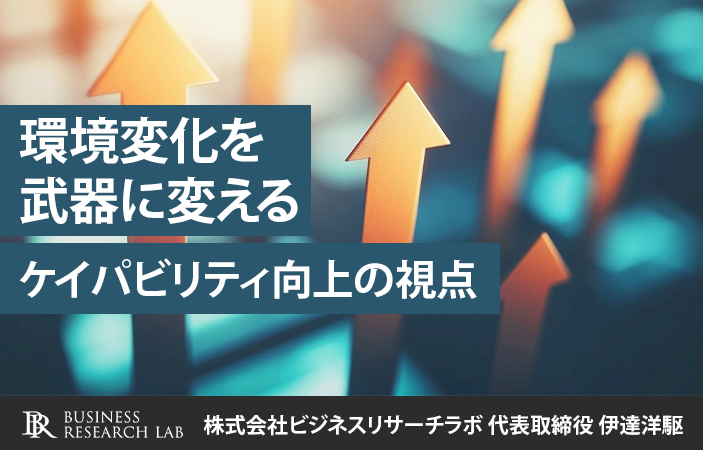2025年7月23日
環境変化を武器に変える:ケイパビリティ向上の視点
企業が成功し続けるためには、変化する環境に適応する能力が必要です。この能力は「ケイパビリティ」と呼ばれ、企業が持つ知識やスキル、経験、組織ルーティンなどの集合体です。テクノロジーの急速な進化や市場の変動、顧客ニーズの多様化によって、企業はこれまで以上に素早く変化に対応する必要があります。
一時的な成功に満足するのではなく、長期にわたって競争優位性を維持していくためには、ケイパビリティを継続的に高めていくことが求められます。しかし、どのようにすればケイパビリティを効果的に高められるのでしょうか。
本コラムでは、ケイパビリティを高める視点について考察します。初めに、企業買収後の成功において、意図的な学習がどのように組織能力を高めるかを見ていきます。続いて、既存の知識や資産が新たな能力開発にどう貢献するかを探ります。そして、変化の激しい環境で企業が継続的に変革を遂げるためのアプローチについて検討します。最後に、企業買収が既存の発展経路を打破し、新たな可能性を開くメカニズムを考えます。
これらの視点は、様々な経営環境において企業がケイパビリティを向上させるための示唆を提供します。本コラムを通じて、変化する環境で持続的に競争優位を築くための洞察を得ていただければ嬉しいです。
意図的な学習が買収後のケイパビリティを高める
企業買収は、新たな市場への参入や技術の獲得、規模の拡大など、様々な目的で行われます。しかし、少なからぬ買収が期待した成果を上げられず失敗に終わることも事実です。なぜ一部の企業は買収を成功させる一方で、他の企業は失敗してしまうのでしょうか。この違いを生み出す要素の一つが「意図的な学習」です[1]。
米国の銀行業界における買収を分析した研究によれば、買収の経験を多く積むことが必ずしも買収成功率の向上につながるわけではありません。ただ経験を重ねるだけでは十分ではないのです。その経験から組織として学び、知識を体系化することが、買収後の統合プロセスを成功させる鍵となります。
この研究では、買収した企業と買収された企業を統合する過程で、過去の経験から学んだ知識やノウハウを意識的に文書化し、マニュアルやガイドラインとして体系化していた企業は、そうでない企業に比べて買収後のパフォーマンスが向上していたことが明らかになりました。特に複雑な統合プロセスが求められる場合には、この「意図的な学習」の効果がより顕著に表れました。
一方で、買収経験はあっても、その知識を体系化せず、暗黙知のままにしていた企業では、同じ失敗を繰り返す傾向が見られました。例えば、ある銀行では過去の買収でも顧客データの移行に問題が生じていたにもかかわらず、その教訓が組織内で共有されず、次の買収でも同様の問題が発生してしまいました。
この研究は、買収プロセスにおける経営陣の役割についても発見をしています。買収された企業の経営陣を大幅に入れ替えることは、一般的には買収後のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。買収前の業績が良好だった企業の場合、経営陣の入れ替えによってその企業が持っていた暗黙知やノウハウが失われ、統合プロセスが困難になることが分かりました。
このことは、買収後の統合プロセスにおいて、被買収企業の持つ知識や能力を理解し、活用することの大切さを示しています。ただし、買収前の業績が悪かった企業の場合は、経営陣の入れ替えがむしろ好ましい結果をもたらす可能性も示唆されています。
これらの結果から、買収後のケイパビリティを高めるためには、経験を積むだけでなく、その経験から意識的に学び、知識を体系化して組織全体で共有することが大切であることが分かります。買収という複雑で不確実性の高いプロセスを成功させるには、過去の経験を「暗黙知」のままにせず、「形式知」として蓄積・共有する仕組みが求められるのです。
補完的な資産とノウハウがケイパビリティを高める
企業が急激な環境変化に適応し、新たな市場ニーズに応えるためには、既存の知識や能力を超えた新しいケイパビリティを開発する必要があります。こうした変化に対応する能力は「ダイナミック・ケイパビリティ」と呼ばれ、企業の長期的な競争力を左右します。ダイナミック・ケイパビリティはどのように蓄積されていくのでしょうか。
米国の石油産業を対象にした研究は、この問いに対する示唆を与えてくれます[2]。1970年代、石油危機を契機に、多くの石油企業が代替エネルギー技術、特に石炭からガスや液体燃料を生成する技術(石炭変換技術)の研究開発に急速に投資を始めました。この急激な環境変化への対応過程を分析することで、企業がどのように新たな技術的能力を獲得するのか、そしてそのプロセスが既存の資産やノウハウとどのように関連しているのかを明らかにしました。
この研究から得られたのは、企業が新しい技術分野に参入する際、その成功は既存の「補完的な」資産やノウハウに依存するということです。とりわけ、既存の精製技術に関する研究開発の蓄積が多い企業ほど、石炭変換技術への投資も積極的に行う傾向がありました。
例えば、石油精製プロセスに関する深い知識を持っていた企業は、石炭から液体燃料を生成する技術開発においても優位性を持っていました。両者の間には技術的な共通点があり、既存の知識が新技術の開発・習得を容易にしたからです。精製技術には、化学反応の制御、触媒の活用、熱交換プロセスなど、石炭変換技術にも応用可能な要素が多く含まれていました。
同様に、石炭資産(鉱山など)を多く保有していた企業も、石炭変換技術への投資に積極的でした。これは物理的な資産の補完性を示しています。石炭の供給源を確保していた企業は、原料の調達コストや品質管理において優位性を持ち、新技術開発のリスクを低減できたのです。
この研究が教えてくれるのは、企業が新たな能力を開発する際、ゼロから始めるのではなく、既存の資源や能力を基盤として、それらを補完的に活用することが成功への近道だということです。企業の成長や変革は完全にランダムに起こるのではなく、ある程度は「経路依存的」であり、過去の蓄積が将来の方向性を形作ります。
企業がダイナミック・ケイパビリティを効果的に蓄積するためには、自社の強みや既存の知識・資産基盤を客観的に評価し、それらと補完性のある新たな分野に戦略的に投資することが賢明だということです。
ただし、この研究では、すべての既存知識や資産が新技術開発に等しく寄与するわけではないことも明らかにしています。精製設備そのものの保有量や、他の代替エネルギー技術への研究開発投資は、必ずしも石炭変換技術の開発成功と強い関連を示しませんでした。このことは、単純に物理的な資産を多く持っているというだけでは不十分であり、その背後にある知識やノウハウが重要であることを示唆しています。
半構造化された変化がケイパビリティを高める
テクノロジーの急速な進化、顧客ニーズの多様化、グローバル競争の激化など、企業を取り巻く環境は流動的です。このような状況下で持続的に成功するためには、企業は継続的に変化し続ける能力を身につける必要があります。絶え間なく変化する組織はどのようにして作られるのでしょうか。
ハイテク産業を対象にした研究によれば、継続的に変化し続け、市場で成功している企業には共通した特徴があることが明らかになっています[3]。それは「半構造化された変化」のアプローチです。
従来の組織変革理論では、組織は比較的長い安定期と、それに続く短期間の劇的な変革期を交互に繰り返すと考えられてきました。しかし、変化の激しいビジネス環境で成功している企業は、このような「断続的均衡」モデルではなく、常に変化し続ける仕組みを組織内に組み込んでいます。
この研究で明らかになった第一の特徴は、「半構造化された」アプローチです。これは、厳格な計画や構造に縛られすぎず、かといって全く構造を持たない無秩序な状態でもない、その中間のバランスを保つことを意味します。
半構造化されたアプローチは、企業のケイパビリティを高める上で重要です。厳格すぎる構造は変化への適応を妨げる一方で、構造がなさすぎると方向性を見失い、混乱を招くからです。適度なバランスを取ることで、企業は変化への対応力を維持しながらも、効率的に目標に向かって進むことができます。
第二の特徴は、「時間ベースの進化」です。成功している企業は、変化のタイミングを市場の変動に完全に委ねるのではなく、一定の時間間隔で計画的に変化を起こしていました。例えば、半年ごとに新製品を発表する、毎年特定の時期に組織構造を見直すなど、リズムを持って変化を起こすことで、組織全体が変化のプロセスに慣れ、そこから学ぶことができます。
このような時間ベースの変化は、組織が変化に慣れ、それを日常の一部として受け入れる文化を醸成します。変化が例外的な出来事ではなく、事業運営の通常の一部となるのです。
第三の特徴は、「相互作用の強化」です。成功している企業では、組織内外の多様なグループ間の交流が活発に行われていました。部門間の壁を低くし、異なる専門知識や視点を持つ人々が協働することで、新しいアイデアが生まれやすくなります。
この研究から学べるのは、組織が絶え間なく変化し続ける能力を高めるためには、適度な構造と柔軟性のバランス、計画的な変化のリズム、そして多様な相互作用を促進する環境を意識的に作り出すことが大切だということです。
こうした「半構造化された変化」のアプローチは、企業が環境変化に受け身で対応するのではなく、むしろ変化を前提とした組織能力を積極的に構築することを可能にします。変化を恐れるのではなく、変化を活かす組織文化と仕組みを作り出すことが、持続的な成功を引き寄せます。
買収はケイパビリティの経路を打破する
企業が成長し、競争優位を維持するためには、新たな資源や能力を獲得し続ける必要があります。しかし、企業の発展は完全に自由に方向転換できるわけではなく、過去の蓄積や経験に縛られる「経路依存性」という制約があります。企業はどのようにしてこの制約を乗り越え、新たな成長経路を切り開くことができるのでしょうか。
米国の医療分野における企業買収を分析した研究は、この問いに対するヒントを提供しています[4]。この研究では、1978年から1995年までの期間に行われた多数の買収を対象に、買収前後での企業の製品ラインがどのように変化したかを分析しました。
その結果、買収が企業の「経路依存性」を打破し、新たな成長経路を開く手段として機能することがわかりました。企業は通常、自社の既存のルーティンや知識、組織文化に制約され、自己変革には限界があります。しかし、買収を通じて外部から新たな資源や能力を取り込むことで、この制約を突破することができます。
研究によれば、買収を行わなかった企業と比較して、買収を行った企業や買収された企業は、その製品ラインや事業構成において大きな変化を遂げていました。これは、買収が規模の拡大だけでなく、企業の資源や能力の再構成をもたらすことを表しています。
しかし、この研究はさらに、買収によって獲得した資源や能力のすべてが同じように扱われるわけではなく、買収後の資源の再構成には一定のパターンが存在することを明らかにしています。
顕著だったのは「経路依存的な変化」です。買収企業と被買収企業が共通の製品カテゴリーや技術を持っていた場合、それらの資源は買収後も高い確率で保持されました。企業は自社の既存の強みと関連性の高い資源を優先的に統合するのです。
一方で、「経路打破的な変化」も観察されました。買収企業と被買収企業の資源が大きく異なる場合でも、戦略的に有望と判断された新しいカテゴリーの資源は積極的に保持されました。これは、企業が買収を通じて意図的に自社の発展経路を変更し、新たな成長機会を追求していることを意味しています。
この研究が示唆するのは、企業が新たなケイパビリティを獲得し、既存の発展経路の制約を超えるためには、買収という手段が効果的だということです。自社では開発が難しい新たな能力や、市場環境の変化に対応するために必要な補完的資源を獲得する上で、買収は戦略的オプションとなります。
ただし、買収によるケイパビリティの拡張を成功させるためには、どの資源や能力を保持し、どれを廃棄するかという意思決定が大事です。自社の強みを補完する資源を重視しつつも、将来の成長につながる新たな領域へと踏み出す勇気も必要です。
買収による経路打破は、企業が環境変化に適応し、長期的な競争優位を維持するための手段となります。適切に実行すれば、買収は規模の拡大を超えて、企業の能力や発展の可能性を変革するダイナミック・ケイパビリティの源泉となるのです。
脚注
[1] Zollo, M., and Singh, H. (2004). Deliberate learning in corporate acquisitions: Post-acquisition strategies and integration capability in U.S. bank mergers. Strategic Management Journal, 25(13), 1233-1256.
[2] Helfat, C. E. (1997). Know-how and asset complementarity and dynamic capability accumulation: The case of R&D. Strategic Management Journal, 18(5), 339-360.
[3] Brown, S. L., and Eisenhardt, K. M. (1997). The art of continuous change: Linking complexity theory and time-paced evolution in relentlessly shifting organizations. Administrative Science Quarterly, 42(1), 1-34.
[4] Karim, S., and Mitchell, W. (2000). Path-dependent and path-breaking change: Reconfiguring business resources following acquisitions in the U.S. medical sector, 1978-1995. Strategic Management Journal, 21(10-11), 1061-1081.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。