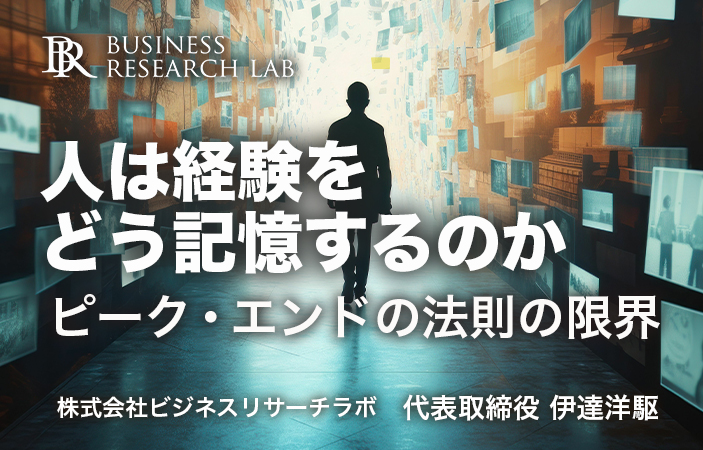2025年7月22日
人は経験をどう記憶するのか:ピーク・エンドの法則の限界
私たちの人生は無数の経験の積み重ねでできています。日々の通勤電車での出来事、職場での会議、友人との食事、週末の映画鑑賞、そして特別な日の旅行まで、これらすべての経験が私たちの記憶を形作っていきます。
しかし不思議なことに、過去を振り返るとき、それらの経験のすべての瞬間が同じ重みで記憶に刻まれているわけではありません。例えば海外旅行を振り返るとき、7日間の滞在すべての瞬間を均等に思い出すことはできず、特定の強い印象や感情を伴った場面が鮮明に記憶に残っているものです。
この記憶の選択的なメカニズムを説明するのが「ピーク・エンドの法則」です。この法則によれば、私たちは経験を評価する際、その経験の中で最も感情が強かった瞬間(ピーク)と終了時点の感情状態(エンド)に影響されると言われています。この法則は、マーケティングや顧客体験、サービス業界など様々な分野で応用されてきました。
しかし、この法則は本当にすべての状況で同じように機能するのでしょうか。例えば、一週間の海外旅行と数分の医療処置では、経験の複雑さや時間の長さが異なります。ピーク・エンドの法則は、このような多様な状況においても同様に適用できるのでしょうか。また、ポジティブな感情とネガティブな感情が入り混じる複雑な経験においても、単純に「ピーク」と「エンド」だけで全体評価が決まるのでしょうか。
近年の研究では、ピーク・エンドの法則には適用限界があることが明らかになってきています。本コラムでは、この法則がどのような条件で有効であり、どのような状況では他の要因が重要になるのかを探っていきます。
ピーク・エンドは長期的な記憶評価に不十分
ピーク・エンドの法則は、短時間の比較的単純な経験(例えば、短い医療処置や実験室での痛み体験など)では頑健に機能することが知られています。しかし、休暇旅行のような長期的で感情が多様に変化する経験ではどうでしょうか。この疑問に答えるために行われた研究があります。
この研究では、大学生49名に休暇旅行中の感情状態を記録してもらいました[1]。参加者は毎日、その日の幸福度について様々な質問に答えました。具体的には、現在の幸福度、前回記録してからの最高に幸福だった瞬間、最も不幸だった瞬間、最も記憶に残りそうな出来事の評価、過去24時間の平均幸福度、そして普段と比べた24時間の出来事の珍しさについてです。
休暇終了後、参加者は2~16日後に全体的な幸福度評価を行い、毎日の幸福度変化を回想するグラフも作成しました。さらに約1ヶ月後にも同様の回想テストが実施されました。
この研究から得られた結果としては、まず、休暇の長さは後から回想する全体的な幸福度評価に影響を与えませんでした。これは「持続時間の無視」と呼ばれる現象で、経験の長さ自体は評価にあまり影響しないことを示しています。7日間の休暇と14日間の休暇では、必ずしも後者の方が良い評価になるとは限らないということです。
ピーク・エンドの法則についてはどうだったでしょうか。実は、最も幸福だった瞬間(ピーク)と休暇終了時(エンド)の幸福度は、全体の評価とそれほど強い関連性を示しませんでした。むしろ、最も記憶に残る一日や最も異常だった(普段と違った)一日の幸福度の方が、回想された全体の幸福度とよく関連していました。
また、参加者は各日の幸福度を正確に回想することができませんでした。時間が経過するにつれて、最も幸福だった瞬間(ピーク)は実際よりも弱まり(過小評価され)、最も不幸だった瞬間(トラフ)は実際よりも幸福に回想される傾向がありました。記憶は時間とともに再構成され、変化していくのです。
こうした結果から、ピーク・エンドの法則は長期的な自伝的記憶には完全には当てはまらないことが分かります。長期的な経験の評価には、ピークやエンドだけでなく、「記憶に残った瞬間」や「普段と違った経験」など、他の要素も影響を与えているようです。
これは実生活でも納得できる結果ではないでしょうか。例えば、3年前の海外旅行を思い出すとき、私たちは旅の最高の瞬間と最終日だけでなく、「最も印象に残った出来事」や「予想外の出来事」をよく覚えているものです。そして、それらの記憶が旅行全体の評価に影響を与えていたとしても不思議ではありません。
ピーク・エンドは複数エピソードでは機能しにくい
長期的な経験におけるピーク・エンドの法則の限界について見てきました。「複数のエピソードから構成される経験」ではどうでしょうか。例えば、ある1日には朝の通勤、仕事での会議、同僚との昼食、帰宅後の家族との時間など、様々なエピソードが含まれています。このような複合的な経験の評価においても、ピーク・エンドの法則は同様に機能するのでしょうか。
この疑問に答えるために行われた研究があります。この研究では、アメリカ(810名)、フランス(820名)、デンマーク(805名)の成人女性を対象に、「日次再構成法」という手法を用いて日常生活の感情経験を調査しました[2]。この方法では、参加者は前日の出来事を思い出し、その日のエピソード(例:食事、仕事、休息など)ごとの感情状態を報告します。そして、その日全体の評価も行いました。
研究者たちは、このデータを用いて、人々が1日全体をどのように評価しているかを分析しました。具体的には、次の感情評価指標を設定して分析を行いました。
- エピソードごとの純感情値(ポジティブな感情からネガティブな感情を引いた値)
- 持続時間加重の純感情値(1日の全エピソードを時間で加重平均した値)
- 自己報告による最高の瞬間(ピーク)および最低の瞬間(ロー)
- 1日の最後のエピソードの感情値(エンド)
分析の結果、最も強い予測因子となったのは「持続時間加重平均」でした。1日の各エピソードを時間で重み付けした平均感情値が、その日全体の評価を最も強く予測したのです。一方、ピークやエンドといったヒューリスティック要素は、追加的には予測に貢献したものの、持続時間加重モデルを超える強さではありませんでした。
特に「ロー」(最低の瞬間)の存在は、その日の評価を低下させる要因として一貫して重要でした。一方、「ピーク」(最高の瞬間)は、アメリカのサンプルでは有意でしたが、他の国では弱いか非有意な結果でした。このことから、人々は特にネガティブな感情体験を記憶に刻み込む傾向があると考えられます。
また、1日の終了エピソード(エンド)の感情は、日常的な複数エピソード経験では全体評価の予測にほとんど寄与しませんでした。これはピーク・エンドの法則の「エンド」部分が、日常的な文脈では機能しにくいことを示唆しています。
この研究から、ピーク・エンドの法則は単一の明確なエピソードには適用できても、日常生活のような複数のエピソードから構成される経験の評価には限界があることが分かります。1日のような複雑な経験を評価する際、人々はヒューリスティック(簡略化された思考法)だけに頼るのではなく、経験全体の感情を時間で重み付けして評価するということです。
複雑な経験ではピーク・エンドの効果は弱まる
長期的な経験や複数エピソードから構成される経験において、ピーク・エンドの法則の限界について見てきました。感情的に複雑で多面的な経験ではどうでしょうか。例えば、興奮と不安、喜びと悲しみなど、様々な感情が入り混じる映画鑑賞のような経験では、ピーク・エンドの法則はどの程度適用できるのでしょうか。
この問いに答えるために、より制御された環境で実施された研究があります。この研究では、バーチャルリアリティ(VR)技術を用いて、複雑で多面的な感情体験を参加者に提供しました[3]。VRは実験室の統制を保ちながら現実的な経験を再現できる手法として評価されています。
この実験では、大学生40名(男性16名、女性24名)が参加し、VRゴーグルを通じて14分間の映画を視聴しました。この映画は、科学的な成功や達成感といったポジティブな感情と、裏切りや暴力といったネガティブな感情を明確に誘発するストーリーを持ち、複雑で多面的な経験を再現することができました。
映画視聴後、参加者は経験した内容をできるだけ詳細に口頭で再構成しました。この再構成されたストーリーに基づいて、体験が複数のエピソードに分割されました。そして、各エピソードに対して「感情価」(快–不快)と「覚醒度」(覚醒–鎮静)を9段階で評価してもらいました。また、映画終了直後と1週間後の2回にわたり、映画全体の感情価と覚醒度の総合評価も求めました。
この実験から得られた結果は、次のようなものでした。経験直後の全体的な感情価(快–不快)は、ピークの感情価が最もよく予測しましたが、1週間後の感情価は平均の感情価が最も強い予測因子となりました。時間が経過すると、ピークの影響力は弱まり、平均的な感情体験の方が全体評価に強く影響するようになったのです。
覚醒度(興奮度)に関しては、経験直後も1週間後も、平均的な覚醒度が最も強い予測因子となりました。注目したいのは、ピーク・エンドの法則(ピークとエンドの感情状態の平均)が、多面的な感情体験ではそれほど強力な予測因子とはならなかった点です。むしろ、全体の平均感情価や覚醒度の方が優れた予測力を持つことが明らかになりました。
これらの結果から、ピーク・エンドの法則は複雑な感情体験においては限界があることが示されました。ポジティブとネガティブの両方の感情が混在するような複雑な経験では、ピークやエンドよりも、体験全体の平均的な感情状態の方が評価に強く影響すると考えられます。
この研究は、ピーク・エンドの法則が特に単純な感情体験に有効なのに対し、日常的な複雑な感情経験には適用が困難である可能性を指摘しています。人間の感情体験と記憶の関係は、単純な法則では説明しきれない奥深さを持っています。
経験評価はピーク・エンドより改善傾向が重要
ピーク・エンドの法則は様々な状況で限界を示しています。それでは、経験を評価する際に私たちが重視しているのは何なのでしょうか。それを探る研究として、経験の「傾き」(改善傾向か悪化傾向か)に焦点を当てた研究があります[4]。
この研究では、経験は継続的で多様な一連の瞬間的な状態(経験プロファイル)から成ると考えました。そして、経験評価において特に重要と考えられる「ゲシュタルト特性」として、次の3つを挙げています。
- ピーク:経験の中で最も感情が強かった瞬間
- エンド:経験の終了時点の感情状態
- 傾き:経験の全体的な変化の傾向(例:改善傾向か悪化傾向か)
この研究では、実際の病院の骨髄移植ユニットで、痛みを経験する患者を対象としたフィールドスタディを行いました。37名の入院患者が参加し、毎時間、0(無痛)から100(想像できる最も強い痛み)の尺度で痛みを評価しました。そして一日の最後に、その日の痛み全体を同じ尺度で評価してもらいました。
この研究の結果、全体評価に最も強く影響したのは、「エンド」(最終評価時点の痛み)と「傾き」(痛みが増加したか減少したか)でした。特に、痛みが時間とともに減少していく「改善傾向」が全体評価を大きく左右しました。一方、「ピーク」(最大の痛み)は、この研究では有意な予測因子とはなりませんでした。
例えば、同じ平均的な痛みレベルを持つ二つの経験を比較すると、徐々に痛みが軽減していく経験の方が、徐々に痛みが強くなる経験よりも、全体として良い評価を受ける傾向があるのです。
なぜ「傾き」や「改善傾向」が重要なのでしょうか。研究者たちは二つの理論的説明を提示しています。
一つは「外挿説」です。経験の傾きやエンドの状態が、将来の状況を推測するための情報となるため重要であるという考え方です。例えば、痛みが徐々に軽減している状態は、「このままいけばさらに良くなるだろう」という予測を生み出し、全体評価を好転させるのかもしれません。
もう一つは「符号化説」です。これは認知資源の限界のため、経験は少数の特徴に符号化(記憶)されるため、重要なゲシュタルト特性が選ばれるという説です。特に変化の傾向は、経験を要約するのに便利な情報であるため記憶に残りやすいのかもしれません。
この研究はまた、経験評価に影響する状況的要因についても指摘しています。
- 期待:経験がどのように変化すると期待しているかによって、改善傾向の好ましさが変化することがあります。
- 連続的vs分節的な経験:経験が連続的に知覚されるか、明確に区切られて知覚されるかにより評価が異なります。連続的な経験の方が改善傾向がより強く評価されます。
- 経験の意味や目的:行列待ちの経験など、目的達成が重要な経験ではエンドが特に重要です。
脚注
[1] Kemp, S., Burt, C. D. B., and Furneaux, L. (2008). A test of the peak-end rule with extended autobiographical events. Memory & Cognition, 36(1), 132-138.
[2] Miron-Shatz, T. (2009). Evaluating multi-episode events: A boundary condition for the peak-end rule. Emotion, 9(2), 206-213.
[3] Strijbosch, W., Mitas, O., van Gisbergen, M., Doicaru, M., Gelissen, J., and Bastiaansen, M. (2019). From experience to memory: On the robustness of the peak-and-end-rule for complex, heterogeneous experiences. Frontiers in Psychology, 10, 1705.
[4] Ariely, D., and Carmon, Z. (2000). Gestalt characteristics of experiences: The defining features of summarized events. Journal of Behavioral Decision Making, 13(2), 191-201.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。