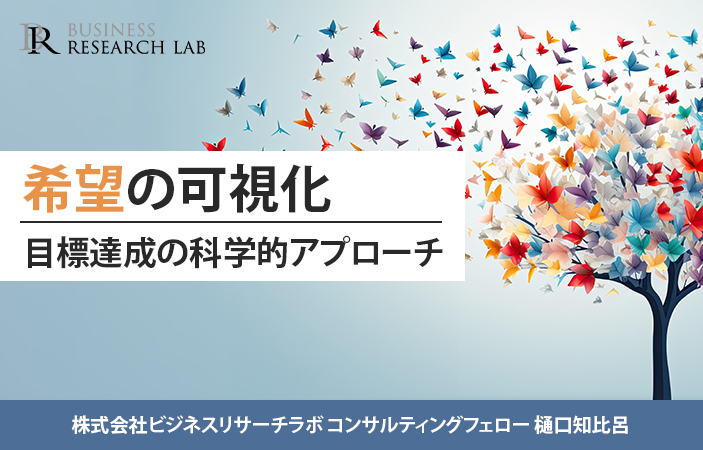2025年7月17日
希望の可視化:目標達成の科学的アプローチ
現代の企業経営において、従業員の心理的資本(Psychological Capital: PsyCap)が業績や職務満足度に与える影響が注目されています。心理的資本とは、希望、自己効力感、レジリエンス、楽観主義の4つの要素から成る概念であり、内なるHERO(Hope, Efficacy, Resilience, Optimism)と呼ばれ、個人のポジティブな心理状態を測る指標として用いられます。
今回のコラムでは、心理的資本の構成要素の一つである「希望」に着目をしていきます。希望は、「成功するために、目標に向かって忍耐強く努力し、必要な場合には目標への経路を転換すること」と定義されています[1]。これまでの研究によると、希望は単なる楽観的な感情ではなく、具体的な行動計画とその遂行能力に関連する概念であることが明らかになってきています。
本コラムでは、希望の目標設定や達成への影響、また希望が個人と組織のパフォーマンス向上にどのように貢献するのか、希望の状態の測定について詳しく解説していきます。
希望はストレスの軽減や目標達成への積極的な行動と強く関連する
楽観主義と希望はどのように異なるのかという問いに対し、メタ分析によって、これらが互いに区別可能な構成概念であることを示した研究があります[2]。メタ分析とは、独立して実施された複数の研究結果を統合し、それらを解析する方法です。
研究は、楽観主義と希望がいずれも将来への肯定的な期待に関連しているものの、楽観主義は「運や環境要因による成功」を信じる傾向が強く、希望は「目標達成に向けた具体的な行動計画」を重視するという違いがあると指摘しています。このメタ分析では、過去の研究を統合し、楽観主義と希望がそれぞれ心理的および身体的なウェルビーイングとどのように関連しているかを検証しました。
結果として、楽観主義は生活満足や身体的健康、抑うつの軽減と強く関連しており、希望はストレスの軽減や目標達成への積極的な行動と強く結びついていました。
特に、楽観主義は「自分でコントロールできない状況」で力を発揮し、希望は「自分の行動次第で変えられる状況」で効果的であることが明らかになりました。これにより、単に「ポジティブでいること」が重要なのではなく、それが楽観主義なのか希望なのかによって、効果が異なるという点が示唆されています。
実務への含意としては、職場でのメンタルヘルス支援や目標設定のアプローチを見直すことが挙げられます。例えば、上司が部下に対して単に「大丈夫だよ」と声をかけるだけではなく、具体的な行動計画やサポートを提供することが効果的です。これにより、従業員は「できるかもしれない」という希望を持ちやすくなり、業務への意欲も高まります。
希望の多面性を学問横断で探る
次に、希望の特徴について異なる学問分野の視点をまとめ、希望の包括的な理解を目指した研究を紹介します[3]。この研究では、経済学、心理学、看護学など10の分野から66の論文を分析し、現象学的アプローチ(人の主観的な経験や意識の構造を重視し、物事を当事者の視点から理解しようとする哲学的・研究的手法)を用いて希望に関する7つのテーマと41のサブテーマを抽出しました。これにより、希望が持つ多面的な性質を浮き彫りにし、従来の単一視点では見えにくかった側面が明らかになりました。
まず、希望は「未来への肯定的な期待」にとどまらず、「具体的な行動計画」や「社会的・文化的文脈」にも大きく依存していることが示されました。例えば、心理学では希望は個人のレジリエンスや目標達成に関連付けられ、看護学では患者が困難な治療を乗り越えるための心理的支えとして重視されています。
また、経済学では希望が消費行動や投資意欲に影響を与える要因とされています。このように、希望は状況や対象によって異なる意味を持ち、単純に「ポジティブな感情」として片付けられない複雑さがあることがわかります。
実践的な含意としては、「社会的文脈」や「文化的背景」を考慮に入れる重要性を強調しています。例えば、企業の従業員満足度調査で希望を測る際には、職場の風土や同僚との関係も評価対象に含めると、より実態に即したデータが得られるでしょう。
マネジメントへの応用としては、従業員の希望を育む環境作りが挙げられます。例えば、キャリアパスの提示や自己啓発の支援は、従業員に「未来への具体的な経路」を与え、希望を喚起します。また、心理的安全性を確保し、失敗しても再挑戦できる文化を作ることは、希望の要素である「行動計画」を後押しします。
さらに、経営層がビジョンを共有し、透明性の高いコミュニケーションを行うことで、組織内に「集団的な希望」が広がります。集団的な希望とは、組織やコミュニティの構成員が共通の目標に向かって進む中で、「達成可能である」という前向きな期待や信念を共有している状態を指します。これにより、従業員のエンゲージメントが高まり、結果として生産性や業績の向上につながると考えられます。
希望は多様な文脈で異なる形をとり得る複雑な現象
希望という人間特有の感情について、多様な視点からの理解を深めるための包括的な枠組みを提供した研究があります[4]。哲学、人類学、心理学、神学、政治学など複数の学問分野を横断し、希望を「忍耐強い希望」「批判的希望」「推定的希望」「断固とした希望」「ユートピア的希望」の5つの様式に分類しました。これにより、希望は単なるポジティブな感情ではなく、多様な文脈で異なる形をとり得る複雑な現象であることが明らかになりました。
まず、「忍耐強い希望」は、未来に対する開かれた姿勢と、目標に対する執着を避ける態度を特徴としています。例えば、長期的なプロジェクトにおいて、結果を急がずに進める姿勢はこの希望に近いでしょう。
「批判的希望」は、現状に対する批判と、より良い未来への信念を併せ持つ様式です。これは、組織改革を進める際に役立つ視点で、現状の問題を認識しつつ、改善の可能性を信じ続ける力になります。
「推定的希望」は、現実的な見積もりと可能性への期待を特徴とし、証拠に基づいた希望です。これにより、ビジネスにおいては、市場調査やデータ分析を通じて合理的な目標設定が行いやすくなります。
「断固とした希望」は、物事はどうあるべきかという証拠に反してでも信じ続ける強い意志を持つ希望です。困難な状況でも目標を見失わず、チームを鼓舞するリーダーシップには、この要素が求められるでしょう。
「ユートピア的希望」は、理想の社会を夢見る希望で、変革を促す原動力となります。例えば、持続可能な経営や社会貢献に積極的な企業ビジョンは、この希望の様式に近いといえます。
実践的な含意としては、希望の様式を理解し、状況に応じて適切な形で希望を育むことが有用です。例えば、短期的な成果が求められるプロジェクトでは「推定的希望」に基づく現実的な見積もりが効果的です。一方で、長期ビジョンや変革期には「ユートピア的希望」を示し、チームのモチベーションを維持することが重要です。
マネジメントへの応用としては、組織のビジョンや目標設定において、希望の様式を活用することが考えられます。トップダウンでの目標設定では「断固とした希望」によって困難に立ち向かう意志を示しつつ、ボトムアップの場面では「批判的希望」によって現場の声を反映する姿勢が求められます。
また、組織文化として「忍耐強い希望」を育むことで、長期的視点に立った事業運営が可能になります。希望の多様な様式を理解し、それを戦略的に使い分けることで、組織の持続的成長を支える強力な基盤が築かれるでしょう。
希望の状態は測定が可能
目標達成に対する希望の状態を測定するための「状態希望尺度(State Hope Scale: SHS)」を開発した研究を紹介します[5]。
希望は、目標達成に必要な行動を起こし維持する「主体性(Agency)」と、目標に到達するための具体的な道筋を見出す「経路(Pathway)」という2つの要素から成ると定義されています。状態希望尺度は、この2つの要素に基づき6項目から成る各項目がこれらの要素を測定しています。
項目と尺度の意味はそれぞれ以下で構成されます。
- 主体性の項目:自分の力を信じ、困難や迷いがあっても目標達成に向けて前進し続ける信念があるかどうか、という意味の尺度で構成されます。
- 経路の項目:目標達成に向けて効果的な経路や解決策を見出し、計画を立てる力があるかを問う意味の尺度で構成されます。
調査結果から、状態希望尺度の信頼性と妥当性が確認されました。このことは状態希望尺度が信頼できるツールであり、その結果に基づいて具体的な行動や戦略を検討する価値があることを意味します。特に、日々の出来事に対する反応を測定できる点が特徴です。
たとえば、目標達成に成功した人は状態希望尺度のスコアが上昇し、失敗した人は下降しました。また、状態希望尺度は性差を示さず、社会的望ましさや自尊心などの影響も受けにくいことが明らかになりました。この結果は、希望が単なる楽観主義とは異なり、状況に応じた目標指向の思考プロセスであることを示しています。
実践的な含意として、目標達成支援に有用です。たとえば、ビジネスの場面では、プロジェクト管理やチームマネジメントにおいて、個人の状態希望尺度スコアを用いることで、メンバーの目標達成に向けた障害を特定し、モチベーション維持のための介入策を検討できます。具体的には、主体性が低い場合は目標達成への自信を高める支援が、経路が不足している場合は具体的な行動計画を立てる支援が効果的でしょう。
また、状態希望尺度は短期間での心理状態の変化を捉えることができるため、人材育成や評価制度においても応用可能です。たとえば、キャリアカウンセリングでは、状態希望尺度の結果を基にキャリア目標への経路を明確にする支援が考えられます。さらに、組織全体で状態希望尺度を活用し、目標管理システムに組み込むことで、個々のメンバーが持つ希望の状態を可視化し、モチベーション向上策やストレスマネジメントに役立てることも有用です。
このように、状態希望尺度はビジネスパーソンが自己効力感や目標達成意欲を向上させるための指標として、効果的に活用できるでしょう。状態希望尺度の結果を活用することで、個人やチームのパフォーマンス向上に貢献できる可能性があります。
希望理論が示す目標達成への経路と動機づけ
希望が学業やスポーツ、心理的適応において好ましい結果と関連していることを明らかにした研究があります[6]。希望を主体性と経路の2要素から成る認知的枠組みとして定義し、大人と子どもを対象に状態希望尺度を用いた調査を行いました。
調査の結果、希望の高い人は目標達成に向けて複数の経路を考え、自信を持って行動に移す傾向がある一方、希望が低い人は行動の選択肢が限られ、困難に直面すると挫折しやすいことがわかりました。また、希望は目標に対して現実的かつ戦略的に対処するための認知的枠組みであると示されています。
特に、困難に直面したときにどのように目標を維持し続けるかは、希望の度合いによって大きく左右されます。希望の低い人は障害に対して悲観的に捉えやすいのに対し、希望の高い人は代替ルートを素早く見つけ、目標に向けた行動を再開する能力が高いことが明らかになりました。
この理論の実践的な含意として、ビジネスパーソンが目標を設定する際には、単に高い目標を掲げるだけでなく、その目標に向かうための具体的な経路と、それを実行に移す自信と主体性の両方を意識することが重要です。
たとえば、営業チームで売上目標を設定する際には、目標達成のための具体的な行動計画を共有し、成功体験を通じてメンバーの自己効力感を高めることが効果的です。また、上司やマネージャーは、メンバーが障害に直面した際に複数の選択肢を提案し、目標達成への希望を維持できるようサポートすることが求められます。
マネジメントへの応用としては、目標管理制度(Management by Objectives: MBO)の中で、状態希望尺度を活用する方法が考えられます。たとえば、四半期ごとに主体性と経路の両方を測定し、低いスコアの社員には目標達成のためのメンタリングや具体的な行動プランを提供することで、モチベーションの維持と向上を図ることができます。また、状態希望尺度を人材育成の指標とすることで、次世代リーダーの育成にも役立てることができるでしょう。
内的希望・外的希望が示す目標達成の多様性
希望理論を拡張し、目標達成における「希望の所在(locus-of-hope)」という新たな次元を提案した研究を紹介します[7]。希望の所在は、目標達成に向けた希望が自分自身の内的資源(自己)だけでなく、家族・友人・スピリチュアルな存在など外的資源にも根ざしている可能性を示す概念であり、希望理論を個人とその社会的文脈に拡張したものです。この研究は、フィリピンの200人の大学生を対象に2つの研究が行われ、希望が個人の内的な力(内的希望)だけでなく、家族や仲間、宗教など外的な要素にも依存する(外的希望)ことを明らかにしています。
調査結果から、希望の所在が異なると目標達成へのアプローチも異なることが示されました。具体的には、内的希望を持つ人は、自分自身の力で目標を達成しようとし、行動力と具体的な計画を重視します。また、外的希望を持つ人は、家族や仲間、宗教的な支えに依存し、目標達成においてこれらの外的リソースを活用します。
また、外的希望は集団主義的文化において特に有効であることがわかり、文化的背景が希望の所在に与える影響が浮き彫りになりました。これは、目標達成が個人の問題にとどまらず、社会的ネットワークや文化的価値観とも密接に関わっていることを示しています。
実践的な含意として、希望の所在に応じた目標管理やモチベーション戦略が有効であると考えられます。たとえば、内的希望が強いメンバーには、個人の力量を活かせる挑戦的な目標と自己決定を尊重するサポートが効果的です。
これに対して、外的希望が強いメンバーには、チームの協力や家族の支援を活用した共同目標の設定や、メンターや仲間からのフィードバックを充実させることが有用です。また、宗教や信念に支えられた外的希望を持つ人には、長期的な目標とその意義を再確認させる機会を提供するとよいでしょう。
マネジメントへの応用としては、希望の所在を評価するためのアセスメントを取り入れ、社員一人ひとりの希望の特徴に合わせたリーダーシップとサポートが求められます。たとえば、フィリピンのように家族や仲間との結びつきが強い文化圏では、チームビルディングや家族参加型のイベントを通じて外的希望を育むことが、業績向上に貢献するかもしれません。
逆に、アメリカのように個人主義が強い文化圏では、目標達成へのプロセスを個人に委ね、自己効力感を高めることが効果的です。希望の所在を理解し、それに応じた戦略を設計することで、組織全体のパフォーマンスと社員の満足度を向上させることができるでしょう。
希望が目標設定に与える影響と実務への応用
希望理論の根底にある仮説と尺度を検討した研究を紹介します[8]。この研究では、アメリカ中西部の大学に通う学生を対象に2つの調査を実施しました。研究1では、162名の学生が希望尺度に回答し、具体的な目標を設定しました。研究者がこれらの目標を評価した結果、希望が高い学生ほど、向社会的(他者や社会全体の利益を考え、自発的に支援や協力を行う態度や行動)で長期的かつ困難な目標を設定しやすいことがわかりました。
研究2では、118名の学生に対して、事後報告形式の測定に加えて、3つの目標を提示しそれぞれの目標を達成のための経路をできるだけ多く作成させて、希望、楽観性、自己効力感との関連を分析しました。その結果、希望が高い人ほどより多くの実行可能な経路を考え出す傾向が確認されました。また、希望は楽観性や自己効力感とは関連がないことも示されました。
この調査から、希望は単なるポジティブな考え方ではなく、具体的な行動計画を生み出す力があることが明らかになりました。特に、希望が高い人は、より難しい目標に対しても複数の経路を考え、計画的に取り組む傾向があります。これは、目標達成において、希望が具体的かつ実行可能なプランニング能力と直結していることを示しています。
また、希望が長期的で向社会的な目標と強く結びついていることは、チームや組織の目標管理にも応用できるでしょう。例えば、希望が高い人材を中心にプロジェクトを編成すれば、困難な目標に対しても粘り強く取り組むことが期待できます。
実務への含意としては、希望を高めるためのトレーニングやフィードバック制度が有用です。例えば、社員が具体的な経路を考えられるようにワークショップを実施し、小さな成功体験を積ませることで、希望と主体性を強化できます。また、目標設定の際には、希望のレベルを把握し、個々人に応じた支援を提供するとよいでしょう。希望が低い社員には、フィードバックを通じて達成可能な短期目標を設定し、少しずつ自信と希望を育てていきながら段階的に主体性を高めるサポートが効果的です。
さらに、マネジメントへの応用としては、状態希望尺度を用いた社員評価が考えられます。希望が高い社員は、より積極的に目標を設定し、問題解決に取り組む傾向があるため、リーダー候補として適しているかもしれません。
希望の測定と活用が、組織の成長と持続可能な成功のカギ
本コラムでは、希望の概念とその測定方法、さらにビジネスにおける実践的な応用について論じてきました。希望は、単なる楽観主義とは異なり、目標達成に向けた明確な行動計画と実行能力を支える重要な要素であることが、さまざまな研究を通じて示されています。特に、状態希望尺度は、個人の希望の状態を定量的に測定し、その結果をもとに具体的な行動戦略を立案するための有力なツールとして活用可能です。
ビジネスの現場において、希望の概念を取り入れることは、従業員のエンゲージメントやモチベーションを高めるだけでなく、組織の目標達成能力を向上させることにもつながります。
例えば、プロジェクトマネジメントの場面では、チームメンバーの希望の状態を測定し、それに応じたサポートやフィードバックを提供することで、メンバーが困難に直面しても前向きに挑戦し続ける環境を整えることができます。また、人材育成の視点からも、希望の状態に応じた育成プログラムを設計することで、個々の強みを最大限に引き出すことが可能になります。
さらに、希望が個人の内的希望だけでなく、家族や仲間、宗教など外的希望にも影響されることが明らかになっており、この点にも注目する必要があります。組織文化やチームの関係性を考慮しながら、希望を育む環境を整えることで、より多様なアプローチで従業員の成長を支援することができます。
今後、企業が希望の概念をどのように取り入れ、活用していくかが、組織の成長と持続可能な成功のカギを握るでしょう。希望を測定し、適切なサポートを提供することで、従業員のモチベーションを高め、組織の目標達成能力を向上させることができます。このように、希望は単なる理論的な概念ではなく、実務において具体的な成果を生み出す重要な戦略要素として位置付けることができるのです。
脚注
[1] Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel psychology, 60(3), 541-572.
[2] Alarcon, G. M., Bowling, N. A., & Khazon, S. (2013). Great expectations: A meta-analytic examination of optimism and hope. Personality and individual differences, 54(7), 821-827.
[3] Pleeging, E., van Exel, J., & Burger, M. (2022). Characterizing hope: An interdisciplinary overview of the characteristics of hope. Applied Research in Quality of Life, 17(3), 1681-1723.
[4] Webb, D. (2007). Modes of hoping. History of the human sciences, 20(3), 65-83.
[5] Snyder, C. R., Sympson, S. C., Ybasco, F. C., Borders, T. F., Babyak, M. A., & Higgins, R. L. (1996). Development and validation of the State Hope Scale. Journal of personality and social psychology, 70(2), 321.
[6] Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological inquiry, 13(4), 249-275.
[7] Bernardo, A. B. (2010). Extending hope theory: Internal and external locus of trait hope. Personality and individual differences, 49(8), 944-949.
[8] Cheavens, J. S., Heiy, J. E., Feldman, D. B., Benitez, C., & Rand, K. L. (2019). Hope, goals, and pathways: Further validating the hope scale with observer ratings. The Journal of Positive Psychology, 14(4), 452-462.
執筆者
 樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
早稲田大学政治経済学部卒業、カリフォルニア州立大学MBA修了、UCLA HR Certificate取得、立命館大学大学院博士課程修了。博士(人間科学)。国家資格キャリアコンサルタント。ビジネスの第一線で30年間、組織と人に関する実務経験、専門知識で、経営理論を実践してきた人事のプロフェッショナル。通信会社で人事担当者としての経験を積み、その後、コンサルティングファームで人事コンサルタントやシニアマネージャーを務め、さらに銀行で人事部長などの役職を歴任した後、現在はFWD生命にて執行役員兼CHROを務める。ビジネスと学術研究をつなぐ架け橋となることを目指し、実践で役立つアプローチを探求している。