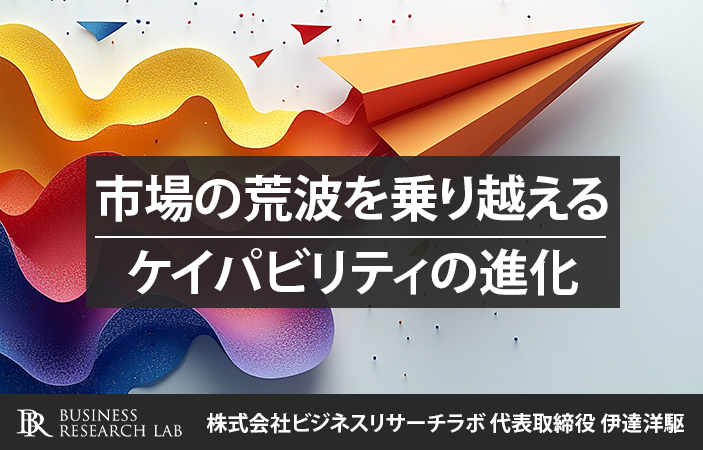2025年7月16日
市場の荒波を乗り越える:ケイパビリティの進化
企業が長期的な成功を収めるためには、変化する市場に柔軟に対応する力が求められます。環境の不確実性が高まる中で、企業の適応能力、すなわち「ケイパビリティ」の重要性が増しています。ケイパビリティとは、企業が持つ資源や能力を効果的に活用し、価値を創造する力を指します。
急速に変化する市場においては、既存のケイパビリティを維持するだけでなく、それを変化させ、進化させなければなりません。ケイパビリティの変化は、企業が競争優位を獲得・維持するための鍵となります。
本コラムでは、ケイパビリティがどのように変化し、進化するのかについて、いくつかの角度から考察します。絶え間ない組織変革、企業間の知識共有、市場環境の変化に対する応答、そして製品イノベーションを通じたケイパビリティの再構築という視点から、企業の持続的成長のメカニズムを探ります。
絶え間ない変形がケイパビリティを進化させる
企業が長期にわたって競争優位を維持することは、変化の激しい市場環境では困難な課題です。急速に変化する環境では、安定した組織形態が変化への適応を妨げる要因となることがあります。
インターネット黎明期に登場したYahoo!とExciteの事例は、この点について教訓を提供しています[1]。両社は短期間で劇的な変化を遂げましたが、その進化の過程と結果には違いがありました。
Yahoo!とExciteは、どちらも検索エンジンとして出発しました。1994年から1996年前半にかけて、両社は異なるアプローチで検索機能を提供していました。Yahoo!は人間の「サーファー」による手作業でのウェブサイト分類を行い、Exciteは高度な自動検索アルゴリズムを使用していました。しかし、検索技術自体がコモディティ化し、検索機能だけでは競争優位を維持できなくなりました。
この状況に対応するため、両社は1996年から1997年にかけて、コンテンツ提供サイトへと変化しました。Yahoo!はブランド構築とマーケティングに力を入れ、「Yahoo! Finance」などの独自コンテンツを提供する「メディア企業」へと変貌しました。一方、Exciteも同様のブランド構築を試みましたが、資金難により組織能力の再構築に苦戦しました。
さらに1998年から1999年にかけて、両社はインタラクティブなサービスを提供するWebポータルへと進化しました。Yahoo!は企業買収を通じて物流やEコマースなどの新たな能力を獲得し、独立した企業として競争優位性を維持しました。対照的に、Exciteは資金難により@Homeとの合併を余儀なくされ、独立性を失い競争優位を喪失しました。
この事例研究から導き出される概念が「連続的変化(Continuous Morphing)」です。これは企業が競争環境の変化に対応して、製品・サービス・資源・能力・組織形態を絶え間なく変化させるプロセスを指します。
連続的変化のプロセスでは、ダイナミック・ケイパビリティが中心的な役割を果たします。ダイナミック・ケイパビリティとは、新たな競争優位性を創出する能力であり、組織形態の変化によって促進されます。企業が資源や能力を柔軟に転用する能力、すなわち戦略的柔軟性も、組織形態の連続的変化を可能にする要素です。
しかし、こうした絶え間ない変化は、一つの矛盾をもたらします。組織の継続的な変化は競争優位性を再生産する一方で、その優位性の持続期間を短くする可能性があるのです。すなわち、変化が激しい環境では、静的な競争優位の保護よりも、絶え間ない再構築が重要になります。
知識共有がケイパビリティを高め競争力を生む
組織が絶え間なく形を変えることでケイパビリティを進化させる過程を見てきました。しかし、ケイパビリティの向上は組織内部の変革だけでなく、企業間の協力関係からも生まれます。知識共有のネットワークを構築・管理することは、企業の競争力を高める上で有効です。
トヨタ自動車の事例は、企業間の知識共有がいかにケイパビリティを向上させるかを理解する上で価値があります[2]。トヨタは自社とサプライヤー企業の間で高度な知識共有ネットワークを構築し、生産システム全体の継続的改善を実現しました。
組織の学習能力や知識管理が競争優位の源泉になるという考え方は広く認識されています。しかし、従来は企業内部の学習に焦点が当てられることが多く、企業間のネットワークを通じた学習の可能性は十分に探求されていませんでした。自動車産業は、製品の品質やコストがメーカー単独ではなく、サプライヤーとのネットワークによって左右される典型例です。
トヨタは企業間の知識共有を促進するため、いくつかの制度化されたルーティン(日常的な活動)を確立しました。例えば、サプライヤー協会(日本では「協豊会」)は、多面的な情報・ノウハウ共有のための定期的会合を開催し、サプライヤー間の交流を促進しています。日本では1943年、米国では1989年に設立され、長い歴史を持っています。
また、現場コンサルティングとして、トヨタの専門家チーム(OMCD/TSSC)がサプライヤーの生産現場を訪問し、具体的な問題解決やトヨタ生産方式(TPS)の実装支援を行います。このサービスは無償で提供され、サプライヤー全体の生産能力向上に貢献しています。
自主研究会(「自主研」)では、サプライヤー同士が小グループで互いの生産現場を訪問し、実践的に生産改善を行います。この活動は日本では1977年、米国では1994年に導入され、相互学習の場として機能しています。
これらに加えて、問題解決チームの結成、従業員の出向・転籍、パフォーマンスのフィードバックとモニタリングといった活動も、知識共有ネットワークの要素となっています。これらのルーティンがネットワーク全体の学習能力向上に貢献しているのです。
トヨタのケースから、効果的な知識共有ネットワークには、いくつかの特徴があることがわかります。知識蓄積のための専任組織を設置することが重要です。トヨタのOMCDやTSSCがこれに当たります。また、生産技術などの特定領域での知識の「非専有化」を推進することで、ネットワーク全体の能力向上が図られています。
さらに、全体的なネットワークと小規模なネットワークを併用する多層的な構造も有効です。大きなネットワークでは広範な知識にアクセスできる一方、小規模なグループでは深い相互学習が可能になります。加えて、知識獲得・応用へのインセンティブを明確化することも重要です。フィードバックなどを通じて、学習のモチベーションを高めることができます。
トヨタが米国に新たなサプライヤーネットワークを構築した際は、日本と同様の順序で制度を導入しました。協会を設立し、現場コンサルティングを始め、その後に自主研究会を導入するというアプローチです。このプロセスにより、ネットワークが成熟するにつれて多層的で高度な知識共有が実現されました。
企業競争優位の源泉としての「ダイナミック・ケイパビリティ」は、企業単独ではなく、企業間ネットワークの次元まで拡張して理解する必要があります。個々の企業の能力だけでなく、ネットワーク全体の学習能力が競争力を左右します。
ケイパビリティは市場環境で性質が変化する
企業のケイパビリティが組織の変革や知識共有によって進化することを見てきましたが、それらのケイパビリティは市場環境によってどのように性質が変化するのでしょうか。この問いに答えるため、ダイナミック・ケイパビリティという概念に焦点を当ててみましょう[3]。
ダイナミック・ケイパビリティは、「企業が資源基盤を統合・再構成し、変化する市場環境に適合または新たな市場機会を創造するために利用するプロセス」と定義されます。具体的には、製品開発プロセス、戦略的意思決定プロセス、アライアンス形成プロセスなどが含まれます。これらは抽象的な概念ではなく、具体的かつ識別可能なルーティンであり、実務的にも観察可能なものです。
ダイナミック・ケイパビリティには、企業固有の側面と企業間で共通する側面が共存しています。例えば、製品開発における機能横断的チームの活用やアライアンスでの外部情報との連携など、多くの企業で見られる「ベストプラクティス」があります。ダイナミック・ケイパビリティは細部においては企業固有であるものの、中核的要素においては企業間で共通していると言えます。
この共通性により、ダイナミック・ケイパビリティは完全に独自で模倣困難なものではなく、ある程度の模倣や代替が可能です。このことは、従来のリソース・ベース・ビュー(企業の資源の希少性や模倣困難性を競争優位の源泉とする理論)とは異なる視点を提供しています。
ダイナミック・ケイパビリティの特質は、市場環境の動態性によって変化します。市場環境は「中程度に動的な市場」と「高度に動的な市場」に大別されます。
中程度に動的な市場では、産業構造が比較的安定しており、変化も予測可能です。このような環境では、ダイナミック・ケイパビリティは複雑で詳細かつ分析的なプロセス(ルーティン)の形をとります。既存知識に基づく分析や予測可能な結果を生み出すため、典型的なルーティンの性質を帯びます。例えば、化学製品の開発プロセスは、細部まで文書化された手順に従って行われることが多いでしょう。
一方、高度に動的な市場では、市場構造やビジネスモデルが不明瞭で変化が激しいため、ダイナミック・ケイパビリティはシンプルで実験的なプロセスとなります。こうした環境では、状況特有の知識を迅速に創出し、不確実性に即応することが必要です。そのため、シンプルなルール(例えばインテルの資源配分ルールやYahoo!のアライアンス形成ルール)によって迅速な意思決定が行われることになります。
これらの対比は、ダイナミック・ケイパビリティの有効性が市場環境によって変化することを表しています。同じ能力でも、置かれる環境によってその価値や機能が変わるのです。
ダイナミック・ケイパビリティは、いくつかの学習メカニズムを通じて進化します。まず、繰り返しの実践によって経験が蓄積され、能力が深まります。また、獲得した経験を明確な手順やマニュアルに落とし込む知識の明示化も、能力の形成を促進します。
さらに、小さな失敗からの学習によって、能力が精緻化されることもあります。ただし、経験のペースも重要で、経験が多すぎても少なすぎても能力構築に悪影響を与える可能性があります。加えて、能力の獲得には順序性があり、基礎的な能力をまず身につけ、その上に高度な能力を構築することが必要です。
ダイナミック・ケイパビリティ自体は長期的な競争優位の直接の源泉ではありません。むしろ、それを用いて創造された資源構成こそが競争優位を生みます。ダイナミック・ケイパビリティが、頻繁に変化する市場において短期的で連続的な優位性を生むために価値があるということです。
製品イノベーションがケイパビリティを再構築
企業は実際にどのようにしてケイパビリティを再構築し、進化させるのでしょうか。製品イノベーションの視点から、このプロセスを探ってみましょう[4]。
製品イノベーションと企業のコンピタンス(企業が特定の活動を行う能力)には相互関係があります。新製品の開発は、企業の既存のコンピタンスを活用するだけでなく、新たなコンピタンスの獲得や既存コンピタンスの組み換えをもたらします。この相互作用を理解することで、企業が長期的に成長し続けるメカニズムが見えてきます。
製品イノベーションに関わるコンピタンスは、主に二つのタイプに分けられます。一つは「顧客コンピタンス」で、顧客のニーズ理解、販売チャネル、顧客とのコミュニケーション、ブランド評判などを含みます。もう一つは「技術コンピタンス」で、製品の設計・製造技術、品質管理などが含まれます。新製品の開発は、これら二つのコンピタンスを結びつける行為だと考えられます。
企業が持つ顧客・技術のコンピタンスを「深化(exploitation)」するか、新たに「探索(exploration)」するかによって、新製品開発は4つのタイプに分類できます。
「純粋な深化」は既存の顧客と既存の技術を利用するタイプです。企業がよく知っている顧客に、既に持っている技術を用いて新製品を提供するこのアプローチは、比較的リスクが低く、短期的な成果が見込めます。ただし、長期的には革新性が限られるという欠点があります。
「顧客コンピタンスのレバレッジ」は、既存顧客に新技術を適用するアプローチです。このタイプでは、顧客のニーズや市場へのアクセス方法は理解していますが、新しい技術的能力を獲得する必要があります。例えば、既存の顧客向けに全く新しい技術を用いた製品を開発するケースが当てはまります。
「技術コンピタンスのレバレッジ」は、既存技術を新顧客に提供するアプローチです。この場合、技術的な能力はありますが、新しい市場に参入するための顧客理解やマーケティング能力を獲得する必要があります。例えば、既存の技術を用いて全く新しい市場向けの製品を開発するケースが該当します。
「純粋な探索」は新顧客・新技術を同時に獲得するアプローチです。これは最も挑戦的であり、リスクの高いタイプです。企業は全く新しい市場と技術の両方を理解・習得する必要があります。ただし、成功すれば長期的な成長につながる可能性があります。
これら4つのタイプの製品イノベーションは、それぞれ異なる学習プロセスを伴い、企業のコンピタンスに異なる変化をもたらします。「純粋な深化」では既存のコンピタンスが強化されますが、「純粋な探索」では全く新しいコンピタンスが獲得されることになります。
企業のコンピタンス蓄積には経路依存性があります。過去の選択が将来の選択肢を限定するということです。例えば、企業が特定の技術や市場に投資してきた場合、その経験や知識に基づいて次の製品開発が行われる可能性が高く、全く異なる分野への展開は難しくなります。
ここで、より高次の能力として「二次コンピタンス」という概念が提案されています。これは新しい「一次コンピタンス」(顧客コンピタンス、技術コンピタンス)を獲得する能力を意味します。例えば、新しい市場へのアクセス方法を学習し習得する能力を「二次マーケティングコンピタンス」、新しい技術を導入する能力を「二次R&Dコンピタンス」と呼びます。
二次コンピタンスが高い企業は、環境変化に対して柔軟に適応し、持続的に成長できる可能性が高まります。新しい市場や技術への移行が効果的に行えるからです。逆に、二次コンピタンスが低い企業は、既存の市場や技術に固執し、環境変化に対応できない可能性があります。
脚注
[1] Rindova, V. P., and Kotha, S. (2001). Continuous “morphing”: Competing through dynamic capabilities, form, and function. Academy of Management Journal, 44(6), 1263-1280.
[2] Dyer, J. H., and Nobeoka, K. (2000). Creating and managing a high-performance knowledge-sharing network: The Toyota case. Strategic Management Journal, 21(3), 345-367.
[3] Eisenhardt, K. M., and Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: What are they? Strategic Management Journal, 21(10-11), 1105-1121.
[4] Danneels, E. (2002). The dynamics of product innovation and firm competences. Strategic Management Journal, 23(12), 1095-1121.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。