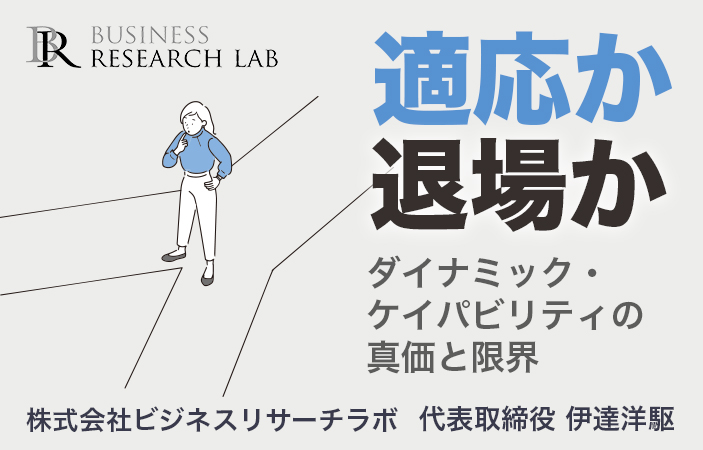2025年7月14日
適応か退場か:ダイナミック・ケイパビリティの真価と限界
激動の荒波が押し寄せる市場で、企業が生き残り繁栄するための秘訣とは何でしょうか。その一つは、環境変化を敏感に感じ取り、自らを柔軟に変容させる力、すなわち「ケイパビリティ」にあります。企業は適応能力を磨き上げなければ競争の舞台から退場を余儀なくされます。とりわけ「ダイナミック・ケイパビリティ」は、企業の命運を左右する能力となります。
しかし、この変革の原動力となるケイパビリティは、掛け声だけでは構築できません。どのような土壌で花開くのか、また何が成長を阻む要因となるのか。その複雑な生態系を理解する必要があります。本コラムでは、研究知見を紐解きながら、ケイパビリティという隠れた実力の正体に迫ります。
嵐が激しいほど優れた航海術が必要ですが、ケイパビリティと環境変化の関係はそれほど単純ではありません。あまりに穏やかな海でも、猛烈な嵐の中でも、その効果は限定的です。続いて、この航海術を構成する技術要素と、それが企業という船の進路にどう影響するかを探求します。
さらに、優れた能力を持ちながらも変革の壁に阻まれる企業の実像として、経営者のマインドセット、リソース活用の盲点、そして組織の慣性という障壁を検証します。最高の船と技術があっても、古い海図だけを頼りに航海すれば、新しい大陸には辿り着けないのです。
ケイパビリティは中程度の環境変化で最も有効
企業のケイパビリティと競争優位の関係について考えるとき、「環境の変化が激しいほどダイナミック・ケイパビリティが重要である」という考え方が一般的です。しかし、ドイツの化学、機械、自動車関連企業を対象とした研究では、この関係はそれほど単純ではないことが明らかになりました[1]。
この研究では、ダイナミック・ケイパビリティの例として「アライアンス管理能力」と「新製品開発能力」に焦点を当て、これらの能力が企業の競争優位にどのような影響を与えるかを調査しています。ここでいうアライアンス管理能力とは、他社との提携関係を効果的に構築・維持する能力のことです。新製品開発能力とは、市場ニーズに合わせた新しい製品やサービスを生み出す能力を指します。
研究者たちは、279社の企業から3年間にわたってデータを収集し、ダイナミック・ケイパビリティと競争優位の関係が環境のダイナミズム(変動性や不確実性の高さ)によってどう変わるかを分析しました。
その結果、ダイナミック・ケイパビリティと競争優位の関係は比例関係ではなく、「逆U字型」の関係にあることが判明しました。環境の変化が中程度の場合に、ダイナミック・ケイパビリティが最も競争優位に貢献するのです。環境の変化が少なすぎる場合も、激しすぎる場合も、その効果は低下します。
環境の変化が少ない場合、ダイナミック・ケイパビリティを構築・維持するコストが、それによって得られる利益を上回ってしまいます。ダイナミック・ケイパビリティは企業の資源を再構成する能力ですが、環境が安定している場合、そもそも資源の再構成が必要ないため、こうした能力への投資は無駄になりがちです。
一方、環境の変化が非常に激しい場合も、ダイナミック・ケイパビリティの効果は減少します。これには二つの理由があります。一つ目は「マッチング問題」です。環境が非常に激しく変化すると、過去の経験に基づいて形成されたダイナミック・ケイパビリティが新しい状況に適合しなくなります。二つ目は「慣性問題」です。極めて変化の激しい環境では、従来のルーティンに囚われて変革への抵抗が強まりやすくなります。
企業はダイナミック・ケイパビリティへの投資を環境条件に応じて慎重に検討する必要があります。環境の変化が中程度の業界では、ダイナミック・ケイパビリティの構築・強化が競争優位につながりやすいでしょう。しかし、非常に安定した業界や、逆に極めて不確実性の高い業界では、ダイナミック・ケイパビリティへの過剰投資は避け、他の戦略的選択肢を検討すべきかもしれません。
動的な環境ほどケイパビリティが業績を高める
環境の変化が中程度の場合にダイナミック・ケイパビリティが最も効果を発揮するという研究を紹介しましたが、一見矛盾するように思える別の研究も存在します。新製品開発(NPD)の現場を対象とした研究では、環境の変動性が高まるほど、ダイナミック・ケイパビリティが企業の業績に与える肯定的な影響が強まるという結果が得られています[2]。
この研究の特徴は、ダイナミック・ケイパビリティを4つの要素に分解したことです。それらは、「センシング能力」「学習能力」「統合能力」「調整能力」です。
センシング能力とは、環境の変化を察知し、市場機会や技術トレンドを見出す能力です。例えば、顧客の潜在的なニーズを把握したり、競合他社の動向を追跡したりする活動がこれに該当します。学習能力は、新たな知識を獲得し、既存の能力を刷新する能力です。外部からの情報を取り入れ、組織内で共有・活用するプロセスがこれにあたります。
統合能力は、個人が持つ知識を集団的な知識として統合し、新しい能力を構築する能力です。部門間の壁を超えた協力体制の構築や、異なる専門知識の融合などがこれに含まれます。調整能力は、資源・タスク・活動を適切に配分し、調整する能力です。プロジェクト管理や部門間の連携促進などの活動がこれに該当します。
研究者たちは、180の新製品開発ユニットを対象に調査を行い、これら4つの能力が企業の運営能力(実際に製品を開発・製造・市場投入する能力)にどのような影響を与えるかを検証しました。その結果、ダイナミック・ケイパビリティは運営能力に正の影響を与え、その影響は環境の変動性が高いほど強まることが明らかになりました。
この研究から得られる実務的な示唆として、企業は4つの能力(センシング、学習、統合、調整)をバランスよく発展させることの大切さが挙げられます。例えば、優れたセンシング能力があっても、それを学習や統合に結びつける能力が不足していれば、環境変化に効果的に対応することはできません。
経営者の認知がケイパビリティの進化を制約する
企業がケイパビリティを発揮する上での制約として、経営者の「認知」が挙げられます。ポラロイド社(Polaroid Corporation)のケースを分析した研究は、たとえ企業が技術的能力を持っていても、経営者の認知が変化に追いつかなければ、適応に失敗する可能性があることを明らかにしています[3]。
ポラロイド社は1937年に創業され、インスタントカメラを中心に成長を遂げた企業です。同社は優れた技術力を背景に、精密機械加工や薄膜塗布技術など専門的な製造能力を有していました。また、マスマーケット向けの強力な販売チャネルも構築していました。
同社の経営方針は「技術主導型」であり、「マーケットではなく技術が製品をつくり、市場を形成する」という考え方が根付いていました。また、ビジネスモデルとしては「本体は安く売り、消耗品で利益を得る」というカミソリ替え刃モデルを採用していました。インスタントカメラ本体を比較的安価に販売し、フィルムで継続的に利益を上げる戦略です。
1980年代に入ると、デジタル画像技術が台頭し始め、ポラロイド社もこの新技術への投資を開始しました。同社は高性能の画像センサーや医療用画像システムなど、技術的に高度なプロジェクトを展開しましたが、デジタルカメラ単独での市場展開には消極的でした。
その背景には、経営陣の強固な「カミソリ替え刃モデル」への固執がありました。彼らは「消費者は即時の物理的な写真プリントを求めている」と考え、デジタル技術を従来のビジネスモデルの延長線上で理解していました。デジタルカメラ単体ではなく、デジタルカメラとプリンタを組み合わせた製品を考えていたのです。
1990年代になると、ポラロイド社は市場主導型の新たな組織体制を構築し、デジタルカメラ開発を本格化しました。しかし、経営陣のビジネスモデルへの固執と、新たな製品開発戦略を提案するデジタル画像部門との間で不協和が生じました。これによって製品の市場投入が遅れ、競争で後れを取ることになりました。
最終的に新CEOの登場により、ポラロイド社の戦略は市場主導型へとシフトしましたが、それまでに築いた技術的優位性はすでに失われていました。この事例から得られる洞察は価値があります。
第一に、技術的能力の構築自体は可能であっても、経営陣が新しい技術の意味を過去の成功モデルの延長線上で理解する場合、環境変化への適応は失敗する可能性があります。ポラロイド社は優れたデジタル技術を開発していましたが、それを活かせるビジネスモデルを構想できませんでした。
第二に、経営陣の認知が組織能力の探索・蓄積を制限し、方向づけることが、組織変化の成否に影響を与えます。ポラロイド社の「カミソリ替え刃モデル」への固執は、デジタル技術の可能性を狭めることになりました。
第三に、組織の慣性(変化に抵抗する力)は能力だけでなく経営者の認知に根ざしている場合があります。ポラロイド社は技術的にはデジタル化に対応できていましたが、経営陣のビジネスモデルに対する認知が変化を阻んでいました。
資源の認識と活用の失敗がケイパビリティを阻害する
企業がダイナミック・ケイパビリティを発揮する上での障壁として、資源の認識と活用の問題があります。タイプライター業界の老舗企業であった「スミスコロナ(Smith Corona)」のケースは、企業が新たな市場への適応に失敗するプロセスを明らかにしています[4]。
スミスコロナは1886年に創業し、長い間タイプライター市場でリーダー的地位を維持していました。しかし1980年代以降、コンピューターの普及に伴い市場環境が急激に変化し、同社はこの変化に対応するため、新たな製品分野への進出を試みました。
この事例研究では、企業が市場変化に対応する際の「資源認識能力」と「資源活用能力」という二つの側面に焦点を当てています。資源認識能力とは、新たな市場機会を認識し、それに必要な資源を特定・評価する能力です。一方、資源活用能力とは、必要な資源を社内外から調達し、既存の組織構造に取り込む能力を指します。
スミスコロナは1980年代初頭、パソコン市場への参入を試みました。同社は「タイプライターの延長」としてパソコンを位置づけ、タイプライターの組立技術や流通チャネルなど既存の能力が新市場でも有効だと考えました。しかし、パソコンに必要なデジタル回路技術やソフトウェア開発能力などの新規資源を正しく評価できず、外部からの資源獲得にも失敗しました。結果、このパソコン事業は損失を出して失敗に終わりました。
続いて、スミスコロナはワープロ専用機市場への参入を試み、一時的には成功を収めました。しかし、ここでも新規の技術資源への理解不足や、既存の流通チャネルへの過剰な依存がみられ、PCの低価格化という環境変化に十分対応できませんでした。
1990年代初頭には、インクジェットプリンター市場への参入も試みましたが、印刷技術の新規性や競争環境の変化を正しく認識・対応できず、短期間で市場から撤退を余儀なくされました。
これらの失敗から、スミスコロナのケースでは次のような問題点が浮かび上がってきます。まず、「資源認識の失敗」があります。同社は新市場への参入に際して、必要な資源を過小評価し、自社資源の活用可能性を過大評価してしまいました。パソコン事業では、ハードウェアとソフトウェアの両方が必要であることを理解していましたが、ソフトウェア開発の複雑さと重要性を過小評価していました。
そして、「資源活用の失敗」があります。新規資源を外部から調達・統合する能力が不足し、技術提携や買収などの外部資源の活用にも消極的でした。他社との提携を模索した時期もありましたが、それらは表面的なものにとどまり、本格的な技術統合には至りませんでした。
「組織の慣性」の問題も見られました。過去の成功体験に囚われ、従来のタイプライター中心の組織構造・文化から抜け出せませんでした。新規事業部門を設立しても、既存事業の延長線上での思考から脱却できず、革新的な製品やビジネスモデルを生み出せませんでした。
スミスコロナのケースは、ダイナミック・ケイパビリティが技術的な能力だけではなく、経営者の認知能力や組織の学習能力とも関連していることを示しています。企業が環境変化に効果的に対応するためには、資源の認識と活用の両面で優れた能力を発揮することが必要なのです。
ルーティンの硬直性がケイパビリティの変革を妨げる
企業がケイパビリティを発揮する上での障壁として、最後に「ルーティンの硬直性」の問題を検討します。新聞業界がデジタルメディアへの移行という大きな技術変化に直面した際の対応を調査した研究では、企業の慣性(変化に抵抗する力)には異なる二つのタイプがあることがわかりました[5]。
この研究では、「慣性」を「資源の硬直性」と「ルーティンの硬直性」という二つの異なるタイプに分けています。資源の硬直性とは、資源配分パターンを変えることができない問題を指します。既存の資源への依存や、市場での強いポジションからくる再投資インセンティブに関連しています。一方、ルーティンの硬直性とは、組織内で確立された業務プロセスや行動パターンを変えられない問題です。これは自己強化型で、組織の構造や人々の思考に深く埋め込まれています。
この研究では、外部からの脅威認識がこれら二つの硬直性に異なる影響を与えることがわかりました。外部からの脅威を強く認識すると、企業は資源の硬直性を克服し、新規事業への資源投入を行うようになります。調査対象となった新聞社は、インターネットの脅威に直面して、オンライン事業への資源配分を増やしていました。
しかし、外部脅威の認識が強まるほど、ルーティンの硬直性はむしろ高まってしまうことが判明しました。脅威を感じると、権限の集中が進み、実験が減少し、既存資源への集中が強まるのです。このため、新しい資源を投入したとしても、従来のビジネスモデルやルーティンに固執する傾向が強まり、イノベーションが進まないという矛盾した現象が生じます。
例えば、調査対象となった新聞社では、デジタル部門への投資を増やしながらも、従来の新聞製作のプロセスや考え方をオンラインメディアにも適用しようとする動きがみられました。記事の作成・編集・配信のプロセスや、広告モデルなど、従来のルーティンを変えることなく、媒体だけをデジタルに置き換えようとしたのです。
ルーティンの硬直性を克服するためには、外部の視点や人材の導入、および新規事業の構造的な分離が重要となります。調査対象のうち、オンライン事業を既存の新聞事業から構造的に分離したケースでは、従来のルーティンから離れた独自の事業展開が可能になりました。別会社や独立部門として運営することで、新しい思考やプロセスが根付きやすくなったのです。
脚注
[1] Schilke, O. (2014). On the contingent value of dynamic capabilities for competitive advantage: The nonlinear moderating effect of environmental dynamism. Strategic Management Journal, 35(2), 179-203.
[2] Pavlou, P. A., and El Sawy, O. A. (2011). Understanding the elusive black box of dynamic capabilities. Decision Sciences, 42(1), 239-273.
[3] Tripsas, M., and Gavetti, G. (2000). Capabilities, cognition, and inertia: Evidence from digital imaging. Strategic Management Journal, 21(10/11), 1147-1161.
[4] Danneels, E. (2011). Trying to become a different type of company: Dynamic capability at Smith Corona. Strategic Management Journal, 32(1), 1-31.
[5] Gilbert, C. G. (2005). Unbundling the structure of inertia: Resource versus routine rigidity. Academy of Management Journal, 48(5), 741-763.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。