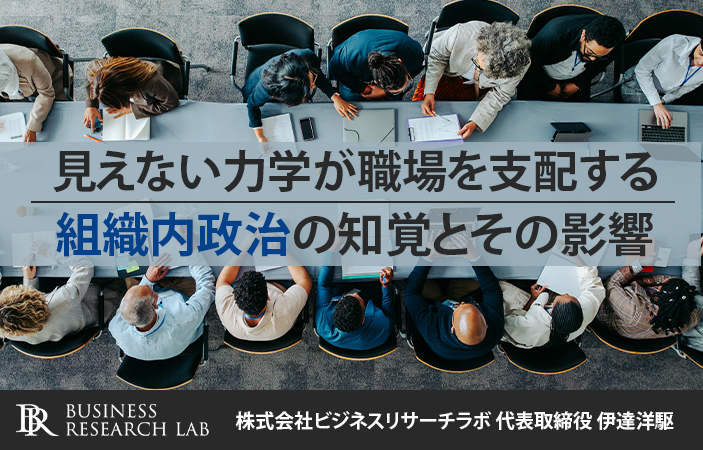2025年7月11日
見えない力学が職場を支配する:組織内政治の知覚とその影響
職場には、公式な規則やシステムだけでなく、目に見えない力学が存在しています。上司の機嫌を取る人が評価される、実力よりも人間関係で昇進が決まる、本音と建前が異なる場面が多い。これらの現象を総称して「組織内政治」と呼びます。組織内政治は、どの組織にも多かれ少なかれ存在するものですが、従業員がこれをどのように感じ取るかが重要です。「組織内政治の知覚」は、従業員の心理や行動に様々な影響を及ぼします。
例えば、ある会社で働くAさんは、自分の提案が、上司との関係が良好な同僚の提案より評価されないと感じています。Bさんは、昇進が能力や成果ではなく、特定のグループに所属しているかどうかで決まると考えています。このような知覚は、彼ら彼女らの仕事への取り組み方や会社への帰属意識にどのような変化をもたらすでしょうか。
本コラムでは、組織内政治の知覚が従業員にもたらす様々な心理的・行動的な結果について、学術研究の知見をもとに掘り下げていきます。組織内の見えない力学をどう感じるかが、私たちの職業生活にどのような波紋を広げるのか、その全体像を理解することは、現代の職場環境を考える上で有益です。
組織内政治の知覚は迎合や昇進に影響する
職場で「ここは政治的な場所だ」と感じたとき、私たちはどのように行動するようになるでしょうか。このような組織内政治の知覚は、従業員の行動パターンに変化をもたらします。
ある研究では、組織内政治の知覚を測定するための尺度(POPS:組織内政治知覚尺度)の開発と検証が行われました[1]。彼らは複数の職場で調査を実施し、3つの要素を見出しました。
第一の要素は「一般的政治行動」です。これは、組織内で他者を貶めて自分を引き立てようとする行動や、影響力のあるグループに逆らえない雰囲気を指します。例えば、ある従業員が自分の評価を高めるために、他の人の成果を自分のものとして報告するような状況です。
第二の要素は「迎合行動」です。これは本音を隠して周囲に迎合する傾向で、特に上司や有力者に同調することが奨励される組織文化を表します。例えば会議で本当の意見を言わず、権力者の意見に合わせるような振る舞いがこれに当たります。
第三の要素は「報酬と昇進施策」に関するものです。これは、昇給や昇進が公式のルールではなく、非公式な政治的プロセスによって決まると感じる状態を表します。能力や実績よりも、誰とゴルフに行くかで昇進が決まるような状況がこれに該当します。
これらの要素は互いに関連しながらも、別個の現象として存在しています。組織内政治の知覚は単純な一次元的なものではなく、複数の側面を持った概念なのです。
組織内政治の知覚は、従業員の行動に変化をもたらします。政治的な職場環境を感じた従業員は、しばしば自分を守るための戦略を取るようになります。例えば、意見を控えめにする、対立を避ける、上司に迎合するといった行動が増加します。
また、昇進に関しても、組織内政治の知覚は影響を与えます。多くの従業員は、仕事をよく行うだけでは昇進できないと感じるようになります。そのため、自己宣伝や人脈づくりといった政治的スキルを磨こうとします。
この現象は若手社員に顕著に見られます。組織内政治を強く感じる新入社員は、早い段階から「見えないルール」を学び、政治的行動をとることで自分のキャリアを守ろうとします。彼ら彼女らは実力よりも見せ方を優先し、上司の趣味に合わせた会話をするなど、実質的な業績以外の側面に力を入れるようになります。
組織内政治の知覚は単なる認識の問題ではなく、具体的な行動の変化を通じて、組織全体の機能や文化にまで波及します。従業員が組織内政治をどのように感じるかによって、日々の行動選択が変わり、ひいては組織全体のあり方にも影響が及びます。
組織内政治の知覚は組織への信頼を損なう
組織内政治を強く感じる従業員は、組織に対してどのような感情を抱くようになるのでしょうか。包括的なメタ分析は、この問いにヒントを提供しています。118の独立した研究(合計44,560人のデータ)を統合し、組織内政治の知覚が従業員の態度や感情に与える影響を詳細に分析しました[2]。
その結果、組織内政治の知覚と組織的信頼の間に非常に強い負の関係があることがわかりました。政治的な駆け引きが支配する職場だと感じる従業員ほど、組織への信頼が著しく低下するのです。組織内政治の知覚が強まるほど、「この会社は私の利益を考えてくれる」「経営陣の決定は公平で一貫している」といった信念が弱まります。
組織内政治の知覚は、組織的公正にも悪影響を及ぼします。手続き的公正(決定プロセスの公平さ)と相互作用的公正(上司や同僚からの扱われ方の公平さ)への認識が大きく損なわれます。政治的な環境では、「ルールは平等に適用されていない」「評価基準が人によって変わる」などの印象が強まり、公正さへの信頼が失われていきます。
組織内政治の知覚は「組織的支援」の認識にも否定的な影響を与えます。組織的支援とは、「組織が自分の貢献を評価し、幸福を気にかけてくれる」という従業員の信念です。政治的な環境では、組織が個人の本当の価値や貢献よりも、人間関係や派閥を優先していると感じられるため、サポート感覚が低下します。
この研究では、組織内政治の知覚が文化的背景によって異なる影響を持つ可能性も指摘されています。北米での研究と北米以外での研究を比較したところ、北米では組織内政治の知覚が職務満足やストレスにより強く関連しているのに対し、北米以外の地域では離職意図や反生産的行動とより強く関連していました。
個人主義が強い北米文化では、職務満足といった個人的な感情への影響が大きくなる一方、集団主義的な文化では具体的な行動(離職など)に結びつきやすいことを示唆しています。
組織への信頼の低下は、情報共有の減少、協力の低下、意思決定への参加意欲の減退など、実質的な行動変化をもたらします。さらに、長期的な視点での関係構築を妨げます。政治的な環境では、従業員は「この会社に将来性はあるのか」「ここでキャリアを築く価値があるのか」といった疑問を抱きやすくなります。これによって、組織との長期的な関係構築より、自己防衛や短期的利益の確保に焦点を当てるようになるのです。
組織内政治の知覚は職場の不安を高める
組織内政治を強く感じる職場は、従業員の心理的状態にどのような影響を与えるのでしょうか。アメリカの大学職員822名を対象に調査を行い、組織内政治の知覚が従業員の心理的不安に関連することを実証した研究があります[3]。
この研究によれば、組織内政治の知覚と職務不安の間には正の相関が見られました。職場を政治的な場として強く認識する従業員ほど、仕事に関連した不安を感じやすくなるということです。政治的環境が心理的ストレスの源泉となることを示しています。
政治的な職場では、従業員はしばしば予測不可能性と不確実性に直面します。「自分の評価は何に基づいて決まるのか」「どのような行動が報われるのか」といった問いへの答えが曖昧になるのです。
また、政治的な環境では「失敗のコスト」が高く感じられます。ミスや失敗が客観的に評価されるのではなく、政治的に利用される可能性があるためです。ミスをすると、それが長期間にわたって自分の評判を傷つける材料として使われることがあるかもしれません。このような状況では、失敗への恐れから警戒心を持つようになります。
組織内政治の知覚は「自分はコントロールできない状況にある」という無力感をもたらします。能力や努力ではなく、見えない力学で結果が決まると感じると、従業員は自分の職業生活の主導権を失ったように感じます。この無力感は慢性的な不安の原因となります。
組織内政治の知覚がどのような要因から生まれるかも明らかになっています。中央集権化(権限が一部に集中している状態)は政治的知覚を強める一方、フォーマライゼーション(規則や手続きが明確に定められている状態)は政治的知覚を弱めることが示されました。意思決定権が少数の人に集中し、かつ明確なルールがない組織では、政治的知覚とそれに伴う不安が高まるということです。
他方で、組織内政治の知覚による不安を緩和する要因も見えてきました。「コントロール感覚」と「状況の理解」という2つの要素が、政治的知覚と不安の関係を調整することが示されたのです。
「コントロール感覚」が高い場合、すなわち従業員が「自分にはある程度の影響力がある」と感じている場合、政治的環境でも不安が低減されることがわかりました。一方、「状況の理解」も重要です。政治的な環境であっても、「なぜそうなっているのか」「どう対処すべきか」を理解していると、不安は軽減されます。
このように、組織内政治の知覚は職場における心理的不安の源泉となり、従業員のメンタルヘルスや仕事の質に影響を及ぼす可能性があります。しかし、コントロール感や状況理解を持つことで、その悪影響は緩和できることも示唆されています。
組織内政治の知覚は離職意図を高める
組織内政治の知覚は、従業員の「この会社にとどまるべきか、去るべきか」という決断にも影響を及ぼします。メタ分析においては、組織内政治の知覚と離職意図の間に正の相関があることを明らかにしました[4]。職場を政治的な場所だと強く感じる従業員ほど、その組織を去りたいと考えるということです。
このメタ分析は1989年から2007年までに発表された多数の研究を統合したもので、異なる業種、地域、職位の従業員を対象としていますが、この関係性は一貫して観察されました。政治的知覚と離職意図の関連は強固なものであり、組織内政治が従業員の定着に脅威となることを示しています。
組織内政治の知覚は「心理的負担(ストレイン)」を引き起こします。政治的な環境では、従業員はどう振る舞うべきか考え、人間関係の複雑な力学に対処しなければならず、これが精神的な負担となります。
この心理的負担が「士気(Morale)」の低下を引き起こします。士気とは、職務満足や感情的コミットメントなど、仕事への前向きな感情や姿勢を表します。心理的負担が増えると、従業員は仕事への喜びや組織への帰属意識を失っていきます。
そして、この士気の低下が「離職意図」につながります。従業員は「このストレスと低いモチベーションに耐え続けるより、新しい環境を探した方が良いのではないか」と考えるようになります。
組織内政治の知覚が離職意図に与える影響は「心理的負担」と「士気」によって完全に媒介されていました。組織内政治の知覚が直接的に離職意図を高めるのではなく、心理的負担の増加と士気の低下を通じて間接的に影響します。
組織内政治の知覚による離職意図の高まりは、単なる意図にとどまらず、実際の離職行動にもつながります。これは組織にとって人材流出リスクを意味します。
組織内政治の知覚による離職意図は、地域や文化によっても違いがあります。北米以外の地域では、組織内政治の知覚と離職意図の関連がより強く見られました。これは集団主義的な文化では、政治的環境を「仕方ない」と受け入れるのではなく、より強い拒絶反応として「去る」という選択をすることを意味しています。
組織内政治の知覚は離職意図を高める要因となり、組織の人材保持に課題をもたらします。政治的環境から従業員が離れたいと思うのは、単なる不満からではなく、心理的負担の増加と士気の低下というプロセスを経た結果なのです。
まとめ
本コラムでは、組織内政治の知覚が従業員にもたらす様々な結果について検討してきました。研究知見から明らかになったのは、この「見えない力学」の認識が、職場における従業員の心理と行動に影響を及ぼすということです。
組織内政治の知覚は、従業員の迎合行動を促進し、本音を隠す組織文化を形成します。組織への信頼を損ない、公正感やサポート認識を低下させます。また、職場での不安や心理的ストレスを高め、最終的には離職意図の上昇につながります。
職場のマネジメントにとっての含意は明白です。組織内政治の知覚を低減することは、従業員のウェルビーイングと組織のパフォーマンスの両方にとって価値があります。例えば、意思決定プロセスの透明性を高めることで、従業員の公正感を向上させることができます。評価基準を明確にし、一貫して適用することも、政治的知覚を低減させる手段となります。
従業員に「コントロール感」を与えることも有効です。彼らが自分の職業生活にある程度の影響力を持っていると感じられれば、政治的環境でも不安が軽減されます。オープンなコミュニケーションを促進し、従業員が安心して意見を表明できるようにすることも大切です。
組織内政治は完全に排除することは難しいかもしれませんが、その知覚とそれがもたらす悪影響は緩和できます。従業員が「この組織は公平だ」「自分の貢献は正当に評価される」と信じられる職場を作ることが、重要な課題なのです。
脚注
[1] Kacmar, K. M., and Carlson, D. S. (1997). Further validation of the Perceptions of Politics Scale (POPS): A multiple sample investigation. Journal of Management, 23(5), 627-658.
[2] Bedi, A., and Schat, A. C. H. (2013). Perceptions of organizational politics: A meta-analysis of its attitudinal, health, and behavioural consequences. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 54(4), 246-259.
[3] Ferris, G. R., Frink, D. D., Galang, M. C., Zhou, J., Kacmar, K. M., and Howard, J. L. (1996). Perceptions of organizational politics: Prediction, stress-related implications, and outcomes. Human Relations, 49(2), 233-266.
[4] Chang, C.-H., Rosen, C. C., and Levy, P. E. (2009). The relationship between perceptions of organizational politics and employee attitudes, strain, and behavior: A meta-analytic examination. Academy of Management Journal, 52(4), 779?801.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。