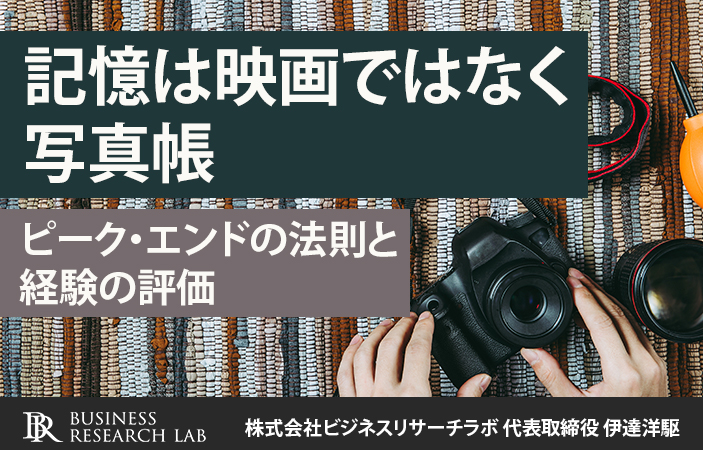2025年7月10日
記憶は映画ではなく写真帳:ピーク・エンドの法則と経験の評価
人生は様々な経験の連続です。楽しい食事、厳しい仕事のプロジェクト、旅行、病院での治療、学校での試験など、私たちは日々多くの出来事を体験しています。これらの経験をどのように記憶し、評価しているかについて考えたことはあるでしょうか。例えば、3時間の映画を見た後、その映画の良し悪しをどのように判断するでしょうか。あるいは、1週間の休暇の後、その休暇が楽しかったかどうかをどのように判断するでしょうか。
研究によれば、人間は経験を評価する際、その経験全体を均等に評価するわけではありません。私たちの脳は「ショートカット」や「ヒューリスティック」を用いて、膨大な情報を処理しています。この中でも興味深いのが「ピーク・エンドの法則」です。この法則は、人が経験を評価する際、その経験の「ピーク」(最も感情が強かった瞬間)と「エンド」(終了時点)が全体の評価を左右するというものです。
ピーク・エンドの法則によれば、経験の持続時間はあまり評価に影響せず、たとえ長い苦痛が伴う経験でも、終わり方が良ければ全体としてポジティブに評価されることがあります。また逆に、素晴らしい経験も、最後が悪ければネガティブな印象として残ることもあるでしょう。
本コラムでは、ピーク・エンドの法則がどのように私たちの経験評価に影響し、どのような状況でこの法則が適用されるのか、また私たちの記憶や意思決定にどう関わっているのかを見ていきます。
経験の評価ではピーク・エンドが持続時間より重要
私たちは日常的に経験を評価しています。「あの映画は面白かった」「この会議は退屈だった」といった具合に、様々な出来事に対して評価を下していますが、その評価の仕組みは複雑です[1]。
直感的に考えるなら、ある経験の評価は、その経験中に感じた感情の総和によって決まるはずです。快適な経験は長ければ長いほど良く、不快な経験は短ければ短いほど良いということになります。これは「一時的統合モデル」と呼ばれる考え方で、経験の持続時間と感情強度を掛け合わせた総和が経験の評価を決めるという仮説です。
しかし実際には、人間の経験評価はそれほど論理的ではないことが研究により分かってきました。代わりに、経験の特定の瞬間、特に「ピーク」(最も感情が強かった瞬間)と「エンド」(終了時点)が全体の評価に影響を与えることが明らかになっています。これが「ピーク・エンドの法則」と呼ばれるものです。
この法則が明らかになったきっかけとなった初期の研究では、参加者に様々な長さの映像クリップを見せ、その評価を調べました。映像の内容は一定で、波が打ち寄せる風景などの単調なものでした。映像視聴中は継続的に感情状態を記録し、視聴後には全体の印象を評価してもらいました。
この実験の結果から、人々が経験を回想的に評価する際、経験の持続時間があまり考慮されないという「持続時間の無視」という現象が見出されました。例えば、不快な映像では、長い映像と短い映像の間で全体評価にほとんど差がなかったのです。快適な映像については、長い時間見せると評価が下がることさえありました。
これらの結果は、人間の経験評価が「感情の足し算」ではなく、経験中の特定の瞬間、特にピークとエンドに依存していることを示しています。その後の研究では、人々が経験を思い出す際に、経験中の多くの瞬間が「忘れられ」、ピークとエンドの印象が強く残ることが確認されました。
特に実験参加者が評価を遅延させると(すぐに評価せず、ある程度時間が経ってから評価すると)、持続時間の影響がさらに弱まり、ピークとエンドの重要性が顕著になることも分かりました。これは人間の記憶が「映画のように連続的」ではなく、「重要な場面の静止画」のように断片的に機能することを示唆しています。
ピーク・エンドの法則は、人間の経験評価の仕組みに対する理解を深めるものです。私たちは経験を論理的に評価するのではなく、記憶に残りやすい特定の瞬間(ピークとエンド)に基づいて評価する傾向があるのです。
ピーク・エンドが過去の経験に意味を与えている
経験の評価においてピークとエンドが持続時間よりも影響力を持つことを見てきました。なぜ人間はピークとエンドをそこまで重視するのでしょうか。ピークとエンドが私たちの経験に「意味」を与える仕組みについて探っていきます。
私たちが過去の経験を振り返る時、「楽しかった」「苦しかった」という感情の強さだけでなく、その経験が自分にとって何を意味したのかを考えることがあります。ピークとエンドが特に記憶に残りやすいのは、これらの瞬間が経験の「個人的意味」を凝縮して含んでいるからだと考えられています[2]。
まず「ピーク」の意味について考えてみましょう。ピークとは、経験中に最も感情が強く表れた瞬間です。例えば、山登りで頂上に到達した時の達成感、試験で難問を解けた時の喜び、あるいは大きな失敗をした時の恥ずかしさなどが挙げられます。
ピークは私たちの「処理能力」を示す指標となります。その経験を乗り越えるために自分がどれだけの精神的・身体的資源を必要としたかを表しているのです。例えば、非常に苦しい経験のピークを思い出すことで、「あの苦しさにも耐えられた」という自己認識が形成されます。これは将来同様の状況に直面した時の対処能力の指標として機能します。
次に「エンド」の意味についてです。経験の終了時点が重要なのは、それが経験全体に「確実性」と「完結感」を与えるからです。人間は未完結な状態よりも、完結した状態を好みます。経験が終わることで、その経験を「過去のもの」として安全に評価できるようになります。
特に目標志向の活動では、終了時点の感情状態がその活動の成功や価値を示すことになります。例えば、プロジェクトの締め切りに間に合って安堵感を覚える、スポーツの試合で最後に逆転勝利する、といった経験では、終了時の感情がその経験全体の評価を左右します。
社会的相互作用においても、エンドが重要であることが研究で示されています。人との交流が終わる時の感情状態が、その関係全体の評価に影響することが分かっています。交流が終わることが明確な場合(例えば、別れの挨拶をする場面など)、その終了時の感情状態が強く評価に影響します。
「快」や「不快」という単純な感情だけでなく、愛情、関心、羞恥、後悔などの特定の感情も、それぞれ独自の意味を持っています。例えば、愛情や関心といった感情は、社会的絆や個人的成長に関連した深い意味を含んでいます。一方、羞恥や後悔は、自己の行動に対するフィードバックとして機能し、将来の行動修正に役立ちます。
これらの特定の感情、特に社会的関係や個人的成長に関連した感情は、快楽や苦痛よりも個人的意味が深いため、記憶や意思決定に影響を与えると考えられています。例えば、単に「楽しかった」という経験よりも、「誰かと深い絆を感じた」という経験の方が、長期的な幸福感や人生の満足度に寄与することがあります。
ピークとエンドが私たちの経験に与える意味を理解することで、私たちは自分の経験をより豊かに捉え、評価することができるようになります。経験の持続時間や全体的な快不快の総和だけでなく、その経験がもたらす「意味」に着目することで、より充実した生活を送るヒントを得ることができるかもしれません。
ピーク・エンドは認知的課題の不快感にも有効
ここまで、感情的な経験や身体的な痛みにおけるピーク・エンドの法則について見てきました。対して認知的な活動、つまり頭を使う課題においても同様の法則が当てはまるのでしょうか。認知的に困難な課題を行った際の「精神的努力」や「不快感」の評価にもピーク・エンドの法則が適用されるかどうかを検証した研究に目を向けてみましょう[3]。
私たちは様々な場面で認知的課題に取り組んでいます。学校での試験、職場での企画書作成、難しい問題の解決など、多くの場面で頭を使う作業を行っています。こうした認知的課題は、時に精神的な疲労や不快感をもたらすことがあります。こうした精神的な経験も、ピークとエンドによって評価されるのでしょうか。
この問いに答えるために行われた研究では、修正された「PASAT」という作業記憶課題が用いられました。この課題では、参加者に視覚的に数字が提示され、連続する数字の合計を計算するというものでした。課題の難易度は「簡単」「中程度」「困難」の3段階で設定され、ランダムに提示されました。参加者はカナダの大学生401名で、実験時間は5-9ブロック(各ブロック約1分)でした。
各ブロック終了後、参加者は「精神的努力」と「不快感」を7段階でリアルタイム評価しました。課題の全体が終了した後には、課題全体の精神的努力と不快感、自分のパフォーマンスの自己評価、そして再度同じ課題をやりたいかどうかを評価しました。
研究の結果、認知的課題においても、ピーク・エンドの法則が当てはまることが確認されました。特に、課題中の「不快感」のピークとエンドは、課題終了後の回想的評価の73%を説明していました。同様に、「精神的努力」のピークとエンドも、回想的評価の58%を予測しました。
「精神的努力」と「不快感」は互いに関連しているものの、異なるパターンで変化することが分かりました。「精神的努力」は課題の進行につれてやや低下しましたが、「不快感」は逆に課題が進むにつれて増加しました。課題に慣れることで必要な精神的努力は減少するものの、時間の経過とともに疲労や退屈さによる不快感が増加することを表しています。
また、「不快感」の終了時点の評価は、「もう一度課題をやりたいか」という将来の意欲を予測しましたが、「精神的努力」の終了時点の評価はそれを予測しませんでした。課題に再び取り組む意欲を決定するのは、その課題が「どれだけ頭を使ったか」ではなく、「どれだけ不快だったか」という側面が重要であることを示唆しています。
他方で、課題の持続時間は、回想的な評価や再実行の意欲にほとんど影響を与えませんでした。認知的課題においても「持続時間の無視」が生じており、課題の長さよりもピークと終了時点の経験が重要であることが示されました。
この研究によって、ピーク・エンドの法則が感情的経験や身体的痛みだけでなく、認知的課題における主観的経験の評価にも適用可能であることが明らかになりました。私たちが頭を使う課題を振り返る際にも、ピークや終了時の経験が全体の印象を決定づけるのです。
将来の選択は記憶された経験で決まりやすい
ピーク・エンドの法則が感情的経験、身体的痛み、そして認知的課題の評価にも適用されることを見てきました。こうした過去の経験の評価は、将来の選択にどのように影響するのでしょうか。
私たちは日常的に「また同じことをしたいか」という選択に直面します。同じレストランにまた行くか、同じ旅行先をまた選ぶか、同じセミナーにまた参加するか。こうした選択は過去の経験に基づいて行われます。その際に参照されるのは「実際の経験」でしょうか、それとも「記憶された経験」でしょうか。
この問いを検証するために行われた研究では、大学生41名を対象に春休みの休暇体験を調査しました[4]。参加者は春休みの約2週間前と数日前に、休暇に対する期待(予測された経験)を評価しました。春休み中は携帯型端末を使用して1日7回ランダムに感情と満足度を評価しました(その場での実際の経験)。そして、休暇終了直後と4週間後に、過去の休暇を振り返っての評価(記憶された経験)を行いました。最後に、約5週間後に「同じ休暇を再び取りたいか」を評価してもらいました。
この研究から得られた結果としては、まず、「予測された経験」および「記憶された経験」は、「実際の経験」よりも明らかにポジティブに評価される傾向がありました。人々は実際に体験中に感じている感情よりも、休暇前後に予測・記憶している感情の方がポジティブでした。これは「バラ色の記憶効果」と呼ばれる現象で、私たちが過去の経験をやや美化して記憶することを指しています。
しかし、予測および記憶された経験では、ネガティブな感情も実際の体験より強く評価されました。これは一見矛盾するようですが、「人々は体験を予測・記憶する際に、ポジティブとネガティブの両方の感情強度を誇張する」という一貫した傾向として解釈できます。記憶の中では感情がより鮮明に、極端になるということです。
本研究の核心的な問いである「将来の選択に影響するのは、実際の経験か記憶された経験か」については、明確な結果が得られました。「同じ休暇を再び取りたいか」という将来の選択に強く関連していたのは、「記憶された経験」でした。「実際の経験」や「予測された経験」は、将来の選択に直接的には影響していませんでした。
私たちが「また同じことをしたい」と思うかどうかは、実際にその時どう感じたかではなく、後からその経験をどう記憶しているかによって決まるのです。そして、その記憶はピーク・エンドの法則に従って形成されることが多いため、結果的に、将来の選択はピークとエンドによって影響されると言えます。
この発見は、私たちの意思決定プロセスについて示唆を与えます。人間は必ずしも「実際の快楽(客観的経験)」を最大化するような選択をするわけではありません。記憶に残りやすいピークやエンドの印象に基づいて選択しています。
例えば、ある観光地で最終日に素晴らしい体験をした人は、滞在中のほとんどが平凡だったとしても、「また行きたい」と感じるかもしれません。逆に、全体的には楽しい旅行でも、最終日にトラブルがあった場合、その経験全体がネガティブに記憶され、再訪を避けるかもしれません。
脚注
[1] Fredrickson, B. L., and Kahneman, D. (1993). Duration neglect in retrospective evaluations of affective episodes. Journal of Personality and Social Psychology, 65(1), 45-55.
[2] Fredrickson, B. L. (2000). Extracting meaning from past affective experiences: The importance of peaks, ends, and specific emotions. Cognition & Emotion, 14(4), 577-606.
[3] Hsu, C.-F., Propp, L., Panetta, L., Martin, S., Dentakos, S., Toplak, M. E., and Eastwood, J. D. (2018). Mental effort and discomfort: Testing the peak-end effect during a cognitively demanding task. PLOS ONE, 13(2), e0191479.
[4] Wirtz, D., Kruger, J., Scollon, C. N., and Diener, E. (2003). What to do on spring break? The role of predicted, on-line, and remembered experience in future choice. Psychological Science, 14(5), 520-524.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。