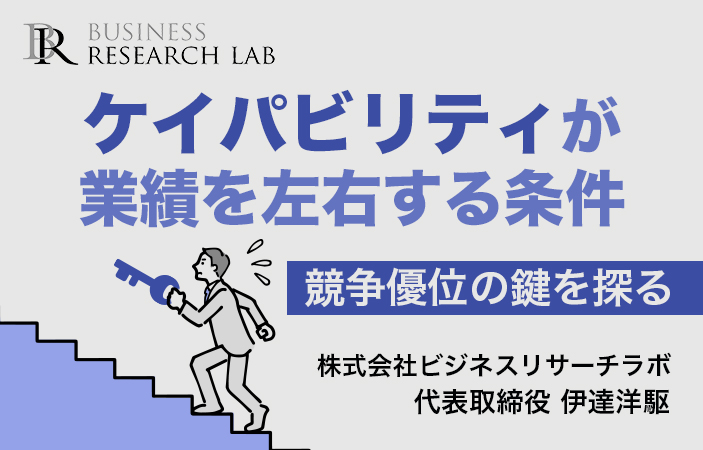2025年7月9日
ケイパビリティが業績を左右する条件:競争優位の鍵を探る
企業が持続的な競争優位を築くための中核的要素として、「ケイパビリティ」があります。ケイパビリティとは、企業が持つ能力や組織的な技能のことであり、単純な資源の保有とは異なります。資源は企業が「何を持っているか」を表すのに対し、ケイパビリティは「何ができるか」を表します。ケイパビリティは、時間をかけて形成され、組織内に埋め込まれた知識やルーティンとして存在するため、容易に模倣できないという特性を持ちます。
しかし、ケイパビリティがあれば必ず企業の成果につながるわけではありません。あるケイパビリティが特定の状況では企業業績を向上させるものの、別の状況では効果がなかったり、時に悪影響を及ぼしたりすることもあります。このような複雑な関係を理解することは、企業戦略を立てる上で価値があります。
本コラムでは、ケイパビリティと業績の関係が条件依存的であることに焦点を当て、「どのような条件下でケイパビリティが効果を発揮するのか」を考えます。具体的には、ケイパビリティが業績に与える間接的な効果、環境の変化によるケイパビリティの効果の逆転現象、競争環境の強度がもたらす影響、そして外部知識の活用や顧客特化型ケイパビリティと管理能力の比較について検討します。
ケイパビリティは間接的に業績を高める
ケイパビリティは企業の業績を直接的に向上させるのでしょうか、それとも間接的な経路を通じて貢献するのでしょうか。このことを理解するために、特にダイナミック・ケイパビリティに着目します。ダイナミック・ケイパビリティとは、環境変化に適応するために企業が自らの資源や能力を再構築する力を指します。
ギリシャの製造業企業271社を対象にした調査によると、ダイナミック・ケイパビリティは企業業績に直接的な効果をもたらすのではなく、「オペレーショナル・ケイパビリティ」を介して間接的に企業業績に貢献することが明らかになりました[1]。
ダイナミック・ケイパビリティは主に3つの要素から構成されています。一つ目は「調整能力」であり、これは組織内の資源を統合し新しい能力を形成するための調整プロセスです。二つ目は「学習能力」で、組織内で新しい知識を生み出し、共有し、蓄積するプロセスを指します。三つ目は「競争戦略的対応能力」で、これは環境変化を察知し迅速に対応する能力です。これらの要素は相互に関連しており、企業が新たなオペレーショナル・ケイパビリティを構築するための基盤となります。
この調査では、ダイナミック・ケイパビリティがマーケティング能力と技術能力という二つのオペレーショナル・ケイパビリティに正の影響を与えることが判明しました。そして、このマーケティング能力と技術能力が、企業の収益性や市場業績といった業績指標に影響を与えていました。特にマーケティング能力は、収益性と市場業績の両方に対して有意な正の影響を示しました。一方、技術能力は市場業績には正の影響を与えたものの、収益性には明確な影響が見られませんでした。
この研究で興味深い点は、ダイナミック・ケイパビリティが直接的には企業業績に影響しないということです。ダイナミック・ケイパビリティが形成されただけでは、企業業績の向上にはつながりません。ダイナミック・ケイパビリティはあくまでも、マーケティング能力や技術能力などのオペレーショナル・ケイパビリティを強化することで、間接的に企業業績に貢献するのです。
また、この研究では、環境が動的であっても静的であっても、ダイナミック・ケイパビリティの重要性が確認されました。市場環境の変化が激しくなくても、ダイナミック・ケイパビリティは企業業績に間接的に寄与するということです。
ダイナミック・ケイパビリティへの投資は直接的な業績向上につながるわけではなく、オペレーショナル・ケイパビリティの向上を通じて初めて実を結ぶものです。したがって、企業はダイナミック・ケイパビリティの構築と同時に、それをオペレーショナル・ケイパビリティの向上にどのように結びつけるかを考慮する必要があります。
環境によってはケイパビリティの効果が逆転する
企業のケイパビリティは、常に良い結果をもたらすのでしょうか。先ほどは、ダイナミック・ケイパビリティが間接的に業績を高めることを見てきましたが、ケイパビリティの効果は必ずしも一定ではありません。環境条件によっては、ケイパビリティの効果が逆転することもあります。
チリの企業48社、合計192のビジネスプロセスを対象にした研究では、「日常的能力」と「ダイナミック・ケイパビリティ」という二種類の能力に焦点を当て、それらが企業業績に与える影響を調査しました[2]。
日常的能力とは、企業が短期的に収益を上げるために日々の業務で用いる能力のことです。例えば、現状の製品やサービス、既存のプロセスを改善するための能力を指します。一方、ダイナミック・ケイパビリティは、企業が日常的能力を変化・拡張し、新たな製品やサービス、ビジネスプロセスを創出・変革するために用いる能力です。
この研究の発見は、日常的能力とダイナミック・ケイパビリティの効果が、企業を取り巻く環境の動態性によって左右されるという点です。環境の動態性とは、企業を取り巻く競争環境が予測困難な変化を頻繁に起こす度合いを指します。
安定した環境では、日常的能力は企業業績に貢献しました。日々の業務を効率的に行うための能力が、安定した状況下では高い業績に結びつくのです。ところが、環境が動的になるにつれて、日常的能力の効果は低下していきました。変化が激しい環境では、既存のやり方に固執することがむしろ逆効果になる可能性があります。
一方、ダイナミック・ケイパビリティは、プロセスレベルでは常に業績にプラスの影響を与えていましたが、企業レベルで見ると、安定した環境下ではむしろ負の影響を示すことがありました。これは、変化に適応するための能力を構築・維持するコストが、安定した環境では見合わないことを示唆しています。しかし、環境が動的になるにつれて、ダイナミック・ケイパビリティの企業業績への貢献は増加していきました。
この研究はさらに、能力の「異質性」(他社と異なる独自性)がどのように業績に影響するかも調査しました。ダイナミック・ケイパビリティが異質であるほど、すなわち他社にはない独自のものであるほど、業績が向上することが明らかになりました。独自のダイナミック・ケイパビリティが競争優位の源泉となることを意味しています。一方、日常的能力については、異質性が必ずしも業績向上に結びつかないことが分かりました。
環境が安定している場合は、日常的能力の向上に注力することで業績を高められます。しかし、環境の変化が激しい場合には、ダイナミック・ケイパビリティの構築が必要です。ただし、どのような環境であっても、ダイナミック・ケイパビリティは他社と差別化されたものであることが望ましいと言えます。
競争が激しいほどケイパビリティの効果は高まる
環境の動態性がケイパビリティの効果を左右することを見てきましたが、環境要因としては他にも競争の激しさが重要です。ケイパビリティは競争環境においてどのような効果をもたらすのでしょうか。
オーストラリアの大企業を対象にした調査によれば、ダイナミック・ケイパビリティの企業業績への影響は、市場の競争強度によって影響を受けることが分かりました[3]。この研究では、ダイナミック・ケイパビリティの構成要素として「センシング」「シージング」「リコンフィギュアリング」の3要素が測定されました。センシングとは市場機会を感知する能力、シージングはその機会を捕捉する能力、リコンフィギュアリングは資源を再構成する能力を指します。
結果、ダイナミック・ケイパビリティ自体は必ずしも直接的に企業業績にプラスの影響を与えるわけではないことが見えてきました。むしろ、一部の分析では売上成長に対して負の影響すら見られました。しかし、市場の競争が激しい場合には、ダイナミック・ケイパビリティの業績への効果が顕著に高まりました。要するに、競争が厳しい市場環境において、ダイナミック・ケイパビリティは特に価値を発揮するということです。
競争が激しい市場では、企業は常に変化に適応し、新たな機会を素早く捉え、資源を再配置する必要があります。このような状況下では、市場機会を感知し、それを捕捉し、資源を再構成するダイナミック・ケイパビリティが企業生存と成長の要諦となるからです。一方、競争が少ない環境では、そうした能力への投資が必ずしも高いリターンをもたらさない可能性があります。
また、この研究は「組織構造」の影響も検証しました。ダイナミック・ケイパビリティの効果は、組織構造によっても左右されることが明らかになりました。特に、「有機的」(非公式で柔軟)な組織構造を持つ企業では、ダイナミック・ケイパビリティの業績への影響が向上しました。一方、「機械的」(公式で硬直的)な組織構造を持つ企業では、ダイナミック・ケイパビリティの効果が発揮されにくいことが分かりました。
有機的な組織構造は、柔軟性や自律性を提供し、迅速な市場変化への対応を促進します。そのため、ダイナミック・ケイパビリティがその効果を発揮できます。逆に、機械的な組織構造では、ダイナミック・ケイパビリティがあっても、その能力が組織の硬直性によって抑制されてしまいます。
この研究は、ダイナミック・ケイパビリティの構築だけでは十分でないことを強調しています。ダイナミック・ケイパビリティの真価は、それが発揮される「内的条件」(組織構造)と「外的条件」(競争強度)によって左右されるのです。企業は自社のダイナミック・ケイパビリティが効果を発揮する条件を理解し、それに適した環境を整えることが求められます。
外部知識を活用するケイパビリティが競争力を生む
企業の競争力を高めるケイパビリティとして、「外部知識を活用する能力」が効果的であることが分かってきました。製薬業界の企業を対象にした研究では、企業の研究能力(コンピタンス)が、企業間の業績の持続的な差異を生み出す要因となるかを実証的に探求しました[4]。この研究では、企業の競争優位の源泉を「コンポーネント能力」と「アーキテクチャル能力」の2つに分類しています。
コンポーネント能力とは、特定の分野や領域に特化したローカルな技術や知識を指します。例えば、製薬企業における特定の疾病領域や科学的領域での深い専門性が該当します。一方、アーキテクチャル能力は、複数の知識領域を横断的・柔軟に統合し、新しい能力を形成・再構築する能力です。組織内外での知識の流れを管理し、相互作用を促進する能力とも言えます。
この研究では、特にアーキテクチャル能力に焦点を当て、2つの重要な特徴を検証しました。一つは「企業境界を超えた外部との情報の流れを促進する能力」、もう一つは「企業内の異なる科学分野や疾患領域間で情報の流れを促進する能力」です。
製薬企業10社の研究プロジェクトデータを用いた分析の結果、コンポーネント能力(特定領域の過去の成功体験や特許保有数)は、研究生産性と非常に強い関連を示しました。しかし、より興味深いのはアーキテクチャル能力の効果です。
アーキテクチャル能力は、企業間の研究生産性の差異を強力に説明することが分かりました。特に、学術界との密接な関係性が生産性を有意に高めることが明らかになりました。具体的には、研究者の昇進に論文出版が重要視される程度(学術界との結びつき)が高い企業ほど、研究生産性が高かったのです。
また、資源配分の方法も重要であることが判明しました。一人の決定者ではなく、委員会方式で資源配分を決める企業の方が、研究生産性が高い傾向がありました。多様な視点が反映された意思決定が、イノベーションを促進するのかもしれません。
この研究から得られる教訓は、企業の境界を超えた知識の流れ、特に学術界との関係性が、研究開発の生産性に大きな影響を与えるということです。外部の知識源へのアクセス能力が、競争優位を持続させるのです。
ケイパビリティは顧客特化より管理能力が収益を高める
外部知識の活用というケイパビリティの重要性を見てきましたが、他にも様々なタイプのケイパビリティが存在します。それらは企業の業績にどのような影響を与えるのでしょうか。
インドの大手ソフトウェアサービス企業から得られた6年間にわたる138件のプロジェクトデータを用いた研究では、ソフトウェアサービス業界に特有な2種類のケイパビリティが、プロジェクトの収益性にどのように影響するかを分析しました[5]。
この研究が焦点を当てたのは、「クライアント特化型ケイパビリティ」と「プロジェクト管理ケイパビリティ」です。クライアント特化型ケイパビリティとは、同じクライアントとの繰り返しの取引から蓄積されるケイパビリティです。特定のクライアント企業のビジネスプロセスやニーズを深く理解することで形成されます。一方、プロジェクト管理ケイパビリティは、研修やシステム整備などの意図的な投資によって形成される、より汎用性の高いケイパビリティです。具体的には、設計能力、工数予測能力、スケジュール管理能力などが含まれます。
分析の結果、両方のケイパビリティがプロジェクトの収益性に正の影響を与えることが確認されました。しかし、その効果の大きさには違いがありました。
クライアント特化型ケイパビリティについては、繰り返し取引しているクライアントでは、プロジェクトの収益性が高くなる傾向が見られました。このことは、クライアントとの関係を深めることで、プロジェクト実施のコストを下げ、収益性を向上させることができることを表しています。しかし、その効果は比較的小さいことも見えてきました。
対して、プロジェクト管理ケイパビリティは、プロジェクトの収益性に対してより強く一貫した影響を与えることが分かりました。特に、工数超過やスケジュール遅延の管理能力が向上すると、プロジェクトの収益性が有意に改善しました。中でもスケジュール管理能力の影響が強いことが明らかになりました。
これらの結果は、ソフトウェアサービス企業において、クライアント特化型ケイパビリティよりもプロジェクト管理ケイパビリティの方が、収益性により大きな影響を与えることを意味しています。特に、スケジュール管理の重要性が浮き彫りになっています。
脚注
[1] Protogerou, A., Caloghirou, Y., and Lioukas, S. (2012). Dynamic capabilities and their indirect impact on firm performance. Industrial and Corporate Change, 21(3), 615-647.
[2] Drnevich, P. L., and Kriauciunas, A. P. (2011). Clarifying the conditions and limits of the contributions of ordinary and dynamic capabilities to relative firm performance. Strategic Management Journal, 32(3), 254-279.
[3] Wilden, R., Gudergan, S., Nielsen, B. B., and Lings, I. (2013). Dynamic capabilities and performance: Strategy, structure and environment. Long Range Planning, 46(1-2), 72-96.
[4] Henderson, R., and Cockburn, I. (1994). Measuring competence? Exploring firm effects in pharmaceutical research. Strategic Management Journal, 15, 63-84.
[5] Ethiraj, S. K., Kale, P., Krishnan, M. S., and Singh, J. V. (2005). Where do capabilities come from and how do they matter? A study in the software services industry. Strategic Management Journal, 26(1), 25-45.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。