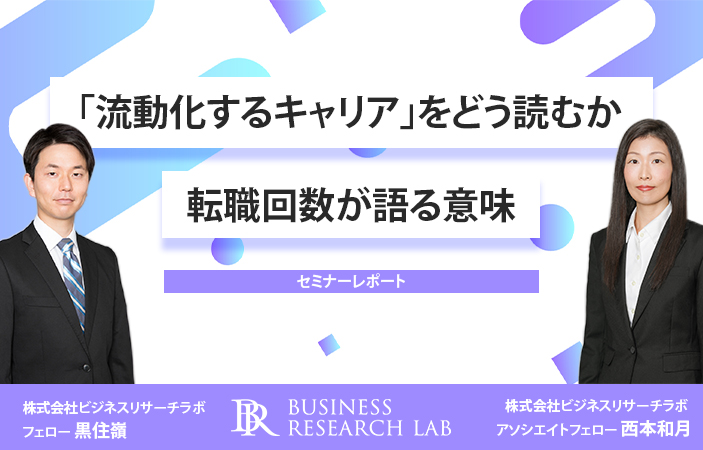2025年7月7日
「流動化するキャリア」をどう読むか:転職回数が語る意味(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年6月にセミナー『流動化するキャリア』をどう読むか:転職回数が語る意味」を開催しました。
一昔前と違い、転職回数が多いことは必ずしもネガティブな印象を与えるものではなくなりました。しかし、職場への定着や適応についての不安が、採用担当者の頭をよぎることも否定できません。柔軟性や多様な経験を評価する声が増えるなかで、「なぜ転職が多いのか」「どのような人なのか」を見極めることが、採用判断においてより重要になっています。
また求職者も、何度も転職をすることは、満足できる仕事や職場環境、待遇につながるのか、それとも自分のキャリアにとってマイナスになるのか悩むところです。
セミナーでは、転職することによって本人が得られる効果や、転職する本人がどのような特徴をもっているのか、転職によって得られる経験をどのように生かしていくのかということについて、採用担当者と求職者の両視点から検討しました。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
転職する自分を理解する
転職と賃金上昇の関係
西本:
まずは、転職と賃金の関係について見ていきます。転職によって社内での昇進以上に賃金が上がることもありますが、逆に働き方や仕事内容を優先して、賃金が下がる転職を選ぶ人もいます。さらに、長く同じ会社に勤め続けることで賃金が上がる場合もあります。つまり、転職と賃金の関係は一概には言えません。
転職の回数とタイミングで10年後の給与を予測した研究[1]では、キャリア開始後2年以内に複数の仕事を経験した人の方が、自分に合った仕事に出会いやすく、結果として将来の賃金上昇につながる可能性があると示されています。この研究では、若年労働者のデータから10年後の賃金を予測するモデルを作成し、次の3タイプに分類しました。
- 定住型:10年間ずっと同じ会社で働く人
- 見極め型:キャリア初期に転職を重ね、自分に合った職場を見つけて長く働く人
(例:半年×4社+2年+6年=10年) - 流動型:2年ごとに転職を繰り返し、どこにも長く留まらない人
最も賃金が伸びたのは「見極め型」の人たちで、特にキャリア初期にいろいろな職場を経験し、その後安定した職場に腰を据えるパターンが有利だと分かりました。この結果から言えるのは、キャリア初期の「目的意識」がとても重要だということです。
働き始めたばかりの頃は、その企業でしか通用しないスキルよりも、どこでも役立つ一般的なスキルが評価されやすい時期です。この時期にさまざまな仕事を経験し、自分に合った仕事や職場を見つけることで、その後長く働ける環境に出会える可能性が高まります。そして、結果的にその職場での勤続年数が長くなり、賃金の上昇にもつながるのです。
転職をする人は、ただなんとなく転職を繰り返すのではなく、「自分がどんなスキルを身につけたいのか」「どんな働き方が合っているのか」を意識することが重要です。採用する側にとっては、応募者の転職パターンや、その背景にある考え方を知ることで、今後の働き方を予測しやすくなります。
転職と情緒的コミットメントの関係
「情緒的コミットメント」とは、働く人が「この会社で働き続けたい」「ここに関わっていたい」といった感情的なつながりを感じている状態のことです。このコミットメントが高いと、離職率の低下や生産性の向上につながります。
入社以降のコミットメントの変動を検討した研究[2]によると、転職直後は多くの人が情緒的コミットメントを高く感じます。これは「自分に合っている仕事に巡り会えた」と考えられることもできるのですが、この感情は一時的な高揚感による場合もあるため、慎重に判断する必要があります。
また、転職回数が多い人ほど「規範的コミットメント」(ここにとどまるべきという意識)が低い傾向にありますが、「情緒的コミットメント」や「継続的コミットメント」(辞めるコストへの意識)とは関係が見られませんでした。
転職した直後に、「この仕事は自分に合っている」「ここでうまくやっていける」と感じることは自然ですが、新しい仕事、新しい職場というものが情緒的コミットメントを上げている可能性もあります。職場が変わること自体が、新たな学習や挑戦の機会となり、情緒的コミットメントを高める可能性があります。
転職をする人は、情緒的コミットメントの高さが新しい環境による一時的な刺激によるものか、本当に長く働ける職場なのかは、ある程度時間が経ってから判断する必要があります。採用側も「転職回数が多いから愛着が湧かない」と決めつけず、時間の経過を見てその人の本当の適応度を判断する必要があります。
転職しやすい人の特徴
性格や価値観は、私たちの行動の傾向を決めるものなので、「転職する・しない」といった選択にも少なからず影響していると考えられます。ただし、性格や価値観には多くの側面があるため、「どの特徴が特に転職と関係しているのか?」ということを慎重に見ていく必要があります。また、もし「転職しやすい性格の人」がいたとしても、その人が長く同じ職場で働き続けることができないとは限りません。転職と性格との関係をどう捉えるかが大切になります。
ここでは、「キャリア志向のタイプ」と「一般的な性格傾向」という2つの視点から見ていきます。
ある研究では、キャリア志向タイプと職務満足度の関係を検討し、次の2つのキャリア志向タイプが示されています[3]。
- 自己中心型キャリア志向:自分の成長やキャリア開発を重視し、転職も前向きに考える
- 組織中心型キャリア志向:安定や組織への貢献を重視し、組織内でキャリアを築こうとする
全体として、入社直後は仕事に対する満足感が高まりますが、6か月ほど経つと、多くの人で満足度が一時的に下がる傾向が見られました。しかしその後の変化には違いがあります。自己中心型キャリア志向の人は、満足度がそのまま低い状態で安定してしまう傾向がありますが、組織中心型キャリア志向の人は、一度は下がるものの、1年ほど経つと再び満足度が回復する傾向が見られました。
この結果から分かることは、「仕事に満足できないと感じたとき、その理由が環境のせいだけとは限らない」ということです。転職をする人は、「自分はどのような考え方で働いているのか」「どのような働き方に価値を感じるのか」といった、自分のキャリア志向を見つめ直すことが今後のキャリア選択において役に立つでしょう。
また採用する側にとっても、このキャリア志向のタイプを把握することは有効です。入社してから6か月ほどの時期には、どちらのタイプの人でも仕事への満足度が下がることが多いため、ここを乗り越えるためのサポートが必要です。しかし、1年後には満足度が回復しにくい自己中心型キャリア志向の人に、特に重点的なケアが必要になる可能性があります。
一般的な性格特性では、次の3つが「退職意向が高くなりやすい人」の特徴として挙げられています[4]。
- 外向性が高い人:社交的でエネルギッシュ。新しい人や環境との出会いを楽しむ傾向がある
- 協調性が低い人:他者との協力や調和を重視しない傾向があり、他者に対して批判的になりやすい
- サイコパシー傾向が高い人:リスクを恐れず、大胆な選択をしやすい。共感や罪悪感を感じにくい傾向がある
転職をする人は、自分の性格も一つの転職の理由としてしっかりと検討してみることが大切です。深く考えずに行動を起こしていないかとか、過去のうまくいかなかった仕事の状況に対して、批判的になりすぎていないかなど、自分を顧みるということは今後のキャリア選択に役立ちます。
採用する側も、転職しやすい性格をネガティブに捉えるのではなく、その人の強みとして活かす視点が重要です。たとえば、外向的な人は初対面でもすぐに打ち解けられ、周囲に活気を与える存在になりやすいという特徴があります。協調性が低い人も、自分の意見をはっきり伝えることができるという強みがあります。
ここまで見てきたことをまとめると、重要なのは「転職の回数」そのものではなく、「どんな思いで転職を決めたのか」「どんな背景があったのか」を理解することです。転職を重ねてきた本人も、迎え入れる側の企業も、その選択の背景を知ることで、より良いマッチングや長期的な活躍につながります。
経験の多さをどう生かすか
「学習の転移」への注目
黒住:
ここからは、「転職数=経験の多さ」という観点に注目します。転職回数が多いということは、多くの職場を経験してきたことは間違いありません。それぞれの職場には共通点や独自性があり、多様な環境で得た経験そのものが価値です。その経験をどう活かすかは、転職する本人にも採用側にも共通の関心事です。
そこで、「経験を新しい職場で活かす」ということを、どうすれば促せるのかという視点でお話しします。注目するのは、「学習の転移(Transfer of Learning)」というテーマです[5]。
学習の転移というテーマは、教育や人材育成の分野で重要視されています。たとえば、研修で得た知識やスキルが、仕事で実際に活用されるかどうか。つまり、これまで身につけたことを新たな場面でどう応用できるかに注目します。たとえば、次のような例が挙げられます。
- ソフトウェアの操作方法を学び、社内ルールに沿って自分の仕事で実践する。
- リーダーシップ研修で学んだ対応を、実際のミーティングで試す。
この例のように、様々なスキルや学習を次に生かすことができるかが、転移の対象になります。そのため、学習の転移というテーマへの注目が、転職によって得た経験を次の職場でどう活かすかに示唆をもたらす視点といえます。
この転移には、学んだ内容を活かすまでの段階があります。具体的には、以下の5つのプロセスです。
- 転移の意図 : 学習後、習得内容を活用しようとする動機・意思
- 開始 : 習得内容を実際に使い始める初期の試み
- 部分的な活用 : 習得内容の一部/全体が一定期間使われている状態
- 意識的な維持 : 「適切」と認識した際に、意識して活用する段階
- 無意識的な維持 : 習慣化され、無意識に使われている状態
このプロセスに基づいて、転職を通して得られた経験の活用を、どうすれば促進できるのかを考えていきます。注目するのは、「本人がその経験をどう捉え活用しようとするか」という「転移の意図」と、想定されているプロセスが進むことに関わる要因です。
「経験を活かそう」と本人が考える意義
まず、「転移の意図」に注目します。学習の転移のプロセスの最初の段階であり、学んだことを仕事で活用しようとする本人の意欲や動機づけに関わるものです。この「活用しよう」という気持ちが、転移の出発点になります。
この考えを転職に当てはめると、前職の経験を新しい職場で活かそうと思えるかどうかが、大きなポイントです。つまり、「過去の経験を活かしたい」と本人が思えるかが、経験の活用に直結します。この「転移の意図」に影響するのが、「態度」「規範」「行動のコントロール」という3つの要素です[6]。
1つ目の「態度」は、自分の経験に対してポジティブかネガティブか、という印象です。「この経験は良かった」「役に立った」といった前向きな意味づけがされているかが影響します。
2つ目の「規範」は、周囲からの期待です。たとえば新しい職場の上司や同僚が「前の経験を活かしてくれるといいな」と思っているかどうかです。
3つ目の「行動のコントロール」は、スキルを自分が再現できると感じているかどうかです。これは「自己効力感」と呼ばれる、自分の力で再現できそうだと思える感覚と、「この環境なら活かせそう」と思える環境要因の2つに分かれます。
これら3要素は、経験を活かせるかどうかに関わっていますが、職種によって影響の度合いが異なることが分かっています。たとえば、裁量が大きいマネジメント職や専門職では、「態度」が特に重要です。「この経験は使える」と前向きに捉えていることが、活用意欲を左右します。一方、一般職のようにタスクや職場の要求に応じた行動が求められる職種では、「規範」、つまり周囲の期待が意欲に影響を与えます。
そして、「行動のコントロール」は職種を問わず共通して重要です。自分が再現できる、あるいは環境的に活かせると感じられるかどうかが、活用を大きく左右します。
こうした転移の意図に関わる知見から、転職する本人と採用担当者のそれぞれができる工夫について考えてみましょう。まず転職を考える本人にできる工夫は、経験を振り返り整理することです。
例えば、成功体験は、「うまくいった」と思える場面を明確にしておくと再現しやすくなります。逆に、失敗体験は自然には活用されにくいということなので、同じ失敗を繰り返さないために、なぜ失敗したのか、どう活かせるかを考えておくと、ネガティブな経験も価値になります。
さらに、「自分のものとして定着したスキルや知識」を確かめることも大切です。「この方法は自然とできるようになった」「あのスキルは今も使える」とコントロール可能であると実感できることが、経験の活用を後押しするといえます。
次に、企業や採用担当者ができる工夫についてです。転移の意図に注目すると、面接や選考で「経験の尋ね方」を工夫するという応用が考えられます。特に、経験を活かすことで自社へ適応できるかという点を見極める意味でも、経験を尋ねることは有効といえるでしょう。
たとえば、過去の成功体験を積極的に尋ねることで、候補者自身が「この経験は活かせる」と考えている内容を確認できます。転移の意図に対する「コントロール」の知見を加味すると、これはどの職種でも効果的です。
そして、マネジメント職や専門職に対しては、過去の経験をどう意味づけているかを聞くと、その人が活用してくれるであろう経験として、どのようものを持っているのかが見えてきます。また一般職での候補者に対しては、「これまでの経験を活かしてほしい」と明確に伝えることが効果的です。この期待が、本人の転移の意図を高めるきっかけになります。
「経験を活かしやすい」環境の整備
もう一つ注目するのは、「転移のプロセスを深める要因」です。先ほど紹介した、学習の転移の5つの段階について、周囲の環境が影響することがわかっています。そうした要因に注目することで、転職する本人が自分の経験を、あるいは採用側が転職者の経験を、活かしやすくするための施策を検討できます。
転移を促す要因としてまず注目するのは、「経験の持つ開放性」[7]です。これは、対象となっているスキルが、手順がどれだけ固定されているか、あるいは汎用性の高さを意味します。
たとえば、パソコンのソフトウェアの使い方のように、手順が明確なスキルは、他職場でも転用しやすいです。一方で、リーダーシップや対人対応のように、状況に応じた対応が必要となるスキルは、転移しにくい傾向があります。
ただし、こうした“開放的なスキル”でも、チームの特徴次第で転用しやすくなることが研究で明らかになっています。特に効果的とされるのが次の2点です[8]。
1つ目は「結束力」です。心理的安全性があり、メンバー同士がサポートし合える環境になっているチームでは、新しい提案や過去のやり方を試しやすいといえます。
2つ目は「誠実性」です。計画性や責任感があり、目標に向かって前向きに取り組むメンバーが多い職場では、新しい知識やスキルも積極的に受け入れられます。結果として、柔軟なスキルでも活用の機会が広がるのです。
つまり、活用が難しいスキルでも、環境が整っていれば実践されやすくなるというわけです。そこで、転職する本人としては、過去の経験と似たタスク・状況・環境を探すことが有効です。「あのときの業務内容は」「どんな人と働いていたか」といった視点で振り返ると、その経験との類似点に気づくことができ、現在の環境にも活かしやすくなります。
逆に、転職者を受け入れる側は、「経験を試しやすい場」を整えるという対応が重要です。転職者が、過去の経験を職場に活かそうとしたとき、まずはその試みを「評価」することが大切です。
たとえば、転職してきた新人が、現在通例とされているのとは異なる方法を、過去の経験から試したとします。このとき、「この会社ではこのルールで」とすぐに変更を求めるのではなく、「新しい視点を提供してくれてありがとう」と、まずは肯定的なフィードバックをすると良いでしょう。
そのうえで、もし転職してきた新人の方法がより良いと感じるならば、その方法を新たに導入することもできますし、通例となっていた社内の方法の一部を見直すといった形で編入することもできるかもしれません。いずれにしても、新人が過去の経験を披露してくれなければ、そうした改善の検討すらできないため、過去の経験を今の職場で試す、という行為・姿勢を認めていくことが重要でしょう。
さらに、採用側の視点としては、実際に過去の経験を行動として活用してもらえずとも、知識として共有してもらえることができれば、今後何らかの形でその経験を活かせるように働きかけることへとつなげられます。当社の別のコラムやセミナーで、組織における知識共有を促す方法について解説していますので、併せてご覧いただければ幸いです[9]。
Q&A
Q1:今回紹介された研究を踏まえて「自分に合った仕事」はどう定義できるか
西本:
「自分に合っている」という感覚は、人によって感じ方が違います。そのため、学術研究では「職務満足度」「組織へのコミットメント」「ワーク・エンゲージメント」など、より具体的な指標を使って分析を行うことが一般的です。そこで、「自分に合った仕事」という言葉を使おうとしている文脈で、その目的に応じた明確化が大切だと考えています。
黒住:
本人の主観だけでなく、職場からサポートを得られるかも関わります。職場からの支援があることで「この職場は自分に合っている」と感じやすくなるということが示されています。つまり、職場や周囲も職場適応を促す役割を担っているという視点も持つことも大切だと思います。
Q2:今回紹介された海外の研究だが、同じ傾向が日本でもあると考えてよいか
西本:
最近は転職やキャリアの考え方が多様化し、「転職回数」よりも「その経験をどう活かせるか」に注目する傾向が出てきていることから、日本も欧米の流れに近づきつつあると言えます。ただ、「個人の意思」や「自分らしさ」が重視される欧米より、日本は「組織への忠誠心」や「周囲との協調性」といった要素が強く働く場面も少なくありません。そのため、日本と欧米の文化的な違いを考慮することも必要です。
Q3:転職数が多い人に対する「離職される懸念」へ企業側の対策はあるか
黒住:
離職を「完全に防ぐ」より、離職の意向が固まった従業員は「円満に送り出す」というアプローチをとることも一策です。無理に引き止めることは、従業員と企業の双方にとって良い対応とはいえません。双方にとって最良の関係を探すことにより、退職後もアルムナイのような形で良好なつながりを実現できれば、長期的に良い効果がもたらされる、と考えるとよいでしょう。
脚注
[1] Yankow, J. J. (2022). The effect of cumulative job mobility on early‐career wage development: Does job mobility actually pay?. Social Science Quarterly, 103(3), 709-723.
[2] Kondratuk, T. B., Hausdorf, P. A., Korabik, K., & Rosin, H. M. (2004). Linking career mobility with corporate loyalty: How does job change relate to organizational commitment?. Journal of Vocational Behavior, 65(2), 332-349.
[3] Doden, W., Pfrombeck, J., & Grote, G. (2023). Are “job hoppers” trapped in hedonic treadmills? Effects of career orientations on newcomers’ attitude trajectories. Journal of Organizational Behavior, 44(1), 64-83.
[4] Kerckhofs, L., Vandenhaute, M. L., & Hardies, K. (2022). Changing jobs like changing clothes: the hobo syndrome among career starters. Discover Psychology, 2(1), 23.
[5] Blume, B. D., Ford, J. K., Baldwin, T. T., & Huang, J. L. (2010). Transfer of training: A meta-analytic review. Journal of management, 36(4), 1065-1105. ; Pham, T. T., Lingard, H., & Zhang, R. P. (2023). Factors influencing construction workers’ intention to transfer occupational health and safety training. Safety science, 167, 106288.
[6] Pham, T. T., Lingard, H., & Zhang, R. P. (2023). Factors influencing construction workers’ intention to transfer occupational health and safety training. Safety science, 167, 106288.
[7] Blume, B. D., Ford, J. K., Baldwin, T. T., & Huang, J. L. (2010). Transfer of training: A meta-analytic review. Journal of management, 36(4), 1065-1105.
[8] Deckers, M., Altmann, T., & Roth, M. (2022). The influence of individual personality traits and team characteristics on training transfer: A longitudinal study. International Journal of Training and Development, 26(1), 69-101.
[9] 例えば、下記のコラムが参考になります。適宜参照ください;
・信頼で防ぐ知識隠蔽:心理的・環境的要因とは
・知識隠蔽か共有か:マイナスとプラスの影響と対策
・自己開示の心理学:本音で話せる職場のつくり方(セミナーレポート)
登壇者

黒住 嶺 株式会社ビジネスリサーチラボ フェロー
学習院大学文学部卒業、学習院大学人文科学研究科修士課程修了、筑波大学人間総合科学研究科心理学専攻博士後期課程満期退学。修士(心理学)。日常生活の素朴な疑問や誰しも経験しうる悩みを、学術的なアプローチで検証・解決することに関心があり、自身も幼少期から苦悩してきた先延ばしに関する研究を実施。教育機関やセミナーでの講師、ベンチャー企業でのインターンなどを通し、学術的な視点と現場や当事者の視点の行き来を志向・実践。その経験を活かし、多くの当事者との接点となりうる組織・人事の課題への実効的なアプローチを探求している。

早稲田大学第一文学部卒業、日本大学大学院文学研究科博士前期課程修了、日本大学大学院文学研究科博士後期課程修了。修士(心理学)、博士(心理学)。暗い場所や狭い空間などのネガティブに評価されがちな環境の価値を探ることに関心があり、環境の性質と、利用者が感じるプライバシーと環境刺激の調整のしやすさとの関係を検討している。環境評価における個人差の影響に関する研究も行っている。