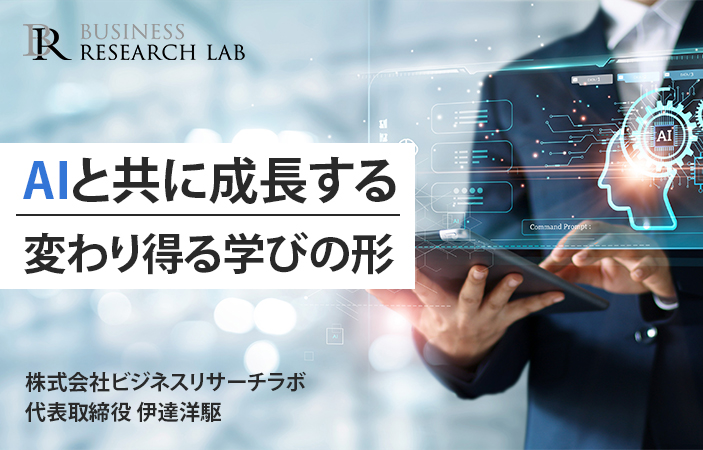2025年7月7日
AIと共に成長する:変わり得る学びの形
対話型の生成AIは、その登場からわずかな期間で多くの人々の働き方や学び方に変化をもたらしつつあります。生成AIの普及によって人間の思考力や創造性が失われるのではないかという懸念の声も多く聞かれました。しかし、実際に生成AIが私たちの生活や学びにどのような影響を与えているのかについては検証が求められています。
本コラムでは、生成AIが人間の心理面や学習面でどのような役割を果たしているのかについて紹介します。メンタルヘルスのサポートとしての可能性、創造的な問題解決への貢献、学習者の感情管理と幸福感への関わり、そして学生の創造的思考力への影響について、実証研究の結果から見えてくる生成AIの姿に迫ります。
これらの研究は、生成AIが情報検索ツールや文章作成ツールを超えて、人間の心理的な支えや学びのパートナーになりうることを示唆しています。もちろん、生成AIにはまだ多くの課題や限界がありますが、適切に活用することで私たちの生活や仕事、学習を豊かにする可能性があります。
本コラムを通じて、生成AIと人間の新しい関係性について理解を深め、生成AIをより良く活用するための視点を得る一助となれば幸いです。生成AIは私たちの心強い味方になり得るのかもしれません。その可能性について研究知見に基づいて考えていきましょう。
生成AIは心理教育や感情支援に効果的
近年、メンタルヘルスの問題は世界的に注目を集めており、適切なケアへのアクセスが課題となっています。心理的サポートを求める人々に対して、専門家の数が十分ではないという状況もあります。このような背景から、生成AIをメンタルヘルス支援に活用する可能性が検討されています。
生成AI(ChatGPT)がメンタルヘルス支援においてどのような効果をもたらすかを調査する研究が行われています[1]。この研究では、不安やうつ病、行動障害などを抱える24人の成人患者が参加し、2週間にわたって毎日最低15分間、自宅でChatGPTを使用してメンタルヘルスの管理に役立てるという実験が行われました。
実験終了後、参加者に対して約54分間の半構造化インタビューが実施され、その内容が分析されました。その結果、ChatGPTがメンタルヘルス支援に与える影響として、8つの肯定的な側面と4つの否定的な側面が浮かび上がってきました。
肯定的な側面としては、まず「心理教育」の効果が挙げられます。参加者の多くがChatGPTから疾患や治療法に関する知識を得ることで、自己管理能力が高まったと報告しました。特にリラクゼーションやストレス軽減のスキルを習得するのに役立ったという声が聞かれました。
次に「感情的支援」の側面では、半数以上の参加者がChatGPTの共感的な対応や非審判的な態度に安心感を得たと答えています。ChatGPTは批判や判断をすることなく対話を続けるため、自分の感情や悩みを素直に表現できる場となったようです。
また、具体的な目標への取り組みにおいて、ChatGPTが「目標設定と動機づけ」の支援を行えることも分かりました。さらに、心理カウンセラーや医療サービスの情報、役立つ文献などの「リソース・紹介情報」の提供、自身の症状評価や生活習慣改善へのアドバイスを通じた「自己評価とモニタリング」の促進なども、ChatGPTの肯定的な側面として挙げられています。
認知行動療法の技術に関しては、ネガティブな思考パターンの特定や置き換えを支援し、認知の再構成を実践するサポートが可能であることが示されました。さらに、危機的な状況における「危機介入」として、自殺予防などの緊急時の連絡先情報を提供することや、日記や誘導イメージ療法などの「心理療法的エクササイズ」を促進し、感情処理能力を向上させる効果も確認されました。
一方で、ChatGPTのメンタルヘルス支援における課題も明らかになりました。「倫理的・法的懸念」として、個人情報の流出や悪用、法的規制の欠如に対する不安が参加者から示されました。また、「情報の正確性・信頼性」についても多くの疑念が呈され、ChatGPTが提供する情報が常に正確であるとは限らないことが問題点として指摘されています。
「限定的な評価能力」の問題もあります。ChatGPTは症状の正確な評価や診断ができず、患者の感情や非言語的な情報を十分に理解することができません。また、「文化・言語的配慮の欠如」も指摘され、特定の文化的背景や言語的ニュアンスを正確に理解できないため、文化に根ざした問題への対応力が不足していることも明らかになりました。
この研究は、生成AIがメンタルヘルス支援において心理教育や感情サポート、動機づけなどの面で有用な役割を果たせる可能性を示していますが、同時に倫理的な問題や情報の信頼性、AIによる感情理解の限界も浮き彫りにしています。
生成AIは学生の創造的問題解決力を高める
教育の現場でも、生成AIの活用が広がっています。高等教育機関では、ChatGPTなどの生成AIが学習ツールとして利用されるようになってきましたが、学生の能力にどのような影響を与えるのかについては、まだ検証が十分に行われていません。
チェコの大学で行われた実験的研究では、生成AI(ChatGPT)が大学生の創造的問題解決能力にどのような影響を与えるのかが調査されています[2]。この研究では、145名の大学生が参加し、ランダムに生成AIを利用する実験群(77名)と利用しない対照群(68名)に分けられました。
実験で使用された課題は「創造的な問題解決」を測定するためのもので、具体的には「玩具のぬいぐるみ(ウサギ)を改善して売上を向上させる斬新かつ有用な方法」を考案するというものでした。実験群はこの課題に取り組む際にChatGPTを自由に利用することができ、対照群はChatGPTを使用せずに課題に取り組みました。
研究者たちは、参加者の解答を「質」(課題の目標に沿った改善案であること)、「精緻さ」(提案された解決策が詳細かつ具体的であること)、「独創性」(アイデアの独自性や新規性)という3つの側面から評価しました。また、参加者自身の「自己効力感」(課題を成功させる自身の能力への信念)、「自己評価の正確性」(自分が提出した成果物に対する客観的な評価とのズレ)、「課題への興味」(課題を行う際の興味や楽しさの程度)、「課題の難易度」(主観的に感じる課題の難しさ)、「精神的努力」(課題解決に費やしたと感じる精神的努力)についても測定されました。
実験の結果、ChatGPTを使用した参加者は、使用しなかった参加者に比べて、質、精緻さ、独創性のすべてにおいて有意に高いスコアを示しました。具体的な効果量(Cohen’s d)は、質で0.69、精緻さで0.61、独創性で0.55という中程度から大きな効果が見られました。
創造性は人間特有の能力であり、AIのような機械的なツールに頼ることで創造性が損なわれるのではないかという懸念もあるでしょう。しかし、この実験の結果は、むしろChatGPTを利用することで、学生たちはより質の高い、詳細で独創的な解決策を生み出せることを示しています。
また、ChatGPTの使用は参加者の自己効力感も高めました。これは、生成AIを利用することで課題がより管理可能であると感じられ、自分の能力に対する自信が向上したためと考えられています。ChatGPTを使用した参加者は課題を有意に容易だと感じ、より少ない精神的努力で課題を解決できたと報告しています。
ただし、自己評価の正確性(メタ認知的評価)に関しては課題も見えてきました。ChatGPTを利用した参加者では、自身のパフォーマンスに関する自己評価と実際の成果の相関が非常に低く、自己評価の際に客観的な指標ではなく、「ChatGPTが役に立ったと感じたかどうか」という主観的な感覚に頼る傾向が見られました。
この研究結果から、研究者たちは「Hybrid Human-AI Regulation理論」という概念を提案しています。これは、ChatGPTがアイデア生成や精緻化を支援し、人間の思考を拡張する一方で、メタ認知的評価(自己評価)においては課題があり、AIの有用性に関する主観的な印象に依存しすぎる可能性があることを示唆しています。
生成AIは感情調整を促し、学習者の幸福感を高める
言語学習は、多くの学習者にとってストレスや不安を伴う過程です。外国語として英語を学ぶ学習者(EFL learners)にとって、言語習得の道のりは心理的な負担が大きいことがあります。生成AIがこうした学習者の心理面にどのような効果をもたらすのかについて、イランで実施された研究が興味深い知見を提供しています[3]。
この研究では、イランの英語教育機関(Milad Language Institute)で学ぶEFL学習者273名を対象に、ChatGPTの使用が学習者のウェルビーイング(心理的幸福感)にどのように影響するのか、そして感情調整(感情をコントロールする能力)がこの関係をどのように媒介するのかが調査されました。
分析の結果、ChatGPTの使用は感情調整と有意な正の相関を示し、ウェルビーイングとも有意な正の相関を示しました。また、感情調整はウェルビーイングと有意な正の相関を示しました。さらに、感情調整がChatGPT使用とウェルビーイングの間の関係を部分的に仲介していることも明らかになりました。
これらの結果から、ChatGPTの使用がEFL学習者の感情調整能力を高め、それが結果的にウェルビーイングの向上につながるというメカニズムが示唆されました。なぜChatGPTの使用が感情調整能力を高めるのでしょうか。
研究者たちは、生成AIが学習者に対して個別化された支援を提供することで、学習過程でのストレスや不安を軽減する可能性を指摘しています。例えば、ChatGPTは学習者からの質問に対して即時に回答し、理解しやすい説明を提供することができます。これによって、学習者は言語学習における不確実性やフラストレーションを減らすことができます。
また、ChatGPTとの対話は非審判的な環境で行われるため、学習者は間違いを恐れずに言語を使用する機会を得ることができます。人間の教師やクラスメイトの前では緊張や不安から発言を躊躇してしまう学習者でも、AIとの対話では心理的安全性が確保されているため、積極的に言語を使用する練習ができるのです。
ChatGPTは学習者のペースや理解度に合わせて情報を提供することができるため、学習者は自分に適したペースで学習を進めることもできます。学習プロセスを自己調整的なものにすることができ、学習に対する自信やモチベーションが高まります。
感情調整能力が向上することで、学習者はネガティブな感情を効果的に管理できるようになり、学習における困難や挫折を乗り越える力が身につきます。これが全体的な心理的幸福感の向上につながるのでしょう。
生成AIは学生の創造的思考力を低下させない
生成AIの教育現場での活用が広がる中、学生がAIに頼りすぎることで創造性が損なわれるのではないかという懸念が示されてきました。こうした懸念に対して、スペインで実施された研究は、重要な知見を提供しています。
この研究では、スペインの大学で幼児教育課程を専攻する学部生28名を対象に、10週間にわたるChatGPTを使用した教育的介入が創造性に与える影響を調査しました[4]。参加者の大部分は、研究開始前にChatGPTを知らないか、知っているが未使用という状況でした。
10週間の介入期間中、学生たちは「細菌の成長」「慢性疾患」「人体」などのテーマに関する教育的課題に取り組む際にChatGPTを活用しました。最初の課題では明確な指示が与えられ、その後の課題では自由にChatGPTを利用して探究型科学教育の方法を考察し、アイデアやベストプラクティスを得る取り組みを行いました。
創造性の測定には、CREA(Creative Intelligence)テストが使用されました。これは、提示された画像に基づいて質問を多数作成することで発散的思考を評価する心理測定テストです。このテストは介入の前後で実施され、スコアの変化が分析されました。
結果的に、10週間のChatGPT使用後、創造性スコアの平均値に統計的に有意な差は見られませんでした。さらに高度な分析では、「創造性は低下しない」という仮説が支持されました。この結果は、ChatGPTの教育的利用が創造性を阻害するという懸念を否定する証拠となります。
研究者たちは、AIツールの使用を根拠なく制限する必要はなく、むしろ教育プロセスへの適切な統合を検討すべきだと提言しています。教育機関や政策立案者は、AI技術を責任ある形で教育に取り入れることで、学生の創造性を損なうことなく、その可能性を拡げられる可能性があるのです。
生成AIが学生の創造性を低下させないという結果は、教育におけるAI活用に対する過度な懸念を和らげ、より建設的な議論を促す可能性があります。重要なのは、AIを教育に取り入れる際の方法や目的を明確にし、学生が受動的にAIに依存するのではなく、AIを創造的な思考のパートナーとして活用できるように導くことでしょう。
脚注
[1] Alanezi, F. (2024). Assessing the effectiveness of ChatGPT in delivering mental health support: A qualitative study. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 17, 461-471.
[2] Urban, M., Dechterenko, F., Lukavsky, J., Hrabalova, V., Svacha, F., Brom, C., and Urban, K. (2024). ChatGPT improves creative problem-solving performance in university students: An experimental study. Computers & Education, 215, 105031.
[3] Rezai, A., Soyoof, A., and Reynolds, B. L. (2024). Disclosing the correlation between using ChatGPT and well-being in EFL learners: Considering the mediating role of emotion regulation. European Journal of Education, 59(4), e12752.
[4] Toma, R. B., and Yanez-Perez, I. (2024). Effects of ChatGPT use on undergraduate students’ creativity: A threat to creative thinking? Discover Artificial Intelligence, 4(1), 74.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。