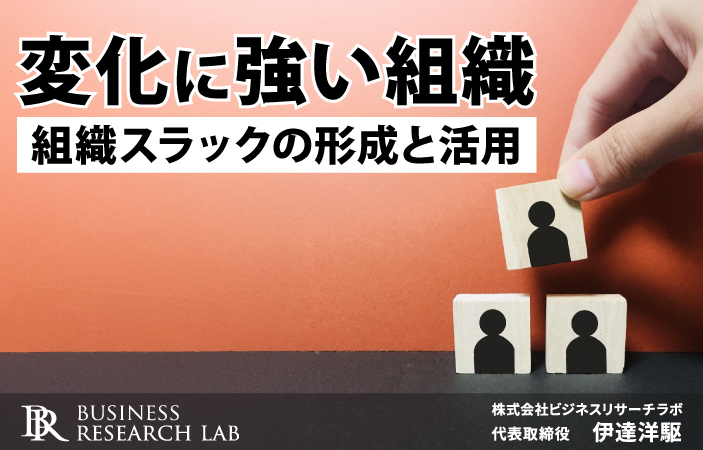2025年7月4日
変化に強い組織:組織スラックの形成と活用
企業や組織が日々の業務に必要な資源を超えて余分に持っている資源のことを「組織スラック」と呼びます。この「余裕資源」は、現金や設備の余力、人員の余裕など、様々な形で存在します。こうした余分な資源は無駄に思えるかもしれません。効率性を追求する経営者の中には、余分な資源は排除すべきだと考える人もいるでしょう。しかし、経営学の研究では、この「余裕」が組織にとって思わぬ価値をもたらす可能性が指摘されています。
組織スラックは、予期せぬ環境の変化への対応力を高めたり、新しい挑戦やイノベーションのための余地を生み出したりする可能性があります。一方で、過剰な余裕は非効率につながる側面もあり、適切なバランスが求められます。この「余裕資源」は組織にどのような意味をもたらし、どのような条件下で価値を発揮するのでしょうか。また、組織はどのようにして、この余裕資源を形成するのでしょうか。
本コラムでは、組織スラックの意義と形成について、4つの側面から検討します。環境の脅威がある状況でスラックが組織の探索活動を促進する可能性、スラックの種類によって企業業績への貢献度が異なること、非公開企業では資源が若干不足している状態の方が業績向上につながる可能性があること、組織スラックがどのような環境要因や組織特性によって形成されるのかを順番に考えていきます。
組織スラックは環境の脅威下で探索活動を促進する
組織が将来に向けて新しい可能性を探る「探索活動」と、既存の強みを活かして確実な成果を上げる「深化活動」のバランスは、経営上のテーマです。環境変化が激しい時代には、将来の生存を左右する探索活動の重要性が高まります。組織はどのような条件下で探索活動に積極的になるのでしょうか。この問いに対して、米国の劇場を対象にした研究が参考になります。
米国の非営利プロフェッショナル劇場を対象とした調査では、劇場が保有する余裕資源(スラック)と、新しい演目への挑戦(探索)や定番演目の上演(深化)との関係が調べられました[1]。この研究では、スラック資源を4つのタイプに分類しています。一つ目は現金などの「財務スラック」で、これは使い道が広く、吸収されていない資源です。二つ目は会員との関係などの「顧客関係スラック」で、これは特殊な価値を持ちながらも吸収されていない資源です。三つ目は余剰設備などの「オペレーショナルスラック」で、これは一般的ですが既に組織内に吸収されている資源です。四つ目は高度な人材などの「人的スラック」で、これは特殊な価値を持ち、組織内に吸収されている資源です。
調査の結果、環境が脅威的だと感じられない通常の状況では、顧客関係スラックとオペレーショナルスラックは探索活動を抑制し、むしろ既存路線の深化を促進することが分かりました。顧客との良好な関係や余裕のある設備は、「現状維持バイアス」を強化し、「うまくいっているのだから変える必要はない」という思考を生み出す可能性があります。
しかし、環境が脅威的だと認識される状況になると、この関係が変化します。環境の脅威が高い場合、財務スラック(現金などの余裕資金)は探索活動を促進し、深化活動を抑制する効果を持ちました。同様に、顧客関係スラックも、環境脅威下では探索への抑制効果が弱まり、深化の促進効果が逆転して抑制効果に変わりました。
この結果は、人間の心理として知られる「プロスペクト理論」で説明できます。プロスペクト理論によれば、人は利益を得る場面ではリスク回避的になりますが、損失が予想される場面ではリスクを取るようになります。環境が脅威的で将来に不安がある状況では、「このままでは立ち行かなくなる」という危機感から、組織は新しい道を探ろうとします。その際、使い道の自由度が高い財務スラックがあれば、新しい試みへの投資が可能になり、探索活動が促進されるのです。
この研究で使われた劇場の例で考えてみましょう。ある劇場が経済不況などで観客減少の危機に直面したとします。このとき、十分な現金(財務スラック)を持っている劇場は、新しい演出方法や革新的な演目に挑戦する余裕があります。また、会員との良好な関係(顧客関係スラック)がある劇場は、会員の理解を得ながら新しい試みをする可能性が高まります。環境の脅威を感じる状況では、余裕資源があることで「守り」から「攻め」への転換が促される可能性があります。
この研究は、組織が環境変化にどう対応するかを考える上で示唆を含んでいます。環境が安定している時期には、余裕資源があっても組織は保守的になる可能性があります。しかし、環境の脅威が高まると、特に自由度の高い余裕資源(現金など)があることで、組織は新しい可能性を探索する方向に動きやすくなります。このことは、不確実性の高い環境下での経営において、ある程度の余裕資源を持つことの価値を表しています。
組織スラックは特に潜在的なものほど企業業績を高める
組織スラック(余裕資源)は企業の業績にどのような影響を与えるのでしょうか。この問いに対して、様々な研究が行われてきましたが、必ずしも一貫した結果が得られていませんでした。ある研究では余裕資源が業績を高めると報告される一方、別の研究では業績を下げるという結果が出ることもありました。こうした矛盾する知見を整理するため、過去の研究結果を総合的に分析したメタ分析の結果を見てみましょう。
1990年から2000年に発表された66件の実証研究(合計54,249社のデータ)を対象としたメタ分析では、組織スラックと企業業績の関係が調べられました[2]。この研究では、スラックを3つのタイプに分類しています。一つ目は「利用可能スラック」で、現金やすぐに活用できる資金など、すぐに使える余裕資源を指します。二つ目は「回収可能スラック」で、間接費など、すぐには使えないものの、必要なら回収して使える資源を指します。三つ目は「潜在的スラック」で、外部からの資金調達能力など、将来的に利用可能になる可能性のある資源を指します。
メタ分析の結果、すべてのタイプのスラックが企業業績と正の相関を持つことが分かりました。基本的には余裕資源が多いほど企業業績が良いという傾向が確認されたのです。これは、スラックが「資源」として組織に価値をもたらすという見方を支持する結果と言えます。
三つのタイプの中でも「潜在的スラック」が業績との相関が最も強いことが分かりました。潜在的スラックは、現時点では使えないものの将来的に活用できる可能性のある資源です。例えば、借入余力(負債を増やす余地)などがこれに当たります。潜在的スラックが業績との相関が強かった理由としては、このタイプのスラックが組織に柔軟性と将来の成長可能性をもたらすためと考えられます。企業が新たな機会に出会ったとき、追加的な資源を調達できる余力があれば、その機会を活かすことができます。
一方、「利用可能スラック」(現金など)は中程度の相関を示し、「回収可能スラック」(間接費など)は小さな相関を示しました。利用可能スラックは使いやすい反面、過剰に持つと非効率になる可能性があります。また、回収可能スラックは既に組織内で使われており、必要になった時に回収するにはコストがかかるため、柔軟性という点では劣ると言えるでしょう。
組織スラックは非公開企業では不足気味が業績を高める
これまで見てきたように、組織スラックは基本的に企業業績に良い影響を与える可能性があります。しかし、すべての企業で同じ効果があるのでしょうか。上場企業と非上場企業(民間企業)では状況が異なるかもしれません。米国の非公開企業900社を対象にした研究では、非公開企業ならではのスラックと業績の関係が明らかになりました[3]。
非公開企業の特徴として、上場企業と比べて資源が不足していることが多いという点があります。資源が制約されている状況では、効率的な資源活用が促される可能性があります。このことから、非公開企業ではスラックの効果が上場企業とは異なるのではないかという仮説が立てられました。
研究では、スラックを「裁量性の高いスラック資源」「裁量性の低いスラック資源」「一時的スラック資源」の3つのタイプに分類しています。裁量性の高いスラック資源とは、現金など使い道の自由度が高い資源を指します。裁量性の低いスラック資源とは、借入金や固定資産など、使い道が限られる資源を指します。一時的スラック資源とは、一時的に利用可能な資源を指し、「資源の利用可能性」と「資源需要」のバランスで測定されます。
調査の結果、非公開企業における「裁量性の高いスラック資源」(現金など)は、予想と異なり、業績と線形に正の関係を持っていました。現金など自由に使える資源が多いほど、業績が良いという結果でした。一方、「裁量性の低いスラック資源」(借入金や固定資産など)は、仮説通り、逆U字型の関係を示しました。ある程度までは業績を改善するものの、それを超えると業績が悪化するという結果でした。
注目されるのは、「一時的スラック資源」に関する発見です。「資源需要」(売上や在庫、買掛金から計算)は業績に強い正の関係を示した一方、「資源の利用可能性」(資本や負債から固定資産を引いたもの)は負の影響を示しました。これは、資源が制約されている状況、つまり需要が供給を超えている状況下で業績が高くなることを意味します。
この結果は、非公開企業では「適度な資源制約」が業績向上につながる可能性を示唆しています。資源が少し足りない状態では、経営者はより効率的に資源を活用し、無駄を省く工夫をするようになります。例えば、資金が潤沢にある場合、新製品開発に多額の投資をするかもしれませんが、資金が限られていれば、最小限の投資で最大の効果を得るための創意工夫が生まれます。
企業の年齢や業界の複雑性によって、スラックの効果が変わることも分かりました。年齢が高い(古い)企業ほど、スラックの業績に与えるプラスの影響が強まりました。これは、経験豊富な企業ほど余裕資源を効果的に活用できることを表しています。一方、業界の複雑性が高い場合は、スラックが業績に与える影響がマイナスに変化しました。複雑な環境では、余裕資源があっても適切な判断が難しく、効果的に活用できない可能性があります。
組織スラックは環境変動や組織特性で形成される
組織スラックが企業の探索活動や業績にどのような影響を与えるかを見てきました。そもそも組織スラックはどのようにして形成されるのでしょうか。スラックの形成要因(先行要因)に焦点を当てた理論的研究から、その形成メカニズムを考えてみましょう[4]。
組織スラックとは「内部的調整や外部環境の変化に対応した戦略変更を可能にする、現在または将来的に利用可能な余剰資源」と定義されます。スラックは資源の裁量性(どれだけ自由に使えるか)によって、「高裁量スラック」と「低裁量スラック」に分類できます。高裁量スラックとは、現金や信用枠、原材料、低スキル労働力、柔軟性の高い機械能力など、用途が広く転用しやすい資源を指します。一方、低裁量スラックとは、加工途中の在庫、熟練労働力、柔軟性の低い機械設備など、用途が特定されており転用が難しい資源を指します。
組織スラックの形成要因は、大きく三つのカテゴリーに分けられます。一つ目は環境要因、二つ目は組織特性、三つ目は組織を支配する人々(ドミナント・コアリション)の価値観・信念です。
環境要因としては、環境変動の速度と規模が挙げられます。変動が早く大きい環境では、組織は高裁量スラック(現金など自由に使える資源)を多く保持する必要があります。突然の変化に対応するには、使い道が自由な資源が便利だからです。例えば、新型コロナウイルスの感染拡大のような予測困難な環境変化に対応するには、現金などの高裁量スラックが役立ちます。
市場の資源の豊富さも影響します。市場資源が豊富であればあるほど、特定用途向けの低裁量スラック(特定の設備など)を保持する傾向が強まります。資源が豊富な環境では、必要な時に調達できる見込みがあるため、汎用的な資源よりも特定目的の資源を持つことが有利になるのです。
産業構造も形成要因の一つです。サービス業は製造業よりも高裁量スラックを必要とし、製造業や成熟産業では低裁量スラックが多くなります。これは業態による資源の性質の違いを反映しています。
組織特性としては、組織サイズが大きいほど多くのスラックを保持できます。規模の経済によって、大きな組織ほど余裕を持ちやすいのです。そして、業績が高い組織ほどスラックを多く持つ傾向があります。ただし、環境が非常に安定している場合は、高業績でもスラックの量が減少することもあります。
組織の年齢も影響します。古い組織ほど、低裁量スラック(特定用途向けの資源)を選択的に保持します。これは長年の経験から、どのような資源が必要かをより正確に予測できるためでしょう。
技術の予測可能性も要因の一つです。技術が予測可能であるほど、低裁量スラック(特定用途向けの資源)を持つことが多くなります。将来必要な技術が予測できれば、それに特化した資源を持つ方が効率的だからです。
組織内部の安定性も関係します。内部が不安定であるほど、高裁量スラック(自由に使える資源)を持ちます。内部の変動に対応するには、柔軟に使える資源が必要になるためです。
組織を支配する人々の価値観や信念も形成要因となります。政治的行動が活発な組織ほど、スラックの総量が増加します。ただし、その場合は特に低裁量スラックが多く、高裁量スラックは少ない傾向があります。政治的な駆け引きの中で、各部門が自らの資源を確保しようとするからです。
リスクに対する態度も影響します。組織が環境を「機会」と認識している場合はスラックを多く持ちますが、「脅威」と認識するとスラックをあまり持たなくなります。これは心理的な要因で、チャンスを活かすための余裕を持とうとする一方、脅威に対しては防衛的になり、余分なものを削ろうとする心理が働くためです。
これらの要因は相互に関連しており、組織スラックの形成に複合的に影響します。例えば、環境変動が激しく、組織が小さく若い場合は、高裁量スラックを中心に持つでしょう。一方、環境が安定し、組織が大きく古い場合は、低裁量スラックが多くなる可能性があります。
脚注
[1] Voss, G. B., Sirdeshmukh, D., and Voss, Z. G. (2008). The effects of slack resources and environmental threat on product exploration and exploitation. Academy of Management Journal, 51(1), 147-164.
[2] Daniel, F., Lohrke, F. T., Fornaciari, C. J., and Turner Jr., R. A. (2004). Slack resources and firm performance: A meta-analysis. Journal of Business Research, 57(6), 565-574.
[3] George, G. (2005). Slack resources and the performance of privately held firms. Academy of Management Journal, 48(4), 661-676.
[4] Sharfman, M. P., Wolf, G., Chase, R. B., and Tansik, D. A. (1988). Antecedents of organizational slack. Academy of Management Review, 13(4), 601-614.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。