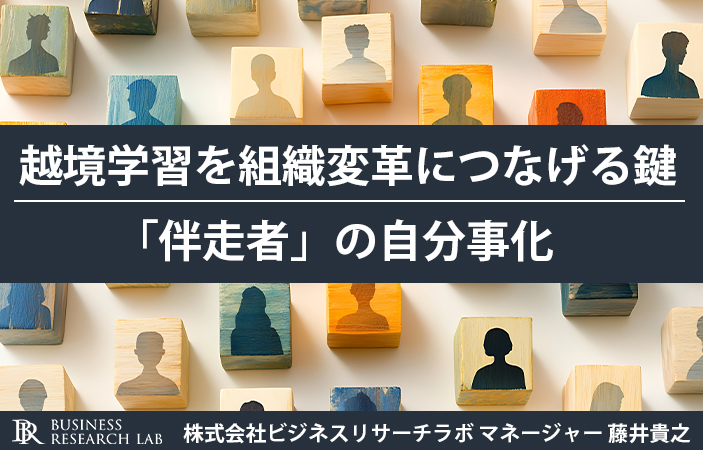2025年7月3日
越境学習を組織変革につなげる鍵:「伴走者」の自分事化
社外や他の組織への短期赴任や、他社での業務体験などを通じて学ぶ越境学習は、多様な価値観を取り入れ、組織を活性化する手段として注目されています。しかし、越境を経験する越境学習の当事者が、個人のやる気や能力だけで組織に変化を起こすのは容易ではなく、彼らを支援する「伴走者」の存在が不可欠です。経済産業省が2025年3月に発行した『越境学習を支える伴走者のための実践ガイドライン』でも、越境学習における伴走者の役割や重要性が強調されています。
ビジネスリサーチラボは、『越境学習を支える伴走者のための実践ガイドライン』の作成に携わらせていただき、私はその中で伴走のご経験をもつ実務家の方々にインタビュアーとしてお話をうかがう機会をいただきました。
本コラムでは、伴走をご経験された実務家の皆様からのヒアリングから得られた示唆や、ガイドライン作成にあたり有識者の方々の意見交換の中で上がった問題意識も手掛かりに、越境学習の伴走者育成の重要性と課題についてご紹介したいと思います。特に、ヒアリングの中で上がった伴走者に求められる資質・スキルや、伴走者の育成の鍵となる「自分事化」について、学術的な観点にも触れて解説します。
伴走者育成の重要性と直面する課題
越境学習者が新しい環境で主体的に動き、潜在能力を発揮するためには、適切なタイミングで多面的な支援を提供できる伴走者の存在が重要です。伴走者は越境学習者の不安を和らげ、学びを促進し、得られた知見を所属組織に橋渡しする役割を担います。では、そうした伴走者をいかに確保し育成していけばよいのでしょうか。
まず、伴走者となる人材をどのように発掘するのか、という課題があげられます。理想的な伴走者の特徴として、「大企業とスタートアップなど複数の現場を知る経験」や「他者の成長をサポートしたいという意欲」をもつこと、そして、「学習者のWill(意思)と企業のMust(要請)を橋渡しできる柔軟性」などがあげられます。
しかし、このような資質を備えた人材は、社内を見渡してもそう簡単には見つからないでしょう。適性のある人が現れるのを待つだけではなく、自社で伴走者候補を計画的に育てていく視点が求められます。
次に、既存の伴走者に過度に依存することによる弊害も無視できません。先の話とも関連し、仮に社内で適性のある人材を見つけられたとしても、その数は多くはないでしょう。結果的に、そのごく少数の選抜メンバーに支援を頼り切りになる、ということが起きてしまいます。越境学習者が困難に直面した際に「特定の人しか頼れない」という状況になると、学習者が孤立しやすくなってしまいます。
また、大きな組織では複数の越境学習が同時に進行することもあるでしょう。その時に、一部の限られた伴走者が複数の越境学習者を同時に担当することになると、1人ひとりに十分時間を割けず支援の質が低下する恐れもあります。このように、伴走者の層が薄いと支援体制が不安定になり、越境学習そのものの成果にも影響しかねません。
組織としての支援不足も課題です。伴走者は通常業務と兼任で支援役を務めることもあり、時間や評価の面で報われにくいケースもあります。ヒアリングによれば、伴走者向けの体系的な研修プログラムを用意している企業はまだ少なく、伴走者自身が手探りで役割を果たすことになり、負担感を抱えたり自信を持てなかったりする可能性があります。
以上のように、伴走者を育成する重要性は高い一方で、人材確保の難しさ・一部メンバーへの偏重・組織的サポートの不足といった課題が浮かび上がります。これらの課題を乗り越えるには、どんな人材を伴走者として育てるべきかを明確にし、伴走者自身の成長と意欲を引き出す工夫が必要です。また、伴走者を組織的に増やし支援体制を整えることが、越境学習プログラムの継続と成功を支える鍵となるでしょう。
伴走者に求められる資質・スキルとは
越境学習を上手く支援できる伴走者として、具体的にはどのような資質やスキルが求められるのでしょうか。実務者の声から浮かび上がるポイントを整理します。
他者の成長を支援したい意欲
まず、ヒアリングのなかで多くの伴走経験者の方から、伴走者の大前提の条件として「越境学習者の成長を喜び、サポートするマインド」があげられました。この意欲があるからこそ、忙しい業務の合間でも学習者との対話に時間を割き、粘り強く見守ることができます。相手の成功や変化を自分事のように喜べるマインドは、伴走者に求められる資質と言えます。
多様な経験と視野
伴走者は越境学習者と派遣先・所属元組織双方の橋渡し役となるため、ビジネスの異なる現場を知っていることが強みになります。異なる企業文化や業務スタイルを理解していると、越境学習者の戸惑いを汲み取りやすく、適切なアドバイスが可能となるためです。
また、自らも越境や転職などの変化を経験していれば、その体験が越境学習者へのアドバイスに説得力をもたらします。成功だけでなく失敗のエピソードも包み隠さず共有することで「今自分が直面している苦労は特別ではない」「自分も変われる可能性がある」と学習者に希望を与えられるでしょう。
優れたコミュニケーション(傾聴と対話)スキル
越境学習者の不安やモヤモヤを引き出し言語化させることも、伴走者の重要な役割の一つです。越境前には「未知の環境でやっていけるか」といった漠然とした不安を抱くものですが、伴走者が丁寧に問いかけることで本人が自分の不安を自覚でき、適切な対処行動を取りやすくなります。
そのような言語化を支えるものとして傾聴力があげられます。越境学習者の思いをしっかり聞き取り、的確な質問で心情を引き出し、「ここは支援できるから大丈夫」と安心させる対話力の高い伴走者は、越境学習者の不安を大幅に和らげられます。
加えて、実際の支援場面では観察による気づきも重要です。例えばオンライン会議で相手の表情の変化に注意を払ったり、後で「今日は少し元気がないようでしたが何かありましたか?」と声をかけたりするなど、相手の状態を観察して本音を汲み取る力も伴走者としての適性と言えます。
新しい環境への適応支援スキル
越境学習者が越境先の文化・慣習・仕事の進め方に早く馴染めるよう手助けする力も欠かせません。これは特に、越境学習者を受け入れる組織の伴走者において重要な観点です。具体例として、「この会議は議論が少なめだから気後れしなくて大丈夫」といった職場の空気感を教えてあげることで、越境学習者の戸惑いを減らせます。
逆にこのスキルが低い場合には、越境学習者が明らかに戸惑っていても「見れば分かるはず」と放置し、越境の本質的ではないところで、無用な失敗や萎縮につながってしまうかもしれません。適応の支援がうまく機能すれば、業務上の齟齬や心理的負担が減り、学習者が自発的に動きやすくなる効果が見込めます。
人脈形成・ネットワーキング支援スキル
新たな環境で成果を出すには、その場にいる人との間で信頼関係を築き円滑に仕事を進めることが必要です。そこで伴走者は、越境学習者が孤立しないように越境先の人と繋がる機会を提供する役割を担うこともあります。
例えば「関係者と早期に顔合わせする場を設定する」「雑談やランチなど非公式な交流を促し、質問しやすい雰囲気づくりをする」といった関わり方があげられます。こうした人脈形成の橋渡し役を伴走者が担うことで、越境学習者が現地のチームに早期に馴染みやすくなり、成果創出もしやすくなります。
モチベーション維持と心理的サポート力:
越境学習者は、途中で壁にぶつかったりスランプに陥ったりすることもあります。その際に伴走者が適切に励まし、必要に応じて目標や業務内容の調整を促すことが大切です。ある伴走経験者は、越境開始後は週1回程度の密度で業務進捗やモチベーションを確認し、3か月目などの節目で方向性のズレがないか見直し、そこで必要ならタスクや目標を修正する、といった進め方をしています。
このように定期的な対話を通じたフォローや目標再設定のサポートも伴走者の重要な役割です。また、学習者が落ち込んだときに寄り添い、「自分ならできる」という自信を取り戻させるような声かけができると理想的です。
学びの橋渡しと成果の組織内展開
越境学習のゴールは、越境学習者本人の成長だけでなく、その学びを所属組織に持ち帰って新たな価値創出につなげることにもあります。そこで伴走者は、越境学習者が得た知見やアイデアを組織内に共有し、活かすための橋渡し役も担います。
その際ポイントになるのが周囲の巻き込みです。越境学習者が職場に戻った後、直属上司だけでなく同僚や他部署のメンバーも交えて「どんな経験をしてきたのか」を聞く場を持つと、多面的なフィードバックが得られます。このような働きかけにより、せっかく得た知見が一過性で終わらず組織に浸透し、越境学習の効果が持続します。
また、上司1人だけがフォローするより、チーム全体で新しい発想の共有に関わった方が、学習者のアイデアを組織で活かす土台が築かれるという指摘もあります。伴走者はこうした場を企画・促進する役回りとして、学習成果の組織展開を後押しするファシリテーターとも言えるでしょう。
以上、伴走者には幅広いスキルセットと資質が求められることが分かります。もちろん最初から完璧にこれらを備えた人はいません。だからこそ、伴走者自身が経験を通じて成長し続けること、組織としてその成長を支えることが大切になってきます。
伴走者育成の鍵は「自分事化」
ここまで伴走者に求められるものを述べてきましたが、そうしたスキルや姿勢はどのように育まれるのでしょうか。その鍵の一つが、伴走者自身が「自分事化」することにあります。自分事化とは字義通り「物事を自分のこととして捉える」ことであり、当事者意識や主体性とも通じるテーマです。
越境学習支援の文脈では、伴走者自身が越境学習のプロセスを自らの成長機会と捉え、主体的・内発的な動機づけを持って取り組むことが、自身の成長と質の高い支援につながると考えられます。越境学習者との関わりの中で、「自分も学びや気づきがある」「新たな経験から変化を遂げられる」という実感を伴走者が持つことができれば、支援にも熱がこもり継続しやすくなります。
実際、越境学習者に寄り添いながら過去の自分のつまずきやそれをどう乗り越えたかを改めて言語化して伝えることは、伴走者自身の内省を深め直す機会にもなります。その結果、「この部分は自分の強みになっていた」「ここはまだ弱いかもしれない」といった自己理解が進み、伴走者自身も再学習・成長できるのです。学習者との“共創”の感覚が生まれ、二人三脚で課題に挑む一体感は、伴走者にとって大きなやりがいとなるでしょう。
では、伴走者の自分事化を促すにはどうすれば良いでしょうか。ここでは、伴走者が自ら選んで支援役を引き受けている感覚と、支援活動を通じて得られる内的報酬に注目してみます。心理学の自己決定理論によれば、人は「自分で決めた」という感覚を持つと内発的動機づけが高まるとされています[1]。
組織として伴走者を募る際も、単なる「任命」ではなく本人の意思や適性を尊重し、手を挙げた人が活躍できるような仕組みにすることが望ましいでしょう。また、伴走者役を担うこと自体がキャリア上の成長機会や承認欲求の充足につながるような内的報酬を感じられるようにすることも大切です。
具体的には、支援を通じて得られる学び(例:コーチングスキルの向上、他社とのネットワーク拡大、自身の視野拡大)を言語化し共有する機会を設けることなどがあげられます。伴走者同士が「自分はこんな気づきを得た」「越境学習者から逆に刺激を受けた」といった経験を語り合えば、互いにモチベーションが上がり、伴走者自身のなかに「伴走には学びがある」という感覚も生まれるのではないでしょうか。
伴走者自身の学びと動機づけ
さらに、伴走者の動機づけを語る上で自己効力感も見逃せません。学術研究では「ある成果を達成するために必要な行動を、実行する自分の能力に対する信念」などと定義されます[2]。ここで注目するポイントは「能力そのものではなく、能力をうまく使えるという自信・信念」に着目しているところです。
伴走者が「自分は支援者としてうまくやれる」という自信を持てるかどうかは、その積極性と粘り強さに影響します。自己効力感は成功体験によって高まるため、小さな成功事例を積み重ねたり、ロールプレイなどで成功体験を疑似的に積ませる研修は有効です。
また、先輩伴走者の失敗談・成功談を共有したり、「メンター・メンティ」関係で起こった出来事を「学びのチャンス」と捉え直す風土づくりも効果的です。先に触れたように、経験豊富な伴走者が自らの変化のストーリーを語ることは、越境学習者だけでなく新人伴走者の励みにもなります。「先輩も最初は苦労したけどこう乗り越えた」という話は、初心者の伴走者に「自分もできるかもしれない」という期待感を抱かせ、自己効力感の醸成につながるでしょう。
最後に、動機づけと関連してアイデンティティの視点にも触れておきます。人は自分の役割や仕事に意義を見出せるとき、深いコミットメントを示すものです。心理社会的発達理論を提唱したエリクソンは、中年期の課題として「世代性(次世代を育成しようとする関心)」を挙げています[3]。これは後進を育て社会に貢献したいという欲求であり、組織で言えばミドル層の社員がメンター役を引き受ける動機ともなります。
実務においても「ベテラン社員が若手の成長支援にやりがいを感じ、自身の経験を伝えたいと望んでいる」という場面は少なくありません。つまり、伴走者という役割は経験を積んだ人にとって自己のアイデンティティの拡張であり、「人の成長を支える自分」という新たな自己像の確立につながります。
それが叶えば、伴走者は単なる仕事やボランティアとしてではなく、自らの使命感を持って取り組めるようになるでしょう。組織はそうした前向きなアイデンティティ形成を支援する場を提供し、伴走者が誇りを持てる文化を育むことに注目してみるのも良いかもしれません。
組織的に伴走者を育てる意義と仕組みづくり
伴走者個人の育成もさることながら、越境学習を持続的に成功させるには組織全体で伴走者を育て支援する仕組みづくりが欠かせません。その意義と具体的な方策について考えてみます。
支援役割の分散と文化醸成
従来、越境学習の支援は特定のメンターや上司に一任されがちでした。しかし、ガイドラインでも提唱しているように、「伴走者は一人ではなくみんなで少しずつ」という方針が望まれます。一人のスーパーマンに頼るのではなく、周囲の同僚・先輩・人事担当者など複数の人がそれぞれ主体性を持って部分的に伴走役を担う方が、学習者の成長を総合的に高め組織全体にも効果が及ぶと考えられます。
例えば、所属部署では上司だけでなく同僚や他部署のキーパーソンも積極的に声をかけてサポートする、受け入れ担当者が全てを抱え込まずチーム全員が当事者意識を持って気にかける、といった体制です。
さらに第三者的な立場のメンター(社外メンターなど)もうまく活用すれば、組織内の人だけでは拾いきれない視点や安心して相談できる場を提供できます。このように支援のネットワークを組織的に張り巡らせることで、一人の伴走者に過度な負担が集中することを避けつつ、学習者に途切れないサポートを提供できるのです。
伴走者コミュニティと相互学習の推進
組織内外に散らばる伴走者同士が情報交換し学び合えるコミュニティも、有効な仕組みです。他社の伴走者との交流は自社内では得られない新しい視点やノウハウをもたらします。社内においても、現在伴走者を務めている人や過去に経験した人が定期的に集まり、成功・失敗事例の共有や悩み相談を行う場を設けると良いでしょう。
伴走経験者の声としても「同じ伴走者同士で越境学習者との失敗・成功事例を共有すれば、スキル習得のスピードが格段に上がる」といった指摘があります。伴走中に起こった問題や発見をすべて「学びのチャンス」と捉えて共有し合うことで、組織全体の支援スキルが底上げされます。
また、そのような場で互いの苦労を理解し合えると心理的なサポートにもなり、「自分だけが大変なのではない」と伴走者のメンタルヘルス面にも良い影響をもたらします。こうしたコミュニティによる相互学習を通じて、伴走者集団が一緒に育っていく仕組みを作ることが大切です。
経営層の理解と後押し
組織的な伴走者育成には、経営層の理解と後押しも不可欠です。越境学習を通じた人材育成やイノベーション創出を本気で目指すなら、トップがそれを自分事として捉え、伴走者となる社員たちを支援する文化を作ることが望まれます。
具体的には、経営陣が越境学習の成果や伴走者の貢献を定期的にレビューし称賛する、伴走者経験を次期リーダー育成の評価項目に入れる、伴走者活動に時間を割くことを容認・奨励する(業務目標に組み込む)といった施策が考えられます。
経営トップ自らが「全員が当事者意識を持って学びを支えよう」というメッセージを発信し、制度面・風土面で後押しすることが、組織的な伴走者育成の仕上げとなるでしょう。
以上、組織的な仕組みづくりの観点から、伴走者を育て支える意義と方法を述べました。ここで取り上げた内容のポイントは、経営層も含めてすべての関係者が「自分事化」し、個人任せにしないで組織ぐるみで取り組むということです。
伴走者は越境学習の「縁の下の力持ち」ですが、その力持ちを一部のヒーローに頼るのではなく、みんなで担い合うことで持続可能な支援体制が築けます。そしてその過程で、社員一人ひとりが互いの学びを支え合う文化が育てば、組織全体の学習能力・変革能力も高まっていくはずです。
おわりに:伴走者育成が組織にもたらすもの
越境学習における伴走者の育成について、重要性と課題、必要な資質、動機づけの鍵となる自分事化、そして組織的な仕組みづくりを概観してきました。伴走者は表舞台に立つ主役ではありませんが、越境学習者という主役を支え、その成長の物語を裏で演出する大切な存在です。
伴走者を育てることは単に支援者を増やすだけでなく、越境学習者の成長と組織にイノベーション創出を促す「土壌」を耕すことにもつながっています。伴走者自身が成長し充実感を得られれば、そのエネルギーが次なる越境学習候補者にも波及し、ひいては組織に新たな価値をもたらす好循環を生み出す可能性を秘めています。本コラムが、越境学習の陰の立役者である伴走者に目を向け、彼らの育成・支援に取り組んでいただく一助になれば幸いです。
越境学習にご関心のある方は、以下の資料も是非ご覧ください。
脚注
[1] Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The” what” and” why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological inquiry, 11(4), 227-268.
[2] Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Macmillan.
[3] Erikson, E. H., & Erikson, J. M. (1998). The life cycle completed (extended version). WW Norton & Company.
執筆者

藤井 貴之 株式会社ビジネスリサーチラボ マネージャー
関西福祉科学大学社会福祉学部卒業、大阪教育大学大学院教育学研究科修士課程修了、玉川大学大学院脳情報研究科博士後期課程修了。修士(教育学)、博士(学術)。社会性の発達・個人差に関心をもち、向社会的行動の心理・生理学的基盤に関して、発達心理学、社会心理学、生理・神経科学などを含む学際的な研究を実施。組織・人事の課題に対して学際的な視点によるアプローチを探求している。