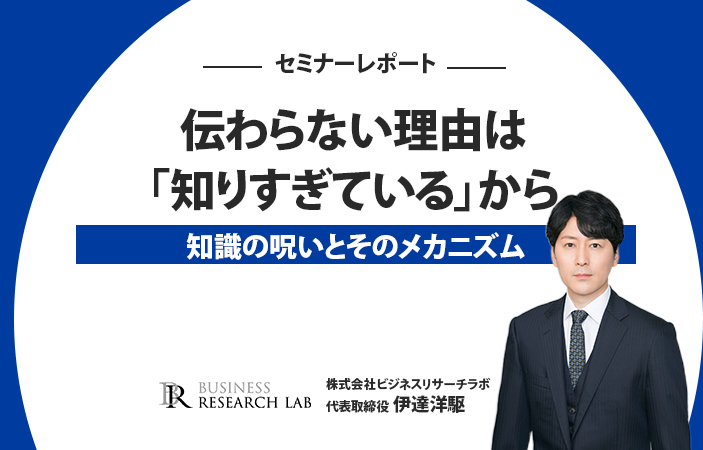2025年7月2日
伝わらない理由は「知りすぎている」から:知識の呪いとそのメカニズム(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年6月にセミナー「伝わらない理由は『知りすぎている』から:知識の呪いとそのメカニズム」を開催しました。
専門知識を持つ人ほど初心者に物事を上手く伝えられなくなる。これが「知識の呪い」という現象です。皆さんの組織でも「何度説明しても理解してもらえない」と感じることはありませんか。コミュニケーションの溝には、心理学的なバイアスが関係しているかもしれません。
「知識の呪い」とは、自分が習得した知識を当然のものと感じるあまり、その知識を持たない人の視点を想像できなくなる心理状態です。企業内ではこの現象により、新人教育の非効率化、チーム内の意思疎通の混乱、さらには重要な意思決定の歪みまで引き起こすことが研究で明らかになっています。
本セミナーでは、研究知見を手がかりに、ビジネス現場における「知識の呪い」の影響を解説しました。投資判断のずれ、専門家と初心者の行き違い、データの解釈における誤解など、職場で起きる問題とその原因に迫っています。
また、このバイアスを実際に克服するための方法や、組織として知識共有を効果的に行うためのアプローチも紹介しました。人材育成の質を高めたいマネージャー、組織内のコミュニケーションを改善したい人事担当者の方々にとって参考になる内容です。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
職場で経験豊富な先輩が新人に業務を教える際、「これくらいは当然分かるだろう」と思い込んで説明を省略してしまうことはないでしょうか。あるいは、専門知識を持つ部署のリーダーが、他部署のメンバーに対して専門用語を多用しながら説明し、相手が困惑している様子に気づかないといったケースも見受けられます。
このような現象の背景には、「知識の呪い」と呼ばれる心理的なメカニズムが働いています。これは、一度何かを深く理解してしまうと、その知識を持たない人の視点を想像することが困難になってしまう認知バイアスです。組織マネジメントや人材育成において、この現象を理解することは重要であり、効果的なコミュニケーションを実現するための鍵となります。
知識の呪いとは
知識の呪いとは、ある分野について豊富な知識や経験を持つ人が、その知識を持たない他者の理解レベルを正確に推測できなくなる現象を指します。職場においては、管理職が部下の理解度を過大評価したり、ベテラン社員が新人の学習進度を見誤ったりする形で現れることがあるでしょう。
この現象を実証的に示した研究では、複雑な作業課題について「初心者がどれくらいの時間で完了できるか」を専門家、中程度の経験者、初心者自身にそれぞれ予想してもらう実験が行われました[1]。その結果、どのグループも実際にかかった時間よりも短めに見積もる傾向がありましたが、特に専門家の予想が現実から大きく乖離していました。
専門家が過度に楽観的な見積もりをしてしまう理由は明確です。長年の経験により、基本的な作業ステップが自動化されているため、初心者が直面する困難を想像することが困難になっているからです。初心者だった頃の記憶は薄れており、当時感じていた戸惑いや試行錯誤の過程を正確に思い出すことができません。そのため、「この程度の作業であれば順調に進むはず」という思い込みが生まれ、現実よりも短い時間を想定してしまいます。
興味深いことに、初心者自身も楽観的な見積もりをする傾向が見られました。経験が全くない状態では、作業の複雑さを十分に把握できないため、「意外と簡単に終わるかもしれない」と考えてしまうのです。しかし、専門家の見積もりの方がより大きく外れることが多く、知識の蓄積が逆に正確な判断を妨げているという皮肉な結果が浮き彫りになっています。
教育現場における知識の呪いも深刻な問題です。物理学を例に取ると、長年研究に携わってきた教授にとって当然の概念であっても、学び始めたばかりの学生には極めて理解困難な内容である場合があります[2]。教える側は「なぜこんな基本的なことが分からないのか」と困惑し、学ぶ側は「どこが分からないのかすら分からない」という状況に陥ってしまいます。
このような認知バイアスは、子どもだけに見られる現象ではありません。大人を対象とした研究でも、知識の呪いが存在することが示されています。例えば、バイオリンが隠された箱の位置を知っている大人は、その情報を持たない他の大人も同じ箱を最初に探すだろうと推測する傾向があります[3]。
さらに、大人の場合、子どもよりも優れた推論能力が知識の呪いを強化する要因として働く可能性があります。論理的思考力が高いほど、自分の知識に基づいて「相手もこのように考えるはず」という推論を組み立ててしまい、結果、知識の呪いから離れることができなくなってしまいます。
このように、知識の呪いは年齢や能力レベルに関係なく、私たち全員に関わる現象です。職場において効果的なコミュニケーションを実現するためには、この現象の存在を認識し、自分自身も例外ではないという姿勢を持つことが重要です。
様々な場面で顔を出す
知識の呪いは、私たちが想像する以上に幅広い場面で姿を現します。例えば、情報の可視化においても、この現象は現れることが研究で明らかになっています。
グラフやチャートを用いたデータ表現に関する実験では、背景情報を事前に与えられたグループが興味深い反応を示しました[4]。彼ら彼女らは「このグラフを見れば、誰でも同じ箇所に注目し、同じ結論に到達するだろう」と考えたのです。しかし実際には、背景情報を持たない人々は、グラフの様々な要素に目を向け、多様な解釈を行っていました。知識の呪いが、効果的な情報伝達の妨げとなり得ます。
競争場面における知識の呪いも見逃せません。クイズの答えを事前に教えられたグループを対象とした研究では、二重の認知バイアスが作用することが分かりました[5]。初めに、答えを知っている人は他者の成績を高めに見積もります(知識の呪い)。同時に、自分の成績を他者以上に高く評価し、「自分なら勝てる」という過度な自信を抱きます(自信過剰)。
医療現場における知識の呪いは、深刻な問題を引き起こす可能性があります。豊富な専門知識を持つ医師が、患者や研修医とのコミュニケーションにおいて、相手の理解レベルを過大評価してしまうケースが報告されています[6]。医師は「要点はすでに説明したはず」と考えているにもかかわらず、患者は治療のリスクを十分に理解できていない状況が生まれてしまいます。研修医への指導においても、基本的な手順の説明を省略してしまい、実際の処置の際に混乱が生じるといったことも見受けられます。
交渉場面でも、知識の呪いは影響を与えます。相手方の資金状況や制約について詳細な情報を持っている当事者は、「相手も自分と同程度に状況を理解しているだろう」と思い込みがちです[7]。しかし、情報を持たない側はそこまで詳しい事情を把握していないため、期待に食い違いが生じ、交渉が決裂するリスクが高まります。
企業の投資判断プロセスにおいても、知識の呪いは無視できない影響を及ぼします。多くの情報を収集した管理職が経営層に報告する際、「相手もある程度の背景知識を持っているはず」という前提で説明を簡略化してしまうことがあります[8]。しかし、経営層が十分な情報を持っていない場合、判断材料が伝わらず、投資決定の精度が低下するかもしれません。
このように、知識の呪いは職場の様々な局面で発生し、コミュニケーションの質を低下させたり、意思決定プロセスを歪めたりします。組織マネジメントにおいて、この現象を認識し、適切な対策を講じることの重要性は明らかです。
知識の呪いのメカニズム
知識の呪いがなぜ発生するのかを理解するために、そのメカニズムを探ってみましょう。
有力な説明の一つが「流暢性の錯覚」です。情報が頭の中でスムーズに想起される状態になると、その情報は多くの人に共有された知識であると誤って判断してしまう現象を指します。
この仕組みを示す実験があります[9]。参加者に問題を出してから正解を教え、「その答えを他の人々も知っているだろうか」と評価してもらいました。すると、一度正解を学んだ人ほど「多くの人が知っている可能性が高い」と判断する傾向が現れました。
興味深いのは、時間が経過して正解を忘れかけていても、この傾向が残り続けることです。実際には答えを思い出せない状態であっても、「以前に自分は正解を知っていた」という記憶の断片が、他者の知識レベルを過大評価する判断につながるのです。
さらには、正解を教えられなくても、問題文を繰り返し読むだけで似たような効果が生まれることが分かりました。文章に何度も触れることで親しみが生じ、その親しみが「きっと他の人も知っているはず」という錯覚を引き起こしてしまいます。
知識の呪いが発生するもう一つの要因が「親しみやすさ」です。自分にとって馴染み深い内容ほど、他の人も当然知っているだろうと考えてしまいます。
子どもを対象とした研究では、学んだ答えが身近な内容だと感じられるときに限って、「多くの友達もその答えを知っている」と過大評価する現象が観察されました[10]。一方、全く馴染みのない内容については、そのような過大評価は起こりにくいことが判明しています。
この結果は、私たちが「自分にとって自然に理解できるもの」を「他の人にも当たり前に通じるもの」と混同してしまう心理を浮き彫りにしています。客観的には高度で複雑な内容であっても、自分にとって馴染み深ければ、相手も容易に理解できるはずだという思い込みが強化されます。
これらのメカニズムを理解することで、知識の呪いが単なる「説明不足」や「配慮不足」ではなく、人間の認知プロセスに深く根ざした現象であることが分かります。職場においても、このような心理的メカニズムを念頭に置いたコミュニケーションを構築することが求められるでしょう。
知識の呪いを抑制するには
知識の呪いを抑制するための方法を検討する前に、一般的に効果があると思われがちな手法の限界を理解しておく必要があります。
「相手の立場に立って考えてください」という指示は、直感的には有効に思えるかもしれません。しかし、研究結果は意外な事実を示しています。コミュニケーションにおいて「情報を持たない相手を意識するように」と明確に指示されても、知識の呪いは十分に抑制されないことが実験で確認されています[11]。
この研究では、話し手の意図(皮肉を込めているなど)を参加者だけが知っている状況を作り、聞き手がどのように解釈するかを予測してもらいました。一部の参加者には「聞き手の視点を強く意識してください」という指示を与えましたが、知識の呪いによる偏りは残り続けました。
パースペクティブ・テイキング(相手の視点に立つこと)の重要性を頭で理解していても、それだけでは認知バイアスを十分に回避することはできないのです。このことは、知識の呪いが表面的な意識レベルではなく、より深い認知プロセスに根ざしていることを示唆しています。
それでは、どのような方法が実際に効果を発揮するのでしょうか。監査業務における研究が、手がかりを提供してくれます。
経験豊富な監査人を対象とした実験では、企業の破綻情報を事前に知らされた監査人が、その兆候を過大評価してしまう知識の呪いが確認されました[12]。興味深いことに、「説明責任を強化する」「より慎重に判断するよう求める」といった一般的な介入では、この偏りは改善されませんでした。
しかし、「反論を作成してください」という課題を与えたところ、知識の呪いが抑制されることが分かりました。具体的には、破綻に至らなかった可能性のあるシナリオを詳細に検討してもらうことで、固定化された思考パターンが緩和され、より客観的な判断が可能になりました。
この「反論思考」の効果は、他の研究でも確認されています。代替シナリオを丁寧に生成することで、一方向に偏った認識を修正し、多角的な視点を取り戻すことができるのです。
これらの知見を職場のコミュニケーションに応用すると、次のような具体的な方法が考えられます。
- 重要な判断を下す前に「この判断が間違っている場合は、どのような展開になるか」を積極的に検討することです。自分の知識や経験に基づく予測が外れる可能性を真剣に考えることで、思考の硬直化を防ぐことができます。
- 部下や同僚への説明場面では「相手が理解していない場合はどうなるか」を具体的に想定することです。単に「相手の立場に立とう」と考えるのではなく、理解不足によってどのような問題が生じうるかをシミュレーションすることで、より効果的な説明方法を見つけることができます。
- チームでの意思決定プロセスにおいては、意図的に「悪魔の代弁者」の役を設定し、主流の意見に対する反論を組織的に検討することも有効です。これによって、知識の呪いによる思い込みを集団レベルで防ぐことが可能になります。
重要なのは、これらの方法を単発的に実施するのではなく、組織の習慣として定着させることです。反論思考や代替シナリオの検討を日常的な業務プロセスに組み込むことで、知識の呪いの影響を抑制することができるでしょう。
知識の呪いをむしろ活かす
知識の呪いを完全に除去することが困難であるならば、この現象を逆手に取って活用することはできないでしょうか。知識の呪いには予想外の利点も存在することが明らかになっています。
情報収集と報告に関する研究では、送信者が受信者の知識レベルを過大評価することが、むしろ情報の質向上につながる場面があることが示されています[13]。「相手も自分と同程度に内容を理解しているだろう」と考える送信者は、いい加減な情報を提供するわけにはいかないというプレッシャーを感じ、より正確で詳細な調査を行う傾向があるのです。
通常であれば「そこまで厳密に調べなくても良いだろう」と考える状況でも、知識の呪いによって「相手は高いレベルで話を聞くはず」と想定することで、自然と情報精度への意識が高まります。ただし、これには注意も必要です。徹底的に調査を行った結果、「どうせ相手も知っているだろう」と説明を省略してしまうリスクも存在するからです。
この知見を踏まえると、知識の呪いを効果的に活用する方法が見えてきます。
- プレゼンテーション準備の場面では、「聞き手も専門知識を持っている」という前提で資料を作成することで、内容の正確性と網羅性を高めることができます。細部まで検証された高品質な資料を準備することは、どのような聞き手に対しても価値のある取り組みです。
- 報告書作成においても、「読み手も業界事情を十分に知っている」という前提で執筆することで、表面的な情報に留まらない深い分析を行うきっかけになります。専門家の視点に耐え得る内容を目指すことで、結果的に質の高い文書が完成するでしょう。
- 重要な判断を下す前の検討プロセスでも、「上司や関係者も同じ情報を持っている」という前提で分析を進めることで、より綿密な準備を行うことができます。中途半端な検討では済まないという意識が、作業の質を向上させます。
知識の呪いが持つもう一つの意外な効果が、知的謙虚さの促進です。「周りの人も自分と同じくらい分かっているはず」という認識は、「自分だけが特別に優秀というわけではない」という謙虚な姿勢につながる可能性があります[14]。
この心理的効果を組織運営に活かすことも可能です。
- 会議運営においては、「参加者全員が有能である」という前提で進行することで、一人ひとりの発言を尊重し、多様な意見を引き出す雰囲気を作ることができます。
- 新人指導の場面でも、「新人は基本的な理解力は高い」という前提で接することで、過度に上から目線になることを避け、相手の自尊心を保ちながら指導を行うことができるでしょう。
ただし、知識の呪いが必ずしも知的謙虚さにつながるわけではないことに注意が必要です。場合によっては、自分の知識レベルを周囲に押し付けるような態度につながる可能性もあります。重要なのは、この現象の両面性を理解し、良い面を意識的に強化する努力を続けることです。
おわりに
知識の呪いは、私たちの職場のコミュニケーションに影響を与える認知現象です。専門家と初心者の時間の見積もりの違いから始まり、教育現場での理解度の誤認、データ可視化における解釈の偏り、医療現場でのコミュニケーション不全、交渉や投資判断での認識のズレまで、その影響は広範囲に及びます。
この現象の根本には、流暢性の錯覚と情報への親しみやすさという心理的メカニズムが働いています。一度頭に入った情報は思い出しやすくなり、馴染み深い内容ほど「他の人も知っているはず」という錯覚を生み出してしまうのです。
知識の呪いを抑制する方法として、単純な「相手の立場に立とう」という指示では不十分であることが研究で示されています。より効果的なのは、反論思考や代替シナリオの検討といった、積極的に異なる視点を構築する取り組みです。
一方で、知識の呪いには予想外の利点も存在します。情報収集の質を向上させたり、知的謙虚さを促進したりする効果が期待できる場合があります。この現象を完全に排除するのではなく、うまく活用する道を探ることも重要です。
Q&A
Q:最近話題の生成AIは、「知識の呪い」を解消するために活用できるのでしょうか。例えば、専門家である自分の考えに対して、AIにあえて素人の視点から反論してもらったり、疑問を投げかけてもらったりするのは有効な使い方でしょうか。
その活用方法は有効であると思います。「知識の呪い」とは、ある分野の専門家が、自分にとっては当たり前の知識が他の人にはそうではないという事実を忘れがちになってしまう状況を指します。この状態を乗り越えるためには、自分の考えを客観的に見つめ直す必要があります。
その手段として、ご提案いただいたように、生成AIにあえて素人の立場で考えてもらったり、意図的に反論させたりすることは興味深く、効果的なアプローチだと感じました。自分一人の頭の中で異なる視点から物事を考えるのは、思いのほか難しいものです。
Q:人事評価の時期になると、評価者である管理職や上司の「知識の呪い」が気になってしまいます。上司が自身の過去の業務経験を基準にしてしまい、「このくらいの仕事はできて当然だ」と判断し、部下が地道に積み重ねた努力や成果を正しく評価できていないように感じることがあります。
人事評価という特定の状況において「知識の呪い」の影響を和らげるためのいくつかの方策が考えられます。初めに、評価基準そのものを、解釈がぶれにくいように、より客観的で具体的なものにしていくことが重要です。個人の主観的な「これくらいできて当然」という感覚で評価が行われると、「知識の呪い」が発生しやすくなります。これを防ぐために、例えば評価項目を「〇〇ができる」といった行動レベルで定義し直したり、評価者によって判断が分かれないような明確な基準を設けたりする、といった仕組みを整えることが有効でしょう。
また、人事部門として取り組めることとして、評価者である管理職向けの研修が挙げられます。その研修の中に、例えば「自分の評価判断がもし間違っているとしたら、どのような可能性があるだろうか」と、あえて自分の考えに反論を加えたり、別の可能性を探ったりするようなワークを取り入れます。こうしたトレーニングは、「知識の呪い」を軽減させるきっかけになるかもしれません。
Q:講演でご紹介いただいた、あえて反対意見を述べる「悪魔の代弁者」や、自分の考えを疑う「反論思考」といった手法は、非常に興味深いと感じました。しかし、同調圧力が強く、「出る杭は打たれる」ような文化の組織では、実践が難しいとも感じます。異論を唱えること自体が否定的に捉えられ、かえって人間関係を悪化させてしまうリスクも心配です。
異論を唱えることに抵抗がある組織で、こうした文化を醸成していくのは簡単なことではありません。重要なのは、経営層や管理職といった立場の方々が、自らこれらの手法を実践し、そのポジティブな効果を組織内に示していくことです。「反対意見は、私たちの意思決定の質を向上させるために不可欠である」というメッセージを、行動で示す必要があります。
ただ、メッセージだけではなかなか浸透しませんので、具体的な仕組みとして導入することも有効です。例えば、どのような会議であっても、議題の中に「代替案の検討」や「潜在的リスクの洗い出し」といった項目を組み込んでしまいます。そうすることで、多様な意見や異論を述べることが特別ではなく、会議のプロセスの一部として当たり前になります。異論を歓迎する時間や場所を意図的に確保することが、第一歩として考えられます。
そうした場で出された少数意見や反対意見のおかげで、より良い結論に至ることができた、という成功体験を積み重ね、その事実を社内で共有していきます。反対意見は、発言者による他者への「攻撃」ではなく、組織全体に対する価値ある「貢献」なのだという認識の転換が図れたとき、それは一過性の取り組みではなく、組織文化として根付いていくのではないでしょうか。
Q:私の上司は、自身の経験からくる「知識の呪い」によって、業務にかかる時間や手間を非常に短く見積もる傾向があります。そのため、次々と業務を指示され、常に自分の処理能力を超えた状態になってしまいます。しかし、それを率直に伝えると、自分の能力不足だと判断されてしまうのではないかと不安で、辛い状況です。
感情的に「時間が足りません」と訴えるだけでは、おっしゃる通り、能力を疑問視されかねません。いくつかの段階を踏んで、客観的な事実をもとに状況を改善していくアプローチが考えられます。
第一に、ご自身が担当した業務内容と、それに実際に要した時間を、主観を交えずに淡々と記録し続けます。「なんとなく時間がかかった」ではなく、「この作業には〇時間〇分かかった」というデータが、対話の基礎となります。
可能であれば、次のステップとして、同じような業務を行っている同僚にも協力をお願いし、同様に作業時間を記録してもらうと、さらに説得力が増します。例えば、上司は「1時間でできるはずだ」と言っている業務に対して、ご自身も同僚も実際には2時間かかっているという事実がデータで示せれば、それは個人の能力の問題ではなく、見積もりそのものにズレがあることの証拠となります。
そして、それらの記録をもとに、「この業務には、現状のやり方ではどうしても2時間かかってしまいます。もし、これを1時間で完了させるための、より効率的な方法をご存知でしたら、ぜひご教示いただけないでしょうか」と、あくまで前向きで建設的な相談という形で、上司にフィードバックを求めてみます。そうすることで、上司も自身の見積もりが現実的であったかを再考するきっかけになり、少しずつ認識のズレを修正していける可能性があります。
Q:これまでの講演を聞いて、私自身も気づかないうちに「知識の呪い」に陥ってしまっているのではないかと、少し不安になりました。他人の「知識の呪い」には気づきやすいものですが、自分のこととなると、客観的に見るのは本当に難しいと感じます。自分が「知識の呪い」に陥っている可能性に気づくために、何か日頃からできることはあるのでしょうか。
ご自身のことを省みて不安に思われるというのは、健全で素晴らしい感覚だと思います。ご自身が「知識の呪い」に陥っていないかを確認するための効果的な方法は、周囲の人々から積極的にフィードバックをもらう機会を、意識的に、そして習慣的に作ることです。
例えば、作成した資料を誰かに説明した後や、会議で発言した後などに、「今お話しした中で、分かりにくいと感じた点や、専門的すぎると感じた言葉はありませんでしたか」と、同僚や部下に尋ねてみるのです。これを一度だけでなく、何度も繰り返して習慣にしていきます。
そうしたフィードバックを通じて、「自分にとっては常識だと思っていたこの言葉は、皆が知っているわけではなかったのか」あるいは「この情報は、自分だけが知っていて、チームには共有されていなかったのだな」といった、自分と他者との認識のギャップに気づくことができます。このように、他者の視点という鏡を通して自分を映し出す機会を自ら設けることが、無意識の思い込みから抜け出し、「知識の呪い」を乗り越えていくための方法になっていくはずです。
脚注
[1] Hinds, P. J. (1999). The curse of expertise: The effects of expertise and debiasing methods on prediction of novice performance. Journal of Experimental Psychology: Applied, 5(2), 205-221.
[2] Wieman, C. E. (2007). The “curse of knowledge,” or why intuition about teaching often fails. APS News, 16(10), 5.
[3] Birch, S. A., and Bloom, P. (2007). The curse of knowledge in reasoning about false beliefs. Psychological Science, 18(5), 382-386.
[4] Xiong, C., Van Weelden, L., and Franconeri, S. (2019). The curse of knowledge in visual data communication. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 26(10), 3051-3062.
[5] Danz, D. (2014). The curse of knowledge increases self-selection into competition: Experimental evidence (No. SP II 2014-207). WZB Discussion Paper.
[6] Choudhury, M. (2018). Your expert knowledge may put them off: Curse of knowledge among anesthesiologists. Anaesthesia, Pain & Intensive Care, 145-147.
[7] Pierrot, T. (2019). Negotiation under the curse of knowledge (No. SP II 2019-211r). WZB Discussion Paper.
[8] Banerjee, S., Davis, J., and Gondhi, N. (2020). The man(ager) who knew too much. SSRN Electronic Journal.
[9] Birch, S. A., Brosseau-Liard, P. E., Haddock, T., and Ghrear, S. E. (2017). A ‘curse of knowledge’in the absence of knowledge? People misattribute fluency when judging how common knowledge is among their peers. Cognition, 166, 447-458.
[10] Ghrear, S., Fung, K., Haddock, T., and Birch, S. A. (2021). Only familiar information is a “curse”: Children’s ability to predict what their peers know. Child Development, 92(1), 54-75.
[11] Damen, D., van der Wijst, P., van Amelsvoort, M., and Krahmer, E. (2018). The curse of knowing: The influence of explicit perspective-awareness instructions on perceivers’ perspective-taking. In Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Cognitive Science Society (pp. 235-240).
[12] Kennedy, J. (1995). Debiasing the curse of knowledge in audit judgment. Accounting Review, 249-273.
[13] Banerjee, S., Davis, J., and Gondhi, N. (2023). Information Provision and the Curse of Knowledge. https://snehalbanerjee.github.io/wp/BDGcursed.pdf
[14] Hannon, M. (2020). Intellectual humility and the curse of knowledge. In A. Tanesini and M. P. Lynch (Eds.), Polarisation, arrogance, and dogmatism: Philosophical perspectives (pp. 104-119). Routledge.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。