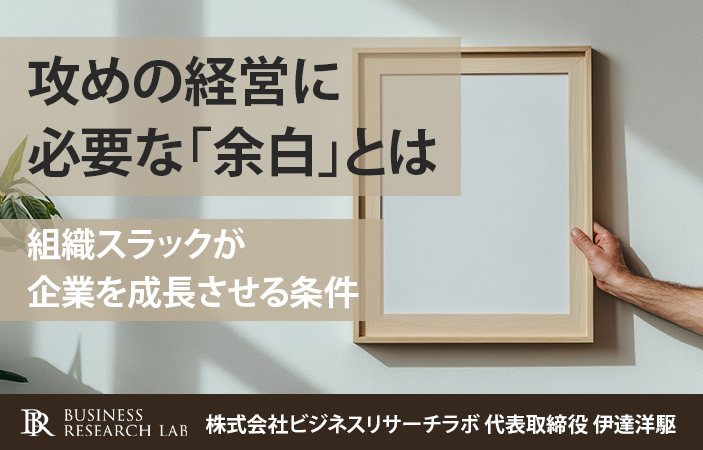2025年7月2日
攻めの経営に必要な「余白」とは:組織スラックが企業を成長させる条件
企業経営において「余裕」はどのような価値を持つのでしょうか。必要以上の資源を持つことは無駄なのか、それとも組織の成長や革新のために不可欠なのか。組織が持つ余剰資源を専門的には「組織スラック」と呼びます。効率性を追求する観点からすると余剰資源は削減すべき対象と見なされますが、学術研究では組織スラックが企業の成長や研究開発、環境適応に寄与する可能性が指摘されています。
しかし、どのような状況でスラックが有効に機能するのかについては、少しばかり複雑な条件があります。余剰資源の種類は何か、企業はどのような戦略を取っているのか、所有構造やガバナンスはどうなっているのか。これらの要素によって、組織スラックの効果は変わってきます。
本コラムでは、組織スラックが有効となる条件について深掘りしていきます。資源の種類による効果の違い、CEO兼任制度との関係性、そして所有構造による研究開発への影響と、三つの異なる視点から組織スラックの機能を探ります。これらを通じて、単純に「スラックは良い」「スラックは悪い」という二項対立を超えた、より精緻な理解を得ることができるでしょう。
この知見は、経営者やマネージャーはもちろん、組織運営に関わるすべての人々にとって、限りある資源をどう配分し活用するかという課題への新たな視点を提供するはずです。
組織スラックは資源の粘着性で成長効果が逆転する
企業が成長戦略を実行する際、余剰資源(組織スラック)があれば常に有利なのでしょうか。直感的には「資源が多いほど良い」と考えられなくもないのですが、実際はそう単純ではありません。資源の種類や企業の成長戦略によって、スラックの効果は異なることが明らかになっています。
組織スラックの中でも区別すべき点として「資源の粘着性」があります。粘着性とは、資源がどれだけ柔軟に別の用途に転用できるかという特性です。例えば、現金などの資金スラックは柔軟性が高く、さまざまな用途にすぐに転用できるため「低粘着性」と言えます。一方、特定の技能を持った人材や専用設備などは容易に別の用途に振り向けることができないため「高粘着性」の資源です。
この資源の粘着性が企業成長にどう関わるかについて、アメリカの製造業112社を対象にした調査があります[1]。この調査では、企業の成長戦略を「市場拡大」と「製品拡大」に分類し、それぞれの戦略において異なる種類のスラックがどのように作用するかを分析しました。
「市場拡大」は既存製品を新しい市場や顧客層に広げる戦略で、既存のルーチンを拡張するため比較的予測可能です。一方、「製品拡大」は新製品の開発・導入を行う戦略で、組織内の新たなルーチン形成が必要となり、不確実性が高くなります。
調査結果から見えてきたのは、資金スラック(低粘着性)と人的資源スラック(高粘着性)が、異なる成長戦略に対して正反対の効果を持つという点です。
市場拡大戦略を取る企業において、人的資源スラックは成長率に対してプラスの効果をもたらしました。これは既存のルーチンを拡張する市場拡大においては、人的資源の専門性や既存業務に関する知識が活きるためと考えられます。人員に余裕があれば、新市場への対応も円滑に進められるのです。
一方で製品拡大戦略を取る企業では、人的資源スラックはむしろ成長率を下げる方向に作用しました。この予想外の結果には、人的資源の粘着性が関係しています。新製品開発においては既存の習慣や思考パターンを変える必要がありますが、特定の仕事に慣れた人材は変化への抵抗感を持ちやすく、新しいルーチンの形成を妨げる可能性があります。
対照的に、資金スラックは製品拡大を行う企業においてこそ成長率を高める効果を示しました。資金の柔軟性が高いため、不確実性の高い新製品開発においてリスクに対応しやすいからです。予期せぬ問題が生じたときに素早く資金を投入できる余裕があることは、新製品開発には価値があります。
この研究は、「どのような種類のスラックが、どのような成長戦略に適しているか」という視点を与えてくれます。市場拡大を目指すなら人的資源に余裕を持たせることが有効である一方、製品拡大を目指すなら資金的な余裕を優先すべきかもしれません。
経営資源の配分を考える際には、資源の総量だけでなく、その特性と企業の戦略方針との相性を十分に検討することが求められます。この視点があれば、組織スラックを「非効率」とみなすのではなく、戦略的に活用すべき要素として捉えることができるでしょう。
組織スラックはCEO兼任で民間に有益、国有に有害
組織スラックの効果を左右する条件として、企業のガバナンス構造も見逃せません。「CEOデュアリティ」と呼ばれる、CEOが取締役会議長を兼任する体制が、スラックの活用にどう影響するかについて、中国企業を対象にした研究から知見が得られています。
中国企業300社(国有企業163社、民間企業137社)を対象とした調査では、組織スラックとCEOデュアリティの関係性が、企業の所有形態(国有か民間か)によって異なる結果をもたらすことが分かりました[2]。
基本的な事実として、組織スラック自体は企業業績と正の関係があることが確認されています。とりわけ「未吸収スラック」と呼ばれる、現金や融資枠など柔軟に利用可能な資源は、環境変動に素早く対応できるため、企業業績にプラスの効果をもたらします。
しかし、このスラックの活用効果はCEOデュアリティとの組み合わせで変わります。民間企業では、CEOデュアリティがあるとスラックの業績向上効果がさらに強まりました。これに対し国有企業では、CEOデュアリティがあるとスラックの業績向上効果が弱まるという正反対の結果が見られました。
なぜこのような違いが生じるのでしょうか。その理由を理解するためには、国有企業と民間企業におけるCEOの立場や動機の違いを考える必要があります。
民間企業では、CEOが所有者自身であることや、所有者と近い関係にあることが多く、企業の長期的利益と自身の利益が一致します。このような状況では、CEOに権限が集中する「デュアリティ」があることで、迅速な意思決定が可能になり、スラック資源を効果的に活用できるメリットが生まれます。環境変化に対して素早くスラック資源を投入したり、新たなチャンスに迅速に対応したりできます。
一方、国有企業では「エージェンシー問題」が深刻になります。エージェンシー問題とは、所有者(この場合は国家)と経営者(CEO)の利益が一致せず、経営者が自己利益を優先してしまう問題です。国有企業のCEOは個人的な成功や短期的な成果、あるいは政治的つながりの強化に関心を持つ可能性もあります。
このような状況でCEOデュアリティがあると、権力が集中することでチェック機能が弱まり、CEOが自己利益のためにスラック資源を用いるかもしれません。例えば、本来は研究開発や設備投資に使うべきスラック資源を、個人的な威信を高めるための無駄な投資や、政治的なつながりを強化するための支出に振り向けてしまうかもしれません。
この研究から導かれるのは、組織スラックの効果はガバナンス構造と関連しているということです。同じ「CEOデュアリティ」であっても、企業の所有形態や背景にある動機づけの違いによって、異なる結果をもたらす可能性があります。スラックというリソースは、それ自体が良いか悪いかではなく、どのような統治体制のもとで、誰がどのような動機で活用するかによって、その効果が変わってくるのです。
組織スラックの研究開発促進効果は所有構造で変わる
企業の革新性を左右する研究開発(R&D)投資。これに組織スラック、特に財務的スラック(自由に使える余裕資金)がどのような影響を与えるのかについて、韓国の製造業企業を対象にした研究を紹介しましょう[3]。この研究では、企業の所有構造がスラックとR&D投資の関係をどう変化させるかに焦点を当てています。
基本的な関係として、財務的スラックとR&D投資の間には「逆U字型」の関係があることが確認されました。これは、スラックが少ない状態から増えていくと、最初はR&D投資が増加していきますが、ある程度以上のスラックを持つと逆にR&D投資が減少し始めるという関係です。
スラックが少なすぎると、不確実性の高いR&Dに資金を回す余裕がなく、日々の業務維持に精一杯になります。一方、スラックが多すぎると組織が怠慢になり、緊張感が薄れてイノベーションへの切迫感が減少するためです。
この基本的な関係性は企業の所有構造によってどのように変化するのでしょうか。韓国企業には主に「家族所有」「系列企業所有」「国内機関投資家所有」「外国投資家所有」という異なる所有形態があります。研究では、これらの所有形態がスラックとR&D投資の関係に及ぼす影響を分析しました。
顕著な結果として、「家族所有」は財務的スラックがR&D投資を促進する効果を強めることが分かりました。家族所有の割合が高い企業では、スラックがあるとR&D投資が増加する傾向がより強く見られたのです。
この理由として考えられるのは、家族所有者は企業を「世代を超えた遺産」と捉え、長期的な視点を持っていることです。短期的な利益よりも企業の長期的な成長や存続を優先するため、余裕資金があれば将来に向けた研究開発に投資します。また、家族所有者は企業に対する強い心理的なつながりを持っているため、リスクのある投資でも企業の将来のために積極的に行う動機があります。
対照的に、「国内機関投資家所有」と「外国投資家所有」は、財務的スラックがR&D投資を促進する効果を弱めることが分かりました。これらの投資家の所有割合が高いほど、スラックがあってもR&D投資が増えにくくなったのです。
この現象は、機関投資家や外国投資家が短期的なリターンを重視する傾向から説明できます。これらの投資家は四半期ごとの業績や株価の上昇を求め、長期的なリターンが不確実なR&D投資より、確実な短期的利益や配当を好みます。そのため、たとえ財務的スラックがあっても、それを研究開発に投じるのではなく、配当や自社株買いなど、より直接的に短期的な株主価値を高める使い方を選好するかもしれません。
「系列企業所有」については当初の予想と異なり、スラックとR&D投資の関係に有意な影響を与えない結果になりました。韓国の系列企業間では資金の流動性があり、グループ内で資金を融通し合うことが可能なため、個々の企業のスラック水準がR&D投資に直接影響しにくい可能性があります。
この研究からは、組織スラックの効果が所有構造という「見えない条件」によって変わることが分かります。同じ量の財務的スラックを持っていても、誰が企業を所有しているかによって、そのスラックがイノベーションにつながるかどうかが変わってきます。
短期的な株主価値最大化が唱えられる現代において、家族所有企業がスラックを長期的なR&D投資に活用する傾向は注目に値します。所有構造の違いが単なる形式的な違いではなく、企業の意思決定の時間軸やリスク選好に実質的な影響を与えることを意味しています。
企業がイノベーションを通じて成長するためには、適切な量の組織スラックを維持することに加えて、長期的な視点を持った所有構造や意思決定プロセスを構築することが大切であることを、この研究は示唆しています。
組織スラックの効果を左右するもの
組織スラックは、適切な条件下で企業に価値をもたらす資源であることが明らかになりました。本コラムで紹介した研究から、組織スラックの効果に影響を与える主な条件として、資源の粘着性、ガバナンス構造、そして所有構造の3つが浮かび上がりました。
資源の粘着性という観点では、企業の成長戦略に合わせた資源の選択が鍵となります。市場拡大を目指す場合は人的資源スラックが有効である一方、製品拡大においては資金的スラックがプラスに働くことを考慮して資源配分を決定することが望ましいでしょう。
ガバナンス構造の面では、CEOデュアリティ(CEO兼任制度)の影響が所有形態によって逆転することは、経営体制を構築する上で重要です。民間企業では意思決定の迅速化をもたらすCEOデュアリティがスラックの活用を促進する一方、国有企業では権力の集中がスラック資源の非効率的利用につながる危険性があります。企業の所有背景に合わせたガバナンス設計が求められるでしょう。
所有構造については、長期的視点を持つ家族所有がスラックをR&D投資に振り向ける効果がある一方、短期的リターンを重視する機関投資家や外国投資家はそうした投資を抑制することが分かりました。イノベーションを通じた成長を目指す企業は、株主構成と時間軸の関係性を認識することが大切です。
これらの知見を総合すると、「どのような種類のスラックを」「どのようなガバナンス・所有構造のもとで」「どのような戦略目的に」活用するかによって、その効果が変わることが分かります。
脚注
[1] Mishina, Y., Pollock, T. G., and Porac, J. F. (2004). Are more resources always better for growth? Resource stickiness in market and product expansion. Strategic Management Journal, 25(12), 1179-1197.
[2] Peng, M. W., Li, Y., Xie, E., and Su, Z. (2010). CEO duality, organizational slack, and firm performance in China. Asia Pacific Journal of Management, 27(4), 611-624.
[3] Kim, H., Kim, H., and Lee, P. M. (2008). Ownership structure and the relationship between financial slack and R&D investments: Evidence from Korean firms. Organization Science, 19(3), 404-418.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。