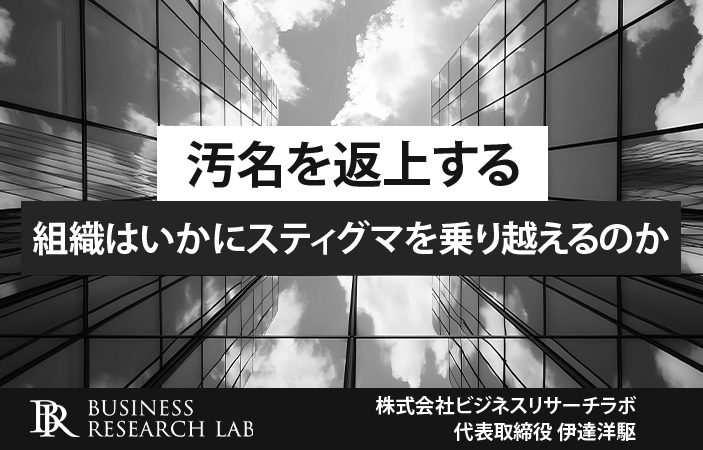2025年7月1日
汚名を返上する:組織はいかにスティグマを乗り越えるのか
私たちの社会には、ときに「スティグマ」と呼ばれる、ある種の烙印や負の評価がつきまとう現象があります。多くの組織や職業が社会的な偏見や否定的評価に直面しています。組織的スティグマは単純なイメージの問題ではなく、資源獲得の困難さ、採用の壁、社会的支持の欠如など、組織の存続にかかわる課題をもたらします。しかし、スティグマを抱える組織の中には、その烙印を克服し、社会的正当性を獲得することに成功した例も存在します。
組織はスティグマとどう向き合い、どのように克服していくのでしょうか。本コラムでは、組織的スティグマをめぐる多様な研究を紹介しながら、スティグマに直面する組織の実態と、その対応戦略について探っていきます。ヴィクトリア朝時代の旅行代理店から現代の医療用大麻産業まで、異なる時代・業界でのスティグマへの対応を見ていくことで、組織が社会からの負の評価を乗り越え、新たなアイデンティティを構築していくダイナミックな過程が見えてくるでしょう。
さらに、いわゆる「ダーティワーク」と呼ばれる社会的に忌避される職業に携わる人々が、どのようにして職業的な誇りを保ち、肯定的なアイデンティティを構築するのかについても考察していきます。組織的スティグマの理解を通じて、私たちの社会における評価の仕組みや、その中での組織の戦略的行動について新たな視点を得ることができるはずです。
スティグマは新たな制度構築で正当性に変わる
社会からスティグマを受けた組織が、どのようにしてそれを克服し正当性を獲得するのか。この問いに答えるため、ヴィクトリア朝時代の英国における旅行業界の草分け的存在であるトーマス・クック旅行代理店の歴史的事例を見ていきましょう[1]。
19世紀の英国社会では、旅行業は「道徳的に疑わしい」とされる産業でした。特に労働者階級が余暇を楽しむことは非道徳的とみなされる時代背景があり、そうした人々の旅行を仲介するトーマス・クック社は社会的な批判に直面していました。しかし同社は約半世紀にわたる活動を通じて、この社会的スティグマを克服し、最終的には広く尊敬される事業へと変貌を遂げました。
この変化は一朝一夕に起こったわけではありません。第一段階として、クック社はスティグマの否定から始めました。同社は旅行が労働者の道徳向上や教育、健康促進に役立つと強調し、娯楽ではなく「節度ある行動」や「宗教的巡礼」として旅行を位置づけました。この戦略は直接的にスティグマに対抗するものでしたが、それだけでは社会的正当性を得るには不十分でした。
そこで第二段階として、クック社は社会的に望ましいアイデンティティの構築に取り組みます。旅行を「社会改革」や「教育活動」と結びつけることで、自社のイメージ向上を図りました。当時英国で盛んだった禁酒運動と関係を深め、旅行者を節度ある模範的市民として描写し、組織自体も道徳的で責任ある団体であるという印象づけを行いました。この過程で、旅行という活動自体の意味が再定義されていったことは興味深いことです。
最も決定的だったのは第三段階です。クック社は「観光」という新たな概念を広め、それを制度化することに成功しました。鉄道会社、宗教団体、教育団体など多くの社会的アクターと連携し、旅行が社会的に有益であることを制度レベルで認めさせたのです。制度化とは、ある活動やアイデアが社会的に受け入れられ、当然視されるようになる過程です。クック社は自社のイメージを改善するだけでなく、旅行業界全体の社会的地位を向上させる制度改革を成し遂げました。
この歴史的事例から学べる教訓は、組織的スティグマの克服には段階的なアプローチが必要だということです。スティグマを否定する段階から始まり、望ましいアイデンティティの構築を経て、最終的には新たな制度ロジックを社会に埋め込むという過程が見られます。クック社は既存の制度に適応するのではなく、自ら新たな制度的カテゴリーを創出し、社会に浸透させることで正当性を獲得しています。
今日でも新興産業や社会的批判に直面する業界は少なくありません。そうした組織にとって、トーマス・クック社の事例は歴史的エピソードではなく、スティグマという社会的課題への対応の青写真を提供するものといえるでしょう。スティグマに対抗するだけでなく、新たな社会的価値や制度的枠組みを創造することで、組織は社会的評価を根本から変革できる可能性があるのです。
医療用大麻企業はスティグマを医療化で軽減する
現代において、組織的スティグマと向き合っている代表的な例として医療用大麻産業があります。大麻は長い間、違法薬物として強いスティグマを受けてきました。しかし近年、医療目的での大麻使用が一部の地域で合法化されたことで、医療用大麻を取り扱う企業が登場しています。こうした企業は、大麻にまつわる社会的スティグマをいかにして軽減し、医療分野の正当なプレイヤーとして認められるよう努力しているのでしょうか[2]。
医療用大麻企業が直面するスティグマは非常に複雑です。一方では、医療目的での使用が法的に認められつつありますが、他方では「大麻」という言葉自体が持つ娯楽目的の使用や違法性のイメージが依然として強く残っています。このような状況下で、医療用大麻企業は社会的正当性を獲得するために様々な戦略を展開しています。
顕著な戦略は「医療化」です。医療用大麻企業は意図的に「医療」というフレームを前面に押し出し、大麻の医学的効能や科学的根拠に焦点を当てています。例えば、医学的用語を積極的に採用し、「大麻」ではなく「医薬品」や「治療法」といった言葉を用いることで、従来の大麻のイメージから距離を置こうとしています。多くの企業のウェブサイトやパンフレットでは、白衣を着た研究者や医療施設の画像を用い、医療という文脈での正当性を視覚的にも強調しています。
「正当性のナラティブ」の構築も一つの戦略です。医療用大麻の利用によって救われる患者のストーリーを伝えることで、社会的理解と共感を得ようとするアプローチです。例えば、従来の治療法では症状が改善しなかった重症患者が医療用大麻によって劇的に回復したという事例を紹介することで、医療用大麻の社会的価値を強調します。こうしたナラティブは、抽象的な議論よりも人々の心に訴えかける力を持ち、スティグマ軽減に有効とされています。
第三の戦略は「正当性の波及」です。既に社会的に認められている医療分野や研究機関との協力関係を構築し、それらの持つ正当性を自分たちの産業にも広げようとする試みです。具体的には、大学の研究機関との共同研究プロジェクトの立ち上げや、主流の医薬品企業とのパートナーシップ、医学会での発表などが含まれます。既存の権威ある機関との関係構築は、医療用大麻そのものの正当性を高める効果があります。
これらの戦略が興味深いのは、否定的イメージを薄めようとするのではなく、積極的に新たなカテゴリーを創造しようとしている点です。医療用大麻企業は「違法薬物」というカテゴリーから自らを切り離し、「医療」というカテゴリーに再配置することで、社会的受容を促進しようとしています。
医療用大麻産業の事例は、スティグマを持つ新興産業が社会的正当性を獲得するための道筋を示しています。特に既存の強力なカテゴリー(この場合は「医療」)と自らを結びつけることで、新たな正当性を構築するアプローチは、他の社会的に問題視される産業にも応用可能な教訓といえるでしょう。
ダーティワーカーはスティグマを再解釈し誇りを保つ
組織全体や産業がスティグマに向き合う方法を見てきましたが、実際にその中で働く個人はどのようにスティグマと向き合っているのでしょうか。特に「ダーティワーク」と呼ばれる、社会的に望ましくないとされる職業に従事する人々に焦点を当てて考えてみましょう[3]。
「ダーティワーク」とは社会的に敬遠されがちな職業を指します。これらの職業は、肉体的な汚れ(実際に汚物などに触れる仕事)、社会的な汚れ(社会的評価が低い仕事)、道徳的な汚れ(倫理的に疑問視される仕事)という三つの次元でスティグマを受けることがあります。
このようなダーティワークに従事する人々は、社会からの否定的評価によって自尊心が傷つけられる危険性があります。しかし実際には、多くのダーティワーカーが自分の仕事に誇りを持ち、肯定的なアイデンティティを維持しています。この一見矛盾する現象はどのように説明できるのでしょうか。
ダーティワーカーたちが用いる主要な戦略の一つが「意味の再構成」です。これは仕事の意味を再解釈し、その価値を肯定的に捉え直す作業です。意味の再構成は単なる言い訳ではなく、実際に仕事の社会的価値や専門性を強調することで、外部からの否定的評価に対抗する力強い防衛機制となります。
もう一つの戦略は「社会的比較」です。ダーティワーカーは自分たちよりも「汚い」と思われる仕事と比較したり(下方比較)、同じ職業の中でも特に優れた部分に焦点を当てたりすることで、自己評価を高めます。
第三の戦略は「仕事に対する認識の操作」です。これは仕事の否定的側面を逆に誇りや忠誠心の対象として捉え直す方法です。
さらに、これらの個人的戦略に加え、職業集団としての結束強化も重要な役割を果たします。ダーティワーカーたちは「我々対彼ら」という枠組みで職業内の連帯感を高め、外部からの批判に対する防衛壁を築きます。職業特有の儀式、伝統、専門用語、冗談などは、こうした集団的アイデンティティを強化する役割を果たしています。
これらの戦略は、職業の性質や直面するスティグマの種類によって異なる形で現れます。例えば、肉体的な汚れを伴う職業では、その専門的技術や社会的必要性を強調する傾向があります。一方、道徳的な汚れを伴う職業では、顧客支援や経済的自立などの側面に焦点を当てることがより多いようです。
ダーティワーカーの研究から見えてくるのは、スティグマを受ける人々が決して受動的な犠牲者ではなく、積極的に意味づけを行い、肯定的なアイデンティティを構築する能動的な存在だということです。社会からの否定的評価をそのまま受け入れるのではなく、それを再解釈し、時には逆手に取ることで、職業的な誇りを維持しているのです。
ダーティワーカーはスティグマを肯定的に捉え直す
ダーティワークに従事する労働者が自らのアイデンティティを守るための様々な戦略を見てきました。しかし、すべてのダーティワーカーが同じように反応するわけではありません。スティグマの強さや広がりによって、アイデンティティ防衛の方法には違いがあります。この点について掘り下げていきましょう[4]。
ダーティワークのスティグマは、大きく二つの次元で捉えることができます。一つは「幅」で、これは職業全体でどの程度スティグマが広がっているかを表します。もう一つは「深さ」で、これはスティグマがどれほど強烈かを表します。この二つの次元を組み合わせることで、ダーティワークは四つのカテゴリーに分類できます。
第一のカテゴリーは「広範囲かつ強烈なスティグマ」を持つ職業です。これらの職業では、仕事全体が強いスティグマにさらされるため、労働者は特に強い防衛戦略を必要とします。彼らは職業的イデオロギーによる正当化(「この仕事は社会に不可欠だ」)、批判者への反発、職業内での連帯感の強化などの戦略を取ります。
第二のカテゴリーは「限定的だが強烈なスティグマ」を持つ職業です。これらの職業では、一部の業務だけが強いスティグマを持つため、労働者はそれを切り離して心理的に距離を置く傾向があります。
第三のカテゴリーは「広範囲だが軽度のスティグマ」を持つ職業です。全般的に軽いスティグマがあるものの深刻ではないため、労働者の防衛意識は比較的弱いですが、それでも一定の職業的連帯感が生まれます。
第四のカテゴリーは「限定的で軽度のスティグマ」を持つ職業です。ほとんど防衛意識がなく、発生した軽いスティグマを個人的に処理する程度にとどまります。
この分類から見えてくるのは、スティグマへの対応が職業によって異なるという点です。スティグマが強く広範囲にわたる職業ほど、労働者は集団としての防衛戦略を発達させる傾向があります。一方、スティグマが限定的で軽度な場合は、個人レベルの対応で済むことが多いのです。
ここで興味深いのは、労働者のアイデンティティ形成には二つの相反する心理的メカニズムが働いていることです。一方では、「社会的アイデンティティ理論」が示すように、人は自己評価を高めるために自分の所属集団を肯定的に評価しようとする傾向があります。他方では、「システム正当化理論」が示すように、低い地位の集団は時に自分たちの低い評価を内面化し、現状を正当なものとして受け入れてしまうことがあります。
ダーティワーカーの場合、この二つの相反する傾向がどのようにバランスを取るかは、職業のスティグマの性質によって異なります。強いスティグマに直面する労働者ほど、職業的アイデンティティを防衛するために積極的な意味の再構成や集団的防衛戦略を展開します。これは社会的アイデンティティ理論が予測する通りです。しかし同時に、特定の側面については社会の評価を内面化し、それを回避したり距離を置いたりすることもあります。これはシステム正当化理論の視点に合致します。
組織の役割もこうした動態に影響を与えます。ダーティワークが組織の中心業務である場合、職業スティグマは組織全体にも波及し、組織レベルでも同様の防衛戦略が採られる可能性が高まります。
脚注
[1] Hampel, C. E., and Tracey, P. (2017). How organizations move from stigma to legitimacy: The case of Cook’s Travel Agency in Victorian Britain. Academy of Management Journal, 60(6), 2175-2207.
[2] Lashley, K., and Pollock, T. G. (2020). Waiting to inhale: Reducing stigma in the medical cannabis industry. Administrative Science Quarterly, 65(2), 434-482.
[3] Ashforth, B. E., and Kreiner, G. E. (1999). “How can you do it?”: Dirty work and the challenge of constructing a positive identity. Academy of Management Review, 24(3), 413-434.
[4] Kreiner, G. E., Ashforth, B. E., and Sluss, D. M. (2006). Identity dynamics in occupational dirty work: Integrating social identity and system justification perspectives. Organization Science, 17(5), 619-636.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。