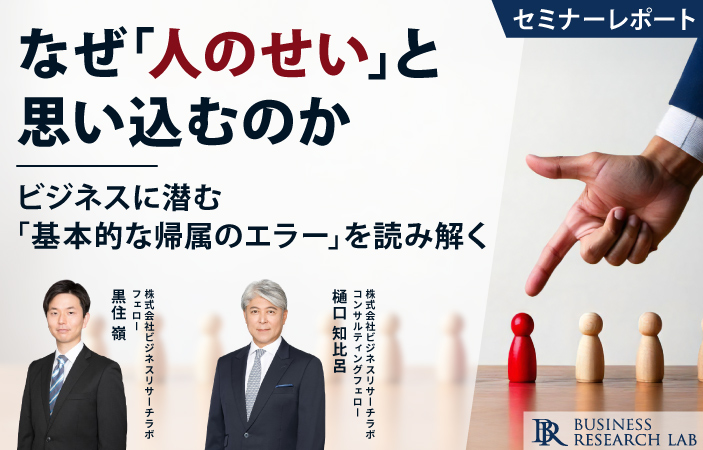2025年6月30日
なぜ「人のせい」と思い込むのか :ビジネスに潜む「基本的な帰属のエラー」を読み解く(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年5月にセミナー「なぜ『人のせい』と思い込むのか :ビジネスに潜む『基本的な帰属のエラー』を読み解く」を開催しました。
「部下のやる気がない」「あの人はほとんど協力してくれない」など、職場にいるメンバーに対して、「その人自身に原因がある」と考えた経験は誰にでもあるでしょう。そうした推論には、「基本的な帰属のエラー(fundamental attribution error)」という無意識のバイアスが潜んでいるかもしれません。
本セミナーでは、ビジネスの現場でも起こりがちな「人のせい」への思い込みのメカニズムを、心理学とマネジメントの視点から解説しました。
基本的な帰属のエラーとは何か
日常的な例と研究の実証例
黒住:
それでは最初に、「基本的な帰属のエラーとは何か」について見ていきます。実は、私たちの日常生活の中でもよく見られる現象ですので、身近な例からご紹介します。
例えば、「他県ナンバー狩り」という現象を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。これは、新型コロナウイルスのパンデミック中、外出自粛の要請が出されていた時期に発生した現象です。
たとえば観光地で、他県のナンバーを付けた車が来ているのを見て、地元の人が「この人たちは、わざわざ他県から遊びに来ている非常識な人だ」と判断し、車に攻撃的な行動を取るということが起きました。
しかし実際には、その車の持ち主が既にその地域に住んでいて、何らかの事情でナンバーを変更していないだけかもしれませんし、仕事の都合でその土地を訪れているだけかもしれません。攻撃的な行動をとる場合、そうしたパターンを見落としている可能性が高いといえるでしょう。
このように、個人の性格や特性などの“内的な要因”を過大評価し、状況や環境といった“外的な要因”を過小評価する心理的傾向を「基本的な帰属のエラー」と呼びます[1]。
たとえば、ある人が遅刻したとき、「この人は時間にルーズな性格なんだ」と思ってしまいがちです。一方で、実は交通機関の遅れや家庭の事情といった、外的な要因があるかもしれません。また、他人の行動についてこのような判断をするとき、私たちは特に状況の影響を見落としがちだと指摘されています。
この「基本的な帰属のエラー」は、長年にわたり多くの実証研究によって確かめられてきました。古典的な研究例ですが、研究史に大きく影響を与えた2つの研究を紹介します[2]。
まず、「強制された発言でもその人の本音だと誤解する」という実験です。この実験では、ある参加者に政治的な主張をテーマにした論文を書いてもらいます。内容は「カストロ(キューバの指導者)支持」といった、欧米の参加者は驚く内容です。そして、別の参加者にその論文を読ませ、「この筆者は、どんな考えを持っていると思いますか?」と尋ねます。
すると、多くの人が「この筆者はカストロを本当に支持しているのだろう」と考えます。驚くべきことに、「この論文は、決められた主張に沿って書かされたものだ」と知らされた参加者でさえ、「それでも筆者の本音だろう」と判断してしまう傾向があることがわかりました。
もう一つの例が、ミルグラムの「服従実験」を題材にした研究です。この実験では、上司役の人から「電気ショックを与えよ」と強く命じられた参加者が、命令に従って電気ショックを加えるというシーンが用意されました。
この様子を観察した人たちは、「命令に従うのは、この人は冷酷な性格だからそんなことができるのだ」と判断しました。ここでも、外的な圧力があるにもかかわらず、「性格が原因だ」と考えてしまう傾向が見られます。
さらに、職場を対象にした研究もあります[3]。産業革命時に、「セオリーX」と呼ばれるマネジメント理論が提唱されました。この理論は、「人間は本質的に働くことが嫌いで、管理や強制が必要だ」という考え方に基づいています。
しかし、実際には劣悪な労働環境の影響も大きく、単調な仕事、長時間労働、危険な作業などが原因で意欲が下がっていたことが確認されています。にもかかわらず、「従業員は怠け者だから働かないのだ」と判断していることは、典型的な帰属のエラーといえるでしょう。
帰属のエラーが起きるメカニズム
続けて、この基本的な帰属のエラーがなぜ起きるのか、そのメカニズムについて解説してまいります。大きく分けて、「原因帰属」と「特性推論」という二つの側面が指摘されています[4]。
一つ目の「原因帰属」とは、ある人が起こした行動などの出来事に対して、「なぜそれが起きたのか」という原因を考える思考過程です。人の行動の原因を考えるとき、「周囲の人や環境への対処」といった外的要因や「その人の性格や考え」といった内的要因を想定する(帰属する)ことができます。この過程で、内的要因が原因だと考えすぎる傾向として、基本的な帰属のエラーが起きるというのが1つ目の解釈です。
この点は先ほどの説明でも触れましたが、もう一つの側面が「特性推論」と呼ばれるものです。「特性推論」とは、人の行動からその人の性格や特性を推測するというものです。先ほどの原因帰属が「なぜ行動が起きたか」を考える過程でしたが、こちらは「行動からその人がどういう人かを推測する」と考える過程で、自動的に起こるメカニズムであると指摘されています。
この「特性推論」について、もう少し詳しく掘り下げてご紹介します。この推論は、大きく分けて次の三つのプロセスで進むと考えられています。
まず一つ目が「カテゴリー化」です。これは、目にした行動がどういう意味を持つのかを判断する、いわば意味づけのステップです。例えば、年配の方が重そうな荷物を持っている場面で、それを代わりに持ってあげる人がいたとします。この様子を見た人は、「親切な行動」と判断するといった具合です。
そのうえで、その行動を通して「この人は親切な人」だと感じるのが二段階目の「特性記述」です。行動の意味と一致するような人間の特性を、無意識のうちに推測するのです。
そして三段階目が「修正」です。これは、その行動が本当にその人の性格によるものなのかを、意識的に考え直すステップです。先ほど例では、「親切だから持った」という以外にも、実はおばあさんから「持ってほしい」と頼まれた結果かもしれません。そうした特性以外の可能性も考慮するという過程によって、私たちは単純な性格判断を避けることができます。
ですが、この修正をきちんと行えるかどうかが重要なポイントであり、修正プロセスが不十分であることによって基本的な帰属のエラーが起きていると解釈されます。つまり、外的要因の影響を加味せずに、「行動と一致する性格の持ち主だ」と早合点するということです。
こうした「行動から性格を推測する」メカニズムは、実は古くから指摘され、近年でもその再現性が高いことがわかっています[5]。複数の研究結果をまとめるメタ分析という手法をとった研究によって、この特性推論は文化を超えて再現されると結論づけられています。
文化的背景と日本における特徴
最後に、基本的な帰属のエラーのメカニズムに、日本の職場に特有の文化的な要因が関係しているのではないか、という点を掘り下げてみます。先ほどの研究では、帰属エラーが文化差を超えて共通に見られる現象とされる一方で、状況の受け取り方やその背景にある価値観には、文化ごとの違いが生じる可能性も指摘されていました。
そうした点を考慮して提案するのが、「我慢」が美徳とされている日本の文化的特徴です。実は海外でも「GAMAN」と表現され、その特徴が注目されています。
日本では、我慢は単なる忍耐ではなく、勤勉や努力といった価値と結びついて評価される傾向があります[6]。また、将来の利益のために今の困難を受け入れるという「将来志向型」の対応であり、今はつらくても将来の成功を信じて耐える、という姿勢です。
この風潮は、職場の中にも表れると考えられます。日本の職場では、チームの流動性が低く、関係が長く続く傾向があります。そのため、仕事で助けを求めて相手の迷惑にならないように、「自分で何とかしよう」と個人での対処や努力を重視する傾向が強まると予想できます。このことから、日本の職場では個人への意識が高まりやすく、基本的な帰属のエラーが「起こりやすい」かもしれない、という仮説が提案できます。
また、我慢と基本的な帰属エラーの関係については、パフォーマンス向上につながっている可能性も考えられます。つまり、職場での行動における個人の要因が重視されることで、「自分でどうにかしよう」と努力する姿勢につながり、実際の成果にも結びつく可能性があります。
実際に、こうした我慢や努力の価値は、教育の中でも長く評価されてきました。たとえば、幼児教育の中でも「我慢できること」は他者理解などにもつながる成長の大切な過程と評価され、教員はその発達を見守ることが重視されています[7]。
また、高等教育における部活動や体育会と呼ばれる活動のなかでも、我慢や忍耐は高く評価されます[8]。つらい練習を続ける、怪我をしていても参加するなどの行動が、「努力できる人」「頑張り屋」として認識され、周囲からの信頼やチームへの所属意識にもつながっていきます[9]。
とはいえ、日本では我慢が文化的に内面化され、教育の中でも良いことと評価されることから、職場での行動評価にも影響を与えると予想できます。努力を促進してパフォーマンスを高める可能性はあるものの、問題行動が起きた際に「あの人のせいだ」と、性格のせいにしすぎてしまうリスクでもあります。そのため、問題の原因分析においては注意が必要といえるでしょう。
ビジネスシーンを想定した対応策と実践的な取り組み提案
基本的な帰属のエラーが発生するビジネスシーン
樋口:
ここからは、ビジネスの現場で起こりやすい例を交えながら基本的な帰属のエラーが発生するビジネスシーンや対策について提案していきます。まず、ビジネスの現場で起こりやすい例お話します。
営業の現場のビジネスシーンを想像してみてください。ある営業担当者の成績がいまいちだったとしましょう。すると、つい上司は「彼は営業スキルが足りない」とか「やる気がない」と、本人の性格や能力に原因を求めてしまいがちです。
その成績不振、ほんとに本人だけの問題でしょうか。もしかすると、担当しているエリアがもともと競争が激しくて市場が縮小しているとか、そういう“外的要因”が関係しているかもしれません。
このように、本当は状況や環境のせいかもしれないのに、つい本人の性格や能力のせいにしてしまう――これが「基本的な帰属のエラー」なんです。ロス(Ross, 1977)[10]という心理学者が提唱したこの考え方は、まさに私たちが日々のビジネスの中で無意識にやってしまっている“思い込み”を指摘しています。
このエラーを理解しているだけで、部下の育成も評価もずいぶん変わります。「この人は何ができていないのか」ではなく、「この状況で、何が彼をうまくいかせていないのか」という視点を持つことが、より公正で効果的なマネジメントにつながります。
次に「会議への遅刻」のビジネスシーンを見ていきましょう。たとえば、皆さんの職場で、同僚が会議に遅れてきたとします。そのとき、心の中でつい「またあの人か、ほんと時間にルーズだよな」と思ったりしませんか。まさにこれが帰属のエラーの典型です。つまり、その人の性格や能力といった“内的要因”だけに原因を求めてしまうというパターンです。
その同僚、もしかしたら会議直前に急なクレーム対応をしていたかもしれません。そういった“状況的な要因”が背景にあった可能性、見落としていませんか。このバイアスを持ったままチーム運営をしてしまうと、人間関係がギクシャクしたり、不必要な摩擦が起きたりします。
だからこそ、このエラーに気づき、「遅刻したのは何か理由があったのかもしれない」と、一歩引いて考える視点がとても大事になってきます。こうした日常の中の“思い込み”に気づいて、それを手放す必要があります。
今度のビジネスシーンは「チーム内の協力不足」です。例えば、プロジェクトを進めている中で、「なんだかあの人、全然協力してくれないな」と感じたこと、ありませんか。そのときに、「この人は協調性がないんだ」とかいった印象を持ってしまうのは、よくあることです。
たとえば、プロジェクトの目的がうまく共有されていなかったとか、自分の役割がはっきりしていなかった、あるいは他の業務とバッティングしていて動けなかった、そんな“環境的な要因”があった可能性もあります。
ですから、チームで協力が得られない場面に直面したときは、「何か共有できていないことがあるのかも」とか「こちらの伝え方が十分だったかな」と、まず状況を確認してみることが大事です。チームづくりのカギは、こうした小さな“見方の転換”にあります。
今度は「残業の多さ」にまつわるビジネスシーンです。たとえば、ある社員が毎日遅くまで残って仕事をしているとします。そうすると周囲はつい、「あの人は仕事が遅い」とか、「段取りが悪い」と、本人の能力や働き方に問題があると考えがちです。
ですが、本人の問題だけとは限らないのです。たとえば、他の人よりも明らかにタスクの量が多いとか、急ぎの案件が集中して回ってきている、あるいはサポートを得られずに一人で抱えてしまっている…そういった“状況的な要因”が背景にあるかもしれません。
そしてこのエラーが放置されてしまうと、その人への評価が不当に低くなってしまったり、周囲との信頼関係が損なわれたりすることもあります。逆に言えば、「この人、何でこんなに残っているんだろう」と状況に目を向けることができれば、マネジメントとしての質も上がります。残業のようなわかりやすい行動の裏にある“見えない背景”に、どれだけ目を向けられるか。これも、リーダーや管理職にとって大切な視点です。
最後のビジネスシーンは「プレゼンテーションの失敗」です。たとえば、ある社員がプレゼンの場でうまく話せなかったとします。そうすると周囲ではすぐに、「あの人はプレゼンが苦手なんだな」とか、「緊張しやすいタイプだよね」と、本人の性格やスキルのせいだと判断してしまうこと、ありませんか。
もしかしたら、直前まで別の業務で忙しくて準備の時間が取れなかったかもしれない。あるいは、機材のトラブルでスライドが映らなかった、音が出なかった、そんな“状況的な要因”が影響していた可能性だってあるかもしれません。
怖いのは、こうした評価がその人の将来のチャンスを狭めてしまうかもしれないってことです。だからこそ、評価するときは、その人の能力だけじゃなくて、「そのとき、どんな状況だったのか」という視点を忘れないことが大事です。これが、組織の中で人を活かすための第一歩です。
対応策と実践的な取り組み提案
ここからは、職場での基本的な帰属エラーの対策を提案していきます。1つ目に紹介する対応策は、「状況要因への意識を高める」というポイントです。
私たちは、自分が何かうまくいかなかったときには「時間が足りなかった」とか「急な対応が入った」といったように、自然と“状況”のせいにすることが多くあります。ところが、これが他人の行動になるとどうでしょうか。同じようにプレゼンがうまくいかなかった人を見て、「あの人はプレゼン苦手だな」って、性格や能力のせいにしてしまう、まさにこれが、帰属のエラーです。
この傾向について、心理学者のGilbertとMalone(1995年)の研究[11]でも紹介されています。彼らは、人間が他人を評価するときに、無意識のうちに「状況を過小評価」してしまい、「その人自身に問題がある」と考えてしまう傾向があると述べています。つまり、私たちは最初の段階では自動的に“内的な要因”に目が行く、ということです。
どうすればいいのかというと、それは、あえて意識的に「どんな状況だったのか」と自分に問い直す習慣を持つことです。部下が行動しなかったとき、単に「やる気がない」と決めつける前に、「他に優先度の高い仕事があったのかも」「指示が曖昧だったかも」と、状況を想像してみます。この一歩を踏むだけで、相手への見方が大きく変わってきますし、公平な評価や関係性づくりにもつながります。
2つ目の対応策として、「多視点からのフィードバックを取り入れる」をご紹介します。これは、360度評価などを活用して、評価を一人の視点に偏らせないという工夫です。
どうしてこれが大事なのかというと、人の行動を評価するときには、自分の価値観や経験が反映されてしまいがちです。つまり、気づかないうちにバイアスが入るのです。
特に基本的な帰属のエラーのような、「この人が悪い」と決めつけてしまうクセは、個人の視点だけで判断していると起こりやすいです。そこで効果的なのが、複数の人からの視点を取り入れることです。同僚、部下、上司など、いろんな立場の人からフィードバックを集めると、ある行動に対する評価が客観的になります。
LondonとSmither(1995年)の研究[12]でも、多面的なフィードバックが、個人の自己理解を深めたり、他者への見方をバランスの取れたものにしたりする効果があると報告されています。つまり、偏った評価を防ぎやすくなります。実際、360度評価を定期的に取り入れている企業では、「この人はこういう一面もある」という新しい発見が生まれたり、単なる思い込みが覆されたりしています。
3つ目の対応策は「認知的負荷を軽減する」、つまり判断に余裕を持つということです。人は忙しいとき、時間がないとき、精神的に余裕がないときって、物事をパッと決めつけてしまいがちです。これは、誰にでもあることです。
たとえば、会議中に誰かが発言しなかったとき、「やる気がない」とか「意見がない」と、すぐにその人自身の性格や能力に原因を求めてしまいがちです。実際は、直前まで別の業務で頭がいっぱいだったとか、タイミングを見計らっていただけだったかもしれないのです。これは、基本的な帰属のエラーの代表的なパターンで、忙しいときほど起こりやすいです。
Gilbert(1989年)の研究[13]でも、人はまず自動的に「この人の性格のせいだ」と内的要因に判断が向きやすいとされています。そして、時間と注意の余裕があるときにだけ、「いや、もしかしたら状況のせいかも」と、修正的な思考が働きます。
だからこそ、判断が必要なときほど、意識して“少し時間を置く”ことが大切です。一呼吸おいて考える習慣を持つ。これだけでも、帰属のエラーを減らすことができます。忙しい職場ほど、この“余裕”をどうつくるかが課題になりますが、例えば「評価は翌日する」など、仕組みでサポートすることも可能です。
4つ目の対応策は、「リフレクション(内省)を習慣にすること」がテーマです。皆さん、日々の業務の中で「あの人のあの行動、なんであんなふうだったんだろう」って考えること、あると思います。ですがそのとき、自分の受け取り方を振り返る機会って、意外と少ないのではないでしょうか。
「やる気がない」とか、「協調性がない」と判断したまま、スルーしてしまうことは、誰しもあると思います。ですが、そうした判断を一度立ち止まって見直すことも大事です。自分の認知や評価を振り返る習慣が、帰属のエラーを減らすためにはとても有効です。
この考え方は、Schon(1983年)が提唱した「リフレクティブ・プラクティス=省察的実践」と呼ばれるアプローチ[14]にも通じます。彼の研究では、専門職が経験を通して学びを深めていくには、自分の判断や行動を意識的に振り返ることが不可欠だとされています。
特に、リーダーや管理職の立場にある方は、自分の評価が部下のキャリアや人間関係に大きく影響するので、この「内省」の力はとても重要です。たとえば、「あの部下は最近報連相が少ない」と感じたときに、すぐに「コミュニケーション能力が低い」と決めつけるのではなく、「こちらの接し方が壁になってないか」と自分を見つめ直す時間を持つことも必要です。こうした習慣が、信頼関係やチーム全体の風通しを良くする大きな一歩になります。
最後の5つ目の対応策は、「対話を通じて相手の視点を知る」ということです。ここまで、状況を想像する、内省する、といった“自分の中で考える工夫”を見てきましたが、それだけではわからないこともあります。一番確実なのは、本人に直接聞いてみることです。
たとえば、ある部下がミスを繰り返していたときに、「この人は注意力が足りない」とか「責任感がない」と決めつけてしまう前に、「最近、何か困っていることないか」とか「どういう状況だったのか」と、オープンに聞いてみることも有効です。
すると、家庭の事情や体調、他の仕事の負荷など、こちらが想像もしていなかった背景が見えてくることがあります。この「聞いてみる」というシンプルな行動が、帰属のバランスを整える鍵になります。
Bolton(1986年)の『People Skills』でも、積極的傾聴やオープンクエスチョンの重要性が強調されています[15]。相手を理解しようという姿勢が、信頼を生み、誤解を防ぎ、結果としてチームの関係性を良くしていきます。
そして、ここで大事なのは、“問いただす”のではなくて、“理解しようとする”対話です。「なぜできなかったの」ではなく、「何があってそうなったのか、一緒に考えよう」というスタンスが、相手の本音を引き出し、状況要因への理解にもつながります。
ここまでご紹介してきた5つの対応策をふまえて、最後に実践的な取り組みのご提案をします。ここまでお話ししてきたように、「基本的な帰属のエラー」は、誰にでも起こり得るものです。決して悪意があってやっているわけではなく、むしろ無意識のうちに、「あの人はこういう人だ」と判断してしまいがちです。
ですが、このエラーを放っておくと、人事評価の場面や日々のマネジメントで、不公平な判断につながってしまうことがあります。たとえば、ある部下が成果を出せていないとき、「努力不足」や「能力不足」といった内的な要因にだけ目を向けてしまうと、その人の本当の課題や、抱えている背景が見えなくなります。
そうすると、「どうせ評価されない」と部下が感じて、モチベーションが下がったり、最悪の場合、離職のきっかけになってしまうこともあります。だからこそ、管理職や評価者の立場にある方々が、この「帰属のエラー」をきちんと理解しておくことがとても重要です。単なる知識として知っておくだけでなく、実際の場面で自分がどう判断しているか、自分の“評価のクセ”に気づくことが大切です。
そのために私がおすすめしているのが、評価者研修や管理職研修の中に、帰属のエラーを扱うパートをしっかり設けることです。たとえば、具体的なビジネスシーンの事例を使って、「このとき、自分だったらどう判断するか」をグループで話し合ってみたり、自分が過去にした評価を振り返るワークを取り入れたりすることが有効です。
そして今日お伝えした5つの対応策はすべて、評価の質を高め、組織の信頼関係を強くするための具体的なヒントになります。ぜひ、研修や日々のマネジメントの中に取り入れて、皆さんご自身の「見方の癖」と向き合う機会を持っていただければと思います。
Q&A
Q1:何度も遅刻する人に対して「本人が悪い」と考えるのは、帰属のエラーでしょうか
黒住:
「何度も繰り返される」場合であれば、一貫性があるという点で、本人に原因があると考えることも、一概に誤りとは言えません。しかし重要なのは、外部環境の影響を見落とさないことです。たとえば、通勤環境の変化や家庭の事情などが影響している可能性もあります。そのため、「何度も遅刻している=本人が悪い」と即断するのではなく、繰り返される背景に共通する要因がないかを考える視点は必要です。
樋口:
行動だけを見て「その人に原因がある」と思ってしまうのは帰属のエラーですが、背景に事情があることも少なくありません。事情を知らないと、「怠けている」と誤解されてしまいます。だからこそ、本人がきちんとチームや上司に状況を伝えることも重要です。ビジネスの現場では、誤解を生まないよう、情報を共有することが一種の「予防策」になります。つまり、帰属のエラーを防ぐためには、本人の伝える努力と、周囲の理解しようとする姿勢の両方が求められます。
Q2:基本的な帰属エラーによって自分が誤解されないようにする対策はありますか。
黒住:
大切なのは「日頃のコミュニケーション」です。普段から自分の考え方や人柄を周囲に伝えておけば、遅刻などが起きた際に「この人には何か事情があるかも」と周囲が配慮しやすくなります。また、実際に問題が起きた後も、きちんと理由を説明し、誠意を持って対応することで、信頼を回復しやすくなります。日本には人間関係が長期的に続く傾向から、一度の失敗で人柄を判断する傾向は弱いとされています。つまり、問題行動の「予防」と「修正」の両面で、対話が有効な対策と言えるでしょう。
樋口:
もう一つの有効な対策は、「プロセスの可視化」です。成果だけでなく、そこに至る過程や努力を周囲に理解してもらうことが大切です。たとえ結果としてうまくいかなかった場合でも、過程での工夫や誠実な取り組みが評価されることがあります。こうした積み重ねがあれば、多少のトラブルがあっても、チームや上司からの信頼を失うことはありません。日々の働きかけや姿勢が最終的な評価に影響するという意識が、ビジネス上のリスク回避にもつながります。
脚注
[1] Ross, L. (1977). The intuitive psychologist and his shortcomings: Distortions in the attribution process. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology, Vol. 10, pp.173–220.
[2] 脚注1と同様
[3] Davison, H.K. & Smothers, J. (2015). How Theory X style of management arose from a fundamental attribution error, Journal of Management History, 21(2), 210–231.
[4] 外山みどり(1998)「基本的な帰属のエラー(Fundamental Attribution Error)」をめぐって 大阪大学人間科学部紀要,24,231-248.
[5] Bott, A., Brockmann, L., Denneberg, I., Henken, E., Kuper, N., Kruse, F., & Degner, J. (2024). Spontaneous trait inferences from behavior: A systematic meta-analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 50(1), 78-102.
[6] 石井雅之(2013) 徳育における「忍耐」の位置づけについて―「生きる力」及び「レジリエンス」概念との関係と問題点― 八洲学園大学紀要,9,11-22. ; Izumi-Taylor, S., Lin, C.-H., & Kaneda, T. (2024). Japanese pre-service teachers’ concepts of gaman (enduring hardship): How gaman relates to the education of preschoolers. US-China Education Review A, 14(9), 557–565.
[7] Izumi-Taylor, S., Lin, C.-H., & Kaneda, T. (2024). Japanese pre-service teachers’ concepts of gaman (enduring hardship): How gaman relates to the education of preschoolers. US-China Education Review A, 14(9), 557–565.
[8] Sylvester, K. (2023). Resilience building pedagogies and women’s university club sport in Japan. Asian Journal of Sport History & Culture, 2(3), 296–317.
[9] なお、それぞれの研究では、我慢が「評価されすぎる」ことへの注意も指摘されています。たとえば、我慢を強いることは本人に過剰な負荷をかけることになったり、ケガをしていても無理をして出場するような、自己犠牲につながる危うさも含んでいます。
[10] Ross, L. (1977). The intuitive psychologist and his shortcomings: Distortions in the attribution process. In Advances in experimental social psychology (Vol. 10, pp. 173-220). Academic Press.
[11] Gilbert, D. T., & Malone, P. S. (1995). The correspondence bias. Psychological Bulletin, 117(1), 21–38.
[12] London, M., & Smither, J. W. (1995). Can multi-source feedback change perceptions of goal accomplishment, self-evaluations, and performance-related outcomes? Theory-based applications and directions for research. Personnel Psychology, 48(4), 803–839.
[13] Gilbert, D. T. (1989). Thinking lightly about others: Automatic components of the social inference process. In Uleman, J. S. & Bargh, J. A. (Eds.), Unintended thought (pp. 189–211). Guilford Press.
[14] Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. Basic Books.
[15] Bolton, R. (1986). People Skills: How to Assert Yourself, Listen to Others, and Resolve Conflicts. Simon & Schuster.
登壇者
 樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
早稲田大学政治経済学部卒業、カリフォルニア州立大学MBA修了、UCLA HR Certificate取得、立命館大学大学院博士課程修了。博士(人間科学)。国家資格キャリアコンサルタント。ビジネスの第一線で30年間、組織と人に関する実務経験、専門知識で、経営理論を実践してきた人事のプロフェッショナル。通信会社で人事担当者としての経験を積み、その後、コンサルティングファームで人事コンサルタントやシニアマネージャーを務め、さらに銀行で人事部長などの役職を歴任した後、現在はFWD生命にて執行役員兼CHROを務める。ビジネスと学術研究をつなぐ架け橋となることを目指し、実践で役立つアプローチを探求している。
 黒住 嶺 株式会社ビジネスリサーチラボ フェロー
黒住 嶺 株式会社ビジネスリサーチラボ フェロー
学習院大学文学部卒業、学習院大学人文科学研究科修士課程修了、筑波大学人間総合科学研究科心理学専攻博士後期課程満期退学。修士(心理学)。日常生活の素朴な疑問や誰しも経験しうる悩みを、学術的なアプローチで検証・解決することに関心があり、自身も幼少期から苦悩してきた先延ばしに関する研究を実施。教育機関やセミナーでの講師、ベンチャー企業でのインターンなどを通し、学術的な視点と現場や当事者の視点の行き来を志向・実践。その経験を活かし、多くの当事者との接点となりうる組織・人事の課題への実効的なアプローチを探求している。