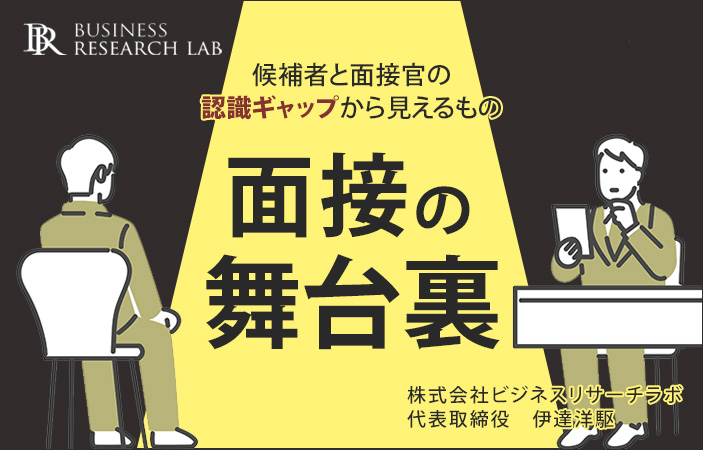2025年6月26日
面接の舞台裏:候補者と面接官の認識ギャップから見えるもの
就職活動や転職において、面接は避けて通れないプロセスです。多くの企業は面接を通じて候補者を評価し、採用の決定を下します。しかし、面接という場は面接官と候補者の両者が参加する相互作用の場でありながら、これまでの議論は主に「企業側からどう評価するか」という視点が中心でした。
実際には、面接を受ける候補者も様々な思いや認識を持ち、面接の場に臨んでいます。候補者はどのような面接形式を好み、どのような質問に対して前向きな反応を示すのでしょうか。また、面接という特殊な状況において、候補者と面接官はどのようにお互いを認識し、どのように振る舞っているのでしょうか。
本コラムでは、「候補者から見た面接」という視点から、面接プロセスを改めて考察します。面接官が好む質問形式と候補者が感じる難しさのギャップ、候補者が好む質問タイプ、そして面接における印象操作の実態について、研究知見をもとに掘り下げていきます。
面接は単なる評価の場ではなく、組織と個人が初めて出会い、互いを知る機会です。候補者の視点を理解することで、面接の本質に迫り、より良い採用活動のヒントが見えてくるかもしれません。面接という複雑な相互作用の場を、新たな角度から一緒に見ていきましょう。
面接官は高度な質問を好むが候補者は難しく感じる
採用面接における質問の形式や内容は、面接の成否を左右する要素です。ある研究では、面接の構造を「質問の一貫性」「評価の標準化」「質問の高度さ」「ラポール形成」という4つの要素から捉え、面接官と候補者の双方がこれらの要素にどのように反応するかを調査しました[1]。
この研究では、428名の面接官と812名の候補者を対象に調査が行われました。面接官は複数の業界から集められ、候補者は大学のインターンシップ選抜面接に参加した学生たちでした。さらに164名の面接官からなる別のサンプルでも追加調査が実施されました。
調査の結果、面接官は「質問の高度さ」が高い面接、すなわち、状況質問や行動質問といった複雑で構造化された質問を用いる面接に対して好意的な反応を示すことが明らかになりました。状況質問とは、「もしあなたがこのような状況に直面したら、どのように対応しますか」といった仮想的な場面を提示し、候補者の判断力や問題解決能力を測る質問です。行動質問は「過去にこのような状況でどのように行動しましたか」と、候補者の経験から将来の行動を予測しようとする質問形式です。
面接官がこうした高度な質問形式を好む理由は、それが候補者の能力やスキルをより正確に評価できると考えているからです。面接官はこのような高度な質問を用いることで、面接の有効性(良い候補者を選抜できる能力)が高まると認識していました。
しかし興味深いことに、候補者側の反応は面接官とは異なっていました。候補者は構造化が高い面接、特に「質問の一貫性」や「質問の高度さ」が高い面接を難しいと感じる傾向がありました。候補者は高度な質問に直面すると、心理的なプレッシャーを感じ、やや否定的な反応を示すことが確認されています。
この研究では、面接官がトレーニングを受けているかどうかも重要でした。トレーニングを受けた面接官は「評価の標準化」や「質問の高度さ」を高める傾向がある一方で、「ラポール形成」も維持していたことが分かりました。適切なトレーニングを受けた面接官は、高度な質問を用いながらも、候補者との信頼関係を築くことの価値を理解していたのです。
ここで考えるべき点は、面接官と候補者の間に認識のギャップが存在することです。面接官は高度な質問を通じて候補者を適切に評価できると考えている一方、候補者はそのような質問を難しく感じ、時にはプレッシャーを感じてしまいます。このギャップは、面接という場が面接官と候補者の間の相互理解に基づいていないことを浮き彫りにしています。
面接の目的によっても、面接の構造化の程度は異なりました。選考目的が強い面接ほど、「評価の標準化」や「質問の一貫性」が高くなる傾向がありました。これは企業が客観的かつ公平な評価を行うためにこれらの要素を重視していることを示しています。
この研究結果が私たちに教えてくれるのは、面接は単なる評価の場ではなく、面接官と候補者の間の相互作用の場であるということです。面接官は高度な質問を通じて候補者を評価しようとしますが、それが候補者にとって難しく感じられ、本来の能力を発揮できない状況を生み出しているかもしれません。
こうした認識のギャップを埋めるためには、面接官が候補者の視点を理解し、高度な質問を用いながらも候補者が回答しやすい環境を作ることが大切です。例えば、状況質問や行動質問を用いる際にも、質問の意図を明確に伝え、候補者が質問の意味を理解できるようにサポートすることが考えられます。
面接では一般的な質問が候補者に好まれる
面接官が高度な質問を好む一方で、候補者はそれを難しく感じることを見てきました。それでは、候補者は実際にどのような質問タイプに対して好意的な反応を示すのでしょうか。この問いに答えるためのヒントを与えてくれる研究があります[2]。
3つの異なる質問タイプ、「状況的質問(SI)」「過去の行動に関する質問(PBDI)」「一般的質問」を比較し、それぞれがどのような構成概念を測定し、候補者がどのように反応するかを調査しました。この研究は3年間にわたり、179名の大学の学生寮アシスタント候補者を対象に実施されました。
3つの質問タイプの特徴を見ていきましょう。「状況的質問」は仮想的な状況を提示し、そこでどう行動するかを尋ねるものです。例えば「住人が孤独を感じていると聞いた場合、どのように対応しますか」といった質問が該当します。これは候補者の将来的な行動意図を測定します。
「過去の行動に関する質問」は、過去の経験を尋ねるものです。例えば「過去に他人同士の争いを解決した経験について教えてください」といった質問です。これは候補者の行動パターンを測定します。
「一般的質問」は、候補者自身の特徴や仕事に対する認識を尋ねるものです。例えば「学生寮アシスタントの最も重要な役割は何だと思いますか?」といった質問がこれに当たります。
研究では、これらの質問タイプの構成概念妥当性(何を測定しているか)と候補者の反応の両方を分析しました。構成概念妥当性に関しては、質問タイプと外部指標(性格特性、リーダー経験、一般認知能力)との関連を調べています。
調査の結果、状況的質問と過去の行動に関する質問の間には強い相関があり、これらがかなり類似した特性を測定していることが明らかになりました。一方、一般的質問は他の2つとは比較的独立しており、性格特性、特に「協調性」と正の関連、「神経症傾向」とも関連していました。
状況的質問と過去の行動に関する質問はリーダー経験と有意な関連がありましたが、性格特性や認知能力との関連は低いことが分かりました。これらの質問タイプが特定のスキルや経験を測定している可能性を示唆しています。
研究者たちが行った多特性多方法分析(MTMM)では、状況的質問と過去の行動に関する質問は、当初意図した個々の職務次元を区別して測定できていない可能性があることが示されました。これらの質問は特定の能力やスキルを測定するというよりも、より一般的な「暗黙の知識」を測定している可能性があります。
ここで着目すべきは、候補者の反応に関する発見です。候補者は3つの質問タイプの中で、一般的質問に対して最も好意的な感情反応を示しました。これは先ほど見たように、候補者が高度な質問(状況的質問や過去の行動に関する質問)を難しく感じる傾向があることと一致しています。
また、表面的妥当性(質問が仕事に関連していると感じられる度合い)についても、過去の行動に関する質問よりも状況的質問や一般的質問の方が高く評価されました。これは候補者が状況的質問や一般的質問をより理解しやすく、仕事に関連していると感じることを示しています。
この研究では、面接官の態度も候補者の反応に影響を与えることが明らかになりました。面接官の温かさやアイコンタクトといった非言語的な要素が、候補者の感情的反応や雇用主への推薦意向と強く関連していたのです。質問の内容だけでなく、面接官がどのように質問を行うかも重要です。
候補者の好意的反応を高めるためには、一般的質問を他の質問タイプと併用することが有効であるということです。一般的質問は候補者にとって回答しやすく、好意的な感情反応を引き出しますが、それだけでは候補者の能力やスキルを十分に評価できない可能性があります。
一般的質問が候補者に好まれる理由はいくつか考えられます。まず、一般的質問は回答の自由度が高く、候補者が自分の強みや価値観を表現しやすいという特徴があります。例えば「あなたの強みは何ですか」という質問では、候補者は自分が最も自信を持っている部分を自由に話すことができます。
また、一般的質問は認知的負荷が低いという特徴もあります。状況的質問や過去の行動に関する質問では、候補者は特定の状況や経験を思い出し、それを構造化して話す必要がありますが、一般的質問ではそのような複雑な認知プロセスが少なくて済みます。面接はそれ自体がストレスフルな状況であり、認知的負荷の低い質問の方が候補者にとって対応しやすいのです。
さらに、一般的質問は候補者が準備しやすいという側面もあります。「あなたの強みは何ですか」「なぜこの職種に興味がありますか」といった質問は面接で頻繁に尋ねられるため、候補者は事前に回答を準備できます。これに対し、状況的質問や過去の行動に関する質問は、より具体的で予測しにくいことがあります。
ただし、一般的質問には限界もあります。一般的質問は候補者の自己認識や表面的な特性を測定することはできますが、実際の行動パターンや問題解決能力を評価するには不十分かもしれません。そのため、複数の質問タイプを併用することが推奨されています。
面接では候補者も評価者も印象操作を行う
面接という場における相互作用の複雑さをさらに理解するため、2014年に発表された包括的なレビュー論文を見ていきましょう[3]。この論文では、面接における評価者の判断や候補者の行動、特に「印象操作」に焦点を当てています。
面接の妥当性について確認しておきましょう。面接は大きく「構造化面接」と「非構造化面接」に分けられます。構造化面接は質問内容があらかじめ決まっており、回答を評価する基準も明確です。非構造化面接は質問内容が自由であり、評価基準も明確ではありません。過去の研究を統合し、構造化面接の妥当性係数は、非構造化面接より高いことを再確認しています。
しかし、面接の妥当性だけでなく、面接という場で起こる評価者と候補者の相互作用、とりわけ「印象操作」に着目することで、面接の複雑な現実が見えてきます。
評価者の判断はどのように形成されるのでしょうか。研究では、評価者の判断に影響を与える要素として、第一印象、評価者のステレオタイプやバイアス、候補者の非言語的行動への反応などが挙げられています。評価者は候補者を見た最初の数分で無意識のうちに判断を形成し、その後の情報収集や評価がその初期判断に引きずられる傾向があります。
評価者も面接という場でさまざまな印象操作を行っています。例えば、組織の魅力をアピールするために良い面だけを強調したり、候補者に好印象を与えるために自分の態度や表情を調整したりすることがあります。これは「嘘をつく」ということではなく、自分や自分の組織を少しでも良く見せようとする自然な心理的傾向です。
評価者の印象操作は、組織に対する候補者の印象に影響を与えます。候補者は面接を通じて組織の文化や価値観を推測するため、評価者の言動は組織全体の代表として受け取られます。そのため、評価者は無意識のうちに組織をより魅力的に見せようとします。
一方、候補者側も面接では様々な印象操作を行っています。候補者の印象操作は大きく次のように分類されています。
- 自己宣伝(Self-promotion):自分の能力や実績を積極的にアピールすること
- 他者との共通点強調(Ingratiation):評価者や組織との共通点を強調すること
- 同調行動(Conformity):評価者や組織の価値観に同調する姿勢を見せること
- 防衛的行動(Defensive IM):自分の弱みや失敗を小さく見せる、または正当化すること
これらの印象操作は多くの候補者が無意識に、あるいは意識的に行っているものです。研究によれば、こうした印象操作は評価者の評価に影響を与えることが検証されています。特に自己宣伝や他者との共通点強調といった積極的な印象操作は、評価を高める効果があります。
懸念されるのは「虚偽の回答(Faking)」です。これは印象操作を超えて、意識的に情報を偽る行動を指します。例えば、持っていないスキルを持っていると偽ったり、経験していない業務経験を誇張したりするケースが該当します。研究では、このような虚偽の回答は非構造化面接で起こりやすいことが指摘されています。
印象操作と虚偽の回答の違いは、前者が自分の良い面を強調する正当な自己表現とも考えられるのに対し、後者は明らかに倫理的問題を含む行為であるという点です。しかし、実際の面接場面では、この境界は時に曖昧になります。
候補者が印象操作や虚偽の回答を行う動機はさまざまです。基本的な動機は「良い評価を得たい」「採用されたい」という欲求ですが、それだけではありません。自己評価を維持したい、不安を軽減したい、自分に対する確信を高めたいといった心理的ニーズも関係しています。
面接という場は、日常生活とは異なる特殊な社会的状況です。限られた時間の中で自分をアピールし、評価されるという状況は多くの人にとってストレスフルです。そのような状況で、人は通常よりも強く印象操作を行います。これは評価者側も同様で、限られた時間で候補者を評価しなければならないというプレッシャーの中で、様々なバイアスや印象操作が生じやすくなるのです。
こうした印象操作や虚偽の回答は面接の有効性をどの程度損なうのでしょうか。研究によれば、印象操作自体は必ずしも面接の妥当性を低下させるとは限りません。なぜなら、印象操作能力自体が仕事のパフォーマンスに関連する場合があるからです。例えば、営業職や接客業などの対人関係が重要な職種では、適切な印象操作能力が業務パフォーマンスに直結することがあります。
一方、虚偽の回答は面接の妥当性を低下させる可能性が高いとされています。虚偽の情報に基づいて候補者を評価すれば、当然ながら正確な評価はできません。このため、虚偽の回答を検出し、予防するための方策が研究されています。
例えば、構造化面接の導入は虚偽の回答を減らす効果があるとされています。構造化面接では、全ての候補者に同じ質問をし、回答を明確な基準で評価するため、曖昧な自己アピールや虚偽の回答がしにくくなります。また、行動的質問(過去の具体的な行動を尋ねる質問)は、状況的質問(仮想的な状況での行動を尋ねる質問)に比べて虚偽の回答がしにくいことも示されています。
脚注
[1] Chapman, D. S., and Zweig, D. I. (2005). Developing a nomological network for interview structure: Antecedents and consequences of the structured selection interview. Personnel Psychology, 58(3), 673-702.
[2] Conway, J. M., and Peneno, G. M. (1999). Comparing structured interview question types: Construct validity and applicant reactions. Journal of Business and Psychology, 13(4), 485-506.
[3] Levashina, J., Hartwell, C. J., Morgeson, F. P., and Campion, M. A. (2014). Beyond employment interview validity: A comprehensive narrative review of recent research and trends over time. Personnel Psychology, 67(1), 241-293.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。