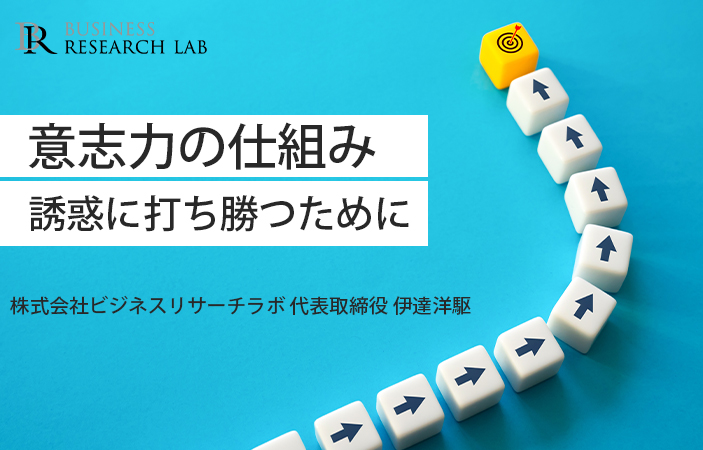2025年5月21日
意志力の仕組み:誘惑に打ち勝つために
私たちは日々、様々な誘惑や衝動と向き合いながら生活しています。朝、少しでも長く寝ていたいという欲求を抑えて起床する瞬間から、夜遅くまで仕事を終わらせるために集中力を維持する努力まで、自分の行動をコントロールする場面は数え切れません。この「自分の行動を意識的にコントロールする能力」は意志力と呼ばれます。
意志力は私たちの生活の様々な側面に関わっています。健康的な食生活を維持するため、デザートの誘惑に抵抗する時。仕事の締め切りに間に合わせるため、SNSの通知を無視して集中する時。将来の目標のために今の楽しみを我慢する時。これらすべてが意志力を必要とする場面です。
しかし、なぜ同じ人でも、ある時は誘惑に簡単に打ち勝てるのに、別の時は負けてしまうのでしょうか。なぜある人は長期的な目標達成に向けて着実に進めるのに、別の人は日々の誘惑に流されがちなのでしょうか。
本コラムでは、意志力に関する研究知見に基づき、こうした問いに迫ります。これらの理解を深めることで、自分自身の行動パターンを把握し、職場における目標達成の可能性を高める手がかりが得られるでしょう。意志力の仕組みを知ることは、私たちの日々の選択や長期的な成功に思いがけない光を当ててくれるかもしれません。
意志力は理性と感情のバランスで決まる
私たちの脳の中では、二つの異なるシステムが活動しています。一方は感情を司る「ホットシステム」、もう一方は理性を司る「クールシステム」です。意志力の強さは、この二つのシステムのバランスによって左右されます[1]。
ホットシステムは私たちの感情や欲求、衝動に関連しています。美味しそうなケーキを見た瞬間に「食べたい」と感じたり、怒りを感じた時に即座に反応したりするのは、このホットシステムが活発に働いている証拠です。このシステムは素早く自動的に反応し、私たちの生存本能に直結しています。危険から逃げたり、報酬に向かって行動したりする即時的な反応を生み出します。
他方で、クールシステムは熟考的で計画的な思考を担当します。「このケーキを食べると、ダイエットの目標から外れてしまう」と考えたり、「今怒りを表すと関係が悪化するかもしれない」と判断したりするのは、クールシステムの働きです。クールシステムは情報を論理的に処理し、長期的な目標や価値観に基づいた判断を下します。
二つのシステムは相互に影響し合っており、その活性化のバランスによって私たちの自己制御の能力が決まります。例えば、子どもを対象にした有名な「マシュマロ・テスト」という実験があります。この実験では、子どもたちに「今すぐ1つのマシュマロを食べるか、15分待って2つのマシュマロをもらうか」という選択を提示します。
この実験において、待つことができた子どもたちは、自分の注意をマシュマロから逸らしたり、マシュマロを雲のように見立てたりする等の戦略を用いていました。これはクールシステムを活性化させ、ホットシステムによる即時的な欲求を抑える方法だと言えます。
ホットシステムとクールシステムのバランスは、様々な要因によって変動します。例えば、幼児期はホットシステムが優位であり、クールシステムはまだ十分に発達していません。そのため、小さな子どもたちは衝動的な行動を取りやすく、自己制御が難しいのです。年齢を重ねるにつれ、クールシステムが発達していき、自己制御能力が向上していきます。
ストレスもこのバランスに関わっています。ストレスを感じると、通常はクールシステムの機能が低下し、ホットシステムが優位になります。これは、危機的状況では素早い反応(逃げるか闘うか)が生存に有利だったという進化的背景があるためです。
しかし、ストレスの影響は単純ではありません。短期的で適度なストレスは、むしろクールシステムを活性化させ、集中力や問題解決能力を高める場合もあります。一方、長期的な慢性ストレスはクールシステムに悪影響を与え、自己制御能力を低下させます。
これらのシステムは学習によっても変化します。あるきっかけに繰り返しさらされると、それに対するホットな反応が形成されるようになります。例えば、毎日同じ時間にお菓子を食べる習慣がある場合、その時間になると自動的に食べたい欲求が生じるようになります。
一方、クールシステムも訓練によって強化できます。メタ認知(自分の思考や感情を客観的に観察する能力)を高めたり、感情を言語化する訓練をしたりすることで、クールシステムの機能を向上させることができます。
意志力を発揮する際の戦略としては、ホットシステムを刺激しないようにする「外部戦略」と、クールシステムを活性化する「内部戦略」があります。外部戦略の例としては、誘惑となるものを目に見えないところに置く、アクセスを難しくするなどがあります。内部戦略としては、注意を別のことに向ける、状況を違った視点から捉え直す(例えば、お菓子を「食べ物」ではなく「化学物質の集合体」と見なす)などがあります。
これらの研究から分かるのは、意志力は単なる「精神力」ではなく、脳内の二つのシステムの相互作用であるということです。自分の意志力を高めたいと考えるなら、この二つのシステムのバランスを整えることが鍵となるでしょう。
意志力の効果は確信度と状況で変わる
意志力に対する考え方は、実際の自己制御能力に影響を与えます。私たちが持つ「意志力理論」と呼ばれる個人的な信念に注目してみましょう。意志力理論には二つのタイプがあります。一つは「意志力は限られており、使うと消耗する」と考える「有限理論」、もう一つは「意志力は無限で、使うほど活性化される」と考える「無限理論」です。
これまでの研究では、一般的に無限理論を持つ人の方が自己制御能力は高いことが報告されています。しかし、最近の研究によれば、この関係はもう少し複雑であることが分かってきました[2]。意志力理論の効果は、その信念に対する確信度や置かれた状況によって変化するのです。
この現象を理解する鍵となるのが「流暢性」という概念です。流暢性とは、ある情報や考えが処理しやすいと感じる主観的な感覚を指します。例えば、読みやすいフォントで書かれた文章は流暢性が高く、逆に読みにくいフォントの文章は流暢性が低いと言えます。この流暢性が、意志力理論の効果を左右することが判明しています。
ある実験では、参加者に意志力に関する特定の考え方(有限理論または無限理論)を提示した後、その考え方を支持する理由を思い出してもらいました。一部の参加者には2つの理由を、別の参加者には8つの理由を挙げるよう求めました。2つの理由を挙げる方が簡単(流暢性が高い)であり、8つとなると難しく(流暢性が低い)なります。
無限理論を持つよう誘導された参加者は、理由を2つだけ挙げた場合(流暢性が高い場合)の方が、その後の自己制御課題でパフォーマンスが良いという結果になりました。一方、有限理論を持つよう誘導された参加者は、理由を8つ挙げた場合(流暢性が低い場合)の方がパフォーマンスが良くなりました。
流暢性は私たちの信念に対する確信度に影響します。何かを容易に思い出せたり、処理できたりすると、その考えが正しいという確信が強まります。逆に、思い出すのが難しかったり処理が滞ったりすると、その考えに対して疑念が生じます。
したがって、無限理論を持つ人が理由を簡単に思い出せた場合、その理論への確信が強まり、精神的疲労を感じにくくなります。一方、理由を多く挙げるのが難しいと、その理論への疑念が生じ、精神的疲労を感じやすくなります。
有限理論を持つ人の場合は逆のパターンが見られます。理由を挙げるのが難しいと、「もしかしたら意志力には限りがないのかもしれない」という疑念が生じ、精神的疲労が減少します。その結果、自己制御能力が向上するのです。
この関係をさらに検証するため、別の実験では、意志力理論に関する文章を読みやすいフォントと読みにくいフォントで提示しました。予測通り、無限理論を持つ人は読みやすいフォントで提示された場合に精神的疲労が少なく、自己制御が高くなりました。一方、有限理論を持つ人は読みにくいフォントで提示された場合に精神的疲労が少なく、自己制御が高くなりました。
この流暢性の影響は、意志力理論について深く考える状況でのみ現れることも判明しています。別の実験では、参加者を「高投資条件」(意志力理論について深く考えるよう促された)と「低投資条件」(あまり考えないよう指示された)に分けました。結果、流暢性の影響は高投資条件でのみ観察されました。低投資条件では、無限理論を持つ人の方が一貫して自己制御が高かったのです。
これらの実験から浮かび上がるのは、意志力理論の効果が単純ではないという事実です。無限理論が常に有利というわけではなく、その効果は確信度や状況によって変動します。意志力理論への確信度が高まると、その理論に沿った形で精神的疲労の認識が変化し、それが自己制御能力に影響を与えるのです。
意志力の信念が翌日の目標達成を左右する
私たちは日々、様々な負荷を抱えながら生活しています。仕事の締め切り、人間関係の調整、家事や育児など、これらの負荷は日によって変動します。特に負荷の高い一日を過ごした後、翌日の自分のパフォーマンスはどうなるのでしょうか。意志力に関する信念が、この問いに対する答えを変えることが研究で判明しています。
先に述べたように、意志力に関しては主に二つの信念があります。一つは「意志力は限られた資源であり、使うと消耗する」と考える「有限理論」、もう一つは「意志力は無限で、使うほど活性化される」と考える「無限理論」です。これらの信念は、負荷の高い日の後の目標達成行動に異なる形で作用することが分かってきました。
大学生を対象にした調査では、参加者に毎日の負荷の程度、不快な課題へのパフォーマンス予測、実際の目標達成行動などを記録してもらいました[3]。
その結果、前日の負荷が高かった場合、無限理論を持つ学生は、翌日の不快な課題への進捗予測が高くなりました。「昨日は大変だったけれど、今日はより多くのことが達成できるだろう」と考える傾向があったのです。一方、有限理論を持つ学生は、前日の負荷が高いと、翌日の進捗予測が低くなりました。「昨日疲れたから、今日はあまりうまくいかないだろう」と予測するということです。
これらの予測は実際の行動にも反映されていました。無限理論を持つ学生は、前日の負荷が高かった後の方が、実際により効果的な目標達成行動を取っていました。反対に、有限理論を持つ学生は、前日の負荷が高いと、翌日の目標達成行動の効率が下がっていました。
これはどのようなメカニズムで起こるのでしょうか。有限理論を持つ学生は、前日の負荷が高いと、翌日の不快な課題に対して強い疲労感を予測していました。「昨日頑張ったから、今日は疲れているはずだ」と考えるのです。それに対して、無限理論を持つ学生は、前日の負荷に関係なく、疲労予測にあまり変化がありませんでした。
有限理論を持つ学生は、前日の負荷にかかわらず、全体的に目標達成の努力が低い傾向がありました。一方、無限理論を持つ学生は、負荷の高い日の後の方が目標達成の努力が増加していました。
これらの結果から、意志力に関する信念が、前日の負荷が翌日の自己調整にプラスにもマイナスにも作用することが示唆されます。無限理論を持つ人にとって、負荷の高い日は「意志力の訓練」となり、翌日のパフォーマンス向上につながります。反対に、有限理論を持つ人にとって、負荷の高い日は「資源の消耗」となり、翌日のパフォーマンス低下につながります。
意志力の信念は自我消耗に常に影響するわけではない
これまで見てきたように、意志力に関する信念が自己制御に影響を与えることは多くの研究で報告されてきました。しかし、この関係がすべての状況で成り立つわけではないことも理解する必要があります。
自己制御研究において長年支持されてきた「自我消耗効果」という概念があります。これは、自己制御を必要とする課題を行った後に、次の自己制御課題のパフォーマンスが低下するという現象を指します。この効果は、意志力が有限な資源であるという「資源枯渇モデル」で説明されてきました。
近年の研究において、この自我消耗効果は意志力の信念によって調整されると主張されています。具体的には、意志力が限定的だと考える人にのみ自我消耗効果が生じ、非限定的な信念を持つ人には生じないというものでした。この結果は、「意志力は使うと枯渇する」という従来の理論に対する反証として注目を集めました。
しかし、最近の再現研究ではこの結果を再現することができないケースが出ています。最近発表された厳密な再現研究では、サンプルサイズを大きくし、統計的手法を改良した上で、オリジナル研究の結果の再現を試みました[4]。
この再現研究では、そもそも自我消耗効果自体が統計的に有意に観察されませんでした。さらに、意志力の信念がこの効果を調整するという証拠も得られませんでした。むしろ、わずかに観察された効果は、オリジナル研究とは逆の方向を示していました。
これらの結果は何を意味するのでしょうか。一つの可能性は、自我消耗効果が非常に小さいか、特定の条件下で生じる現象である可能性です。自我消耗効果の効果量は当初考えられていたよりもずっと小さい可能性があります。
また、意志力の信念の影響も、特定の状況や測定方法によって変わる可能性があります。例えば、前述の通り、意志力理論の効果は確信度や状況によって変動します。同様に、自我消耗効果への影響も、様々な要因によって変わるのかもしれません。
これらの研究結果から学べることは、意志力の信念が自己制御に与える影響は確かに存在するものの、それは状況や個人の特性、測定方法などによって変わる可能性があるということです。単純な「この信念を持てば自己制御が良くなる」という主張ではなく、より複雑な相互作用を理解する必要があります。
意志力研究の再現性の問題は、混乱を招く結果のように見えるかもしれませんが、実は人間の認知や行動の複雑さと多様性を反映しているとも言えます。今後の研究が進むにつれ、意志力のメカニズムについての理解はさらに深まっていくことでしょう。
脚注
[1] Metcalfe, J., and Mischel, W. (1999). A hot/cool-system analysis of delay of gratification: Dynamics of willpower. Psychological Review, 106(1), 3-19.
[2] Clarkson, J. J., Otto, A. S., Hirt, E. R., and Egan, P. M. (2016). The malleable efficacy of willpower theories. Personality and Social Psychology Bulletin, 42(11), 1490-1504.
[3] Bernecker, K., and Job, V. (2015). Beliefs about willpower moderate the effect of previous day demands on next day’s expectations and effective goal striving. Frontiers in Psychology, 6, 1496.
[4] Carruth, N. P., Ramos, J. A., and Miyake, A. (2023). Does willpower mindset really moderate the ego-depletion effect? A preregistered replication of Job, Dweck, and Walton (2010). PLOS ONE, 18(6), e0287911.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。