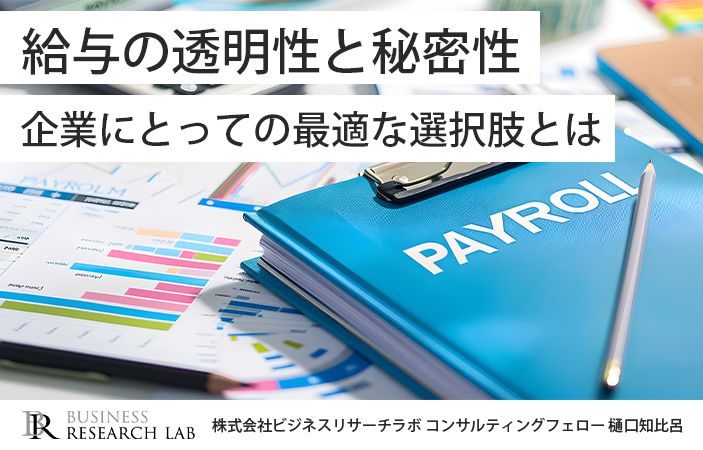2025年5月12日
給与の透明性と秘密性:企業にとっての最適な選択肢とは
給与の透明性と秘密性は、企業の経営戦略において重要な論点となっています。給与情報の開示度合いは、従業員のモチベーションや組織文化に直接的な影響を及ぼします。透明性が高まることで、給与の公平性が確保されやすくなり、従業員の納得感やエンゲージメントが向上する一方、同僚間の比較意識が高まり、不満や競争意識の強まりを招く可能性も指摘されています。
一方、給与の秘密性が高い場合、従業員同士の比較が抑制され、組織内の協力関係が維持されやすくなる利点があります。しかし、給与の決定プロセスの不透明さが不信感を招き、経営側の恣意的な判断が生じるリスクも指摘されています。そのため、企業は適切な給与管理のあり方を模索し、最適な開示戦略を構築する必要があります。
本コラムでは、給与の透明性と秘密性のメリット・デメリットを整理し、各企業にとって最適な給与情報の開示戦略について考察します。研究結果を基に、企業が取るべき給与管理の方向性を明確にし、従業員のエンゲージメント向上や組織の安定性を両立させるための方法を探ります。
給与の秘密性がもたらすコストとベネフィット
給与秘密主義の研究では、そのコストとベネフィットが明らかになっています。給与秘密の影響を詳細に分析し、そのメリットとデメリットを明らかにした研究があります[1]。この研究では、過去の文献を批判的に分析し、組織が給与秘密を採用する際の背景要因や、その影響を理論的に整理しています。
調査の結果、給与秘密には明確なコストとベネフィットが存在することが示されました。まずコストについては、給与秘密は、公平性に対する認識が低下しモチベーションの低下を招くリスクがあります。従業員が自分の給与が適正か判断できず、不信感を抱きやすくなるため、離職率の上昇やパフォーマンスの低下を引き起こします。
また、給与秘密は管理職の負担を増大させます。従業員からの給与交渉や不満への対応が増え、評価基準の説明責任も重くなります。そして、給与の不透明さは組織文化を悪化させる要因になります。不信感や噂が広がり、チームワークが低下し、努力が正当に評価されないと感じる従業員が増加します。
一方で、給与秘密が組織にとって一定のベネフィットをもたらす場合もあることが明らかになりました。具体的には、給与の秘密が職場の対立を軽減し、組織統制を強化する可能性があることが指摘されています。例えば、給与の違いが明確になると、従業員間の不満や競争意識が高まり、職場の調和が乱れる可能性があります。
給与を秘密にすることで、こうした問題を抑制し、組織内の安定性を維持することが期待されます。また、組織の視点から見ると、給与秘密により従業員の転職や離職が少なくなり、組織特有のスキルを持つ人材を長期的に確保することができるという利点もあります。
この研究では、給与秘密の影響を左右する重要な要因として、人的資本の性質、給与配分の基準、従業員の相対的な給与ステータスの把握が挙げられています。例えば、企業固有のスキルを持つ従業員は、外部労働市場での比較が困難であるため、給与の秘密が必ずしも不利に働かない可能性があります。また、客観的な業績基準を導入することで、給与秘密がもたらす不透明性を軽減し、従業員の納得感を向上させることができると示唆されています。
マネジメントへの応用として、この研究の知見は、組織が給与情報の管理方法を再考する際に有用です。まず、給与秘密を完全に廃止するのではなく、従業員が納得できる透明性を確保することが重要です。具体的には、給与の決定プロセスを明確にし、客観的な業績基準に基づく評価制度を導入することで、従業員が自身の給与に対する理解を深めることができます。
また、給与秘密の影響を最小限に抑えるためには、従業員のエンゲージメントを高める施策が効果的です。例えば、キャリア開発の機会を提供し、従業員が自身の成長を実感できる環境を整えることで、給与の透明性が低くても納得感を向上させることができます。さらに、組織文化として、従業員間の協力やチームワークを重視することで、給与の比較によるネガティブな影響を軽減することが可能です。
不公平に対する寛容度がタスクパフォーマンスに影響
給与の秘密主義が個人の課題遂行能力に与える影響について、その心理的メカニズムを詳細に検討した研究があります[2]。この研究は、イスラエルの大学生144名を対象とし、実験室ベースのシミュレーションを通じて、給与秘密が個人の業績にどのように影響を及ぼすかを分析しました。
調査の結果、給与秘密が個人のタスクパフォーマンスに与える影響は、不公平感に対する寛容度によって大きく異なることが明らかになりました。不公平に対する寛容度が低い人々にとって、つまり不公平を許容しにくい人にとって、給与が非公開だと成果が正当に評価されているのかが分かりにくくなり、その結果、頑張っても報われないと感じ、仕事の意欲や成果が下がることが明らかになっています。
反対に、不公平に対する寛容度が高い人々は、給与秘密下でも高いパフォーマンスを維持する傾向がありました。これは、彼らが給与の透明性に対して強い関心を持たず、自身の業績や職務遂行に集中できるためです。また、組織の評価制度に対する信頼が高く、不確実な状況でもモチベーションを維持しやすい点も影響しています。そのため、給与情報が公開されていなくても、自身のスキル向上や目標達成に注力し、安定した業績を発揮することが確認されています。
この研究の知見は、組織における給与管理のあり方に対して重要な示唆を与えます。特に、従業員が業績と報酬の関係をどのように認識するかが、給与秘密の影響を左右する要因となるため、組織は透明性のバランスを考慮することが有用です。例えば、厳格な給与秘密ポリシーを採用する場合でも、従業員に対して給与決定の基準や評価基準を明確に伝えることで、仕組みを明確化し、不公平感の軽減につなげることができます。
また、マネジメントの観点からは、給与秘密の影響を最小限に抑えるために、個々の従業員の特性に応じた対応が重要です。不公平感に敏感な従業員が多い組織では、給与の透明性を高めることが、従業員のモチベーション維持に寄与するでしょう。その一方では、比較的安定した環境で、従業員の不公平感に対する許容度が高い場合は、給与秘密を維持しながらも、パフォーマンス評価の明確化に注力することが効果的です。
給与秘密を違法とした州は大卒女性の給与が高い
給与の秘密主義が男女の給与格差に与える影響を明らかにした研究を紹介します[3]。米国では、一部の州で給与秘密を禁止する法律が施行されており、こうした政策が女性の収入にどのような影響を与えるのかを分析しました。研究対象は、1977年から2012年までの米国の労働者を対象とした大規模データであり、特に給与秘密を禁止する州と禁止していない州の給与格差を比較しました。
調査の結果、給与秘密が違法とされている州に住む女性、とりわけ大卒者の給与が高いことが明らかになりました。具体的には、違法の州の大卒女性の給与は3%高く、男女の給与格差が5~6%縮小することが確認されました。対照的に、低学歴の女性に関しては、有意な影響は見られませんでした。
これらの結果は、給与秘密の禁止が、特に高学歴の女性にとって、より公平な給与交渉の機会を提供する可能性を示唆しています。給与の透明性が向上することで、自分の給与が適正かどうかを判断し、交渉の余地が生まれるため、特に交渉力を持ちやすい高学歴女性の給与が上昇すると考えられます。
この研究の実践的含意として、給与の透明性が女性の労働市場における地位向上に寄与する可能性が示されました。企業にとって、給与情報の開示は、従業員のエンゲージメントや公平性の認識を高める要因となるかもしれません。特に、高学歴の女性従業員の離職防止やキャリア形成の支援につながると考えられます。給与の透明性を確保することで、従業員の納得感が高まり、組織への信頼が向上することが期待されます。
また、マネジメントの視点では、給与の透明性を向上させるための具体的な施策が有用です。例えば、給与決定の基準を明確にし、一定の範囲で公開することが考えられます。完全な給与開示が困難な場合でも、給与レンジや評価基準の共有は、従業員の不公平感を軽減し、組織全体のパフォーマンス向上に寄与するでしょう。また、定期的な給与レビューやフィードバックの機会を設けることで、従業員が自らの報酬について理解を深めることができ、適切なキャリア戦略を立てやすくなります。
給与の透明性が専門性認識と協力を促進
給与の秘密性が新しく形成されたバーチャルワークグループにおける効率的な援助探索行動(新しく結成された仮想作業グループのメンバーが、自身の業務遂行のために、専門知識を持つと認識した他者に積極的に助けを求める行動)に与える影響を明らかにした研究があります[4]。特に、給与情報の透明性が、メンバーが最も適切な支援者を特定し、援助を求める能力に影響を与えるかどうかを検証しました。
シンガポールの大学に通う146名のビジネス学部生を対象とした実験的研究を実施し、複数ラウンドにわたるシミュレーションを用いて、給与情報の透明性と援助探索行動の関係を分析しました。参加者は、秘密・透明・混合といった異なる給与情報の公開条件のもとで、熟練度の異なる仮想チームメンバーと相互作用し、その行動を観察しました。
調査の結果、給与の透明性が高いほど、ワークグループ内で最も高給を得ているメンバーの専門性を正確に認識できることが確認されました。また、給与情報が透明である場合、参加者は適切な専門家に対して援助を求める傾向が強まり、援助探索の効率性が向上することが示されました。
特に、高業績者および平均的業績者の間では、給与の透明性が効率的な援助探索の頻度を増加させることが明らかになりました。反対に、給与の秘密性が維持されると、メンバーは専門知識を適切に評価することが難しくなり、結果として援助を求める際の意思決定に影響を及ぼす可能性が示唆されました。
この研究の実践的含意として、給与の透明性を高めることが、バーチャルワークグループにおける情報共有や協力の促進に寄与することが示されました。特に、専門知識を迅速に特定し、必要な支援を得ることが求められる環境では、給与の透明性が協力関係を構築する上で有用であることが示されています。また、給与情報の公開が、従業員のモチベーションや相互の信頼を高める効果を持つ可能性も指摘されています。
マネジメントの観点からは、給与の透明性を適切に導入することが、組織内の協力や知識共有を強化する手段となるでしょう。特に、バーチャルワークグループやリモートワーク環境では、チームメンバー間の能力や貢献度を可視化することが重要です。そのため、給与決定のプロセスや評価基準を明確にし、従業員が自身の役割や貢献を正しく理解できる仕組みを構築することが有用です。また、給与の透明性を高めることで、適切な人材に適切な支援を求める文化を育成し、組織全体の生産性を向上させることが期待されます。
給与の透明性が満足度と組織コミットメントを向上
給与に関する会社と従業員の間のコミュニケーションのあり方が、従業員の態度や満足度にどのような影響を及ぼすかを検討した研究を紹介します[5]。特に、給与の決定方法に関する情報共有が、給与の公平性に対する認識を介して、従業員の組織コミットメントや給与満足度にどのように影響するかを分析しました。
米国中西部の公益事業会社の従業員を対象に調査を実施し、給与コミュニケーション、給与の公平性、給与満足度、および組織コミットメントとの関係を検証しました。
調査の結果、給与の決定プロセスに関する情報を受け取ることで、従業員は自分の給与が公正に決定されていると認識しやすくなり、その結果、組織へのコミットメントや給与満足度が向上することが示されました。特に、給与の公平性に対する認識は、給与水準に対する満足度だけでなく、給与管理全般に対する満足度にも影響を与えることが明らかになりました。
一方、文書化された給与の秘密保持方針が従業員の態度に与える影響は限定的であり、むしろ暗黙の給与秘密方針があると認識される場合に、給与管理に対する満足度が低下することが示されました。これは、組織が給与に関する透明性を欠いていると従業員が感じると、公平性が損なわれ、ネガティブな態度につながる可能性を示唆しています。
この研究の実践的含意として、給与の決定プロセスに関する情報を積極的に開示することが、従業員のエンゲージメントや満足度を高める上で有効であることが挙げられます。特に、給与の透明性を向上させることで、従業員が組織の報酬制度を理解し、自らの給与が公正であると認識することを促すことができます。これにより、組織への信頼が醸成され、モチベーションや生産性の向上につながる可能性があります。
マネジメントの観点からは、給与に関する適切な情報提供が、組織の安定性を高める要素となるでしょう。経営者や人事部門は、単に給与水準を設定するだけでなく、その決定プロセスや評価基準について明確に伝えることが求められます。
例えば、給与の決定方法を説明するガイドラインを設ける、定期的な報酬制度に関する説明会を開催する、上司が部下に給与に関する情報を適切に伝えるトレーニングを実施するなどの取り組みが有効です。また、給与の透明性を高めることで、従業員の間に不必要な憶測や不信感が生じるのを防ぐことができるでしょう。
同時に、給与の透明性を高める際には、組織文化や従業員の価値観に配慮することも重要です。給与情報の開示が、必ずしもすべての組織や従業員にとって望ましいとは限らず、個人のプライバシーを尊重しつつ、どの程度の情報を共有するのが最適かを慎重に検討する必要があります。そのため、給与の開示レベルや情報提供の方法については、組織の特性や従業員の意見を踏まえながら、段階的に進めることが望ましいでしょう。
給与の秘密性が高いほど、職場逸脱行為が増え、組織市民行動が減少する
給与の透明性が従業員の行動にどのような影響を及ぼすかを検証した研究があります[6]。具体的には、給与の秘密性と給与の透明性が、組織市民行動(Organizational Citizenship Behavior: OCB)や職場逸脱行為にどのように関係するかを分析しました。組織市民行動とは、従業員が職務上の義務を超えて積極的に貢献する行動を指し、職場逸脱行為とは、遅刻や生産性の低下、不正行為など組織に悪影響を与える行動を指します。
この研究では、情報的公正(給与に関する情報がどれだけ透明に伝えられているか)と分配的公正(給与が適正に配分されているかの認識)が、これらの関係を媒介(ある要因が別の要因に影響を与える際の仲介要素)する要因となるかも検証しました。
調査は、米国在住の労働者611名を対象に実施されました。対象者は、現在雇用されている18歳以上の労働者であり、給与の透明性や組織内での行動に関する質問に回答しました。分析の結果、給与の秘密性が高いほど、職場逸脱行為が増え、組織市民行動が減少することが確認されました。
特に、情報的公正が給与の秘密性と従業員行動との関係を媒介していることが明らかになりました。すなわち、給与情報の不透明さが不公平感を生み、それが職場での否定的な行動につながる可能性が示唆されました。一方、分配的公正の影響は限定的であり、給与の公平な配分が直接的に従業員の行動を決定する要素ではないことが分かりました。
この研究の実践的含意として、企業が給与の透明性を高めることで、職場の秩序を維持し、従業員の積極的な貢献を促すことができる点が挙げられます。特に、給与に関する情報を適切に伝えることで、従業員の公平性認識を向上させ、組織に対する信頼を高めることが可能です。
透明性を確保する方法として、給与決定のプロセスを説明するミーティングを設ける、従業員が自身の給与水準の根拠を理解できる資料を提供する、業績評価と給与決定の関連性を明確にするなどが有用です。これにより、従業員の不満を軽減し、職場での積極的な行動を促進できるでしょう。
マネジメントの観点からは、給与の完全な公開には慎重な対応が求められます。例えば、業績評価に基づく昇給や報酬の差を明確にすると、従業員間での比較が発生し、不公平感を抱く可能性もあります。そのため、給与の透明性を高める際には、報酬決定の合理性を十分に説明し、組織内での信頼関係を構築することが重要です。
給与の透明性が情報共有と不満を同時に促進
企業が給与の透明性と秘密性のどちらを選択することが従業員のモチベーションや組織のパフォーマンスにどのような影響を与えるのかを分析した研究を紹介します[7]。従業員同士の給与情報の開示が組織に与える影響は、長らく議論されてきましたが、この研究では特に説明責任と社会的比較という2つの視点から、給与の透明性と秘密性のメリット・デメリットを明確にしています。
この研究では、理論モデルを構築し、企業が給与の透明性を高めることで、従業員間の情報共有が進み、組織の説明責任が向上すると共に、社会的比較による不満や嫉妬が発生しやすくなることを示しました。
具体的には、給与の透明性が高い企業では、従業員が自分の給与が適正かどうかを判断しやすくなり、経営陣が公平な給与制度を維持する動機が強まります。しかし、同時に、他者との比較による嫉妬や不満が生じやすくなり、組織の生産性や職場環境に負の影響を与える可能性もあります。
一方、給与の秘密性が高い企業では、従業員は同僚と給与を比較しにくくなるため、競争意識によるストレスが軽減されます。しかし、その一方で、経営陣は給与決定の過程を説明する必要がなくなるため、恣意的な昇給や報酬設定が行われる可能性が高まり、公平性や信頼性が損なわれるリスクが指摘されています。
実務への示唆として、給与の透明性と秘密性のどちらが優れているかは一概には言えず、組織の特性に応じて最適なバランスを考えることが重要です。例えば、長期的な雇用関係が築かれており、従業員が企業の給与制度を信頼している場合は、給与の秘密性が比較的適している可能性があります。なぜなら、従業員が給与決定のプロセスを経営陣に委ねることで、社会的比較による不要な摩擦を避けることができるためです。
成果主義が強く、業績による報酬差が大きい組織では、透明性を高めることで、給与の公平性に関する納得感を向上させ、従業員のエンゲージメントを促進することが有効でしょう。特に、明確な業績評価基準が存在する場合、給与の透明性は従業員に対し、自身の報酬が正当な基準に基づいて決定されているという安心感を与えます。
マネジメントへの応用として、給与の透明性を高める場合でも、個人間の給与比較を助長しないよう、報酬に関する説明を適切に管理することが重要です。さらに、企業文化や業界特性も考慮する必要があり、フラットな組織文化を持つ企業では透明性が好まれるのに対して、ヒエラルキーが強い組織では秘密性を維持する方が適している場合もあります。
給与の透明性と秘密性の利点と課題
企業における給与情報の開示が、従業員の態度や行動、さらには組織全体のパフォーマンスにどのような影響を及ぼすのかを明らかにした研究があります[8]。従来、給与情報の開示については「透明性(オープンにする)」と「秘密性(非公開にする)」という二極的な概念で議論されてきましたが、この研究ではその中間的な段階も含めた連続的なアプローチを採用し、給与情報がどのように伝達され、どのような結果をもたらすのかを包括的に分析しています。
研究では、給与情報の開示に関する過去の研究をレビューし、情報の非対称性の観点から統合的な枠組みを提案しました。情報の非対称性とは、企業と従業員、または従業員同士で給与情報の取得に格差がある状況を指します。企業が給与情報をどの程度開示するかによって、従業員のモチベーション、組織の公平性、職場環境の健全性などに影響が及ぶと考えられています。この研究では、給与情報開示の程度に応じた従業員の反応や、組織の成果に関する研究を整理し、今後の研究課題を提示しました。
調査の結果、給与の透明性と秘密性のそれぞれには利点と課題があることが明らかになりました。透明性が高い組織では、給与の公平性が確保されやすく、従業員の納得感が向上すると同時に、同僚間の比較意識が強まり、不満や対立を生むリスクが指摘されています。特に、自身の給与が低いと感じる従業員にとっては、透明性が高まることが逆にモチベーションの低下につながる可能性があります。
一方、給与の秘密性が高い組織では、従業員間の比較が抑制され、組織内の協力関係が維持されやすいという利点がありますが、企業側の裁量が大きくなることで、不透明な給与決定が行われるリスクも存在します。この不透明性は、従業員にとって不公平感を生む要因となり、給与に対する不信感や組織へのエンゲージメント低下につながる可能性があります。
マネジメントへの応用として、ジェンダー間の給与格差を是正するためには、一定の透明性を確保することが有効です。過去の研究では、給与の透明性が向上すると、男女間の給与格差が縮小する傾向があることが示唆されており、企業のダイバーシティ推進の観点からも、適切な情報開示が求められます。
企業がとるべき給与情報管理の方向性
企業が給与の透明性と秘密性のバランスを適切にとるためには、組織の特性や業界特性を考慮し、情報開示の範囲を慎重に設計することが求められます。例えば、成果主義が強く、業績による報酬差が大きい組織では、給与の透明性を高めることで、従業員の納得感を向上させ、エンゲージメントの向上につながるでしょう。対照的に、職務ごとの成果の測定が難しい業務では、過度な透明性が不公平感を生む可能性があるため、一定の秘密性を保つことが効果的と考えられます。
また、企業が給与情報の透明性を確保する際には、報酬決定のプロセスや評価基準を明確にすることが重要です。給与額そのものを開示するのではなく、評価基準や昇給の仕組みを説明することで、従業員に納得感を与えることが可能です。さらに、定期的なフィードバックやキャリア成長の機会を提供することで、給与の透明性が低い環境でも従業員のエンゲージメントを高める施策を実施できます。
給与の透明性と秘密性のどちらを選択するかは、組織の状況や文化に応じて最適な方法を模索する必要があります。重要なのは、従業員が給与決定のプロセスを理解し、公平性を感じられる環境を整えることです。企業は給与管理のあり方を戦略的に検討し、組織のパフォーマンス向上につなげることが求められています。
給与の透明性を高めることで従業員の信頼を得ることができる一方、情報の開示がもたらす影響を慎重に評価し、組織内の公平性と安定性のバランスを取ることが不可欠です。最適な給与管理の在り方は、一律の方針ではなく、各企業の文化や経営方針に適した形で設計されることが望まれます。
脚注
[1] Colella, A., Paetzold, R. L., Zardkoohi, A., & Wesson, M. J. (2007). Exposing pay secrecy. Academy of Management Review, 32(1), 55-71.
[2] Bamberger, P., & Belogolovsky, E. (2010). The impact of pay secrecy on individual task performance. Personnel Psychology, 63(4), 965-996.
[3] Kim, M. (2015). Pay secrecy and the gender wage gap in the United States. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 54(4), 648-667.
[4] Belogolovsky, E., Bamberger, P., Alterman, V., & Wagner, D. T. (2016). Looking for assistance in the dark: Pay secrecy, expertise perceptions, and efficacious help seeking among members of newly formed virtual work groups. Journal of Business and Psychology, 31, 459-477.
[5] Day, N. E. (2012). Pay equity as a mediator of the relationships among attitudes and communication about pay level determination and pay secrecy. Journal of Leadership & Organizational Studies, 19(4), 462-476.
[6] Marasi, S., Wall, A., & Bennett, R. J. (2018). Pay openness movement: Is it merited? Does it influence more desirable employee outcomes than pay secrecy?. Organization Management Journal, 15(2), 58-77.
[7] Fahn, M., & Zanarone, G. (2020). Accountability versus social comparisons: A theory of pay secrecy (and transparency) in organizations. Unpublished working paper.
[8] Brown, M., Nyberg, A. J., Weller, I., & Strizver, S. D. (2022). Pay information disclosure: Review and recommendations for research spanning the pay secrecy–pay transparency continuum. Journal of Management, 48(6), 1661-1694.
執筆者
 樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
早稲田大学政治経済学部卒業、カリフォルニア州立大学MBA修了、UCLA HR Certificate取得、立命館大学大学院博士課程修了。博士(人間科学)。国家資格キャリアコンサルタント。ビジネスの第一線で30年間、組織と人に関する実務経験、専門知識で、経営理論を実践してきた人事のプロフェッショナル。通信会社で人事担当者としての経験を積み、その後、コンサルティングファームで人事コンサルタントやシニアマネージャーを務め、さらに銀行で人事部長などの役職を歴任した後、現在はFWD生命にて執行役員兼CHROを務める。ビジネスと学術研究をつなぐ架け橋となることを目指し、実践で役立つアプローチを探求している。