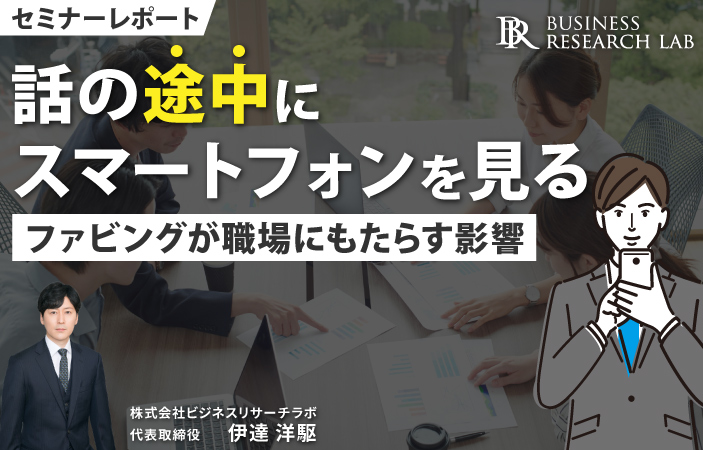2025年5月8日
話の途中にスマートフォンを見る:ファビングが職場にもたらす影響(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年4月にセミナー「話の途中にスマートフォンを見る:ファビングが職場にもたらす影響」を開催しました。
会議中、上司はスマートフォンを見つめ、あなたの報告に目を合わせようとしない。このような光景はありませんか。「ファビング」と呼ばれる、対話中にスマートフォンに没頭してしまう行為は、職場の人間関係や生産性に影響を及ぼします。
この度、企業における重要な課題ともなり得るファビングについて、研究知見をもとに理解を深めるセミナーを開催しました。ファビングは単なるマナーの問題ではありません。部下の心理的安全性を損ない、チームの信頼関係を蝕み、従業員のエンゲージメントを低下させる可能性があります。
さらに、休憩時間中のファビングが職場の人間関係に及ぼす影響や、在宅勤務の増加に伴うオンラインコミュニケーションとの関係性など、現代の働き方に直結する課題についても掘り下げていきます。
セミナーでは、調査結果を踏まえて、ファビングがもたらす職場への影響と、その対策について考察しました。人事部門として取り組むべき施策のヒントが得られる内容となっています。
デジタル技術が働き方を大きく変える中、対面でのコミュニケーションの質を保つことは、これまで以上に重要な課題です。この機会に、次世代の職場環境づくりのための新たな視点を見出していただければと思います。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
私たちの生活にスマートフォンが浸透するにつれて、人と人とのコミュニケーションの形も変化してきました。便利さと引き換えに、私たちは何かを失っているのかもしれません。現代社会では、家族や友人、同僚と実際に対面している場面でさえ、会話の相手よりもスマートフォンの画面に気を取られてしまうことが珍しくありません。この現象は単純なマナー違反を超えて、人間関係の質や心理的健康に影響を及ぼしています。
特に職場においては、この行動パターンが仕事の効率性や人間関係の構築に悪影響を及ぼす可能性があります。上司と部下の間でこのような行動が生じると、信頼関係の構築が難しくなり、組織全体の雰囲気にも影響を与えかねません。
本講演では、スマートフォンが介在することで生じるコミュニケーションの歪みについて、研究知見をもとに多角的に検討していきます。私たちは職場における何気ない日常の中で、デジタル機器の使い方を見直す必要があるのかもしれません。
ファビングとは
「ファビング」という言葉を聞いたことがありますか。これは「Phone(電話)」と「Snubbing(無視する)」を組み合わせた造語で、対面での会話中にスマートフォンを操作することで相手をないがしろにする行為を指します。例えば、職場での打ち合わせ中に上司が部下の発言に対して目を合わせるのではなく、スマートフォンの画面を見ながら返答する場面や、同僚との昼食中に会話よりもSNSのチェックを優先する行動などが典型例です。
この「ファビング」という概念は2010年代に登場し、スマートフォンの普及とともに急速に研究対象として注目を集めるようになりました。ある文献調査によれば、2010年代半ばから関連する学術論文が徐々に増加し始め、2019年前後には急増したとされています[1]。心理学、コミュニケーション論、教育学、情報技術論など、様々な分野の研究者がこの現象に関心を寄せています。
疎外感からの悪影響
ファビングが人の心理にもたらす影響は想像以上に深刻です。ある研究では、ファビングを測定するための尺度を開発し、100名以上の若者を対象に調査を行いました。その結果、対面でスマートフォンを使われて「放っておかれる」感覚が高まると、それを補おうとSNS利用が増え、さらには不安や抑うつ感につながるという流れが明らかになりました[2]。
「仲間外れにされている」という感覚は人間の基本的な欲求を脅かします。別の研究では、実験参加者を「1回だけファビングされる条件」と「3回ファビングされる条件」に分け、その心理的影響を比較しました[3]。3回ファビングされた参加者は、1回だけの場合よりも強い排除感を報告し、自己肯定感や存在価値に関する感覚が低下する傾向が見られました。さらに、この実験では信頼ゲームも実施され、複数回ファビングされた参加者は相手への信頼度が低くなることも確認されました。
興味深いことに、ファビングの記憶は必ずしも正確ではありません。ある観察研究では、学生ペアの会話を10分間記録し、その後のアンケートで自分たちのスマートフォン使用について質問しました[4]。多くの参加者が「自分はスマートフォンを使っていない」と回答したにもかかわらず、実際には使用していたケースが複数見られました。このことは、ファビング行為が無意識のうちに行われている可能性を示唆しています。
しかし、意識しているかどうかにかかわらず、ファビングが発生すると会話の親密度は低下します。同じ観察研究では、相手がスマートフォンを取り出した場面があった組ほど、会話の親密度評価が低くなりました。一方で、画面を共有して一緒に何かを見るケースでは、必ずしも否定的に捉えられないこともありました。
なぜファビングは不快感を生むのでしょうか。ある実験では、スマートフォンで無視されるケースと雑誌を読まれて無視されるケースを比較しました[5]。結果、スマートフォンを見る行為のほうが強い不満や苛立ちを生じさせることがわかりました。雑誌を読む行為は学習や情報収集など有益な活動と想像されやすいのに対し、スマートフォンの内容は外からは見えないため「どうせゲームやSNSだろう」と価値の低い活動と判断されます。そのため、相手への配慮よりもスマートフォンを優先しているように映り、不快感が増大するのです。
職場における休憩時間中のファビングも人間関係に影響を与えます。電気工事業や医療業界の従業員25名を対象としたインタビュー調査では、同僚がスマートフォンに没頭すると会話が途切れ、周囲との交流が難しくなるという不満が多く聞かれました[6]。一方で、自分自身もストレス発散や気まずい沈黙を紛らわすためにスマートフォンを使ってしまうという矛盾も浮かび上がりました。
周囲の人がファビングをしているのを見ても、直接注意することは多くありません。波風を立てたくない、相手の気分を害したくないという思いから、不満があっても表明しないケースがあります。そのため、ファビングは知らないうちに人間関係に壁を作り、蓄積していく危険性があります。
ファビングを行う側にも悪影響をもたらすという研究結果もあります。日常的にファビングを行う人を対象とした研究では、ファビングの頻度が高い人ほど他者への共感や思いやりが低下する傾向が見られました[7]。さらに実験でも、ファビングの場面を多く経験するほど、相手への共感が弱まり、助けようとする行動の意図が減少することが確認されています。このことから、ファビングは社会的スキルや対人関係の質を全体的に低下させる要因となり得ます。
ボス・ファビングの問題
上司が部下とのコミュニケーション中にスマートフォンを操作する「ボス・ファビング」は、職場環境に特有の問題を引き起こします。ある研究では、職場の従業員302名を対象に、上司のスマートフォン利用が会話中にどれほど多いかを調査しました[8]。この研究では「会議の途中で上司が端末を触っていることに気づく頻度」などが質問され、心理的状態との関連が分析されています。
そうしたところ、上司がコミュニケーション中にスマートフォンを操作する頻度が高いほど、部下の疎外感や仕事への興味喪失度が上昇することが明らかになりました。研究では「対人感受性」という特性にも着目しており、周囲からの評価や言動に敏感な人ほど、上司のファビングに強い不快感を抱き、職務への集中を意図的に弱めてしまう傾向が示されました。
上司のスマートフォン使用による「話を聞いてくれない」という感覚は、部下にとって職場への信頼を後退させる問題です。対面での指示場面で上司が画面に集中していると、「自分は重要な存在ではない」という思いが生じやすくなります。そして、仕事への意欲が徐々に失われ、人間関係が悪化する可能性があります。
ボス・ファビングはまた、職場での孤立感や「サイバーローフィング」(業務時間中に私的なネット利用をすること)を助長することも分かっています。インドの267名の従業員を対象とした研究では、上司のファビング行動と従業員の私的なオンライン活動との間に有意な関連が見られました[9]。会話中に上司が画面を見る、ミーティング中に突然メッセージを確認するといった行動が報告されるほど、部下の孤立感も高まりました。
この孤立感が高まると、従業員は内面的に不安定になり、仕事への集中力が低下します。その末に、業務とは無関係のインターネット利用やSNS閲覧に時間を費やすサイバーローフィングが増加するのです。研究では「心理的デタッチメント」(仕事上のストレスをオフタイムに切り離す能力)も測定されており、この能力が低い人ほど孤立感からサイバーローフィングへ流れやすいことが示唆されました。
ボス・ファビングは部下の仕事への熱意(エンゲージメント)も低下させます。ある研究では、アンケート調査と実験的手法を組み合わせて検証が行われました[10]。数百名の従業員を対象としたアンケートでは、上司のファビング頻度が高いほど上司への信頼が低下し、「この仕事は自分の成長に有意義だ」という認識も弱まることが分かりました。最終的に、職務へのエンゲージメントが低下するというパターンが見出されました。
実験パートでは、参加者を「上司が会話中にしきりに端末を操作している映像」を見るグループと「上司が部下の話に集中している映像」を見るグループに分けました。ファビング映像を見たグループは上司への信頼感が低く、仕事の意義を感じにくくなるという結果が得られました。
ボス・ファビングが「社会的承認欲求」の高い部下に強く影響するという研究もあります[11]。自分が評価されたい、認められたいという思いが強い従業員ほど、上司から目を向けてもらえないと感じたときのストレスが高まることが見えてきました。承認欲求の高い部下は、上司がスマートフォンに気を奪われていると深く傷つき、「仕事に打ち込んでも評価してもらえないかもしれない」と考えます。作業への取り組みが消極的になり、パフォーマンスが低下するという流れが明らかになりました。
ファビングをどうするか
ファビングに対して私たちはどのように向き合えば良いのでしょうか。重要なのは、ファビングが生じやすい環境要因を理解することです。ある研究では、64組の参加者を対象に「スマートフォンを使って相手をないがしろにすることをどう思うか」「周囲の人はファビングをどの程度許容すると思うか」などを調査しました[12]。ファビングに前向きな姿勢を持つ人ほど、実際にファビング行動を取りやすいことが明らかになりました。
要するに、ファビングを許容する雰囲気が形成されると、この行動はさらに広がりやすくなるのです。少人数の集まりでは、誰かが最初にスマートフォンを触り始めると、連鎖的に周囲の人も同じ行動を取るという「伝染」現象も観察されています。こうした状況を嫌う人がいても、否定的意見を言いにくい雰囲気があるため、歯止めがかかりにくいという問題があります。
一方、スマートフォン使用に関する規範意識が強いほど、ファビングが減少することも報告されています。ある研究では、「モバイルフォン使用規範」(MPN)、「見逃し恐怖」(FOMO)、「常にオンラインでつながっている感覚」(POPC)などを測定し、ファビングとの関連を調査しました[13]。結果として、MPNが強いほどファビングは減少し、FOMOやPOPCが高い人ほどファビングが多いことが確認されました。
MPNが強い人は「友人や知人と実際に顔を合わせているときにスマートフォンを見るのは良くない」という認識をはっきり持っており、対面の相手を無視する行動を控える傾向があります。一方、FOMOが強い人はオンラインでの出来事を逃したくないという気持ちから、リアルの会話よりもスマートフォンに視線を落としがちになります。
職場では、ファビングが問題であるという認識を共有することから始めるべきです。多くの人がファビングの悪影響を理解せずに行動している可能性があります。また、スマートフォン使用に関する規範意識を高めるため、組織内でのマナーやガイドラインを明確にすることも有効でしょう。
ファビングの背景には退屈感も関係しています。ある調査では、退屈感が強い人ほど、その埋め合わせにスマートフォンを触りたくなることが示されました[14]。さらに、「取り残されたくない」という不安を抱えている場合、会話中であってもすぐに画面を確認してしまう傾向があります。ファビングは退屈をまぎらわす意図と、周囲の動きを追いかけたい気持ちが複合的に絡み合って生じるのです。
このような知見を踏まえると、ファビング対策としては「仕事の魅力を高める」ことが効果的だと考えられます。退屈感が引き金になるなら、会議や打ち合わせをより魅力的で参加者全員が関与できる形式にするなど、場の活性化が重要です。
意図的なファビング
これまでファビングの負の側面に焦点を当ててきましたが、すべてのスマートフォン使用が悪影響をもたらすわけではありません。時にはスマートフォンを介したコミュニケーションが対面での会話を補完し、豊かにすることもあります。
例えば、電気工事業や医療業界の従業員へのインタビュー調査では、スマートフォンを触る理由として「ストレス発散」や「外部との連絡」が挙げられました[15]。高度に連携が求められる現代の職場では、瞬時に情報を取得したり、離れた場所にいる関係者と連絡を取り合ったりする必要があります。そのような状況では、一時的なスマートフォン使用が業務の効率化につながることもあるでしょう。
また、スマートフォンを共有して画面を一緒に見るような使用法は、ファビングとは区別されるべきです。画面を共有することで会話そのものを深める可能性がある点が指摘されています。これは「同じコンテンツを共有する行為」であり、相手の存在を無視するファビングとは本質的に異なります。
心理的な回復という観点からも、一時的なスマートフォン使用には価値があるかもしれません。インタビュー調査では、スマートフォンが「個人的な空間へ逃げ込む手段」として機能することが語られました。対人関係に疲れを感じているときに、画面に集中することで一時的な休息を得られるのです。このような使用が適切な時間と場所で行われれば、むしろストレス軽減につながる可能性があります。
問題なのは、無自覚なファビングが繰り返されることです。意図的なファビング、つまり「今からちょっとスマートフォンを確認させてください」と前置きした上での使用であれば、相手に対する配慮を示すことができます。
したがって、ファビングを完全に否定するのではなく、その使用の「意図」と「タイミング」を意識することが求められます。例えば、会議の前に「緊急の連絡が入る可能性があるので、通知があればチェックさせてください」と伝えておくだけでも、相手の不快感は軽減されるでしょう。また、使用後に「お待たせしました」と一言添えることで、相手への敬意を示すことができます。
このように、ファビングをすべて排除するのではなく、意図的に行い、その意図を周囲と共有することが、デジタル時代のコミュニケーションにおいては重要な姿勢かもしれません。テクノロジーとの関わり方のバランスを見つけることが、現代社会に生きる私たちの課題です。
おわりに
スマートフォンの普及によって私たちのコミュニケーションは変化しました。対面での交流が希薄になる懸念がある一方で、テクノロジーが新たなつながりの形を生み出していることも事実です。ファビングという現象を通して、私たちは人間関係の本質や相手を尊重するという基本姿勢について改めて考える機会を得られます。
研究が示す通り、ファビングは対人関係、心理的健康、仕事の効率性など、多岐にわたる影響を私たちに及ぼしています。職場においては、上司と部下の信頼関係や組織全体の雰囲気に関わる大事な問題です。しかし同時に、適切な使用法を見つけることで、スマートフォンが私たちの生活や仕事を豊かにする可能性もあります。
無意識のうちに相手をないがしろにするのではなく、対面での交流とデジタル機器の使用のバランスを意識的に取ることが求められます。テクノロジーに翻弄されるのではなく、私たちがテクノロジーをコントロールし、より豊かなコミュニケーションを実現するための一歩として、ファビングという現象に向き合っていくと良いでしょう。
Q&A
Q:会議中のスマートフォン利用に関するガイドラインを作りたいのですが、作成する際にどういった点に気をつければよいでしょうか?
ガイドラインを作成する際には、「禁止」という形で「スマートフォンを使ってはいけません」というように制限するよりも、期待する行動を明確にしていくアプローチの方が効果的だと思います。例えば、「緊急の連絡が入る可能性がある場合には事前に共有しましょう」や「情報を調べるためにスマートフォンを利用する際には、その旨を周囲に伝えるようにしましょう」など、会議を円滑に進めるためのポジティブな行動指針を提示する方向性がうまくいきやすいでしょう。
とはいえ、ガイドラインを作ると、それが過度にルール化して独り歩きし、職場の雰囲気が息苦しくなる可能性もあります。そのため、会議の目的や種類によってはガイドラインの例外を設けたり、柔軟に運用できる余地を残したりすることもポイントです。
Q:ファビングをするという行為は、相手よりも優位な状況に立っているということを暗に示すためのものなのでしょうか?
必ずしもそうとは限りません。単純に癖になっていたり、通知が来たので見るといった条件反射的な行動であったりすることもあります。先ほど紹介した研究知見によれば、情報を見逃してしまうことへの不安という心理もファビングを促します。
ファビングは様々な理由で行われるものであり、必ずしも相手より優位に立っていることを示すために行うわけではありません。また、特定の立場の人だけがファビングを行うというわけでもなく、幅広い人々がファビングを行う可能性があります。
Q:ファビングの悪影響はスマートフォンに限定されるのでしょうか。会議中に明らかに会議とは関係ない業務をPCで行っている事例が散見されており、その風土も改善していきたいと思っています。
ファビングにはPhoneという言葉が含まれている通り、これはファビングの定義には厳密には当てはまらないかもしれません。しかし、ファビングと同じような原理が働いていると考えることはできます。会議と関係ない業務をしていると思われてしまうと、「自分がここにいる意味があるのか」と疑問を抱かせますし、自分が発言しているときにそのような行為をされたら不快に感じるでしょう。
逆に、対面の打ち合わせで、プロジェクターにPCを接続して議事録を一緒に作成したり画面を共有したりする場合、不快感は生じません。それは何をしているかが分かるため、自分がないがしろにされているとは思わないからです。
Q:テレワークとオフィスワークのハイブリッド環境では、ファビングの問題はどのように変化していくと予想しますか。
ハイブリッド環境においては、対面の価値が高まると思われます。対面で集中的に対話を行うことの重要性が増すでしょう。そうなると、対面時間の質を高めなければならないという意識も強くなるはずなので、ファビングの深刻度が増すのではないでしょうか。以前よりもファビングが深刻な問題になる可能性があります。
他方で、テレワークをしている人もいるため、「常につながっていなければならない」というプレッシャーも増すでしょう。これによって、ファビングを促す力が強く働く一方で、ファビングを行うとその悪影響がより深刻になるという難しい状況になるかもしれません。
Q:健全なスマートフォンの利用とファビングの境界線はどこにあるのでしょうか。一律に禁止するのではなく、これは許容される、これはマナー違反という基準を設けるとしたらどうなりますか。
明確に境界線を引くことは難しいですが、いくつか補助線を引くことはできるでしょう。一つは「意図を共有する」という観点です。例えば、「今から少し情報を調べてみますね」と言ってからスマートフォンを触るケースは許容されやすいでしょう。相手が自分をないがしろにされたとは思いにくいからです。行為の意図が相手に伝わっているかどうかが一つの基準になるでしょう。
もう一つは、スマホの画面を一緒に見るような場合は、ファビングには該当しないということです。これも結局、何をしているのかが分かるということが重要で、さらにスマートフォンを一緒に見ることで共同行為になっています。自分がないがしろにされるどころか、一緒に何かをしているという状態になるため、健全なスマートフォンの使用と言えるでしょう。
Q:ファビングが習慣化してしまっています。自分自身の行動を変えるための方法はありますか。無意識にスマートフォンを手に取ってしまいます。
ファビングの問題の一つは、知らないうちに手に取っている、自分が自覚していないというケースがあることです。対処法としては、まず客観視することです。自分がスマートフォンを手に取るのはどういうタイミングなのかを理解します。例えば、会議中に手に取る、緊張すると手に取る、退屈に感じると手に取るなど、自分のパターンを認識します。
そのパターンが見えてくると、別の行動に置き換えていくことができます。例えば、会話の間に知らないうちにスマートフォンを触ってしまうのであれば、代わりにメモを取るという行動に置き換えることができます。あるいは退屈してきたときには姿勢を変えるなど、別の行動を取ることで、習慣を少しずつ変えていくことができるでしょう。
環境のデザインも大切です。例えば、通知をオフにする、会議中は画面を下にしておく、振動に気づかないようにカバンに入れるなど、取りにくい場所に置くといった工夫をすることで、習慣化されたファビングを減らしていくことができるでしょう。
脚注
[1] Garrido, E. C., Issa, T., Gutierrez Esteban, P., and Cubo Delgado, S. (2021). A descriptive literature review of phubbing behaviors. Heliyon, 7(5), e07037.
[2] David, M. E., and Roberts, J. A. (2020). Developing and testing a scale designed to measure perceived phubbing. International journal of environmental research and public health, 17(21), 8152.
[3] Knausenberger, J., Giesen-Leuchter, A., and Echterhoff, G. (2022). Feeling ostracized by others’ smartphone use: The effect of phubbing on fundamental needs, mood, and trust. Frontiers in Psychology, 13, 883901.
[4] Abeele, M. M. V., Hendrickson, A. T., Pollmann, M. M., and Ling, R. (2019). Phubbing behavior in conversations and its relation to perceived conversation intimacy and distraction: An exploratory observation study. Computers in Human Behavior, 100, 35-47.
[5] Mantere, E., Savela, N., and Oksanen, A. (2021). Phubbing and social intelligence: Role-playing experiment on bystander inaccessibility. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(19), 10035.
[6] Martinsson, P., and Thomee, S. (2025). Co-worker phubbing: A qualitative exploration of smartphone use during work breaks. Scandinavian Journal of Psychology, 66(1), 158-173.
[7] Schmidt-Barad, T., and Chernyak-Hai, L. (2024). Phubbing Makes the Heart Grow Callous: Effects of Phubbing on Pro-social Behavioral Intentions, Empathy and Self-Control. Psychological Reports, 00332941241284917.
[8] Yao, S., and Nie, T. (2023). Boss, can’t you hear me? The impact mechanism of supervisor phone snubbing (phubbing) on employee psychological withdrawal behavior. Healthcare, 11(24), 3167.
[9] Saxena, A., & Srivastava, S. (2023). Is cyberloafing an outcome of supervisor phubbing: Examining the roles of workplace ostracism and psychological detachment. International Journal of Business Communication. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/23294884231172194
[10] Roberts, J. A., and David, M. E. (2017). Put down your phone and listen to me: How boss phubbing undermines the psychological conditions necessary for employee engagement. Computers in Human Behavior, 75, 206-217.
[11] Xu, T., Wang, T., and Duan, J. (2022). Leader phubbing and employee job performance: The effect of need for social approval. Psychology Research and Behavior Management, 15, 2303-2314.
[12] Buttner, C. M., Gloster, A. T., and Greifeneder, R. (2022). Your phone ruins our lunch: Attitudes, norms, and valuing the interaction predict phone use and phubbing in dyadic social interactions. Mobile Media & Communication, 10(3), 387-405.
[13] Schneider, F. M., and Hitzfeld, S. (2021). I ought to put down that phone but I phub nevertheless: Examining the predictors of phubbing behavior. Social Science Computer Review, 39(6), 1075-1088.
[14] Al-Saggaf, Y. (2021). Phubbing, fear of missing out and boredom. Journal of Technology in Behavioral Science, 6(2), 352-357.
[15] Martinsson, P., and Thomee, S. (2025). Co-worker phubbing: A qualitative exploration of smartphone use during work breaks. Scandinavian Journal of Psychology, 66(1), 158-173.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。