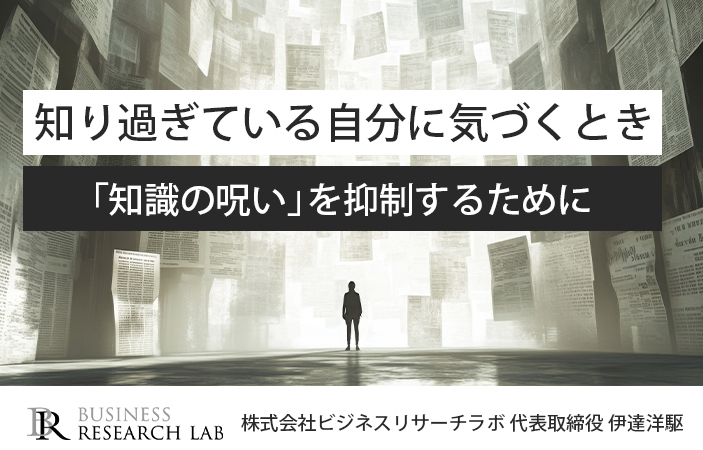2025年5月8日
知り過ぎている自分に気づくとき:「知識の呪い」を抑制するために
人は自分の知識や経験を土台にして物事を考えますが、その一方で、いざ他者の視点を理解しようとすると、自分がすでに持っている情報から離れられなくなることがあります。これは「知識の呪い」と呼ばれる現象です。
周囲の人が知らないはずの情報を知っていると、その人がどんなふうに世界を見ているのかを正確につかみにくくなることがあります。子どもだけでなく、大人にも起こるとされており、職場におけるコミュニケーションにひそかな障壁を生んでいる可能性があります。
そこで本コラムでは、知識の呪いがどのような研究を通じて検討されてきたのかを見ながら、その現象の大きさや性質を考えていきます。先行研究では、事前の期待や知識が、人の判断や推測に影響を及ぼすことを示してきました。
ここでは実験手法や分析結果がどのように組み立てられ、何が発見されたのかを読み解きながら、大人が持つ認知的バイアスの姿を掘り下げます。読者の方々には、この現象の背景を理解し、身近な場面を見直すきっかけとしていただけると幸いです。
知識の呪いは意外に小さい
事前に知っている情報が誤信念推論にどの程度関わるのかを大規模サンプルの実験で確かめようとした取り組みがあります[1]。成人を対象とした被験者デザインを多数組み込み、合計で7つの実験を行っています。誤信念課題で自己中心的な誤りを起こす度合いが、以前報告された数字より小さいかもしれないという見通しが語られています。
第一の実験では、知識の妥当性を操作した条件下でも、想定されていた誤信念推論の偏りがほぼ確認されませんでした。とりわけ、赤い容器に関する知識をもつ状況では、過去の文献で言われていたほど顕著な偏りが生じませんでした。この時点で、研究者たちは実際の誤信念推論における知識の作用を慎重に検討する必要があると考え、連続する実験を追加で実施しています。
次の実験群では、容器の色や位置がどれくらい筋の通ったものか(妥当性)を変えながら、回答がどう変化するかを比較しています。知識があると赤い容器を優先して評価しやすくなることは確かめられましたが、その度合いは当初示されていたレベルに比べると微弱でした。赤い容器の評価が高まる条件とそうでない条件の差分を計測したところ、平均的な差はやや存在するものの、有意とは言い切れないパターンも含まれていました。
その後の実験では、以前の研究と似通った傾向が得られつつも、知識があるかどうかで生じる数値上の開きが小さいと報告されています。誤信念推論に何らかの形で知識の呪いがかかわっているのではないかという仮説は排除されなかったものの、それを大きく裏付ける結果にも至りませんでした。中には、知識をもつ集団の方が回答を控えめに見積もる可能性が示唆されており、単純な自己中心バイアスだけでは説明しにくい複雑な認知過程があるのかもしれません。
最後に行われた統合的な分析(メタ分析的手法を用いた評価)では、個々の実験における誤信念推論の誤差をまとめて数値化し、知識の呪いがどれほど広く再現可能かを検証しています。その結果、もとの研究が想定していた効果量をおおむね半分以下にとどめる推定値が得られ、加えて妥当性操作に関しても先行文献の三分の一ほどに縮小されました。以前の報告をもとに実験を組むと、統計上の検出力が十分でない可能性があり、本来の誤差範囲を正確にとらえられなかったのではないかという指摘がなされています。
こうした視点から、成人の誤信念推論で「知識の呪い」が果たしている作用は思ったほど大きくないかもしれない、という見解が浮かび上がります。研究者たちは、知識が存在する場面でも人が他者の思考を読む際のずれは意外に限定的で、別の要因や状況によって変動する余地が大きいのではないかとしています。
大人も知識の呪いに陥る
幼児が他者の誤った信念を理解するのは難しいという話は聞かれます。代表的な実験では、人形がある場所に物を隠したあと、別の人形が勝手に持ち出して別のところに置いてしまう場面を子どもに示し、最初の人形がどこを探すかを当てさせる手法があります。小さな子どもは、自分が見ていた移動の事実を他の人形も知っているように思い込み、本来とは違う場所を答えがわりにします。これは、子どもの認知能力や概念理解が未熟なためという説が提起されてきましたが、別の観点として、事の結果を知っていることで他者の立場を考える力が阻害される可能性も考慮されています。
成人の世界でも、よく似たバイアスがあるのではないかという発想から、大人を対象とした誤信念課題を工夫し、複数の条件を設定して検証した研究があります[2]。参加者に、音楽家がバイオリンをどの箱にしまったか、そのあと部屋の中でどのように位置が変えられたかといった情報を示し、それが妥当だと思われる移動かどうかを分類させたうえで、当事者が最初に探しそうな箱の割合を数値で答えさせたのです。この場面では、赤い箱が元の場所と似た印象を与える場合や、そうでない紫色の箱が提示される場合など、いくつかの条件が用意されていました。
結果によると、参加者は移動の事実を知らされていない場合、元の箱を探す確率を高く見積もります。しかし、移動先が赤くて元の箱と見た目が近いとされると、自分の知識を手がかりに、演奏者も同じようにその赤い箱を疑うのではないかと推測する率が高まります。その一方で、紫色の箱のように一見してつながりが薄い移動先の場合は、大きな変化は生じにくいとされています。
こうした結果は大人のように推論力が十分に育っている状況でも、知っている情報が無意識に混ざり込み、情報を共有していないはずの相手にも同じ事実を知っているかのように想定してしまう危険性があると考えられます。ただ、実験の条件によっては知識の妥当性の認識が関係し、赤い箱の移動には納得感があるが紫色の箱にはそうした感覚がない、といった個人的な判断基準が結果を左右する側面も見いだされました。
この研究では幼児の段階で顕在化する誤信念課題の失敗と、大人が陥る知識のバイアスとをつなぎ合わせる視点が提示されています。まだ言語や概念の理解が不十分な子どもと、認知力は十分な成人との間でも、知っていることを切り離す作業には共通する難しさがあるのではないかというのです。大人の場合は、そもそも他者と同じ情報を持っていないかもしれないという念頭はあっても、移動先が「もっともらしい」場合にはつい同じ認識を共有していると見なしてしまうということです。
ここでは、子どもは思考能力が低くて誤信念を誤って判断するわけではなく、いわゆる「知識の呪い」という認知のゆがみが大人にも通じることが強調されています。先に見た「意外に小さいかもしれない」という知見とは別の角度から、大人にとってもこの現象が無縁ではないという事例が浮かび上がっています。
知識の呪いは指示でも消えない
「コミュニケーションにおいて情報を持たない相手を意識しなさい」という指示を与えれば、知識の呪いによる誤った思い込みが薄れるかどうかを調べた事例があります[3]。皮肉を含んだ発言を聞き手がどう捉えるかという場面をつくり、参加者に「話し手と聞き手で共有されていない情報」に特に注意してほしいと明言しました。この段階で多くの人が、あたかも相手が見えていない部分まで共有していると思い込まないように心がけるだろう、と予想されるかもしれません。
実際の手続きとしては、話し手が特定の意図(皮肉を込めて言っている、など)を持って発話しているという事実を、参加者だけが知るという設定にします。その上で、聞き手にはそうした意図が開示されていない状態を想定させ、聞き手がどのような解釈をするかを見積もってもらうのです。
研究者は一部の参加者に対して、聞き手の視点を強く意識するためのセッションを入れ、そこでは「自分とは違う情報しか持っていない人」を思い描く訓練的な操作を加えました。興味深いのは、そうした操作があった群とそうでない群を比較しても、知識の呪いが消えなかったということです。
被験者は、皮肉の意図を知った上であれば、聞き手も同じように皮肉として理解すると推測します。そして、その推測を修正しようとしても、視点取得の意識づけだけでは十分ではなかったのです。これは、言語理解の過程における抑制の難しさや、最初に抱いた情報を押しとどめる認知的負荷が大きいことなどが要因として考えられます。たとえ他者の視点を念頭においても、自分の中にある知識が優先されてしまい、聞き手の認識を過小評価しにくいわけです。
加えて、教育歴などによる個人差も見受けられ、学習経験が少ない人のほうが特権的な情報に左右されやすいことが示されました。ここでは言語処理や認知制御力の違いが、相手の理解度を考慮できるかどうかに関係している可能性が示唆されています。なお、実験で提示するシナリオの順番を変えると、最初に肯定的な発話例を見てしまった参加者が、後に出てくる皮肉な発言をより皮肉らしく捉えてしまうケースも確認されました。
こうした結果から、視点取得の大切さを頭でわかっていても、それだけでは知識の呪いを回避しきれない面が明確になったと言えます。
知識の呪いは反論で消える
監査の判断に関する研究でも、知識の呪いに相当する偏りが観察されています[4]。財務情報の審査や、企業が今後も事業を続けられるかどうかを見極める場面で、事前に破綻を知ってしまった後から監査資料を振り返ると、破綻の兆候を過大に評価してしまう可能性があります。
実験では、専門知識をもつ監査人と経営学の学生を比較し、どちらもすでに結果を知っていると他者の推測を高く見積もる偏りが出ることが確認されました。ここで「説明責任」を課しても、その偏りは下がらなかったとされます。判断の質は努力だけでは変化しないという指摘と合致するかもしれません。
経験のある監査人ですら、先入観を払拭しきれない事例が示されています。逆に努力や能力が高いほど、一度手に入った情報を後から切り離すのはかえって難しくなるという見方もあります。こうした結果を踏まえて別の実験が行われた際、面白い展開が報告されました。反論を作成するという操作により、起こらなかった可能性を考え、破綻に至らないシナリオを思い描くプロセスを課したところ、知識の呪いに該当する偏りが抑制されたのです。
その実験では、被験者に対して高い販売数が出た結果と低い販売数が出た結果を提示し、それぞれ別の集団が知らない前提で予測を行わせました。結果を認知していると本来よりも高めあるいは低めに予想を寄せてしまう現象が確かに見られたものの、起こらなかった展開を頭の中で組み立てる作業を追加すると、そうした偏りが見当たらなくなりました。
なぜこの操作が特別に働いたのかについては、認知心理学でいうところの代替シナリオを丁寧に生成することで、一方的に固まっていた思考を緩める効果があったという解釈がなされています。ほかの手法(説明責任の強化や単純なインセンティブなど)では達成しにくかったため、こうした反論形成の意味合いは重要だと考えられます。
認識のずれを埋める
ここまで見てきたように、知識の呪いは必ずしも極端な形で働くわけではありませんが、大人でも思いがけず思考を偏らせる一因となることがうかがえます。結果を先に知っていると、他者の視点を適切に捉えることが難しくなり、誤信念課題やコミュニケーション上の推測にゆがみを生じさせるかもしれません。
とりわけ職場では、専門知識をもつ人とそうでない人の間に認識のずれが生じやすく、必要な情報共有がうまくいかなくなる恐れがあります。そこで組織や管理者は、このズレをどのように扱うかを考えるだけでも意味があるでしょう。
実務の観点からは、ある特定の知識が及ぼす力を自覚し、別の視点も想定しやすくする工夫が望まれます。その際、誰かに責任を求めるだけでは十分でないと各実験からうかがえるため、もっと効果的な方法を模索する余地がありそうです。同時に、そうした取り組みは当事者だけでなく周囲にも理解されると、結果として職場のコミュニケーションに安定感を与える可能性があります。
知識の呪いが完全に消えるわけではなくても、偏りを意識し合うだけで誤解を減らすきっかけになるかもしれません。実際、監査や言語理解の場面で報告されてきたように、いかに認知の歪みが生まれ、それがどのように続いてしまうかを検討する作業そのものが、組織全体での視点共有を促進する手がかりになり得ます。そうした視点を踏まえて、知識の呪いを一度見直してみることは、コミュニケーションの難しさを改めて理解するうえで意味があるでしょう。
脚注
[1] Ryskin, R. A., and Brown-Schmidt, S. (2014). Do adults show a curse of knowledge in false-belief reasoning? A robust estimate of the true effect size. PloS one, 9(3), e92406.
[2] Birch, S. A., and Bloom, P. (2007). The curse of knowledge in reasoning about false beliefs. Psychological Science, 18(5), 382-386.
[3] Damen, D., van der Wijst, P., van Amelsvoort, M., and Krahmer, E. (2018). The curse of knowing: The influence of explicit perspective-awareness instructions on perceivers’ perspective-taking. In Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Cognitive Science Society (pp. 235-240).
[4] Kennedy, J. (1995). Debiasing the curse of knowledge in audit judgment. Accounting Review, 249-273.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。