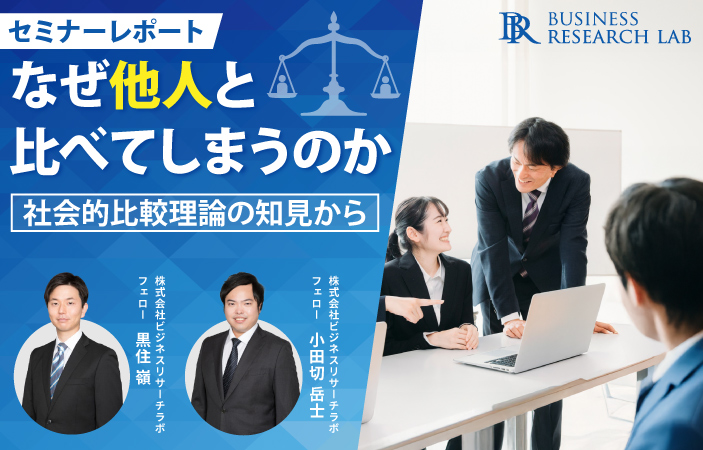2025年5月7日
なぜ他人と比べてしまうのか:社会的比較理論の知見から(セミナーレポート)
株式会社ビジネスリサーチラボは、2025年4月にオンラインセミナー「なぜ他人と比べてしまうのか:社会的比較理論の知見から」を開催しました。
「自分と比べて、あの人は何だかうまくいっている気がする」などと思ったことがある方は少なくないでしょう。逆に、「自分もあのようになりたい」と憧れを持ち、日々の仕事にやる気を感じることもあるかもしれません。
こうした「人と比べる心理」は、なぜ・どのように起こっているのか。また、そのような心理を、一人ひとりのパフォーマンスを高め、組織を成長させる力に変えるには、どうすればよいのか。この問いに答えるべく、本セミナーでは、学術的な観点から「人と比べる心理」に関する理論や研究知見を紹介し、その心理が組織内でのパフォーマンスとどのように結びつくかについて検討しました。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
研究知見から紐解く社会的比較
社会的比較はなぜ起きるのか
小田切:
社会的比較とは、「人が自分の意見や能力を評価するために、他人と比べる心の働き」[1]であり、「社会的比較理論」と呼ばれる理論によって説明されています。その社会的比較理論の中身について、要点をご紹介していきます。
この理論によると、人が他人と自分を比較する理由は、人間に「自分の価値を確かめたい」という根本的な欲求があるから、とされています。
前提として、人間には「自分の考えや能力に価値があるのかどうかを確かめたい」という、根源的な欲求があります。その前提のもとで、絶対的な評価基準が存在しない場合、人は他人と比較することで、自分の考えや能力の価値を測ろうとします。たとえば、自分のプレゼンを上司や同僚のものと比べたり、人事評価やSNS上の友人の生活と自分の状況を比較して判断したりする、といった行動が挙げられます。
どのような相手と比較するのか
最初の視点は、「目的によって比較する相手を選んでいる」という点です。比較には、大きく分けて二つのタイプがあります。
一つは「上方比較」で、自分よりも優れているように見える相手と比較することを表します。上方比較は、「より良い自分になりたい」「もっと成長したい」といった目的を背景に行われます。
もう一つは「下方比較」で、自分よりも劣っていると感じる相手を比較することです。下方比較は、「自分には価値があると思いたい」「安心したい」といった感情が背景にあります。
次の視点は、「自分と似た相手を比較対象にしやすい」という点です。まず、年齢や性別、職場などの「属性が自分と近い人」と比較する傾向があります。なぜなら、同じ条件下の人と比較することで、より正確に自分を評価できると考えられているからです。たとえば、20代の新卒社員がベテラン社員と生活水準を比べることは少なく、同期や同年代の他社社員と比較する方が自然です。
また、「考え方や能力が似ている人」も比較対象になりやすいです。これは、自分の能力が妥当なものであるかを確かめるためです。たとえば、難しいプロジェクトに取り組んでいて、それを同期も難しいと感じていると知れば、「自分の能力のせいではなく、プロジェクト自体が難しい」と安心できます。
補足として、「社会的な環境」も大きく影響していると考えられます。キャリアや生活水準、幸福感などは、相対的な評価が伴うことが多く、つい無意識に比較してしまいます。もちろん、人間の本質的な欲求が比較を促す面もありますが、私たちが暮らす社会そのものが「他人と比較せざるを得ない環境」であるということも見逃せません。
社会的比較がもたらすもの
上方比較がもたらすもの
上方比較は「相反する効果をもたらす」とされています[2]。仕事への満足感や業務パフォーマンスが向上することもあれば、逆に低下する場合もあります。このような真逆の結果が生まれる理由の一つは、「上方比較によって異なる感情が生まれること」にあります[3]。
一つは、他人の成功を前向きに受け取り、自分の努力を後押しする感情です。たとえば、同僚の昇進を見て「自分も頑張ろう」と思ったり、友人のダイエット成功に刺激を受けて運動を始めたりするような気持ちです。
一方で、他人の成功を「脅威」と感じてしまい、否定的な感情が生まれることもあります。たとえば、昇進した同僚を悪く言いたくなったり、「あれは運が良かっただけ」と思ってしまったりするようなケースです。
つまり、それぞれの感情が生み出された結果として、相反する効果が生まれるのです。前向きな感情が生まれると、仕事への意欲や成長意識が高まり、パフォーマンスの向上につながります。逆に、否定的な感情が強まると、陰口や非協力的な行動、締め切りを守らないなどの「非生産的な行動」が増える傾向があります[4]。
下方比較がもたらすもの
下方比較には、「安心感」や「自尊心の向上」といった効果があります。不安が和らいだり、自分の価値を感じられたり、仕事の満足度が高まるといった点が研究で示されています[5]。
ただし、下方比較にはネガティブな側面もあります。安心感を得る一方で、不安や不快感を抱くこともあるのです[6]。たとえば、病院で自分より重い症状の人を見て安心する反面、「自分も悪化するかも」と不安になることがあります。また、職場で自分より能力の低い人を見たとき、「自分が支えなければ」と負担を感じたり、「この人のせいで仕事が進まない」と不満を覚えたりすることもあります。
このように、下方比較にもポジティブな効果とネガティブな効果の両方が存在することがわかっています。
施策が含む社会的比較に注目した改善案
黒住:
私のパートでは、実際の施策が含む社会的比較に注目し、それがどのように生じ、どのように活用できるのかを考察していきます。従業員が他人と自分を比較するのをやめるのは難しいため、組織には「比較をどう活かすか」という視点が求められます。つまり、「比較をやめさせる」のではなく、「どうすれば前向きに活かせるか」を考えることが大切です。その前提で、施策に期待されるポジティブな効果を引き出し、ネガティブな効果をどう抑えるのか、3つの施策に注目して考えていきましょう。
表彰制度
自分への脅威による自己卑下が起こるリスク
まず取り上げるのは表彰制度です。この施策は一般的な取り組みで、本人だけでなく周囲の社員にも良い影響を与えると期待されています。たとえば、企業がエンゲージメント向上のために表彰を活用する例では、努力や成果が認められることで「もっと頑張ろう」と思える動機づけが生まれます。これは主に表彰される本人に対する効果です。一方、周囲の社員にとっても、「どんな行動が評価されるか」が明確になり、企業理念や価値観の共有に繋がります。
しかし「社会的比較」の観点から見ると、表彰制度にはポジティブな効果だけでなく、一定のリスクも存在することが指摘されています。そのリスクとは、表彰される社員を見る周囲の人が「自己卑下」を感じてしまう可能性があることです。
他者の優れた成果を目の当たりにしたとき、「自分にはあれほどの成果を出せない」「自分には価値がないのではないか」と、脅威を感じる場合があります。より細かい反応としては、自分よりも優れた成果を上げている人を見て、ネガティブな感情が喚起されることがあります。そして、そのネガティブな感情を整理しながら仕事に向き合おうとすると、集中力が下がったり、仕事への意欲が低下してしまったりすることも報告されています[7][8]。
さらに、自分が価値を発揮できない場にいることが心理的な負担となり、「逃避的な行動」につながるケースもあります。表彰制度を活用する際は、こうしたネガティブな影響にも目を向ける必要があります。
改善案:表彰の方法
自己卑下のリスクを抑えつつ表彰制度の良い効果を高めるには、表彰をどのようにするか、その方法に関する2つのポイントが重要です。1つ目は表彰される人との「関係性」、2つ目は表彰の「内容」です。「関係性」については、研究によると表彰される人と見る側の関係性が遠いほど、前向きな気持ちが生まれやすいとされています[9]。そこで、違う部署の社員が表彰される機会に触れられるようにするという改善案があります。
他の部署の人が表彰される場合は、自分と同じ部署の人と比べて関係性が遠いので「脅威」に感じにくく、「自分も頑張ろう」と思えるからです。そのため、部署を横断した表彰や、他部署を推薦できる仕組みが有効です。
たとえば、共同プロジェクトで他部署の社員に助けられた人を貢献者として推薦できる制度や、表彰を部署を超えて称賛し合う場の設置が考えられます。また、感謝の手紙を社内ツールなどで送る文化や、ピアボーナスのようにポイントで感謝を示す制度も、日常的に表彰の効果を広げる方法です。
次に、表彰の「内容」を工夫するという改善策もあります。特に、個人による大きな成果以外のを表彰する機会があると良いでしょう。優れた社員による目覚ましい成果だけが強調されていると、「そのような成果を上げるのは自分には無理だ」と自己卑下に繋がりやすくなるため、多様な評価基準を用意することが重要です。
たとえば、個人ではなくチーム単位の表彰や、「新しいやり方に挑戦した」「連携を深めた」といった努力や挑戦を表彰することが有効です。これらの評価対象は「成果」に比べて、周囲の社員が「自分にもできるかも」と感じやすくなります。このように、表彰の方法と内容を工夫することで、制度のポジティブな効果を高めながら、社会的比較によるリスクを抑えることができます。
メンター制度
実現不可能と感じて自己卑下がおこるリスク
次に取り上げるのはメンター制度です。先輩社員が後輩に知識や経験を伝える仕組みとして、メンター制度は多くの企業で導入されています。社内ルールや業務ノウハウの共有、悩み相談などを通じて、さまざまな効果が期待されています。
メンター制度に期待される効果の一つに、「ロールモデルとしての作用」があります。後輩が先輩の働き方を観察することで、タスク遂行にとって適切な方法を学んだり、「こうなりたい」と思える目標を持ち、動機づけにつながる効果があるとされています。メンター制度が機能すれば、こうした前向きな影響は大きなメリットです[10]。
しかし一方で、自己卑下のリスクもあります。優秀すぎる先輩を見て「自分は同じようにはできない」と感じると、かえってモチベーションが下がることがあります。本来は身近な目標としての先輩が望ましいのですが、目標が遠すぎると逆効果になるのです。研究でも、「自分にも目指せそう」と感じる場合にポジティブな影響があり、逆に「到底無理だ」と感じるとネガティブな影響が出ることが示されています[11]。
改善案:メンター候補者へのマネジメント
そこで、メンター制度の良さを活かしつつ、リスクを抑えるために、2つの改善ポイントを紹介します。いずれも、メンターを担当してもらう候補者に、マネジメントによって対策を講じます。
1点目は、「パフォーマンスの実現可能性」に注目することです。後輩にとって目標が高すぎる場合には自己卑下のリスクが生まれるため、逆に「この人なら自分も近づける」と感じられるように、メンターは「手が届きそうな目標」であることが理想です。
これを実現するには、企業側でメンター選出に工夫が必要です。たとえば、「ハイパフォーマー」はメンターの候補者からあえて外すこと、あるいは、ハイパフォーマーとのペアの経過に注意することが考えられます。新人にとっては距離がありすぎて逆効果になることがあるため代わりに、共に成長してもらうことを期待して「伸びしろのある若手社員」をメンターに任命するのが良いでしょう。
また、メンターを紹介する際に、その人の成長の過程を伝えるのも効果的です。「今では優秀だけども、失敗もしたし、苦労や努力をしてきた」というように紹介すると、現在のスキルとの対比だけでなく、より身近に感じられます。
2点目の工夫は、「メンターとの交流の質」を高めることです。メンターと後輩の交流において、どのような要因が、その教育効果を高めるのかをまとめた研究があります[12]。
その結果として、メンターがどんな考えや理由でその行動を選択したのかを伝えること(=認知プロセスの共有)と、具体的にどう実践すればいいのかを見せること(=行動の示範)が重要であると指摘されています。これらの結果を参考に、活動が開始される前の段階で研修を行い、後輩とどのように接するのが良いかを、メンターを担当する先輩社員と共有することが有効です。
たとえば、なるべく「共同作業」をするという方針が挙げられます。難易度に応じて作業を「分担」するよりも、一緒に取り組む中で、自然に意図や背景を伝えやすくなります。また、背伸びをせずに「ありのままで接してよい」と伝えることも重要です。メンターに「これまで以上に成果を出さねば」を気をはる必要はないことを共有し、自然体で後輩と向き合ってもらうことで、安心感のある関係が築かれます。
「失敗談」の共有
後から参照する人の成長にもつながるメリット
最後に取り上げるのが、失敗談を共有する場や施策についてです。プロジェクト終了後の反省会や、過去のトラブルや失敗を他の社員と共有し再発防止に努める取り組みは、多くの企業で実施されています。座談会形式で気軽に話すものや、体系的にまとめて企業資産として残すものなど、さまざまな形があります。
近年ではIT企業を中心に「ポストモーテム(post-mortem)」という手法も注目されています。これは失敗の原因を冷静に分析し、教訓や再発防止策を明文化してレポートに残す方法です。たとえば、インシデントやうまくいかなかった施策について、「なぜそうなったか」を深掘りし、経験を組織全体で共有します。
ポストモーテムに代表されるように、失敗共有の目的は主に再発防止です。原因を丁寧に分析し、効果的な対策へとつなげることが重要です。たとえばGoogleでは、インシデントの経緯や根本原因を詳しく分析し、具体的な対策に活かしていることが報告されています[13]。
こうした振り返りの機会は、原因分析や対策立案といった側面だけでなく、「社会的比較」の観点からは別の価値があると考えられます。具体的には、過去の失敗をまとめた資料を、後から読む人にとっての成長機会として活用するという視点です。
たとえば、自分が今問題を抱えていたり、うまくいっていないと感じていたりするときに、同じような状況で苦労した他者の事例を知ることで、「自分も頑張ろう」と前向きになれます。こうした心理的な効果が下方比較における現象として、研究でも指摘されています[14]。
改善案:当事者を意識できる記録と参照法
では、下方比較の観点で示唆されたメリットを、実際の施策として活かすためのポイントは何でしょうか。1つ目のポイントは、振り返りの資料を単なる事実の記録にとどめず、見る人がより共感しやすいような“人間らしさ”を残す工夫が有効です。
たとえば、失敗を振り返る際の記録に、当事者の声を残すという方法があります。「似たようなアラートが何度も出るので、緊急性が薄く感じられて対応を後回しにしてしまった」など当時の状況が語られていれば、読み手がよりリアルにイメージし、自分の経験と重ね合わせやすくなるため、成長の効果が得られやすくなるでしょう。
もう1つのポイントは、失敗の記録を参照する際に直接的に社会的比較を促すことです。過去の事例を参照する際に、「現在の自分の状況と、何が似ていて、どこが違うのか」も意識的に参照することを推奨するなど、社会的比較をより積極的に促すことができるでしょう。過去の事例を見て、「このプロジェクトではこう進めればよいのか」とハウツーを学ぶだけではなく、「今の自分の状況とどう重なるのか」「どんな教訓が活かせそうか」と考えてもらうことで、学びが深まると考えられます[15]。
Q&A
Q1:マウンティングも、下方比較によるものと考えられますか。
小田切:
自分より下だと見なす相手に対して優位性を示そうとする行動を「マウンティング」と言いますが、これは典型的な下方比較のパターンといえるでしょう。
Q2:学歴や過去の業績など、自分では今から変えることができない要素で下方比較をしてくる相手には、どう接すればよいでしょうか。
小田切:
大きく二つのステップがあると考えられます。まず一つ目は、私のパートでお話しした通り、「下方比較をする側は、自分に価値があると確認したい、安心したい」という心理からそのような行動をとるという点です。つまりマウンティングしてくる人は、今の自分に対して自信がない、あるいは能力に不安を感じている可能性があります。
ですので、まずはその背景を理解することが大切です。「この人は、自分に自信が持てないでいるのかもしれない」と、少し俯瞰的な視点で相手を見ることが、第一歩になるのではないかと思います。
二つ目のステップとしては、「今のその人の価値を認めてあげる」ことです。相手が不安を感じている状態なのであれば、「今のあなたにもこういう良いところがありますよ」とポジティブなフィードバックを行うことが効果的です。
Q3:「到達可能な相手」との比較が大切ならば、「自信がある人」はどのような相手からも良い影響を受けられるのでしょうか。
黒住:
研究の中で、「自己効力感(self-efficacy)」という概念があります。これは「自分は課題に対して適切に対応し、成功することができる」という感覚を指します。自己効力感が高い人ほど、社会的比較をしたときに、それを前向きに活用できる傾向があると言われています。ですので、自信がある人、自己効力感の高い人であれば、どのような相手からであっても学びを得やすいという側面があるのは確かです。
また、そうした自己効力感を高めるためには、小さな成功体験を積んでもらうことが有効です。さらに「失敗しても大丈夫」と思えるような、安心して挑戦できる環境を整えることも重要です。つまり、自信がある人ほど社会的比較をうまく活かせるという点はありますが、周囲が支援的な環境を作ることでも、自己卑下の可能性を下げられるといえます。
脚注
[1] Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human relations, 7(2), 117-140. https://doi.org/10.1177/001872675400700202
[2] Sterling, C. M. (2013). A tale of two envys: A social network perspective on the consequences of workplace social comparison. Theses and Dissertations–Management. 5. https://uknowledge.uky.edu/management_etds/5
[3] Li, Y., & Wang, S. (2023). “Comparisons are Odious”?—Exploring the dual effect of upward social comparison on workplace coping behaviors of temporary agency workers. Psychology Research and Behavior Management, 4251-4265. https://doi.org/10.1007/s12144-022-02999-y
[4] Crusius, J., Gonzalez, M. F., Lange, J., & Cohen-Charash, Y. (2020). Envy: An adversarial review and comparison of two competing views. Emotion Review, 12(1), 3-21. https://doi.org/10.1177/1754073919873131
[5] Yang, Y., & Chae, H. (2023). The Effect of Downward Social Comparison on Creativity in Organizational Teams, with the Moderation of Narcissism and the Mediation of Negative Affect. Behavioral Sciences, 13(8), 633. https://doi.org/10.3390/bs13080633
[6] 脚注5 (Yang & Chae, 2023)と同じ
[7] Muller, D., & Fayant, M. P. (2010). On being exposed to superior others: Consequences of self‐threatening upward social comparisons. Social and Personality Psychology Compass, 4(8), 621-634.
[8] 脚注2(Sterling, 2013)と同じ
[9] 脚注2(Sterling, 2013)と同じ
[10] Abbasianchavari, A., & Moritz, A. (2020). The impact of role models on entrepreneurial intentions and behavior: a review of the literature. Management Review Quarterly, 71, 1-40. https://doi.org/10.1007/s11301-019-00179-0. の研究を参考
[11] Lockwood, P., & Kunda, Z. (1997). Superstars and me: Predicting the impact of role models on the self. Journal of personality and social psychology, 73(1), 91–103. https://doi.org/10.1037/0022-3514.73.1.91
[12] Mok, S., & Staub, F. (2021). Does coaching, mentoring, and supervision matter for pre-service teachers’ planning skills and clarity of instruction? A meta-analysis of (quasi-)experimental studies. Teaching and Teacher Education, 107, 103484. https://doi.org/10.1016/J.TATE.2021.103484. の研究を参考
[13] Google. (2017). Example postmortem. Google SRE. https://sre.google/sre-book/example-postmortem/ (最終アクセス:2025年4月16日)
[14] Nie, T., Wu, J., & Yan, Q. (2024). Facilitation or hindrance? The impact of downward social comparison on adversarial growth. Frontiers in Psychology, 15, 1307393.
[15] 脚注14(Nie, Wu, & Yan, 2024)と同じ
登壇者

黒住 嶺 株式会社ビジネスリサーチラボ フェロー
学習院大学文学部卒業、学習院大学人文科学研究科修士課程修了、筑波大学人間総合科学研究科心理学専攻博士後期課程満期退学。修士(心理学)。日常生活の素朴な疑問や誰しも経験しうる悩みを、学術的なアプローチで検証・解決することに関心があり、自身も幼少期から苦悩してきた先延ばしに関する研究を実施。教育機関やセミナーでの講師、ベンチャー企業でのインターンなどを通し、学術的な視点と現場や当事者の視点の行き来を志向・実践。その経験を活かし、多くの当事者との接点となりうる組織・人事の課題への実効的なアプローチを探求している。

小田切 岳士 株式会社ビジネスリサーチラボ フェロー
同志社大学心理学部卒業、京都文教大学大学院臨床心理学研究科博士課程(前期)修了。修士(臨床心理学)。公認心理師。働く個人を対象にカウンセラーとしてのキャリアをスタート。その後、企業人事として制度・施策の設計・運用などに携わる。現在は主な対象を企業や組織とし、臨床心理学や産業・組織心理学の知見をベースに経営学の観点を加えた「個人が健康に働き組織が活性化する」ための実践を行っている。特に、改正労働安全衛生法による「ストレスチェック」の集団分析結果に基づく職場環境改善コンサルティングや、職場活性化ワークショップの企画・ファシリテーションなどを多数実施している。