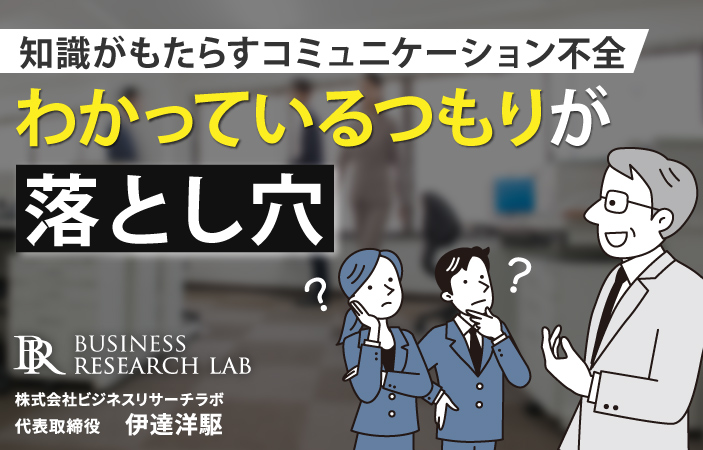2025年5月2日
わかっているつもりが落とし穴:知識がもたらすコミュニケーション不全
ある知識を持っていると、その知識を持たない相手の視点を想像しにくくなるという現象があります。日常会話でも仕事の場でも、このような状態に陥るとコミュニケーションがうまく進まなくなります。伝えたいことを正しく伝えているつもりでも、受け手は全く違う解釈をしてしまうことがあるからです。こうしたすれ違いは、深刻な局面では重大な問題につながりかねません。
専門用語を使う側は当然のように使っていても、知らない側にとっては意味が分からず誤解が生じます。この溝が大きくなると、組織内の意思疎通や共同作業が難しくなるだけでなく、業務の決定過程にも悪い歪みが発生するかもしれません。知識とは本来、仕事の質を高める助けになるものですが、ある条件下では却って足かせにもなり得ます。
本コラムでは、そのような知識が陥らせる落とし穴について、いくつかの研究を参照しつつ整理していきます。この問題が投資判断や福祉、教育、そして競争心にどのように関わるかを、過去の実験や理論検討を踏まえて紐解いていきます。
知識の呪いが投資を歪める
企業内で投資判断を行う際、社内の情報をどのように共有し解釈するかは大事だと考えられています。ある研究では、組織内のコミュニケーションを調べるために、経営者と投資判断を任される管理職の間で情報がどのようにやりとりされるかをモデル化し、実証的な分析を行っています[1]。その際、管理職が抱える知識の深さが利点になる面だけでなく、問題点を生むケースも確認されました。
研究においては、架空の企業を仮定し、経営者と担当管理職を想定した実験的手法が用いられました。担当管理職は製品開発や研究開発にまつわる情報を取得するために一定のコストを支払うことができますが、その情報が真に有用か否かを現場ですぐに判断しきれないという設定になっています。いわば、どこまで深く調べるかが自分にも分からず、思い込みに左右されやすい構造になっているのです。
無作為にグループを分け、管理職役にさまざまな追加情報を付与した群と、追加の説明を受けていない群を比較したところ、情報量が多い群のほうが投資判断に先んじて必要と思われるデータを熱心に集める一方、経営者に報告するときの言葉づかいは短くなり、重要な点を丁寧に説明しない傾向がありました。こうした報告の省略は、経営者がそれほど情報に精通していないときに決定過程を歪め、企業全体の価値を下げる結果につながります。
実験の結果からは、知識を持つ側が自分の理解と相手の理解を同じレベルにあると錯覚してしまうと、意思疎通がかえって乏しくなる可能性が浮かび上がりました。情報収集を積み重ねると、管理職は状況を深く理解しているつもりになります。しかしそのために、相手側も当然この程度は把握しているはずだ、といった想定をしてしまうのです。
この想定が成り立たない場合、経営者側は管理職が発する概念や用語の意味を取り違えたり、大事な裏付けを聞かされずに投資を決めてしまったりするリスクを抱えます。結果として、投資案件が不適当な方向へ流れ、全体の利益が損なわれる可能性を無視できません。
ただ、情報を深く入手する行為そのものは、研究開発であれ新技術導入であれ、組織にとって有益な発見をもたらす場合があるため、知識が増えること自体を否定するわけにはいかないという見方も提示されています。実際、管理職が積極的に知見を集めたおかげで成果が向上した場面も観察されています。知識を得ることは価値創出につながる一方、共有の段階で誤った前提を抱えてしまう点にリスクがあるということです。
知識の呪いが福祉を低下させる
人々の行動が互いに関係し合う場面では、各個人がどれだけ多くの知識を持つかが集団全体の利害に関わってくると考えられます。ある研究では、知識が社会にとって常に望ましいわけではなく、集団の水準を逆に下げる場合があると論じられています[2]。その論文で取り上げられた事例では、複数の個人が自分の利益だけを追求するとき、多くの情報を持つほどかえって協力し合わなくなると指摘されています。
理論部分では、進化ゲーム理論を応用したモデルが提示されました。個々の参加者は、ある種の2×2ゲームを繰り返し実行する想定で、その際に状態Aか状態Bかが発生する確率が示されます。各自がどの行動をとるかで得られる報酬が変わる仕組みです。このとき、参加者がどちらの状態かを知らないほうが、結果として平均報酬が高まる場面が確認されました。情報を手にしたがために行動が変わり、全体的には望ましくない方向へ誘導される可能性があります。
同じ研究において、知識のあるタイプのプレイヤーと、知識をもたないタイプのプレイヤーを混在させたときのシミュレーションも行われました。その結果、知識を有するプレイヤーは短期的に見ると高い報酬を得るため、生き残りやすいものの、全員が知識を持つ方向に偏ると、協力的な戦略が崩れて集団としての平均水準が下がってしまう局面があります。
具体例のひとつとして、感染症対策におけるマスク着用が挙げられていました。マスクの有効性やウイルスの性質を深く知る個人が増えた結果、自分にとってリスクが小さいと判断するとマスクをしなくなる人が出てきます。それが多数の人の行動に波及し、最終的には集団全体の衛生水準が下がる帰結が論じられています。みんなが無知ならばとにかく用心に走るものの、中途半端に理解があるときこそ油断が生まれやすい、ということです。
論文の後半では、知識を持たない層が生き残るケースにも触れられています。知識のある集団どうしが競合するとお互い警戒してしまい、利益を得にくくなるという動きを数理的に描いた結果、それほど知識がない人々が逆に有利になる状況も想定されるようです。
情報が豊富になればなるほど良いという単純な図式に、一石を投じた研究だと言えるでしょう。大きな規模で見ると、人々が共有する知識が増大することで損なわれる協力行動がある、という主張は目を引きます。一方、まったく知識がなければ別の問題が出てくるため、どの程度の情報が社会に流通しているかによって全体の帰結が変わってくるのではないかと考えられます。
知識の呪いで物理教育がうまくいかなくなる
物理を教える現場でも、専門家が当たり前に感じていることを初心者には理解しにくい場合があります。ある論考では、物理の教授が学生に教えるとき、自分が当たり前に思っている概念を学習者がまだ把握できていない可能性を軽視することがあると指摘されています[3]。その結果、教わる側は十分に基礎を固められないまま先の話を聞かされることになり、学習効果が下がってしまいます。
物理の授業風景を観察したり、学生の回答を分析したりして、その原因を探った調査が報告されています。専門家になるまでに長い時間をかけて身につけた思考様式は、学生の視点との間に隔たりを生みます。問題演習を実施すると、教える側には容易に感じられる計算でも、学習者にとってはとらえどころが分からない難問に映ることがあります。講師はどうしてそれが分からないのか理解できず、逆に学生はどこが分からないかを明確に伝えられない状況が生じます。
講義形式の授業を行って試験で点数を測定し、その結果をもとに学習の進捗を推定する方法についても懸念が示されています。答案の表面上の正答率だけを見ても、学生の頭の中にどういった誤解が残っているかまでは把握しにくいからです。問題の解決手順を丸暗記しているだけで、本質的な理解には至っていない例があるかもしれません。これは、知識のある教員が「このように教えれば伝わっているはずだ」と思い込む気持ちと対応している部分があります。
さらに、少人数クラスで対話型の学習を取り入れたグループと、大人数の講義中心のグループを比較したところ、テストの得点が違ったという研究も示されています。前者では実際に自分たちで問題に取り組むプロセスが重んじられ、その途中で出てくる疑問を意欲的に語り合う機会があった結果、誤解が早期に発覚して修正されました。後者では、黒板やスライドを使った講義を中心に進めることで、「教員はこれくらい説明すれば伝わる」と考えてしまう状況が見受けられました。
ただ、この現象を単純に「教師の力不足」とみなすのは誤解かもしれません。教員が知識をたくさん持っているほど、学生との思考ギャップを想像しにくくなるという側面が認められるからです。専門家である講師は、自分が学んできた過程を思い返すとき、多くのステップを短絡的にまとめてしまいます。そこに、学び始めたばかりの人の躓きポイントを推し量れない要因が存在しています。
専門家の脳は特定の問題を素早くパターン認識できるよう変化している一方、初心者はまず目の前の事象をどう分類すればいいかさえつかめません。専門家が「これはこういうことですよね」と言っても、前提が共有されていないため、会話がかみ合わないまま進んでしまいます。
知識の呪いは競争心を高める
ある実験では、問題の解答を一足先に知っている人が、そうでない人より自分の成績を高く見積もりやすいという結果が得られていました[4]。研究のデザインはおおむね次のような流れです。
被験者たちにクイズや作業タスクを解いてもらうにあたり、一部のグループには事前に正しい答えやヒントを知らせます。他方のグループには何も知らせず、純粋に自力だけで回答してもらいます。その後、参加者それぞれに「他の人と比べて、自分は何番目くらいの順位になると思うか」「勝ち残り式の競争に参加するかどうか」といった質問を行うのです。
事前に答えを聞かされていたグループは、タスクの難度を低く認識しやすく、他者の成績も高めに予想しつつ、自分が競争で勝ち残れる確率をさらに過大に見込みました。実際に競合相手の過去のスコアを見せられた場合でも、「自分ならもっと高い点を取れるはず」と考えて競争参加を選ぶ割合が高まりました。このような過剰な自己評価は、本来あまり成績が高くない層ほど強く表れたと報告されています。
実験を細かくみると、他者の成績を推定させる段階では、「答えを事前に知っていたグループ」は、そうでないグループに比べて他者の得点を高めに見積もっていました。これは、答えを知っている側が「このタスクは簡単だ」と思い込み、だから他の人もスムーズに解けるだろうと考える心理を反映しています。一方、自分の成績を推定するときには、他者の得点以上に自分の点数を高く見込み、「自分なら競争で勝てる」と感じる度合いが増しました。
実際に競争に参加するかどうかを選んでもらったところ、事前情報を得ていたグループは、そうでないグループと比べて参戦しようとする割合が高かったとされています。その上、報酬をどの程度なら参加するかという基準額を設定してもらった場合も、事前情報を持つ側が高めの水準を提示していました。自分は勝ち残れるだろうとの前提で、報酬に対する要求も強気になるということです。
このように、一部の情報を先に知っていたり、過去の成功談を聞いていたりすると、自分の勝算を勘違いしてしまう可能性があります。特に他者と比較して「自分ならできる」と思い込むプロセスの根底に、タスクの難しさを実際よりも軽く見積もってしまう錯覚があるという点は興味深いところです。
理解の非対称性
ここまで見てきたように、ある知識を備えた人ほど、その知識を持たない相手の状態を推し量れなくなる側面があります。企業で投資判断を下すときも、社会全体で協力が試されるときも、教育の場でも、そして競争の状況でも、この認知的な落とし穴が作用してコミュニケーションや行動選択が変わってしまいます。それは誤解を生むだけにとどまらず、組織内外の意思決定の方向をゆがめたり、集合的な成果を損なったりし得ます。
この現象は人材育成や情報共有をめぐるやり取りの各所に潜むと考えられます。ベテランが自分の経験から得た見通しを当然のこととして語れば、新人は根本的な理解が抜け落ちたまま仕事を進めてしまうかもしれません。リーダーが組織の方針を示す際も、自らの見解が共有されていると誤信してしまう可能性は否定できません。知識が増えれば多方面で助けになる一方、それを持つ人間と持たない人間との間で溝が生まれる危うさがあるのです。
現場では、こうしたすれ違いが不満の原因となったり、非効率な意思決定につながったりするでしょう。本人にその気はなくとも、相手を置いてきぼりにするような話し方をしてしまい、成果を下げてしまうこともあり得ます。
それだけに、この認知的な落とし穴を念頭に置いておくことは有用だと思います。専門知識を持つ人ほど、自分がわざわざ説明しなくても相手は分かっているはずだと思いやすい点を踏まえるなら、職場の意思疎通やリーダーシップのあり方などを考察する際に、見逃せない要素になります。
脚注
[1] Banerjee, S., Davis, J., and Gondhi, N. (2020). The man(ager) who knew too much. SSRN Electronic Journal.
[2] Basu, K., and Weibull, J. (2024). A knowledge curse: how knowledge can reduce human welfare. Royal Society Open Science, 11(8), 240358.
[3] Wieman, C. E. (2007). The “curse of knowledge,” or why intuition about teaching often fails. APS News, 16(10), 5.
[4] Danz, D. (2014). The curse of knowledge increases self-selection into competition: Experimental evidence (No. SP II 2014-207). WZB Discussion Paper.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。