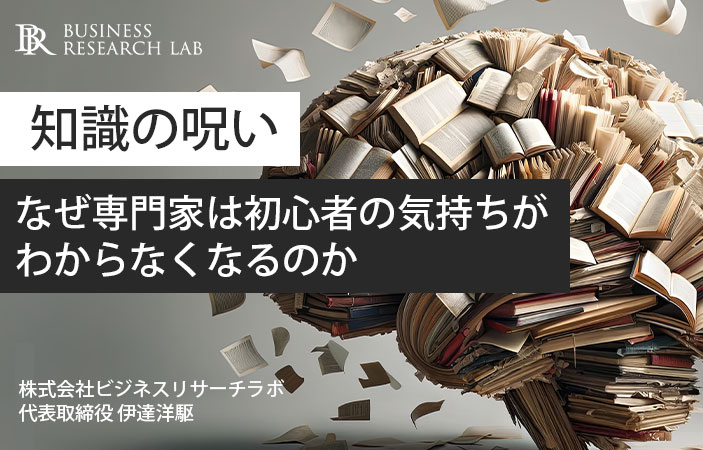2025年5月1日
知識の呪い:なぜ専門家は初心者の気持ちがわからなくなるのか
人は一度習得した知識を後から忘れることがあっても、自分が初心者だったときの戸惑いや理解の浅さを正確に思い返すのは難しいものです。例えば、仕事のマニュアルをつくるとき、ベテランほど「これくらいの説明で伝わるはずだ」と思い込み、新人にとって何が障壁になるかを想定しきれない場合があります。
こうしたすれ違いの原因の一つとして、心理学の領域で「知識の呪い」と呼ばれる現象が議論されてきました。これは、自分が持つ知識や経験を当然のものだと感じすぎるあまり、他者にはそのような土台がないことを十分に考えられなくなるバイアスを指します。
本コラムでは、知識の呪いが生じる仕組みを複数の先行研究からたどり、いくつかの場面に当てはめて考えていきます。初めに、一般的な作業を題材にした実験で、専門家や中程度の経験者、初心者がどのように他者を見積もったかを取り上げます。続いて、医療現場の麻酔科医が患者や研修医とやり取りするときに起こる問題点を掘り下げ、グラフを使ったデータ提示の場面で生じる認識のズレについても目を向けます。
最後に、交渉の際に当事者が持つ情報量に差があるとき、合意を得にくくなる構造を整理し、まとめとして職場のマネジメントに対する含意を述べます。知識の呪いは専門家と初心者のギャップを表すだけでなく、組織内外のコミュニケーション全般に潜む見落としを照らす概念として、大いに考察に値するかもしれません。
知識の呪いで専門家は初心者を誤解する
まず視野に入れたいのは、複雑な課題を用いて専門家と初心者の思考の行き違いを調べた一連の実験です[1]。そこでは被験者を「専門家」「中程度の経験者」「初心者」の三群に分け、それぞれに同じタスクを課し、初心者が完了するまでの所要時間を予想してもらいました。同時に、いくつかの補助的な手法を組み合わせることで、専門家と初心者の推測がどのように変化するかが検証されました。
初心者のグループには未知の作業を出題し、「自分ならどれくらい時間がかかるか」を答えてもらいました。一方で専門家と中程度の経験者には「初心者ならどの程度時間を要するか」を見積ってもらい、実際の完了時間との差を評価しています。
すると、どのグループも実測値を下回る数字を思い描く例が多かったのですが、その下振れが特に大きかったのは専門家でした。中程度の経験者も正確さを欠く部分はあったものの、初心者の苦労をある程度は想像できていたようです。
専門家の見積もりが実際の数値を下回る背景としては、長くその分野に携わるうちに、基礎的なステップを無意識に処理してしまう現象が強く働いていることが挙げられます。自分が最初に学び始めたころを思い返そうとしても、記憶が曖昧になり、初心者の時分に直面していた難しさを再現しにくいのです。そのため、「これくらいの作業ならスムーズに進むはずだ」と決めつけ、現実の所要時間を大幅に下回る数字を想定してしまいます。
目を引く点として、初心者自身も「やってみたらあっさり終わるかもしれない」と楽天的にとらえ、進行を甘く見るケースが少なからず見受けられました。経験を全く積んでいない状態では、タスクをしっかり思い描けないため、「それほど手こずらないだろう」と思ってしまうのです。
研究の中では補正策として、被験者に過去の経験を想起させたり、初心者が遭遇しがちな問題点を事前に示したりする方法が試されました。初心者は若干ながら予想を修整できた一方、専門家にはあまり響かなかったと報告されています。専門家は、自分が積み重ねてきたノウハウを基準に必要な時間を推測する習慣を持っているため、数値を大幅に書き換えることに抵抗感があるのかもしれません。
この現象は現場でのOJTなどでもよく見られ、熟練社員が新人に業務を教える際に「ここは簡単だろう」と思い込み、説明を省く場面が少なくないでしょう。そうした思い込みが何気なく繰り返されると、初心者が抱える学習上のつまずきに気づかないまま先へ進んでしまいかねません。
麻酔科医も知識の呪いに陥る
医療の領域でも、知識の呪いが課題として指摘されています[2]。とりわけ麻酔科医は、術前に短時間で患者と接触しなければならない場合が多く、複雑な専門用語や技術的内容を使いこなします。
ところが患者側は医学的知識に乏しいだけでなく、不安や恐怖を抱えているかもしれません。それにもかかわらず、「この程度の表現なら伝わるだろう」と想定すると、患者が本来もっと聞いておきたいことや、自分の状態について相談したいことを言い出しにくい雰囲気が生じる恐れがあります。
ある報告では、術前面談がわずかな時間で終わり、患者が麻酔に伴うリスクを正確に把握できないまま手術に臨むケースが紹介されています。医師のほうも「要点はすでに伝えたはずだ」と考え、患者の疑問に十分答えていない可能性があります。そして研修医に対しても、教える側が「こんな初歩的なことは知っているだろう」と思い込み、要所を省いてしまうことが問題視されています。その結果、研修医が肝心な手順を理解しきれずに進んでしまい、実際の処置で戸惑う展開になり得ます。
外科医との共同作業でも、麻酔科医が「ここは手術チームなら当然わかっているはず」と思い込む一方、外科医の側は「全身管理は麻酔科医の領域だろう」と考え、事前打ち合わせを軽く済ませてしまう場面があります。
双方の知識が専門的であるために、互いに細かい説明を不要と感じてしまうわけです。しかし実際には、手術当日になって初めて「この患者にはどのような既往歴があり、麻酔の計画がどうなっているのか」が十分共有されていなかったとわかることもあります。
麻酔そのものの技術は進歩し、高度な薬剤やモニタリング機器の導入によって安全策は拡充されています。しかし知識の呪いがコミュニケーションを滞らせると、患者との意思疎通が不完全になったり、新人医師が十分な指導を得られなかったりする懸念がぬぐえません。
実際、麻酔科医が「患者は術後の痛み止めについて知っているだろう」と思い込んだまま退室し、患者が痛みを自己申告できず苦痛が長引いたとしたら問題です。そこには、自分の専門領域に詳しすぎるがゆえに、相手がどれほど理解しているかを正確に推し量るのが難しいという構造的な問題が潜んでいます。
グラフ理解も知識の呪いが歪める
業務指導や医療の領域だけでなく、データを視覚的に提示する場面でも知識の呪いが現れます。ある調査では、参加者を複数の条件に割り振り、一部のグループに政治的イベントや社会的背景に関する情報を先に読ませ、それから折れ線グラフなどを見せました[3]。その結果、情報を先取りしたグループは、「ここで強調される変化が決定的だろう」と思い込み、それを他の人々も同じように最も際立つ特徴だと捉えるはずだと予測したのです。
背景情報を与えられたグループでは、グラフ内でどの点が最も重要と映るかを自分の感覚で決めつけ、情報を持たない第三者も同じ地点に目が行くだろうと信じていました。しかし実際には、グラフを読む際の視点は人それぞれ異なり、縦軸や色分けの違いによって「目立つ」と感じる部分が変わるかもしれません。それでも、一度「ここが核心だ」と理解すると、「誰が見てもこの部分が最初に目につくに違いない」と早合点しやすいのです。
背景知識なしで同じグラフを眺めたグループは、データを多様な切り口でとらえ、特定の要素に極端に注目する度合いが低かったと報告されています。情報を最初に得たグループは、自分たちの学んだストーリーを普遍的なものだと想定し、その視点を他者にも重ね合わせました。
可視化されたデータは客観的に見えても、実際には観察者が持つ前提知識によって評価や解釈ががらりと変わります。こうしたバイアスは、知識の呪いの典型例として取り上げることができるでしょう。
データ活用の場面で作成者が「このグラフを見れば誰でも同じ結論に至るだろう」と考えると、説明不足を招く可能性があります。実際には、読み手がその事象を知らずに目を通したとき、「線が交差している原因は何か」とか「この伸び率は大きいのか小さいのか」といった疑問を抱くかもしれません。
作成者がそうした点を十分に補足しないと、見落としや誤解が起こりやすくなります。自分が知っている知識や文脈を他者も共有していると感じてしまうのが、知識の呪いの特徴であり、グラフの読み方においても例外ではありません。
知識の呪いが交渉の失敗を増やす
ビジネスや私生活のさまざまな交渉でも、知識の呪いは障害になると指摘されてきました。ゲームを使った実験では、一部の参加者だけが相手の資金情報や配分に関する追加データを知らされ、どのようにオファー金額や要求水準を変えるかが比較されています[4]。情報を与えられた側は「相手にはもっと潤沢なリソースがあるはずだ」と思い込み、高めの条件を提示しても受け入れられると想定するようになりました。
情報を持たない側は、そこまで大きな要求をされるとは思わずに交渉に臨むため、両者の期待値が大きく食い違い、合意に達しない展開が増えます。なかには、情報を持たない側が「相手は大した余力を持っていないだろう」と思い込み、現実の資源を大きく下回る想定で押し問答を繰り返すパターンもあります。こうした誤算の根底には、どちらも「相手も同じように状況を理解しているだろう」という思いが潜んでおり、その結果、提示額と受容ラインがうまく合わなくなるのです。
参加者同士が「最低でもこれぐらいが欲しい」「相手ならこれくらい応じられるだろう」という心づもりを固めていたとき、追加情報を得た側は自分の期待をいっそう高く設定し、わずかなオファーでは満足できなくなることもあります。
しかも、相手も自分と同程度の背景知識を持っているはずだと決めつけると、「どうして譲歩してくれないのか」と疑いを深め、互いに不満を募らせてしまいます。知識の呪いは戦略的駆け引きだけが原因ではなく、認知的錯覚によって「相手も同じ情報を踏まえて考えている」という想定が生まれる点に特質があります。
この錯覚が起きると、「もう少し交渉すれば合意できるはず」と期待して強気の態度を続けたり、逆に「きっと相手には余裕がないから大幅に譲らないといけない」と早々に不利な条件を受け入れたりと、極端な判断が誘発されるかもしれません。
その結果、双方が得られるはずの利益が目減りしたり、話し合いが途中で終わってしまったりする可能性があります。こうした紛糾の例は、社会のさまざまな場で確認され得る現象であり、知識の呪いが交渉を複雑化させる要因の一つとして注目されています。
認識のギャップを超えて
ここまで見てきたように、知識の呪いはごく身近な指導や説明から、医療行為、データの可視化、そして交渉にいたるまで、幅広い局面で姿を現します。職場のマネジメントを考える上でも、この認知上のズレを放置すると、せっかくの指示や研修内容が十分に伝わらず、人材育成や組織全体の成果に悪い影響を及ぼしかねません。熟練者であればあるほど、自分の知識を前提としてコミュニケーションを展開するので、聞き手との間に隔たりが生じるリスクが高まります。
一方で、すべての人が同じレベルの知識を持つ状態を作るのは簡単ではなく、実務の速度や専門性を踏まえると、熟練者の担当部分を安易に他人に任せるのも難しいでしょう。とはいえ、相手の理解度を過大評価しないよう心がける姿勢は、適切な連携を図るうえで重要と考えられます。
小さな伝達ミスの積み重ねが組織に大きなロスをもたらす懸念も拭えません。知識の呪いを意識しながらコミュニケーションを見直していく動きは、今後いっそう増えていくでしょう。職場のマネジメントの観点では、誰が何をどの程度知っているのかをきちんと見極め、誤解が生じそうな点を早期に確認する工夫が求められるでしょう。
脚注
[1] Hinds, P. J. (1999). The curse of expertise: The effects of expertise and debiasing methods on prediction of novice performance. Journal of Experimental Psychology: Applied, 5(2), 205-221.
[2] Choudhury, M. (2018). Your expert knowledge may put them off: Curse of knowledge among anesthesiologists. Anaesthesia, Pain & Intensive Care, 145-147.
[3] Xiong, C., Van Weelden, L., and Franconeri, S. (2019). The curse of knowledge in visual data communication. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 26(10), 3051-3062.
[4] Pierrot, T. (2019). Negotiation under the curse of knowledge (No. SP II 2019-211r). WZB Discussion Paper.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。