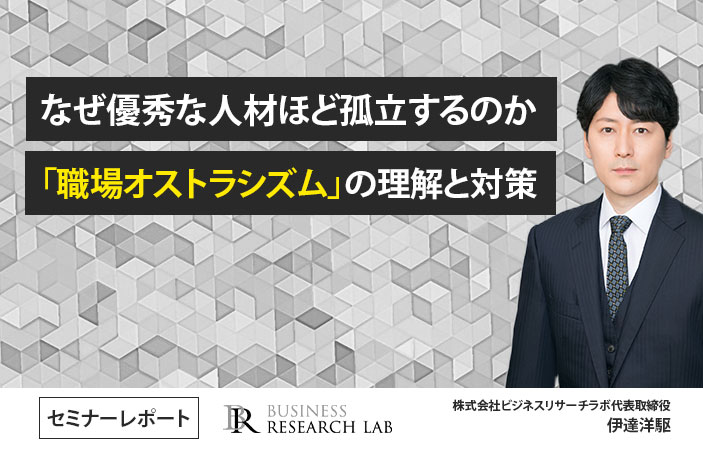2025年4月30日
なぜ優秀な人材ほど孤立するのか:「職場オストラシズム」の理解と対策(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年4月にセミナー「なぜ優秀な人材ほど孤立するのか:『職場オストラシズム』の理解と対策」を開催しました。
職場で誰かが孤立していませんか。一見普通に見える日常の中で、実は起きている「職場オストラシズム」。打ち合わせから知らされずに外される、メールのCCから外れる、休憩時の会話の輪に入れないなど、誰かを排除してしまう現象です。
研究によれば、このような見えにくい排除が、従業員のモチベーションや創造性を低下させ、知識共有を妨げ、組織全体の活力を奪うことが明らかになっています。本セミナーでは、職場オストラシズムが生じるメカニズムと、それを防ぐためのアプローチを、豊富な研究事例とともに解説しました。
心理的安全性の高い職場づくりに関心をお持ちの経営者、人事担当者、チームリーダーの方々にとって有益な内容です。一人ひとりが尊重され、能力を発揮できる職場づくりのヒントが得られるはずです。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
私たちは職場で日々様々な人と関わりながら働いています。挨拶を交わし、会議で意見を述べ、時には休憩時間に雑談をする。こうした何気ない交流は、仕事の満足度や生産性にも影響を与えています。
しかし、そのような交流から継続的に排除されることは、深い傷となり得ます。表立った嫌がらせや暴言と異なり、「何もしない」という形で表れる排除は、周囲からも気づかれにくく、対応が遅れることもあります。
本講演では、職場における「オストラシズム(社会的排斥)」について、その実態と影響、そして対策を考えていきます。目に見えにくい形で個人と組織を蝕むこの問題について理解を深め、より良い職場環境を作るためのヒントを探っていきましょう。
職場オストラシズムとは
職場オストラシズムとは、職場において特定の個人が周囲から意図的に無視されたり、疎外されたりする現象を指します。例えば、挨拶を返さない、目を合わせない、会話に入れない、メールの返信をしない、会議に招待しないなど、様々な形で表れます。暴言や嫌がらせといった「熱い暴力」と異なり、「冷たい暴力」とも表現されるこの現象は、深刻な影響をもたらします。
職場オストラシズムに関する研究は、2014年以降に急速な広がりを見せています[1]。特に2018年と2019年には非常に多くの研究論文が発表されました。この背景には、職場環境の改善やメンタルヘルスへの関心の高まり、そして働く人々の心理的健康が組織のパフォーマンスに影響を与えることへの認識があります。
遠心力が働く
職場オストラシズムの悪影響は様々な角度から検証されています。まず、排斥された従業員に組織からの「遠心力」が働くような影響が生じることを見ていきましょう。
例えば、職場オストラシズムが従業員の組織への帰属意識を低下させることが明らかになっています[2]。排斥を受けた従業員は自分が組織の一員であるという感覚が弱まり、職場での存在意義を見失います。組織内での自己評価も低下させ、その結果、仕事に対する満足度も減少していきます。職場環境を否定的に捉えるようになり、日々の業務に喜びを見出せなくなるのです。
職場オストラシズムが従業員の情緒的消耗と心理的ストレスを増大させることも確認されています。情緒的消耗とは、物事に対する興味や活力を失い、心理的・身体的に消耗した状態を指します。排斥された従業員は自己否定や孤立感を抱き、精神的なリソースを消耗させていきます。この消耗が回復されないまま続くと、ストレスが蓄積され、幸福感が損なわれることになります。
組織市民行動の減少も報告されています。組織市民行動とは、職務として定められていない自発的な協力や貢献のことで、他の従業員を助けたり、職場の雰囲気を良くしようと努力したりする行動を指します。中国の石油・ガス企業で行われた調査では、排斥を受けた従業員の組織市民行動が減少することが確認されました[3]。特に排斥する側が上司である場合、その傾向は一層強くなります。
さらに、様々な研究を統合的に分析したメタ分析によると、職場オストラシズムと離職意思の間には一貫した関係性があることが明らかになっています[4]。排斥を経験した従業員は、そうでない従業員と比べて高い離職意思を示します。この関係性は業種や地域を問わず観察され、特に若年層の従業員において顕著です。
なぜこのような現象が起こるのでしょうか。資源保存理論によれば、職場オストラシズムは従業員の職場での支援や社会的つながりといった重要な資源を奪います。排斥された従業員は、「この組織には居場所がない」と感じるようになります。その結果、新しい職場を探そうとするのです。
問題行動につながる
職場オストラシズムがもたらす影響は、組織からの遠心力にとどまりません。排斥された従業員は様々な問題行動を起こすようになることがあります。
例えば、職場で排斥を経験した従業員が、他者への逸脱行動を増加させることが確認されました[5]。例えば、同僚の失敗を喜んだり、悪口を言ったりするような攻撃的な態度です。これは排斥によって失われた力を取り戻そうとする心理が働くためで、自分が無力だと感じる状況を補うために、他者に攻撃的になります。
中国の企業で行われた別の研究では、職場排斥が道徳的無関与という心理状態を介して、不道徳な行動を引き起こすことも判明しています[6]。道徳的無関与とは、本来は倫理的に問題のある行動であっても、それを正当化して受け入れてしまう心理状態です。
調査によると、排斥された従業員は心理的なストレスや不安を感じ、その負担を軽減するために道徳的な判断基準を一時的に停止させ、「この行動は仕方がない」といった考えで不道徳な行動を正当化するようになります。例えば、他者の業績を故意に低く評価したり、チームの一員としてふさわしくない行動を取ったりするケースが報告されています。
また、パキスタンの繊維産業で行われた調査では、職場オストラシズムが知識隠蔽行動を促進することも明らかになっています[7]。知識隠蔽には「回避的隠蔽」(知識の共有を先延ばしにしたり、意図的に誤った情報を提供したりする行動)と「無知のふり」(知識を持っているにもかかわらず知らないと装う行動)があります。
調査の結果、排斥された従業員は特にこれらの行動を増やすことが分かりました。これは資源保存理論で説明できます。職場で排斥された従業員は、人間関係という重要な資源を失った状態にあるため、自分の知識という別の資源を守ることで心理的なバランスを保とうとするのです。
重要な人材への影響
職場オストラシズムがもたらす影響の中でも注目すべきは、組織にとって有益な人材がその対象となった場合の深刻さです。優れた能力や高い意欲を持つ従業員が、排斥の影響を強く受けやすいという皮肉な事実があります。
中国の複数のホテルで働く従業員を対象とした調査では、内発的動機づけが高い従業員ほど、排除による職務没入感(ジョブ・エンベデッドネス)の低下が顕著であることが判明しました[8]。内発的動機づけとは、仕事そのものにやりがいを見出し、達成感を重視する傾向を指します。
仕事に対する期待や価値を高く持っている人ほど、排斥による心理的なダメージが大きくなるのです。例えば、新しいプロジェクトのアイデアを提案しても無視される、チームでの話し合いから外されるといった経験は、仕事への意欲が高い従業員にとって打撃となります。
内発的動機づけが高い従業員は仕事を通じて自己実現を図ろうとするため、他者との協働や意見交換を重視します。しかし、排除されることでそれらの機会が失われ、「ここには居場所がない」という感覚を強く抱くようになります。職場での交流や対話から締め出されることは人間関係の問題以上の意味を持ち、仕事そのものの価値や意義を損なう体験となります。
加えて興味深いのは、台湾の様々な業界(製造業、IT、サービス業など)で実施された調査で明らかになった、優秀な部下が排斥される理由に関する知見です[9]。一般的に高い能力を持つ従業員は組織にとって価値ある存在とされますが、皮肉なことに部下の優れた能力が上司の不安を引き起こし、その結果として排斥につながることがあります。
調査では、能力の高い部下を持つ上司が不安を感じ、その不安が排斥行動を引き起こすという関係が確認されました。これは社会比較理論で説明できます。人は他者との比較を通じて自己評価を行う生き物であり、上司は部下と自分を比較する際に、部下の能力が自分を上回っていると感じると、自身の役割や地位が脅かされるのではないかという不安を抱きます。
この不安は上司を排斥行動へと駆り立てます。部下との接触を避け、意図的に情報共有を控えたり、会議での発言機会を制限したりするといった行動が見られます。不安を感じる対象を遠ざけることで心理的な安定を得ようとする自己防衛の現れであり、上司の不安が強いほど顕著に表れることが示されています。
排斥する動機
これまで見てきたように、職場オストラシズムは個人と組織に悪影響をもたらします。では、なぜ人は職場で他者を排斥するのでしょうか。その動機について、主に二つのタイプが挙げられています[10]。
一つ目は「懲罰的動機」です。これは集団の秩序や効率を維持するために行われる排斥です。例えば、職場のルールを守らない人や、チームの目標達成に貢献しない人が排斥の対象となることがあります。この場合、排斥は一種の警告として機能し、他のメンバーに対して「規範を守らなければ同じ扱いを受ける」というメッセージを送ることにもなります。
もう一つは「防御的動機」です。これは自己防衛の手段として行われる排斥で、他者との比較で劣等感を感じたり、自分の地位が脅かされると感じたりしたときに、その対象となる人を排斥するというものです。例えば、創造性の高い同僚が上司から高く評価されている場合、それを脅威と感じた人がその同僚を排斥することがあります。
防御的動機による排斥には、いくつかの典型的なパターンがあります。一つは、自分より優れた能力や実績を持つ人を排斥するケースです。このような場合、排斥者は自己イメージを守るために、優れた同僚との接触を避けようとします。もう一つは、上司との関係が良好な同僚を排斥するケースです。これは、その同僚との関係が自分の立場を脅かすと感じることから生じます。
悪影響を緩和する
職場オストラシズムが既に発生している場合、その悪影響をどのように緩和することができるのでしょうか。研究は、いくつかの方法を示しています。
一つ目は「許しの雰囲気」の醸成です。中国の企業を対象とした調査では、職場での「許しの雰囲気」が排斥による悪影響を緩和する可能性があることが明らかになりました[11]。許しの雰囲気とは、チームメンバー間のミスや失敗を寛容に受け入れる風土のことです。
研究によると、許しの雰囲気が強いチームでは、排斥による情緒的消耗の影響が弱まることが分かりました。これはチーム内の信頼感と協力が、情緒的消耗を回復するリソースとして機能するためです。許しの雰囲気は否定的な感情を軽減し、従業員への支援を増加させることで、心理的な負担を和らげます。
許しの雰囲気を醸成するためには、上司が率先して自分の失敗を開示することが有効でしょう。「私も間違えることがある」というメッセージを伝えることで、チーム内での失敗に対する不安や恐れを減らすことができます。また、ミスを責めるのではなく、そこから学ぶことを重視する姿勢を示すことも重要です。「なぜ失敗したのか」ではなく「どうすれば次は成功するのか」という視点で話し合いを行うことで、許しの雰囲気が生まれやすくなります。
二つ目は「自己効力感」の向上です。パキスタンの組織を対象とした研究では、自己効力感の高さが職場オストラシズムの悪影響を緩和することが確認されました[12]。自己効力感とは、困難な状況に直面してもそれを乗り越えられるという信念のことです。
自己効力感が高い人は困難な状況に直面してもそれを乗り越えるための創造的な解決策を考え出します。例えば、他の情報源を活用したり、別のネットワークを頼ったりして、不足する知識を補うことができるのです。
自己効力感を高めるためには、小さな成功体験を積み重ねることが有効です。特に新しい業務や困難な課題に取り組む際には、段階的な目標設定を行い、一つずつクリアしていくことで成功体験を得られるようにします。また、他者の成功体験を観察することも自己効力感を高める方法です。特に自分と似た立場や背景を持つ人の成功は「自分にもできるかもしれない」という思いにつながります。
発生を予防する
職場オストラシズムの悪影響を緩和する方法があるとはいえ、そもそもこのような問題が発生しないようにすることが本質的には重要です。職場オストラシズムをどのように予防できるのでしょうか。
職場におけるサポート体制の構築が効果的です。職場内での支援ネットワーク(友人や協力者)が弱い人は排斥のリスクが高まることが分かっています[13]。支援が少ない人は他者との関係を維持する力が弱く、排斥が成功しやすいのです。逆に言えば、職場内での支援ネットワークを強化することで、排斥のリスクを低減することができます。
サポート体制を構築するためには、助けを求めることから始めましょう。多くの人は助けを求めることを躊躇しますが、「助けを求める」という行為自体が人間関係を強化します。例えば、「この問題について、意見を聞かせてもらえませんか」といった簡単な働きかけでも構いません。また、自分が持っている情報や知識を積極的に共有することも、サポート体制の構築につながります。「今度の会議に向けて、私がまとめた資料を共有するので、もしよければ意見をください」といった形で、協力の機会を作り出します。
次に有益なのは「ユーモア」の役割です。ポルトガルの研究グループが40社の上司と部下を対象に実施した調査では、職場におけるユーモアの存在が、上司の侮辱的管理と部下への排斥の関係を弱めることが判明しました[14]。
調査によると、同僚間でユーモアが頻繁に使われる職場では、上司の侮辱的管理があっても、それによる排斥の影響が緩和されることが分かりました。職場でのユーモアがポジティブな感情を生み出す社会的資源として機能するためです。同僚間でユーモアが交わされると、心理的な距離が縮まり、仲間意識が高まります。その結果、侮辱的管理を受けている従業員に対しても共感を示しやすくなり、排斥する必要性が低下します。
ただし、ユーモアを職場に取り入れる際には注意が必要です。他者を傷つけたり、特定の属性を揶揄したりするようなユーモアは逆効果となります。状況や自分自身を笑いの対象にするもの、あるいは誰もが共感できる日常の出来事に関するユーモアが求められます。
とはいえ、いきなり「昨日起きた面白い話を教えてください」と尋ねるのは現実的ではありません。まずは雑談の機会を増やすことを目指すと良いでしょう。仕事以外の話をする中で、自ずとユーモアが発現する可能性が高まります。
おわりに
本講演では、職場オストラシズム(社会的排斥)について、その実態と影響、そして対策を見てきました。挨拶を返さない、目を合わせない、会話に入れないといった行為が、個人と組織に深刻な影響をもたらすことが分かりました。
職場オストラシズムは、組織からの遠心力として働き、従業員の帰属意識や満足感を低下させ、離職意思を高めます。また、自己防衛や失われたパワーを取り戻そうとする心理から、逸脱行動の増加や知識隠蔽行動といった問題行動を引き起こします。
内発的動機づけが高い従業員や優れた能力を持つ部下など、組織にとって有益なはずの人材が排斥の対象となりやすく、またその影響も強く受けやすいという皮肉な事実もあります。そして、排斥する側の動機としては、集団の秩序を維持するための懲罰的動機と、自己防衛のための防御的動機の二つがあることが明らかになりました。
職場オストラシズムの悪影響を緩和するためには、許しの雰囲気の醸成や自己効力感の向上が有効です。また、そもそもの発生を予防するためには、職場でのサポート体制の構築やユーモアの活用などが有効でしょう。
見えにくい形で個人と組織を蝕む職場オストラシズム。しかし、私たち一人一人が行動することで、その連鎖を断ち切ることは可能です。より良い職場環境のために、今日からできることを始めてみませんか。
Q&A
Q:優秀な部下・人材が上司の不安を引き起こし排除されるという現象について、評価制度の設計で予防できる部分はありますか。逆に上司と部下の競争を促すような評価システムが排除を助長する可能性はあるのでしょうか。
評価制度は重要な観点です。上司と部下を同じ土俵でパフォーマンスが上がるかどうかを評価するような仕組みや、誰かが高い評価を得ると誰かの評価が低くなる相対的な評価システムを採用していると、上司だけでなく同僚も含めて、防御的動機による職場オストラシズムが発生しやすくなります。
そのため、チームにおける成果や、お互いの協力関係・協働・助け合いといった面をきちんと評価する指標を導入することが大切です。また、優秀な部下を持っていることや、部下を育成・成長させていくことが評価の中に含まれていると、優秀な部下の存在が上司にとってもプラスになります。そうすれば、オストラシズムを緩和させることができるでしょう。
Q:職場オストラシズムを行う従業員を止める・行動を変えさせる方策はありますか。
職場オストラシズムを抑制するためには、二段階のアプローチが必要でしょう。第一に「気づき」の段階です。自分の何気ない行動が排除につながっていることを学び、気づく必要があります。そこまで強く意図せずに行っているケースも少なくないからです。
第二に「行動変容」の段階です。気づくだけでは不十分で、行動を変える必要があります。例えば、会議で発言していない人に意見を求めたり、雑談の場にいつも参加していない人を誘ったりすることが職場オストラシズムを防ぎます。
さらに、自分は加担していないが目撃するケースもあるでしょう。そのときにどう介入すれば良いかを組織内で話し合っておくことも重要です。どう話しかければ自然かなど、事前に考えておけば、その行動をとりやすくなります。
Q:テレワークなど対面以外のコミュニケーションにおける職場のオストラシズムはどんな特徴がありますか。対面状況と比較すると、より一層見えにくくなってしまうのではないでしょうか。
リモート環境やオンラインでのコミュニケーションにおいては、対面とは異なる形でオストラシズムが生じる可能性があります。例えば、チャットやメッセージへの返信を考えてみましょう。全てのメッセージに返信していますか。特定の人のメッセージだけが返信されていないとすれば、それはオストラシズムになる可能性があります。また、情報共有の際に特定の人が含まれていないケースもあるでしょう。
このようにオンラインコミュニケーションでは、対面よりも見えにくく、気軽に行われてしまいます。これがオンライン特有の特徴と言えるでしょう。
対処法としては、オンラインコミュニケーションを行うとき、いつも発言しない人がいれば発言を促すと良いでしょう。また、チャットツールを使う際にはリアクション機能も有効です。特定の人のメッセージだけにリアクションがつかないのは問題です。リアクションを活用して「あなたのメッセージはきちんと受け取っています」と示しましょう。
Q:職場のユーモアがときにオストラシズムの手段となることがあるように思います。冗談や皮肉が排除の道具となるケースとその対処法を教えてください。
ユーモアは研究の中ではオストラシズムの悪影響を緩和する一つのアプローチとして挙げられていますが、確かに諸刃の剣となる面があります。うまく活用できれば良い効果をもたらしますが、使い方が適切でないと、オストラシズムの手段となってしまうこともあります。
例えば、知っている人にしかわからない内輪ネタを特定の人が常に入れない形で使えば、それは笑いの形を取りながらも実質的に排除していると同等でしょう。また、ある人を標的にした皮肉や笑いも排除の道具として機能するかもしれません。
これに対する考え方としては、一つに「笑いの対象が何なのか」ということがポイントです。対象が個人になると、それを自然な形で笑いに昇華するのは困難かもしれません。状況を笑いの対象にしていくことが観点になるでしょう。
とはいえ、状況だけで笑いを生み出すことは現実的ではないとも考えられます。個人を対象とする場合、笑いの対象となった人も一緒に笑えるかどうかが判断基準になります。笑いの対象とされた個人が笑えないのであれば、それは排除につながり得ます。
脚注
[1] Kaushal, N., Kaushik, N., and Sivathanu, B. (2021). Workplace ostracism in various organizations: A systematic review and bibliometric analysis. Management Review Quarterly, 71(4), 783-818.
[2] Li, M., Xu, X., and Kwan, H. K. (2021). Consequences of workplace ostracism: A meta-analytic review. Frontiers in Psychology, 12, 641302.
[3] Wu, C.-H., Liu, J., Kwan, H. K., and Lee, C. (2016). Why and when workplace ostracism inhibits organizational citizenship behaviors: An organizational identification perspective. Journal of Applied Psychology, 101(3), 362-378.
[4] Das, S. C., and Ekka, D. (2024). Workplace ostracism and turnover intention in organizations: A meta-analytic review. BIMTECH Business Perspectives, 5(1), 48-73.
[5] Fiset, J., Al Hajj, R., and Vongas, J. G. (2017). Workplace ostracism seen through the lens of power. Frontiers in Psychology, 8, 1528.
[6] Liu, X., Zhang, H., and Yu, X. (2023). Effects of workplace ostracism on pro-job unethical behavior: The role of moral disengagement, interpersonal sensitivity and self-serving political will. Psychological Reports.
[7] Riaz, S., Xu, Y., and Hussain, S. (2019). Workplace ostracism and knowledge hiding: The mediating role of job tension. Sustainability, 11, 5547.
[8] Lyu, Y., and Zhu, H. (2019). The predictive effects of workplace ostracism on employee attitudes: A job embeddedness perspective. Journal of Business Ethics, 158(4), 1083-1095.
[9] Chang, K., Kuo, C.-C., Quinton, S., Lee, I., Cheng, T.-C., and Huang, S.-K. (2019). Subordinates’ competence: A potential trigger for workplace ostracism. The International Journal of Human Resource Management, 32(8), 1793-1817.
[10] Henle, C. A., Shore, L. M., Morton, J. W., and Conroy, S. A. (2023). Putting a spotlight on the ostracizer: Intentional workplace ostracism motives. Group & Organization Management, 48(4), 1014-1057.
[11] Wang, L.-m., Lu, L., Wu, W.-l., and Luo, Z.-w. (2023). Workplace ostracism and employee wellbeing: A conservation of resource perspective. Frontiers in Public Health, 10, 1075682.
[12] De Clercq, D., Haq, I. U., and Azeem, M. U. (2019). Workplace ostracism and job performance: Roles of self-efficacy and job level. Personnel Review, 48(2), 400-422.
[13] Howard, M. C., Cogswell, J. E., and Smith, M. B. (2020). The antecedents and outcomes of workplace ostracism: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 105(6), 583-596.
[14] Neves, P., and Pina e Cunha, M. (2017). Exploring a model of workplace ostracism: The value of coworker humor. International Journal of Stress Management, 25(4), 330-347.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。