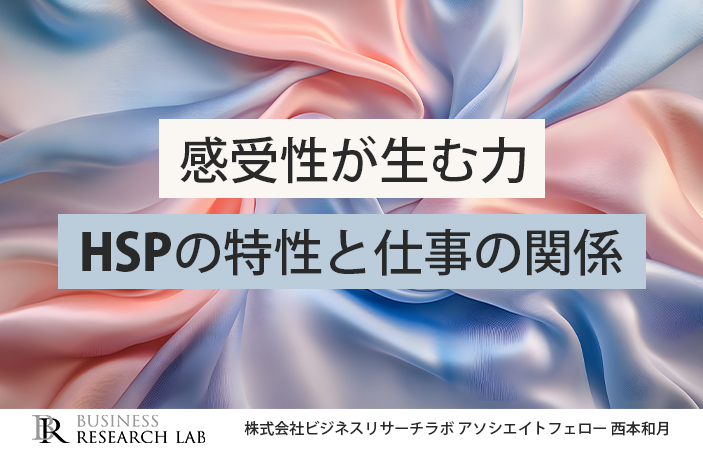2025年4月30日
感受性が生む力:HSPの特性と仕事の関係
もし、部下に「人間関係に悩みを抱えやすい」「何気ない出来事に対して大きなストレスを感じる」といった特徴があったとしたら、どう思うでしょうか。どうしてこんな些細なことがストレスになってしまうのか?打たれ弱すぎるのではないか?と疑問に感じてしまう人もいるかもしれません。
ストレスは従業員個人の健康や幸福さだけでなく、組織の人間関係や生産性、離職率などに影響を与えるため、現代の職場ではストレス対策が重要な課題となっています。そのため、ストレスを感じやすい特徴はやっかいなものとして捉えられがちです。
しかし先ほど挙げた、人間関係や何気ない出来事に反応しやすいという特徴は、本当はネガティブなだけのものではないはずです。
同僚や取引先、顧客の不満にさっと気が付いて対処ができたり、満足していることや興味を示していることを敏感に感じ取って、それをさらに発展させることができるということは、相手の要求にフィットした仕事につながるでしょう。
他の人がたいしたことではないと流してしまったトラブルの芽に注意を向け、大きな問題になる前に対処できたり、逆に小さなチャンスを察知できることも仕事において大切な能力だと言えます。
本コラムでは、一般的に「繊細でストレスを感じやすい人」と認識されてしまいやすいHSP(Highly Sensitive Person ハイリー・センシティブ・パーソン)について、その特徴、ストレスとの関係、あまり知られていないポジティブな側面について説明します。
HSPはどのような人か
ポジティブな刺激にもネガティブな刺激にも感受性が高い
マスメディアやSNS上の議論などでは、HSPを「繊細な人」と表現することがよくあります。しかし、実は繊細という言葉だけでは正確な姿はつかめません。そこで、学術研究をもとに、HSPがどのような特徴を有しているのか、より網羅的に確認していきます。
HSPに関係する学術上の概念や理論は複数あります。それらの知見を概観すると次のような特徴があげられます[1][2][3]。
- 光や音などの五感が鋭く、小さな環境刺激に敏感に気が付く
- 刺激を強く感じやすいために、その刺激に圧倒され疲れやすい
- カフェインなどの体内に摂取するものに反応しやすい
- 痛みや空腹感などの自分の感覚にもよく気が付く
- 他人の感情をよりしっかりと感じ取り、共感しやすい
- 物事を深く考える
- 繊細な美に気が付き、芸術作品などを楽しめる
これらの特徴を踏まえると、HSPは感度の高いアンテナをもっているといえます。周囲や自分について細かい刺激をキャッチし、その刺激を深い処理にかけるため、さまざまなものに圧倒され、ストレスを感じてしまうことも多くなります。例えば、オフィスのざわめきや光の反射などの無意味な刺激に翻弄されることによって仕事が妨害されたり、監視や評価をされている状況を過剰に意識して失敗が怖くなってしまうことがあるかもしれません。
ただ、ここで重要なことは、HSPが敏感に感じ取る刺激はネガティブなものだけではないということです。ネガティブなものも、ポジティブなものも敏感に感じ取り、深い処理をするということがHSPの重要な特徴です。
例えば、同僚の嬉しい気持ちを察知し、共感することができますし、繊細な香りや味に気が付いてそれを楽しんだり、仕事に活かすこともできます。自分が取り組んでいる仕事についても「こういうものだ」と単純に済ませてしまわずに、さまざまな視点から慎重に判断し、問題解決や新しいアイデアを出すことにも長けています。問題を改善するための介入などの効果が高く出やすいことも、ポジティブな刺激に対してより反応していると言えます。
感受性の高低は、良し悪しではない
「HSPとはどのような人か」をより深く理解するために、別の研究アプローチも紹介します。環境に対する感受性の高さを、「花」に例えて説明するという面白い試みを行った研究があります[4]。この研究では感受性の高さで3グループに分け、各グループをタンポポ、ラン、チューリップに例えています。
まず、タンポポとは低感受性のグループです。このグループは回答者全体の約30%で、一般的に環境の質に対する感受性が低く、どこでも育つタンポポです。高感受性のグループも約30%で、理想的な条件下では特別によく育ちますが、劣悪な条件下では本当にうまく育たないランです。そして残りの40%が中程度の感受性をもつチューリップです。チューリップはとても一般的な花で、ランほど繊細ではないけれど、タンポポよりは気候に敏感です。
上記の例は、HSPが「善し悪しではない」という特徴を、上手く捉えています。土が硬くても、寒くても、雨が降らなくても育つ根性にも魅力がありますし、整えられた条件がそろったときに姿を見せてくれる姿にも格別の美しさがあります。程よく手をかけて安心して育てられる馴染みやすさも大切です。つまり、どれが優れているということではなく、それぞれに特徴があるということが分かりやすい例えです。
HSPとストレスの関係
ここからは、HSPが職場で見せるストレスへの弱さを理解することにつながる研究知見を紹介していきます。一般的な理解と沿うように、HSPは、ある種のストレスへの脆弱性を抱えている可能性が指摘されています
過剰な刺激に翻弄されてしまう
さまざまな刺激に対する感受性が高いゆえに刺激に圧倒されやすいHSPは、ネガティブな状態になりやすいことを調べた研究[5]があります。オランダの労働者を対象に行われた調査では、刺激に敏感であることと、その刺激に圧倒されやすいことは、仕事ストレス全体と正の関係があることが確認されています。
調査では、特に「仕事における不満や不快」と「回復の必要性」が、HSPの特徴と正の関係があるという結果が示されました。これらの指標はストレスが積み重なった状態を表す指標です(ストレスになりそうなことがあった場合にすぐに反応が出そうな指標ではなく)。この結果から、感受性が高い人はストレスが蓄積しやすいと考えることができます。
また、この研究ではストレスだけでなく、感受性の高さは自己効力感の低さと仕事からの疎外感の高さと関係があることが示されました。自己効力感とは、自分が問題を解決したり、目標を達成することができるという自分の能力に対する肯定的な認識のことです。刺激に圧倒されているHSPは、自分は物事に影響を与えたり、解決したり、変化させたりすることができないという思いをもっていました。
加えて、刺激に圧倒されていることが原因で、目の前の仕事に取り組むことが非常に難しくもなります。そのため、仕事から感情的に距離を置くようになる結果、HSPは仕事の意義や自分にとっての意味を感じられなくなってしまうことが示唆されました。
日本の社会人を対象に行われた研究でも、環境刺激に対する感受性の高さはストレスの知覚と、何をしても退屈だと感じるといった疎外感の高さと正の関係が報告されており、海外の研究知見は日本の企業においても有効であることが示されています[6]。
自分のネガティブな状態を感じ続けてしまう
しかしHSPとネガティブな状態の関係は、ただ強い刺激に疲れているという単純なものではなく、複数の要因が複雑に関係しているようです。環境刺激の感受性の高さが否定的な感情につながるという関係の間に、感情を制御することと苦痛への耐性という要因があることを示唆する研究があります[7]。
この研究では、環境刺激への感受性が高いことが、ネガティブな気分にどのように影響するのかを検討しました。その結果、自分の感情によく気がついてしまうことを通して、うつの症状と不安を高めることと、自分の感情をコントロールする方法の不足を通して、うつの症状を高めるという結果が示されました。
感受性の高さは、自分のネガティブな感情を強く意識させ(「私はこんなネガティブな感情を感じている」など)、そして、ネガティブな感情を受け入れられないこと(「こんな気持ちを感じるべきではないし、受け入れられない」など )、そのような感情をコントロールする能力の不足(「私にはこの気持ちをどうすることもできない」など )につながってしまいます。
つまり、感受性の高さゆえに、否定的で不快な心の状態にさらされる傾向があり、それが繰り返されることによって、さらに否定的な認識とコントロールできない状態を招いてしまいます。その結果として、うつや不安、ストレスというネガティブな状態に陥ると考えられるのです。
HSPの仕事におけるポジティブな側面
ネガティブな環境ではネガティブな影響を大きく受けてしまうHSPですが、その能力の高さは注目に値します。次は、仕事のパフォーマンスや職場の人間関係を向上させることにつながるHSPの能力に目を向けてみましょう。
HSPは創造性が高い
まず、HSPと創造性に関連があることを示した研究があります[8]。目指すべきものが明確に示されておらず、新しい価値や製品、サービスなどを生み出すことを求められている仕事では、創造性の高さは重要になってきます。しかし、この創造性と関連する個人の特性が何かということを特定することは難しく、未だ課題として研究が行われています。
この研究では感受性を、2つの観点に分けて検討しました。具体的には、環境刺激に対する感受性と、ネガティブな感情に対する感受性を分けて、知的好奇心や想像力などに関する「開放性」という個人の特性とともに、感受性と創造性との関連を検討しています。
その結果、環境刺激に対する感受性と開放性は、どれだけアイデアを生み出せるかといった創造的思考能力と、達成した創造的な業績と正の相関があることが示されました。また、感受性と開放性の創造性への影響は関連しあっており、環境刺激に対する感受性が高い場合に、開放性の高さが創造性の高さにつながることも示されました。こうした結果から、創造性を発揮するには、新しい経験や価値観などを受け入れる柔軟性があるだけでなく、細かい刺激を察知できるかどうかということも重要であることが示されたのです。
HSPは身近な人のポジティブ感情に反応しやすい
HSPがストレスが高くなる理由の一つとして、人間関係においても敏感であることがあげられています。他者のネガティブな気分を敏感に察知し、それに自分の気分にもつられてネガティブになってしまうことがあります。
しかし、HSPが敏感に感じ取る刺激はネガティブなものだけではありません。実は、他者のポジティブ感情に対する感受性が高く、ポジティブな感情に共感しやすいことも研究で示されています。
fMRIを用いて、親しさが異なる人の、嬉しい表情と悲しい表情を見ているときに、脳がどれくらい活性化しているかを検証した研究があります[9]。HSP、親しい他者の感情、特に肯定的な感情をより強く感じ、よりその情報を処理するようにはたらくことが示唆されました。
具体的には、HSP得点が高いほど、他者の感情に対する気づきや情報の処理、共感、行動の準備に関係する脳領域の活性化が強かったことが示されましたが、幸せな状況に反応する領域で強い活性化が認められ、ポジティブなものに対する感受性の強さも示されました。またパートナーと見知らぬ他人を直接対比させたとき、HSP、他人よりもパートナーの表情に反応して、より強い脳活性化を示すという結果になったのです。
先ほど紹介した日本における研究でも、環境刺激に対する感受性と共感の間に正の関係が認められており、HSPの他者に共感しやすいというポジティブな側面が、労働環境において円滑な人間関係の構築のための貴重な資源となる可能性を示しています[10]。
もし自社で採用するなら、「簡単にストレスに負けて退職してしまう人」よりも、「大抵のことでは揺らがない人がいい」という考えは、幅広い企業に共通するものでしょう。しかし、仕事の細部に気がつき、その仕事の本質にまで考えが及び、ミスが少なく、同僚や顧客の意図をくみ取ることができる人も、仕事で成果をあげるためには必要な人材ではないでしょうか。
HSPが労働人口の約3割を占めることからも、感受性が高い人が仕事で活躍しながら、健康に長く働き続けられる状態を作っていくことは、HSP個人にとってだけでなく、組織にとっても重要な課題であるといえます。
脚注
[1] Aron, E. N., & Aron, A. (1997). Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. Journal of personality and social psychology, 73(2), 345.
[2] Pluess, M. (2015). Individual differences in environmental sensitivity. Child development perspectives, 9(3), 138-143.
[3] Greven, C. U., Lionetti, F., Booth, C., Aron, E. N., Fox, E., Schendan, H. E., … & Homberg, J. (2019). Sensory processing sensitivity in the context of environmental sensitivity: A critical review and development of research agenda. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 98, 287-305.
[4] Lionetti, F., Aron, A., Aron, E. N., Burns, G. L., Jagiellowicz, J., & Pluess, M. (2018). Dandelions, tulips and orchids: Evidence for the existence of low-sensitive, medium-sensitive and high-sensitive individuals. Translational psychiatry, 8(1), 24.
[5] Evers, A., Rasche, J., & Schabracq, M. J. (2008). High sensory-processing sensitivity at work. International Journal of Stress Management, 15(2), 189.
[6] 井奥智大・綿村英一郎(2024). 企業で働くHighly Sensitive Personはストレスを感じ、共感しやすいか. 応用心理学研究, 50(1), 11–20.
[7] Brindle, K., Moulding, R., Bakker, K., & Nedeljkovic, M. (2015). Is the relationship between sensory‐processing sensitivity and negative affect mediated by emotional regulation? Australian Journal of Psychology, 67(4), 214-221.
[8] Bridges, D. & Schendan, H. E. (2019). The sensitive, open creator. Personality and Individual Differences, 142, 179-185.
[9] Acevedo, B. P., Aron, E. N., Aron, A., Sangster, M. D., Collins, N., & Brown, L. L. (2014). The highly sensitive brain: an fMRI study of sensory processing sensitivity and response to others’ emotions. Brain and behavior, 4(4), 580-594.
[10] 脚注6(井奥・綿村, 2024)と同じ
執筆者
 西本 和月 株式会社ビジネスリサーチラボ アソシエイトフェロー
西本 和月 株式会社ビジネスリサーチラボ アソシエイトフェロー
早稲田大学第一文学部卒業、日本大学大学院文学研究科博士前期課程修了、日本大学大学院文学研究科博士後期課程修了。修士(心理学)、博士(心理学)。暗い場所や狭い空間などのネガティブに評価されがちな環境の価値を探ることに関心があり、環境の性質と、利用者が感じるプライバシーと環境刺激の調整のしやすさとの関係を検討している。環境評価における個人差の影響に関する研究も行っている。