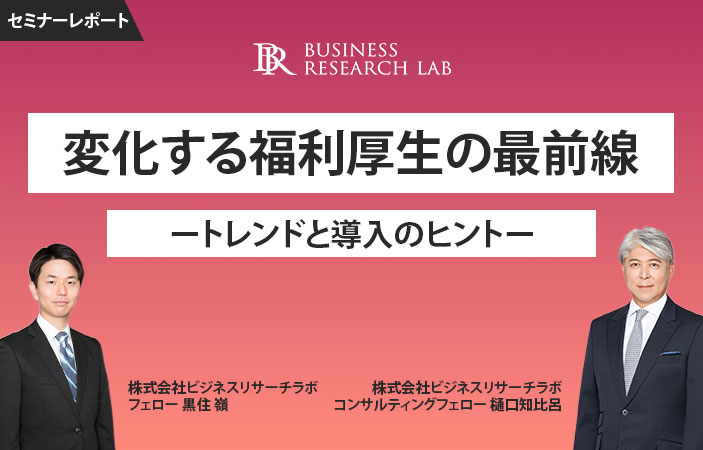2025年4月28日
変化する福利厚生の最前線:トレンドと導入のヒント(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年3月にセミナー「変化する福利厚生の最前線:トレンドと導入のヒント」を開催しました。
近年、働き方に対する従業員の意識が大きく変化する中、福利厚生の在り方にも新たな方向性が求められています。特にコロナ禍を経て、従業員が求めるものは、金銭的な支援だけでなく心身の健康や働きやすさ、そして働き甲斐へとシフトする傾向がみられます。
また、エンゲージメントサーベイの普及により、従業員の声を細かく分析し、より適切な施策を立案できる環境が整いつつあります。福利厚生は、そうした声を活かせる、重要な施策の一つです。
本セミナーでは、福利厚生がもたらす社員への効果を、学術研究をもとにミクロ視点で紐解きました。また、マクロ視点として、福利厚生の歴史・変遷やトレンドを取り上げ、その背景や、トレンド導入のためのヒントを解説しました。
福利厚生の重要性と背景
樋口:
まず、福利厚生って、皆さんの中でどういうイメージをお持ちでしょうか。「福利厚生=コスト」と思われがちなところもありますが、実はそうではありません。福利厚生は、従業員の満足度や生産性を向上させる「戦略的な投資」なんです。
たとえば、JILPT(労働政策研究・研修機構)の「企業における福利厚生施策の実態に関する調査」[1] にこんなデータがあります。福利厚生制度・施策について、重視する目的を尋ねたところ(複数回答:3つまで選択)、「現在」の目的については、「従業員の仕事に対する意欲の向上」(60.1%)とする企業割合が最も高く、次いで「従業員の定着」(58.8%)、「人材の確保」(52.6%)など雇用維持・確保の関連事項が5割を超えてい 。以下、「従業員同士の一体感の向上」(35.0%)や「従業員が仕事に専念できる環境づくり(生活の安定等)」(32.5%)などが続いています。
また、「今後」については、「企業への信頼感やロイヤリティの醸成」や「従業員が仕事に専念できる環境づくり(生活の安定等)」が「現在」と比べ5ポイント程度高くなっています。
では、なぜ今、福利厚生がこれほど重要視されているのか。それは、働き方が大きく変化しているからです。皆さんもご存じのように、近年はリモートワークが当たり前になり、働き方改革も進みました。これによって、従業員一人ひとりのニーズがどんどん多様化してきています。
特に注目すべきは、若い世代の働き手の価値観の変化です。昔は「お給料が高ければそれでいい」という傾向が強かったのですが、今は違います。若い世代は、「働きがい」や「自分らしい働き方」を求めています。そのため、福利厚生も従来型の一律なものから、より柔軟で多様なニーズに応えられるものへと進化しているんですね。
例えば、リモートワークを支援するための手当や、自宅で働くための設備を提供する企業が増えています。また、メンタルヘルスをサポートするためのカウンセリングサービスや、健康増進を目的としたプログラムも注目を集めています。
ここで大事なのは、福利厚生が「会社からの一方的な施し」ではなく、従業員との信頼関係を築くためのツールであるということです。福利厚生を通じて、会社が「従業員を大切に思っている」というメッセージを発信できるんです。これが従業員のモチベーション向上につながり、ひいては企業の成長にも寄与します。
まとめると、福利厚生は単なるコストではなく、企業の未来を支える「投資」です。そして、これからの時代においては、より個々のニーズに応じた多様な福利厚生が求められていくでしょう。
福利厚生の最新トレンド5選
ここからは第二部ということで、「最新トレンド5選」についてお話しします。今の時代、福利厚生は単なる「付加価値」ではなく、企業の競争力そのものと言っても過言ではありません。そんな中で、今企業はどのような福利厚生施策を充実させたいと考えているのでしょうか。JILPTの調査によると、「メンタルヘルス相談」が12.4%と最も割合が高く、次いで「治療と仕事の両立支援策」(11.5%)、「人間ドック受診の補助」(10.7%)、「社内での自己啓発プログラム」(10.7%)、「ノー残業デー等の設置」(10.4%)、「社員旅行の実施・補助」(10.3%)、「社外の自己啓発サービスの提供・経費補助」(10.1%)などの順でした。健康管理、両立支援、自己啓発、働き方などに関心が向けられています。
また、規模が大きいほど「充実させたい」割合が高いカテゴリは「働き方」および「高齢者」で、「働き方」では「フレックスタイム制度」「テレワーク」「ノー残業デー等の設置」、「高齢者」では、「退職前準備教育(セミナーなど)」「定年退職後の保養施設、レクリエーション施設の利用」で規模の大きい企業の割合が高い傾向が見られます。
こうしたトレンドを踏まえて、特に注目すべき5つのトレンドについて具体例を交えながらお話ししていきます。(メンタルヘルス相談、治療と仕事の両立支援策、健康増進、自己啓発、柔軟な働き方)
トレンド1:メンタルヘルス相談
まず最初にご紹介するのは「メンタルヘルス相談」です。最近、特に注目を集めている分野ですよね。コロナ禍以降、精神的な健康の重要性がますます認識されるようになりました。
私たちの日常生活では、ストレスを感じる場面が増えています。リモートワークの普及や仕事と家庭の両立といった新しい働き方が浸透する中で、精神的な負担を感じる従業員が増えているんです。こうした背景から、企業が従業員のメンタルヘルスを積極的に支援することが求められています。
例えば、Googleが提供しているエンプロイーウェルビーイングプログラムが一つの成功例として挙げられます。このプログラムでは、オンラインカウンセリングのサービスが導入されていて、従業員が気軽に専門家に相談できる環境を整えています。
また、瞑想アプリの提供など、従業員が自分自身でストレスを軽減する手段も用意されています。フィットネス施設の提供、栄養指導、ストレス管理ワークショップなど、多岐にわたるサポートを提供しています。こうした取り組みは、仕事のパフォーマンス向上だけでなく、ストレスレベルが低減して、従業員の離職率の低下にもつながるんです。
さらに、最近ではAI技術を活用したメンタルヘルスサポートも登場しています。たとえば、AIチャットボットが従業員の相談に対応し、初期段階でのストレス管理や問題解決を支援するという取り組みです。これにより、従業員はいつでもどこでも必要なサポートを受けることが可能になりました。
メンタルヘルスの支援を充実させることで得られる効果は、従業員一人ひとりの働きやすさを向上させるだけではありません。企業全体としても、生産性の向上や職場環境の改善といった形でプラスの影響が現れます。また、こうした取り組みが外部からも評価されることで、企業のブランド価値を高めることにもつながるんです。
大切なのは、メンタルヘルスを支援する施策を「一時的なもの」ではなく、企業文化の一部として根付かせることです。そのためには、経営層の理解とサポートが欠かせません。企業全体で「従業員の心を大切にする」という姿勢を示すことが、従業員のエンゲージメントを高める大きな鍵となります。
これからの時代、メンタルヘルスの支援は「選択肢」ではなく「必須項目」になるでしょう。このトレンドを積極的に取り入れることが、企業の持続的な成長にとって欠かせない要素となるのです。
トレンド2:治療と仕事の両立支援
今、がんや生活習慣病の治療を受けながら働く人が増えています。厚生労働省の調査によると、日本の労働人口のうち約3割の人が何らかの持病を抱えながら仕事をしているそうです。こうした状況の中で、企業が「治療と仕事を両立できる環境」を整えていくことが、これまで以上に求められています。
超高齢社会が進む中、がんや糖尿病、精神疾患を抱えながら働く人も増えています。厚生労働省の調査では、がん患者の約40%が「働き続けたい」と考えている一方で、治療と仕事の両立が難しく、やむを得ず辞めてしまう人も多いのが現実です。
さらに、治療には高額な費用がかかるため、収入を維持しながら生活を安定させることが不可欠です。企業の支援がないと、治療と仕事の両立はとても難しくなり、働き方や休暇制度の選択肢が少ないと、結果的に離職せざるを得なくなってしまいます。
では、実際に企業はどんな「治療と仕事の両立支援策」を取り入れているのでしょうか。例えば、フレックスタイム制や時短勤務制度を活用して、治療のスケジュールに合わせた柔軟な働き方を支援する企業が増えています。サイボウズでは「100人100通りの働き方」を推奨し、それぞれの事情に応じた勤務スタイルをサポートしています。
また、通院や治療のための特別休暇を設ける企業も増えていて、大手企業では「がん治療休暇」を導入し、従業員が安心して治療に専念できるような環境づくりが進んでいます。さらに、リモートワークを活用することで、自宅で治療を受けながら仕事を続けることが可能になってきました。例えば、Google Japanでは社内カウンセリング制度やストレス管理プログラムを導入し、メンタルヘルスのサポートを充実させています。
こうした支援策があることで、企業と従業員の双方に大きなメリットが生まれます。従業員が安心して働けるようになると、企業に対する信頼感が増し、仕事へのモチベーションもアップします。さらに、治療のために離職する人が減ることで、経験豊富な従業員を長く確保できるというメリットもあります。実際、福利厚生の充実によって離職率が低下した企業の事例はたくさんあります。加えて、健康経営を推進することで企業のブランド価値が向上し、経済産業省の「健康経営優良法人」に認定される企業も増えてきています。
トレンド3:健康増進
今、従業員の健康管理は企業にとって非常に重要な課題となっています。健康経営という言葉を聞いたことがある方も多いと思いますが、これは企業が従業員の健康を支援し、その結果として生産性向上や医療費削減につなげる考え方です。
現代社会では、長時間労働やストレス、運動不足、偏った食生活などが原因で、生活習慣病やメンタルヘルスの問題が深刻化しています。厚生労働省の調査によると、従業員の約6割が「健康維持が難しい」と感じているそうです。特にストレスによる精神的な負担は、業務パフォーマンスの低下や離職率の上昇にもつながるため、企業が積極的に支援することが求められています。
では、実際に企業はどんな「健康増進策」を取り入れているのでしょうか。例えば、ウォーキングイベントや社内フィットネスプログラムを導入する企業が増えています。ある企業では、歩数を競うアプリを活用して、従業員の運動習慣を促進し、健康意識を高めています。また、健康診断の拡充やストレスチェックの実施も一般的になってきました。例えば、大手IT企業では、社内にカウンセリングルームを設置し、メンタルヘルスの相談が気軽にできる環境を整えています。さらに、食事の面では、社員食堂で栄養バランスの取れたメニューを提供する企業も増えており、健康的な食生活を支援することで、従業員の生活習慣改善を後押ししています。
また、リモートワークの普及により、在宅勤務が増える中で、健康管理の重要性がさらに高まっています。座りっぱなしの生活が長時間続くと、血流の悪化や運動不足が原因で、体調不良を引き起こすこともあります。これを防ぐために、一部の企業ではオンラインフィットネスプログラムを導入し、従業員が自宅で簡単にエクササイズできる環境を整えています。例えば、毎日決まった時間にストレッチタイムを設けたり、ウェアラブルデバイスを活用して健康データを管理する仕組みを導入することで、従業員の健康意識を高めています。
こうした健康増進策を導入することで、企業と従業員の双方にメリットがあります。健康支援が充実すると、従業員のモチベーションやエンゲージメントが向上し、生産性が高まります。さらに、病気の予防や早期発見が可能になることで、企業の医療費負担が軽減される効果も期待できます。実際に、健康経営を推進した企業では、従業員の健康意識が向上し、欠勤率や離職率の低下につながった事例が数多く報告されています。
また、従業員の健康管理に投資することは、企業のブランド価値向上にも寄与します。健康支援に積極的な企業は、採用市場においても魅力的に映り、優秀な人材を確保しやすくなるのです。経済産業省の「健康経営優良法人」に認定されることで、企業のイメージ向上にもつながり、長期的な競争力強化にも貢献します。
トレンド4:自己啓発
今、従業員が自己啓発に対する関心を高め、企業にもその支援が求められる時代になっています。その背景には、働き方の多様化やキャリアアップの重要性が高まっていることが挙げられます。
現代のビジネス環境では、技術の進歩や市場の変化が激しく、個々のスキル向上がますます必要とされています。特に、デジタルスキルやマネジメント能力、語学力などの習得が求められ、従業員は学び続けることがキャリアを築くうえで欠かせない要素となっています。ある調査によると、約7割の従業員が「成長できる環境がある会社で働きたい」と考えているそうです。企業が従業員の自己啓発を支援することは、結果的に会社の競争力強化にもつながります。
では、実際に企業はどんな「自己啓発支援策」を取り入れているのでしょうか。例えば、研修制度の充実や、社内外の講座受講補助を提供する企業が増えています。ある企業では、オンライン学習プラットフォームを導入し、従業員が好きな時間にスキルアップできる環境を整えています。また、語学習得を支援するために、英会話スクールの費用を会社が一部負担するケースもあります。さらに、社内メンター制度を設け、経験豊富な社員が若手の成長をサポートする仕組みを作っている企業も多くなっています。
また、自己啓発の支援があると、従業員のエンゲージメントが高まり、会社への定着率向上につながります。例えば、スキルアップの機会があることで「この会社で成長できる」と感じる人が増え、モチベーションの向上にもつながります。ある企業では、自己啓発の支援を強化した結果、離職率が大幅に下がったという報告もあります。また、新しいスキルを身につけた従業員が社内で活躍することで、企業全体の生産性向上にも寄与します。
自己啓発支援に積極的な企業は、採用市場においても魅力的に映ります。求職者は「スキルアップできる環境があるかどうか」を重視する傾向にあり、企業が学びの機会を提供することで、優秀な人材の獲得がしやすくなります。また、従業員の成長を支援することは、企業のブランド価値向上にもつながります。
トレンド5:柔軟な働き方
次にご紹介するのが「柔軟な働き方」です。リモートワークやフレックスタイム制といった言葉、今では日常的に聞くようになりましたよね。
Gallupが2023年に発表した「State of the Workplace」[2]によると、柔軟な働き方が従業員のエンゲージメントを大幅に高めることが明らかになっています。リモートワークを導入することで通勤時間を削減でき、従業員のストレスが軽減されるだけでなく、家族との時間を確保することもできます。
一方で、リモートワークだけではなく、ハイブリッドワークという形態も注目されています。これは、週に数日はオフィスで働き、残りの日はリモートで働くというスタイルです。これによって、オフィスでの対面コミュニケーションによる創造的なアイデアの交換と、リモートワークによる集中作業の両立が可能になります。
また、フレックスタイム制の導入も重要な要素です。従業員が自分のライフスタイルに合わせて勤務時間を選べる制度を取り入れることで、仕事と生活のバランスを取りやすくなります。特に子育てや介護をしている従業員にとって、この柔軟性は大きな魅力となります。
ただし、柔軟な働き方を実現するためには、明確なガイドラインや適切なツールの提供が必要です。例えば、オンラインミーティングツールやプロジェクト管理ツールを活用することで、離れた場所で働く従業員同士の連携がスムーズに行えます。
柔軟な働き方を取り入れることで、従業員の満足度やエンゲージメントが向上し、企業全体の生産性向上にもつながるでしょう。これからの時代、働き方に柔軟性を持たせることは、企業の成功に欠かせない要素となります。
歴史的な変遷からの含意
研究上の定義と実態の対比
黒住:
私からは学術研究の視点からお話しできればと思います。企業における施策というのは非常に多様で、また時代のトレンドにも左右されます。その中で、「自社ではどのような福利厚生制度を導入すべきか」という判断には悩ましい点が多く、なかなか一概には決められないのが実情です。そのような背景を踏まえて、今回は研究の成果がどのように制度設計のヒントになるのかという観点から、少し掘り下げてお話しできればと思います。
はじめに、福利厚生の歴史的変遷についてです。研究によって明らかになっている歴史的な背景をもとに、そこからどのような示唆が得られるのかを考えてみます。
まず、研究における「福利厚生の定義」を紹介します。例えば、次のような2つの定義があります。
- 「福利厚生とは、企業から従業員に対して給与とは別に支給される報酬の総称の一部である」[3]
- 「企業が主体となり、従業員およびその家族の経済的安定や、心身の健康維持・増進を目的として、賃金や労働時間などの中核的な労働条件以外に提供される金銭的・現物的なサービスの総称」[4]
両者はその具体性が異なりますが、「給与とは異なる報酬である」という点は共通しています。また、後者は少し厳密で、「企業が自主的に提供するもの」であることが明示されています。実は、研究上の定義ではこのように明確に示されている一方で、実践の現場では定義がやや曖昧であるという経緯があります。
その点を指摘する研究として、福利厚生が日本企業の中でどのように発展してきたのかを整理した研究があります[5]。たとえば明治維新以降、近代化を支えた産業の一つである紡績業では、多数の作業員を雇用していたことから、企業側が住居、食事、保険などの生活支援を提供する必要がありました。そういった作業場の環境や、労働環境の改善も目的に整備されたものが「福祉施設」「厚生施設」と呼ばれ、福利厚生の原型と考えられています。
つまり、制度としての定義が先にあったというより、まず実践的な整備が先に行われ、それに後から名前がついた、という歴史的な経緯が想像されます。福利厚生には法定内・法定外の分類がありますが、特に法定外の領域では多様性が広がっています。この多様性もまた、定義とは別に実践の中で徐々に形作られてきた名残といえるでしょう。
研究によって提案された分類法
さらに、日本独自の福利厚生の特徴について研究[6]で報告されているいくつかの分類法があります。たとえば、「導入理念」に基づいて三つのパターンが提示されています。
- パターナリズム(父親的支援):企業や経営者が“父親的”な存在として、従業員の生活を包括的に支援するべきだという考え方。従業員を“家族”と見なし、その生活全体を守るという理念に基づいて、福利厚生制度を整備する。
- 使用者責任:企業が雇用主として当然負うべき責任として、従業員の安全・健康・生活の安定を支える制度を整える、という考え方。企業側からの義務的な意味合いが強い。
- 経営戦略:福利厚生を、企業の経営目標を達成するための戦略的手段として導入するという考え方。従業員満足度や定着率の向上、生産性向上など、直接的な経営効果を狙って福利厚生を整備します。
これら三つの理念は、現代の福利厚生を評価・設計する上でも、重要な指針となりえます。また、日本の福利厚生がどのような特徴をもっているかという分類[7]も存在します。
- 網羅性が高い:健康・医療支援、経済的支援、住宅支援など、多岐にわたる施策が揃えられている
- 目的・機能の多様性:福利厚生が持つ目的は「従業員満足」や「生産性向上」など多様である
- 法定外福利の比重が高い:法律で定められたもの以上に、企業独自の取り組みが多く、特に大企業ほどその傾向が強くなっている
- 住宅支援の重視:歴史的に、住居支援が早期から制度化されていたため、現在もこの分野を重視する傾向は残っている
- 企業規模による差異:大企業では幅広く手厚い福利厚生が整備されている一方で、中小企業では内容が限定的である
以上のように、歴史、理念や特徴の分類を踏まえると、福利厚生制度の設計において、「通例を踏襲するか」「独自性を出すか」という選択肢が生まれます。つまり、自社がどこに重点を置き、どのような形で導入していくかを判断するための基準として、歴史的な変遷や理念的分類が活用できます。
特に人材マネジメントの観点からは、在籍社員の定着と新規採用への惹きつけの両面で福利厚生は重要な役割を果たします。自社がどのようなスタンスをとるのかを検討する上で、過去の系譜も判断材料になればと思います。
テレワーク研究からの含意
テレワーク導入の現状と定着状況
ここからは、テレワークに関する研究についてご紹介したいと思います。テレワークは近年広がった柔軟な働き方の一つであり、多くの企業が福利厚生の1つとしても関心を持っています。そのため、これまでの研究成果を掘り下げることで、自社における導入のヒントを得る手がかりとなるかもしれません。
まず、テレワークの「現在の定着状況」についてです。テレワークという言葉や概念自体はかなり認知が進んでおり、自社で導入すべきかどうかを検討している企業も多いでしょう。実際の導入率を見ると、高くはないものの、一定の企業において定着してきたという報告もあります。
つまり、コロナ禍という特殊な状況によって一気に認知が広がったテレワークですが、その後の導入については、各企業が「無理のない範囲で定着させる」方向にシフトしていることが読み取れます。
テレワークを福利厚生として捉える視点
さて、テレワークを「福利厚生の一環」として捉えるかどうかには、議論の余地があります。多くの企業がテレワークを導入する理由としては、「多様な働き方を認めることによって、従業員を支援したい」という意図があります。このような考え方は、テレワークは従業員支援型の福利厚生と捉えることができます。
一方で、「テレワークによって業務の効率が上がる」「成果が向上する」といった経営的な視点から導入を進めている企業もあります。この場合、テレワークは福利厚生というよりも、「経営戦略の一部」として位置づけられることになります。このように、テレワークの導入目的によって、その制度が持つ意味合いが変わるという点は非常に興味深いところです。
加えて、海外で大手企業が次々とオフィス勤務に戻す傾向が見られるのに対して、日本独自の事情から、テレワークが生産性を高めることを指摘する研究結果[8]も存在します。具体的には、通勤時間や通勤ラッシュの影響です。
まず、日本でもテレワーカー全体でみると、「仕事と家庭の両立」に悩むケースが増え、ストレスが増加していました。しかし、そういったストレスがあるといって、必ずしも生産性が下がるわけではなかったのです。とりわけ、通勤時間が1時間以上ある、または通勤ラッシュがある人たちに注目すると、オフィスへ出社するよりテレワークの方が、仕事の生産性が高い傾向がわかったのです。
通勤にかかる負担が大きい場合、その時間を省略できるテレワークは時間的・精神的コストの削減につながり、結果として生産性の向上に貢献するということだと考えられます。この点は、日本特有の都市圏通勤の実態とも関係が深いといえるでしょう。
柔軟な働き方の副作用と健康リスクへの配慮
もう一つ注目されている研究テーマが、「テレワークにおける柔軟な働き方が持つ副作用」です。柔軟な働き方をしている人、つまりテレワークなどで自分の働き方をある程度コントロールできる人は、仕事への熱意や自己裁量感が高い傾向にあります。しかしその一方で、疲労感が高く、健康よりも成果を優先する傾向があるというリスクも報告されています。
つまり、柔軟に働けること自体が裏目に出てしまうことがある、というのが研究の示す重要なポイントです。こうした副作用をどうすれば軽減できるのかという点については、当社の別のセミナー[9]で詳しく取り上げておりますので、ここでは要点だけお伝えします。
最も重要なのは、健康を第一に考える姿勢を企業として伝え、支援することです。たとえば、柔軟な働き方が可能になったことで「もっと働ける」と感じてしまい、無理をして労働時間を増やしてしまうケースが見られます。一時的には成果が出るかもしれませんが、長期的には健康を損ない、職場や家族に負担をかける結果にもなりかねません。
したがって、自分の限界を受け入れた上での現実的な業務計画を立てることや、周囲が互いにフォローし合う仕組みを整えることこうした点は、テレワークを「福利厚生」として導入する際に特に意識しておくべきです。
ミクロ視点の研究からの含意
ニーズ把握の必要性
最後に、3つ目の視点として「ミクロ視点」に関する研究をご紹介します。ここでは、福利厚生を利用する従業員の視点に立った研究結果をご紹介し、それが企業での制度導入にどのようなヒントを与えるかを考えていきます。
まず最初のポイントは、従業員のニーズを把握することの重要性です。背景として、コロナ禍以降、従業員の仕事に対する考え方や、福利厚生への関心が高まったと報告があります。
海外ではこの傾向が特に顕著で、「大辞職」や「静かな退職」といった現象がおき、多くの人々が自分に合った働き方や報酬、待遇を求めて職場を離れていったのです。企業側としても、こうした離職を防ぐために、福利厚生制度の見直しや充実を図る必要があるという認識が広まり、制度設計の再検討が進んだと報告[10]されています。
また、制度を設ける際には、その制度を利用できない従業員がどのように感じているかにも注意が必要です。一例として、育児休暇制度についての調査があります[11]。この調査では、育児休暇制度が「従業員に求められて導入された」にもかかわらず、満足度が低いというアンケートの結果が出たのです。
その理由を詳しく見てみると、実際には、制度を利用する資格を有していない人からの不満の声が、集計結果に大きく反映されていたということです。この結果はいくつかの捉え方が可能ですが、企業側への含意としては、要望に応えて制度を用意するだけでも十分とは言えず、利用者に対する周囲の理解や、制度を利用しやすい職場環境の整備も並行して進めなければ、本当の意味でニーズに応えることはできない、ということが示されたのです。
「認知度」を高める必要性
ミクロ視点の研究からの含意のもう1点は、福利厚生制度の「認知度」を高める必要性です。研究によれば、福利厚生制度が「自分にも利用できる」とおもう制度が多いほど、従業員の離職率が下がり、在職期間が長くなるという傾向が見られています[12]。実際に利用するかとは別に、整備されていると気づいてもらうだけでも、制度の価値が出てくるのです。
しかし実際には、企業側が多くの制度を用意していても、従業員がその存在を知らないというケースが少なくありません。せっかく整備された制度であっても、認識してもらえていないことで、結果として「制度の有効性が十分に発揮されない」という問題を引き起こします。この点から考えると、福利厚生制度の整備に加えて、その制度の存在をしっかりと従業員に伝えるための施策が必要です。
では、制度の認知度を高めるためには、どのような取り組みが効果的なのでしょうか。ここでは研究や実践例に基づく2つの具体策をご紹介します。
まず一つ目が、福利厚生のマニュアルの整備です。これは、自社が提供している福利厚生制度を、従業員に分かりやすく紹介するための文書やガイドを用意する取り組みです。文章では目を通してもらいにくいこと、担当者をつけて相談に一人ひとり応じるコストを省く目的から、AIチャットボットを活用する事例もあるそうです。会社ごとに、こうしたマニュアル整備の質にはばらつきが大きいといわれているため、福利厚生の見直しの一環として、再検討するのも良いでしょう。
もう一つの取り組みが、福利厚生のアンバサダーを設置する方法です。近年では、社内ブランドの強化や制度の周知を目的にアンバサダー制度を導入する企業が増えていますが、それを福利厚生にも応用する形です。
この事例を検討した研究[13]では、アンバサダーが活動する機会をきちんと設けることが鍵になると指摘されています。制度の紹介ワークショップを開催したり、従業員の質問に対応する場を設けることで、情報伝達の質を高める工夫がなされています。
ミクロ視点の研究や実践例から言えるのは、従業員のニーズや働き方の変化に柔軟に対応しながら、「認知」と「理解」を促進する仕組みをどう設けるかが、今後の制度運用における重要なポイントになると言えるでしょう。
Q&A
Q:共有されたトレンドの中で、導入しやすいものと慎重にすべきものについて教えてください。
樋口:
導入のしやすさは、まず「予算」が大きなポイントです。施策を進めるにはコストがかかるため、経営側の理解と予算確保が必要です。そのためには、従業員のニーズをサーベイやアンケートで把握し、「求められている」というデータを示すことが説得材料になります。また、本編でも紹介した「アンバサダー」のように、既存の仕組みを活用すれば、コストをかけずにできる取り組みもあります。予算の有無に応じて工夫していくことが大切です。
Q:福利厚生に関わるエンゲージメントサーベイの活用について教えてください。
樋口:
サーベイでは、数値でエンゲージメントの状態を把握できます。ただ、「どんな施策が必要か」といった具体的な声は、自由記述に表れることが多いです。そのため、コメントを丁寧に読み、共通するニーズを見つけることが重要です。また、まず試しに導入して反応を見る「トライアンドエラー」の姿勢も必要です。特に福利厚生については、定性的な声をどう読み解くかが鍵になります。
Q:人材や費用といったリソースが限られる中で、従業員のニーズに応えるために優先すべき対応は何でしょうか。
黒住:
施策の存在をしっかり伝えることが、従業員のエンゲージメントや定着につながるという研究での報告が参考になります。 つまり、新しい施策を追加できなくても、「企業として従業員を大切にしている」「そのために取り組みを進めている」といったことを丁寧に周知できれば、間接的ですが従業員のニーズに答えることにつながります。リソースが限られているなかでも、情報の共有は、比較的取り組みやすいと考えられます。
樋口:
別の視点では、お金とのバランスは避けて通れないところだと思います。本日ご紹介したトレンド5選のように、サーベイや統計で導入率が高いとされている人気施策の中で、まだ取り入れていないものがあれば、まずはそうした実績のあるものから検討するのが良いと思います。限られたリソースの中でも、他社で評価されているもの、導入が進んでいるものを参考にすることで、優先度の判断もしやすくなるのではないでしょうか。
[1] 独立行政法人労働政策研究・研修機構(2020). 企業における福利厚生施策の実態に関する調査-企業/従業員アンケート調査結果. p25
[2]Gallup, Inc. (2023). State of the global workplace: 2023 report.
[3] Li, X. (2023). Employee Benefits and its Impacts on Business Performance-A Systematic Review. SHS Web of Conferences. https://doi.org/10.1051/shsconf/202317003021.
[4] 谷田部光一(2014)「わが国の福利厚生の現状とこれからの方向」『政経研究』第51号第1巻, pp. 81-114
[5] 福本 恭子(2013).戦前における紡績業従事者の福利厚生—先進的な企業の取組み— 経営研究, 64(2), 49-65. の研究を参考
[6] 脚注4と同様
[7] 脚注4と同様
[8] Kazekami, S. (2020). Mechanisms to improve labor productivity by performing telework. Telecommunications Policy.
[9] 柔軟な働き方の落とし穴:自己危険行動から従業員を守るには(セミナーレポート)(https://www.business-research-lab.com/250327-3/)
[10] Zhang, O., & Xue, Y. (2023). Employee resignation study in Fairfax County. Journal of Emerging Investigators. https://doi.org/10.59720/22-141.
[11] Crosgrove, D., Wedding, D., Zugelder, M., & Blandford, K. (2023). Childcare Assistance Not a Major Draw for Most Employees. American Journal of Management. の研究を参考
[12] Yamamoto, H. (2011). The relationship between employee benefit management and employee retention. The International Journal of Human Resource Management, 22(17), 3550-3564
[13] Perrault, E., & Hildenbrand, G. (2019). Development of a Benefits Ambassadors programme to leverage coworker relationships to increase employee knowledge. Knowledge Management Research & Practice, 17, 306 – 315. https://doi.org/10.1080/14778238.2019.1609342.
登壇者
 樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
早稲田大学政治経済学部卒業、カリフォルニア州立大学MBA修了、UCLA HR Certificate取得、立命館大学大学院博士課程修了。博士(人間科学)。国家資格キャリアコンサルタント。ビジネスの第一線で30年間、組織と人に関する実務経験、専門知識で、経営理論を実践してきた人事のプロフェッショナル。通信会社で人事担当者としての経験を積み、その後、コンサルティングファームで人事コンサルタントやシニアマネージャーを務め、さらに銀行で人事部長などの役職を歴任した後、現在はFWD生命にて執行役員兼CHROを務める。ビジネスと学術研究をつなぐ架け橋となることを目指し、実践で役立つアプローチを探求している。
 黒住 嶺 株式会社ビジネスリサーチラボ フェロー
黒住 嶺 株式会社ビジネスリサーチラボ フェロー
学習院大学文学部卒業、学習院大学人文科学研究科修士課程修了、筑波大学人間総合科学研究科心理学専攻博士後期課程満期退学。修士(心理学)。日常生活の素朴な疑問や誰しも経験しうる悩みを、学術的なアプローチで検証・解決することに関心があり、自身も幼少期から苦悩してきた先延ばしに関する研究を実施。教育機関やセミナーでの講師、ベンチャー企業でのインターンなどを通し、学術的な視点と現場や当事者の視点の行き来を志向・実践。その経験を活かし、多くの当事者との接点となりうる組織・人事の課題への実効的なアプローチを探求している。