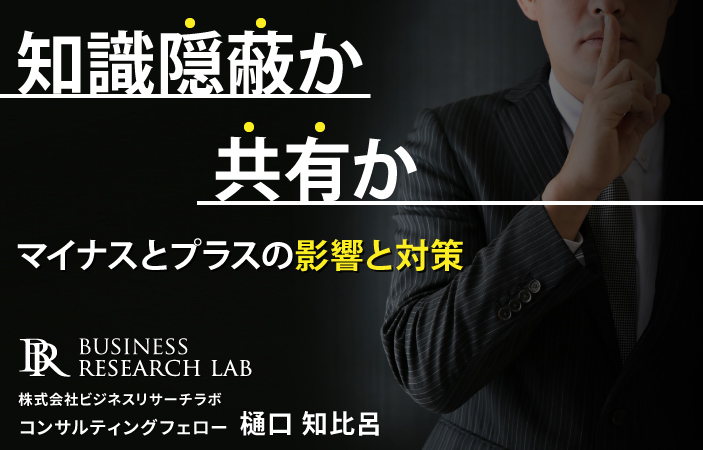2025年4月28日
知識隠蔽か共有か:マイナスとプラスの影響と対策
現代の組織が抱える課題の中で、「知識隠蔽」は特に深刻な影響をもたらす問題として注目されています。従業員間の知識共有が阻害されることで、創造性や生産性の低下、信頼関係の希薄化など、組織の健全な発展を妨げる多くのリスクが生じます。本稿では、知識隠蔽に関する近年の研究成果に基づき、その先行要因や結果、そしてそれに対処するための実践的な示唆について考察します。
具体的には、知識隠蔽を引き起こす要因の分析だけでなく、それが組織や従業員にどのような影響を及ぼすかについてそのマイナス面とプラス面を明らかにします。また、その解決に向けてどのような取り組みが有効であるかについても詳しく述べます。さらに、このテーマを掘り下げ、知識隠蔽がもたらすリスクを軽減し、それを克服するための具体的な道筋を提案します。
虐待的リーダーシップや不信感、燃え尽き症候群、知識縄張り意識などが知識隠蔽に関係する
組織における知識隠蔽の研究は、近年急速に発展を遂げ、その複雑性と影響の広がりを示す重要な分野として注目されています。知識隠蔽の領域の研究をメタ分析の手法を用いて体系化し、知識隠蔽の先行要因と結果の関係を包括的に整理した研究を紹介します[1]。メタ分析とは、独立して実施された複数の研究結果を統合し、それらを解析する方法です。本研究では、131の研究、147の先行要因の標本数(職務特性、リーダーシップ、態度、モチベーションなど)、47,348人の参加者から得られたデータを分析し、知識隠蔽に関する新たな知見を提供しています。
調査の結果、知識隠蔽にはいくつかの顕著な先行要因があることが明らかになりました。例えば、虐待的リーダーシップ(リーダーが従業員に対して侮辱や批判、無視などの有害な行動を取ることで、従業員の心理的安全性やモチベーションを低下させるリーダーシップスタイル)や不信感、燃え尽き症候群、知識縄張り意識(自分が持つ知識を個人的な資産と見なし、他者に共有することを避けたり制限したりする心理的態度や行動)などが知識隠蔽と強い正の相関(一方が増えれば、もう一方も増える関係)を示しました。
一方で、倫理的リーダーシップ(公正さ、誠実さ、透明性を重視し、従業員に対して模範的な道徳的行動を示すリーダーシップスタイル)や心理的安全性、向社会的動機づけ(他者や社会に貢献したいという思いや、他者の利益を優先する行動を促す内的な動機)は負の相関(一方が増えると、もう一方は減る関係)を示しました。また、知識隠蔽は創造性や業務遂行能力の低下、不公正や職場行動の悪化など、組織や個人におけるネガティブな結果と関連していることも確認されました。
一方で、知識隠蔽と知識共有の欠如は異なる概念であることが実証的に示されています。知識隠蔽は意図的に知識を隠す行為であり、知識共有の欠如は積極的に知識を提供しない状態であるため、それぞれの動機や行動の意図が異なるからです。
これらの知見には、いくつかの実践的含意が考えられます。まず、組織は倫理的リーダーシップや心理的安全性を高める施策を導入することで、知識隠蔽を緩和する可能性があります。リーダーが部下との信頼関係を築き、心理的に安全な環境を提供することは、知識共有を促進し、業務の効率性や創造性を向上させるために有用です。また、従業員の燃え尽き症候群や不信感を軽減するために、適切なストレス管理や職場環境の改善に注力することも効果的でしょう。
マネジメントの観点からは、知識隠蔽を防ぐための包括的な戦略が重要です。本研究で示された知識隠蔽の先行要因を踏まえ、組織文化の見直しや職務設計の工夫が求められます。例えば、競争的風土を緩和し、協調的風土を育むことで、従業員が知識を共有することへの心理的障壁を下げることが期待されます。また、知識隠蔽と関連のあるリーダーシップ行動に対する研修を実施し、リーダーの行動変革を促すことも有効です。
さらに、知識隠蔽の影響を長期的に捉える視点も重要です。創造性やタスクパフォーマンスの低下、職場関係の悪化といった負の影響は、短期的な業績だけでなく、組織の持続可能性にも影響を及ぼす可能性があります。そのため、知識隠蔽の予防策を組織全体のナレッジ・マネジメント戦略に組み込むことが必要です。
心理的安全性や倫理的リーダーシップ、協力的な組織風土などは、知識隠蔽を減少
もう一つメタ分析を紹介します。知識隠蔽に関する過去10年間の研究をレビューし、その特性や影響、そして今後の研究課題について整理した研究があります[2]。本研究では、2008年から2018年の間に発表された35本の論文を対象に、文献の特性をナラティブな方法で分析し、知識隠蔽に関わる理論的枠組みや実践的な課題を明らかにしました。
このレビューの結果、知識隠蔽がさまざまな要因と関連していることが示されました。主な先行要因として、従業員間の不信感や虐待的リーダーシップ、役割の曖昧さやタスクの過剰負担などが挙げられます。一方、心理的安全性や倫理的リーダーシップ、協力的な組織風土などは、知識隠蔽を減少させる要因として確認されました。さらに、知識隠蔽は創造性や業務遂行能力、職場の人間関係に悪影響を及ぼし、従業員間の協力を阻害する結果が示されています。
これらの知見を基に、組織における知識隠蔽への対応策として、いくつかの実践的含意が導き出されています。例えば、従業員間の信頼関係を構築するために、定期的なフィードバックの共有やチームビルディング活動を行うことが効果的です。また、心理的安全性を高める施策を導入することで、従業員が知識を共有しやすい環境を整備することが重要です。さらに、役割の曖昧さやタスクの過剰負担を軽減するための職務設計や労働条件の見直しも、知識隠蔽の抑制に寄与するでしょう。
マネジメントの観点からは、リーダーシップの質を向上させることが鍵となります。特に、倫理的で変革的なリーダーシップスタイルは、従業員のモチベーションを高め、信頼関係を促進する効果があります。これには、リーダーが従業員の意見を尊重し、公平性や透明性を重視する姿勢を示すことが含まれます。また、従業員が自らの業務において意思決定の自由度を感じられるよう、権限委譲を進めることも有用です。
さらに、知識隠蔽が個人の性格特性や文化的背景と密接に関連していることから、組織は多様性を尊重しつつ、従業員の感情的知性を高める研修プログラムを導入することが有益です。例えば、従業員が自己管理や共感能力を向上させることで、職場での協力的な行動が促進され、知識隠蔽が減少する可能性があります。
また、文化的多様性が進む現代の職場においては、異文化間の違いを理解し、それに応じたアプローチを採用することが求められます。例えば、直接的な意見交換を好む文化もあれば、間接的な表現を重視する文化も存在します。そのため、企業は異文化トレーニングを実施し、従業員が多様な視点を理解し、適切に対応できるようにする必要があります。
知識隠蔽は、従業員個人、チーム、さらには組織全体に影響を与える
次に、体系的な文献レビューを通じて、知識隠蔽の先行要因、結果、そしてその緩和のための戦略を包括的に検討した研究を紹介します[3]。本研究は、過去の文献を批判的に分析し、知識隠蔽を説明するための理論的フレームワークとして組織行動修正モデルを提案しています。
組織行動修正モデルは、行動科学の原則に基づき、従業員の行動を強化または修正するためのアプローチです。このモデルでは、知識隠蔽を従業員の学習された行動として捉え、それを形成する要因(例えば、組織の報酬制度、上司の管理スタイル、職場の心理的安全性)を特定し、望ましい行動へと導く仕組みを設計することが重要とされます。具体的には、知識を共有する行動に対して適切なインセンティブを提供する、あるいは知識隠蔽を抑制する環境を整えることで、組織全体のパフォーマンス向上を目指します。
研究では、知識隠蔽は個人的要因(内発的)および組織的要因(外発的)によって誘発され、従業員個人、チーム、さらには組織全体に影響を与えることが明らかになりました。例えば、従業員間の不信感や競争的な職場環境、ナルシシズムや縄張り意識といった性格特性が知識隠蔽の原因となることが確認されています。
一方で、心理的安全性や協力的な組織文化は知識隠蔽を抑制する効果があるとされています。さらに、知識隠蔽は従業員の創造性や生産性を低下させ、チームワークやイノベーションの阻害要因となることも示されました。
実践的な含意として、知識隠蔽を軽減するためには、従業員間の信頼構築や心理的安全性の向上が鍵となります。これには、フィードバックの共有を促進し、従業員が安心して意見を表明できる職場環境を整えることが有効です。また、リーダーシップの質を高めることも重要です。
具体的には、倫理的で支持的なリーダーシップスタイルが従業員のモチベーションを向上させ、知識共有を促進する効果が期待されます。リーダーが模範を示し、従業員に協力的な行動を奨励することで、組織全体での知識隠蔽の削減につながるでしょう。
さらに、組織の文化や構造の見直しも必要です。柔軟で支持的な文化を育むことで、従業員が積極的に知識を共有する意欲を高めることができます。また、役割の曖昧さや過剰なタスク負担を減らす職務設計の改善も、知識隠蔽を抑制する上で有用です。これに加え、従業員の感情的知性を高めるための研修プログラムを導入することも効果的です。これにより、従業員は自己管理能力や共感力を向上させ、協力的な行動が促進されるでしょう。
本研究で提案された組織行動修正モデルは、知識隠蔽行動を包括的に捉えるためのフレームワークとして、マネジメントへの重要な洞察を提供します。このモデルは、知識隠蔽を引き起こす要因とその結果、さらにその行動を修正するためのメカニズムを統合的に説明しています。たとえば、心理的安全性の向上や知識共有の動機付けといったポジティブな強化を通じて望ましい行動を促進し、不信感や不公正な待遇などネガティブな強化の影響を最小化することで、知識隠蔽を効果的に軽減できることが示されています。
組織においては、知識隠蔽を抑制し、知識共有を奨励する戦略を統合的に実施することが重要です。これには、リーダーシップ研修や文化的多様性を考慮した施策の導入が含まれます。また、従業員の行動を定期的に観察・評価し、知識隠蔽を減らすための具体的な行動計画を策定することも効果的です。
知識隠蔽の動機に、同僚の隠蔽、責任回避、罰則回避あり
企業内における問題隠蔽の動機を分析し、その要因や影響を理論的に解明した興味深い研究があります[4]。本研究は、部下と管理職が共存する多世代型組織を対象に、特定の問題が隠蔽される状況について数理モデルを用いて検討しました。企業が抱える問題が時間の経過とともに拡大する場合、部下が報告をためらう動機が強まるという点に焦点を当てています。このような隠蔽行動が組織全体の効率や社会的福祉にどのような影響を与えるのか、詳細に分析されています。
本研究の主な結果として、以下の点が明らかになりました。第一に、他のメンバーが報告するか否かが、個々の報告インセンティブに大きく影響を与える「相補性」が存在することが示されました。つまり、同僚が報告を行えば自分も報告する可能性が高まり、逆に隠蔽する場合には自分も隠す傾向が強まることが分かりました。
第二に、問題の規模が大きくなるほど、部下が報告をためらう傾向が強まることが示されました。例えば、実験結果においても、問題の深刻度が増すにつれ、部下が上司への報告を控える割合が有意に上昇していました。これは将来的に自身が管理職となった際に、その問題の責任を引き継ぐことを避けたいという意識が働くためと考えられます。
第三に、管理職に対する罰則が厳しくなる場合、部下は罰則回避のために問題を隠蔽する動機が増加するという逆説的な結果が得られました。ここで「逆説的な結果」とは、本来であれば問題の抑止や適切な対応を促すことを目的とした管理職への罰則強化が、むしろ部下による問題の隠蔽を助長し、結果として組織全体の問題解決を遅らせるという意外な現象を指しています。つまり、厳しい罰則が組織の透明性を高めるどころか、部下が責任回避のために情報を隠すインセンティブを生み出し、逆に組織の健全な機能を阻害するという予期せぬ影響をもたらしているのです。
本研究から得られる実践的な示唆は、組織設計やインセンティブ設計において重要です。特に、問題の報告と解決を促進するための報酬体系や罰則の設計について慎重な配慮が必要であることが強調されています。例えば、管理職が問題を解決する能力や努力に対して適切な報酬を提供することは有用ですが、罰則を過度に強調すると部下が報告をためらう可能性があるため、バランスの取れた設計が求められます。
また、組織文化の役割も重要です。本研究では、隠蔽行動が「複数の均衡」を形成する可能性が示されています。つまり、ある文化では報告が奨励され、他の文化では隠蔽が常態化することがあります。このため、企業は報告を奨励する文化を育むためのトレーニングや啓発活動を積極的に実施する必要があります。さらに、組織内で問題を公正に扱い、報告者がリスクを感じることのない環境を整備することが重要です。
マネジメントへの応用として、本研究は問題報告に対する柔軟なアプローチを提案しています。具体的には、問題が未解決である場合の責任を個々の管理職に集中させるのではなく、チームや組織全体で共有する仕組みを導入することが効果的です。また、問題報告を促進するために、報告の利点を強調し、隠蔽によるリスクを明確に伝えることも有用です。さらに、報告された問題が迅速かつ公平に処理される仕組みを構築することで、部下の信頼を得ることができます。
トップマネジメントの支援が知識共有文化を醸成する
知識隠蔽が組織のパフォーマンスに及ぼす負の影響は広く知られていますが、その防止に向けた文化の形成におけるトップマネジメントの役割についての研究は十分に進んでいません。このギャップを埋めるべく、英国のハイテク・グローバル企業内の研究所を対象に実施した研究があります[5]。本研究は、従業員が知識隠蔽を避け、知識共有を促進する文化を醸成するためにトップマネジメントが果たす行動を探ることを目的としています。
この研究では、自然な環境で行動を観察する事例研究の手法を用いました。調査対象となった企業は、知識共有を業務の中核に位置づけており、従業員が自主的に知識移転に取り組んでいることが特徴です。データはインタビューや観察を通じて収集され、知識隠蔽行動を防ぐためのマネジメント行動に焦点を当てて分析されました。
調査の結果、トップマネジメントの積極的な支援が知識共有文化の醸成に極めて重要であることが明らかになりました。具体的には、ラインマネージャーやチームリーダーが従業員に知識移転を奨励し、これを昇進基準の一つとして設定することが、知識共有を促進する効果があることが示されました。
また、オープンプランのオフィス環境や、オープンドアポリシー(従業員が上司や経営陣と自由に意見や懸念を共有できるようにする開かれたコミュニケーション方針)も、同僚間での対話や協力を活性化し、知識隠蔽を抑制する要因となっていました。このような職場環境は、信頼やオープンなコミュニケーションを基盤としており、従業員が安心して知識を共有できる雰囲気を生み出していました。
さらに、経営陣が従業員の知識貢献を評価する具体的な行動も効果的であることが示唆されました。例えば、従業員が新しいアイデアを提出したり、特許を取得したりした場合、それを評価し、昇進の機会を提供することが重要です。こうした取り組みは、知識隠蔽を防ぐだけでなく、従業員のモチベーションを高め、組織全体の知識管理の質を向上させることにつながります。
本研究の実践的な含意として、知識共有文化の形成には、トップマネジメントが積極的な役割を果たす必要があることが挙げられます。管理職は、従業員に知識共有の重要性を理解させ、それを具体的な行動で示すことが求められます。また、職場の物理的な環境や組織文化も見直し、信頼と協力を促進するような仕組みを整えることが重要です。特に、オープンなコミュニケーションを奨励し、知識共有の価値を明確に伝えることで、従業員の知識隠蔽行動を軽減できるでしょう。
マネジメントへの応用としては、まず、知識共有を促進するためのインセンティブ制度を導入することが挙げられます。昇進や報酬の基準に知識共有を組み込み、それを評価対象とすることが効果的です。また、経営者は自らが模範を示し、知識共有を実践する姿勢を従業員に示す必要があります。さらに、物理的なオフィス環境やデジタルツールの活用によって、日常的な知識移転を支えるインフラを整備することも有益です。
回避的隠蔽が持つ社会的影響の深刻さ
職場における知識隠蔽行動の複雑なダイナミクスを明らかにした研究を紹介します[6]。本研究では、知識を意図的に隠す行為がどのように解釈され、どのような結果をもたらすのかについて、隠蔽者と対象者の双方の視点を分析しました。研究は2段階で行われ、オンラインパネルを通じて英語を話す多様な職種の従業員を対象に調査を実施しました。それぞれ、隠蔽者と対象者の視点から知識隠蔽の影響を検討しています。
本研究の結果は、知識隠蔽行動が単一の否定的行動ではなく、異なるタイプの隠蔽が異なる結果をもたらすことを示唆しています。具体的には、知識隠蔽の3つの主要な形態として、「合理化された隠蔽(隠蔽の正当性を説明する行動)」、「回避的隠蔽(意図的に重要な情報を回避する行動)」、および「間抜けなふりをする(知らないふりをする行動)」が挙げられます。
合理化された隠蔽は、相手との関係を損なう可能性はあるものの、他の2つの形式ほど報復意図を生じさせることは少ないとされます。一方、回避的隠蔽は人間関係の悪化や将来的な知識隠蔽意図を強く促進し、間抜けなふりをする行動も相手に否定的な感情を与えやすいことがわかりました。
特に注目すべきは、回避的隠蔽が持つ社会的影響の深刻さです。この形式の隠蔽は、対象者が拒絶と感じやすく、結果として報復行動や知識共有の低下を引き起こします。ここでの「報復行動」とは、回避的隠蔽によって知識や情報を意図的に共有されなかった人(対象者)が、それに対する不満や敵意を抱き、加害者(情報を隠蔽した側)や組織全体に対して対抗的な行動をとることを指します。このような連鎖反応は、職場全体の知識共有文化を損なう要因となり得ます。
一方で、合理化された隠蔽は比較的肯定的に受け取られることが多く、場合によっては関係の改善に寄与する可能性も示唆されています。これにより、知識隠蔽が一律に否定的な結果をもたらすわけではないという洞察が得られました。
この研究から得られる実践的な含意として、知識隠蔽を防ぐための戦略が挙げられます。たとえば、組織内での一体感や信頼関係を強化することが有用です。また、知識共有の重要性を啓発し、それを促進する制度や報酬体系を導入することも効果的です。
さらに、管理職は、知識隠蔽が持つ影響について従業員に意識を高めるとともに、特に回避的隠蔽行動を減少させるための取り組みを進める必要があります。具体的には、隠蔽行動を引き起こす要因となる職場環境の改善や、チームメンバー間のオープンなコミュニケーションを促進することが求められます。
また、この研究は知識隠蔽の発生を完全に抑止するのではなく、それに伴う悪影響を軽減することも重要であると示唆しています。従業員間の関係性を深め、報復行動の動機を減少させることが、職場全体の協力と透明性を向上させる鍵となるでしょう。管理者はこれらの知見を活用し、知識隠蔽行動の悪循環を断ち切るとともに、組織全体の知識共有文化を向上させることが期待されます。
知識隠蔽がポジティブな役割を果たす場合もある
職場における知識隠蔽の影響について包括的な文献レビューを行い、その概念と影響を探るとともに、今後の研究の方向性を示した研究があります[7]。本研究は、1997年から2017年の間に発表された英語および中国語の学術論文52本を対象とし、知識隠蔽が職場でどのような影響を及ぼすかを理論的および実証的に検討しています。特に、知識隠蔽が必ずしも否定的な結果をもたらすものではなく、状況によってはその影響が異なることを強調しています。
調査の結果、知識隠蔽は従業員間の信頼関係を損なう可能性がある一方で、一部の状況ではポジティブな役割を果たす場合があることが示されました。例えば、知識を隠す行為は、個人や組織の安全を守るために合理的に行われることがあります。さらに、未完成のアイデアや不確実な情報を早い段階で共有することを避けることで、誤解や混乱を防ぎ、組織の意思決定の質を向上させる場合もあります。
例えば、研究開発の段階で十分な検証が行われていない技術情報を安易に共有すると、誤った期待を生んだり、競争上のリスクを招いたりする可能性があります。そのため、情報を慎重に管理し、適切なタイミングで共有することが、組織にとって戦略的に有益となる場合もあります。
しかし、一般的には、知識隠蔽は組織内のコミュニケーションや協力を妨げ、結果としてパフォーマンスの低下や従業員のモチベーション低下につながるリスクがあります。また、中国のように権力格差が大きい文化では、知識隠蔽の発生頻度やその影響が他の文化と異なる可能性が指摘されました。
本研究は、実践的な含意として、知識隠蔽を最小化し、知識共有を促進するための人材管理戦略の重要性を強調しています。具体的には、信頼関係を構築し、透明性のあるコミュニケーションを奨励する職場環境を作ることが効果的です。例えば、リーダーは、従業員間の信頼を強化するために、一貫性のある行動や誠実さを示す必要があります。
また、従業員自身の貢献が認識され、評価されると感じられるような文化を醸成することも有用です。さらに、知識共有のインセンティブを提供することや、協力的な行動を奨励するプログラムを導入することで、知識隠蔽の減少が期待できます。
マネジメントへの応用として、リーダーシップの役割が重要です。特に、上司と部下の関係における権力差が知識隠蔽に与える影響を考慮する必要があります。中国のように権力格差が大きい文化では、リーダーが部下に対して強い尊敬と敬意を求める傾向があるため、リーダーはその影響を理解し、信頼を築くための対策を講じることが重要です。
また、社会的ネットワークの活用も知識隠蔽を減らすための有効な手段となり得ます。従業員間の結びつきを強化し、相互信頼を促進することで、知識の流れをスムーズにすることが可能です。
知識隠蔽への対応が組織の未来を形づくる
知識隠蔽が組織に与える影響は、創造性や生産性の低下、信頼関係の希薄化など、決して軽視できるものではありません。その要因としては、虐待的リーダーシップや不信感、燃え尽き症候群、知識縄張り意識といった問題が挙げられますが、同時にこれらを解決するための道筋も明らかになりつつあります。本稿では、心理的安全性や倫理的リーダーシップ、協力的な組織風土の重要性を強調しました。
知識隠蔽を防ぎ、知識共有を促進するためには、単なる個別施策ではなく、組織全体を巻き込む包括的な取り組みが必要です。例えば、リーダーシップ研修を通じて倫理的な行動を育むことや、フィードバック文化の確立によって従業員間の信頼を築くことが挙げられます。また、ストレス管理やタスクの過剰負担を軽減する施策は、燃え尽き症候群を防ぐとともに、より健全な職場環境を実現する鍵となります。
さらに、知識隠蔽の影響は短期的な業績だけでなく、組織の持続可能性にも関わる重大な課題です。創造性や業務遂行能力の低下、職場関係の悪化といった負のスパイラルを断ち切るためには、知識隠蔽を減少させる施策を組織の戦略に組み込む必要があります。
これからの時代、知識隠蔽を克服する取り組みは、単なる危機管理ではなく、組織の競争力を高める重要な投資と捉えるとよいでしょう。組織が従業員の声に耳を傾け、心理的安全性と協力的な風土を育むことで、知識共有が文化として根付いた職場を構築することができます。こうした取り組みは、組織が未来に向けて持続的に発展していくための土台となるでしょう。
脚注
[1] Skerlavaj, M., Cerne, M., & Batistič, S. (2023). Knowledge hiding in organizations: Meta-analysis 10 Years Later. Economic and Business Review for Central and South-Eastern Europe, 25(2), 79-102.
[2] Ruparel, N., & Choubisa, R. (2020). Knowledge hiding in organizations: A retrospective narrative review and the way forward. Dynamic Relationships Management Journal, 9(1), 5-22.
[3] Siachou, E., Trichina, E., Papasolomou, I., & Sakka, G. (2021). Why do employees hide their knowledge and what are the consequences? A systematic literature review. Journal of Business Research, 135, 195-213.
[4] Tajika, Tomoya, Concealment as Responsibility Shifting in Overlapping Generations Organizations (January 22, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3320364 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3320364
[5] Jasimuddin, S. M., & Saci, F. (2022). Creating a culture to avoid knowledge hiding within an organization: The role of management support. Frontiers in psychology, 13, 850989.
[6] Connelly, C. E., & Zweig, D. (2015). How perpetrators and targets construe knowledge hiding in organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(3), 479-489.
[7] Xiao, M., & Cooke, F. L. (2019). Why and when knowledge hiding in the workplace is harmful: a review of the literature and directions for future research in the Chinese context. Asia Pacific Journal of Human Resources, 57(4), 470-502.
執筆者
 樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
早稲田大学政治経済学部卒業、カリフォルニア州立大学MBA修了、UCLA HR Certificate取得、立命館大学大学院博士課程修了。博士(人間科学)。国家資格キャリアコンサルタント。ビジネスの第一線で30年間、組織と人に関する実務経験、専門知識で、経営理論を実践してきた人事のプロフェッショナル。通信会社で人事担当者としての経験を積み、その後、コンサルティングファームで人事コンサルタントやシニアマネージャーを務め、さらに銀行で人事部長などの役職を歴任した後、現在はFWD生命にて執行役員兼CHROを務める。ビジネスと学術研究をつなぐ架け橋となることを目指し、実践で役立つアプローチを探求している。