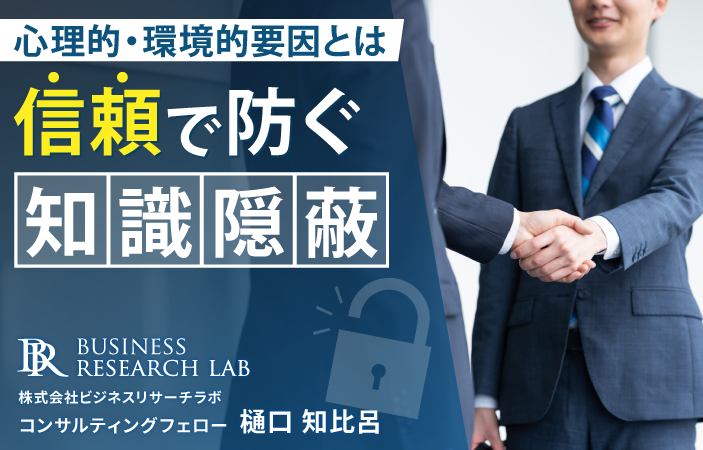2025年4月25日
信頼で防ぐ知識隠蔽:心理的・環境的要因とは
職場における知識隠蔽の影響は、近年、組織のパフォーマンスや従業員の行動に関する研究の中で注目を集めています。知識隠蔽とは、従業員が自身の持つ知識や情報を意図的に共有しない行動を指し、その背景には不信感や競争意識などの複雑な心理的・環境的要因が存在します。これまでの研究によれば、知識隠蔽は単なる知識共有の不足ではなく、組織内の信頼関係や文化、職務特性といったさまざまな要素に影響される意図的な行動であることが明らかになっています。
本コラムでは、知識隠蔽が組織に与える影響を多面的に分析し、職場環境の改善やマネジメントの実践的示唆について考察します。知識という貴重な資源を最大限に活用するためには、隠蔽行動を減少させる取り組みが重要です。具体的な研究成果を基に、組織が取ることが望まれる方策について深掘りしていきます。
知識隠蔽の3つの分類
組織における「知識隠蔽」という新たな概念を提唱した研究を最初に紹介します[1]。知識移転の失敗に焦点を当てたものです。本研究では、従業員が意図的に知識を共有しない「知識隠蔽」の行動を分類し、「無知を装う」「回避する」「虚偽の情報を提供する」といった具体的な形態を示しています。
研究はカナダ、アメリカ、インドを含む複数の地域の従業員を対象に、実施されました。その結果、知識隠蔽が組織内で実際に発生しており、不信感がその主要な要因であることが明らかになりました。
知識隠蔽の行動は「回避的隠蔽」「合理化された隠蔽」「間抜けなふりをする」という3つのカテゴリーに分類され、それぞれ異なる対人的・状況的要因によって影響を受けることも示されました。
- 回避的隠蔽
自分が知っている情報を意図的に隠しつつ、相手には提供するふりをする行動を指します。具体例として、相手に曖昧な答えをしたり、誤った情報を与えることで、相手の要求をかわそうとする行為が挙げられます。 - 合理化された隠蔽
知識を隠す理由を正当化し、隠蔽を納得させる行動を指します。例えば、情報の共有が困難である、または許可されていないという理由を用いて隠蔽を説明します。 - 間抜けなふりをする
自分がその知識を持っていないふりをして、相手に情報を提供しない行動を指します。自分の知識や能力を意図的に隠して、情報提供を避ける形です。
調査の結果、知識隠蔽は単なる知識共有の欠如とは異なり、意図的に知識を隠す行動であることがわかりました。例えば、「回避的隠蔽」では、要求された知識をあいまいな形で提供する行動がみられ、一方で「合理化された隠蔽」では、知識を共有しない正当な理由を提示することで要求をかわすケースが多いことが分かりました。
また、「間抜けなふりをする」行動では、知識を知らないふりをすることでその要求を避ける傾向が見られました。これらの従業員の行動は、従業員が相手に対して不信感を抱くほど顕著になることが示されています。さらに、知識の性質や職場環境もこれらの行動に影響を及ぼし、たとえば知識が複雑である場合には回避的隠蔽が選ばれる傾向が強いことが確認されました。
この知識隠蔽の研究にはいくつかの実践的な示唆があります。組織としては、従業員間の信頼を育む取り組みが有用です。具体的には、信頼関係を強化するために、共有されたアイデンティティの形成や成功事例の積極的な共有が効果的でしょう。例えば、企業のミッションやビジョンを明確にし、それを従業員全体で共有することで、一体感を醸成することができます。
また、従業員が知識を共有することの価値を実感できるような文化を醸成することが重要です。例えば、社会的交流の場を設けたり、知識共有を奨励するインセンティブを設けたりすることで、職場における知識隠蔽の発生を抑えることが期待されます。
マネジメントの観点では、リーダーは知識隠蔽を防ぐための信頼構築に取り組むことが求められます。たとえば、チーム間や個人間で約束が守られた際にその事実を積極的に認めること、従業員が他者の成功を支援する機会を増やすことが考えられます。また、組織内の競争が過剰にならないようにすることも重要です。特に、従業員が同僚と知識を共有しやすくするためには、協力的な職場環境をつくり出すことが不可欠です。
タスクの相互依存性が高いと知識隠蔽行動を助長する
次に、知識の共有と隠蔽に影響を与える動機づけとワークデザインの役割について検討した研究を紹介します[2]。オーストラリアの知識労働者を対象とした調査と、中国の知識集約型企業の従業員を対象とした調査を通じて、動機づけや職務設計の特徴が知識共有や隠蔽行動にどのように影響を及ぼすかを分析しました。
この研究では、自己決定理論(Self-Determination Theory: SDT)を基盤として、特に職務の自律性や認知的職務要求が知識共有の自律的動機づけを高め、知識隠蔽を抑制する可能性について検討しました。自己決定理論は、人間の動機づけを「自律性」「有能感」「関係性」という三つの基本的欲求の充足によって高める理論です。
職務の自律性は、従業員が自身の業務において、意思決定や作業手順の選択に関する自由度を持つ度合いを指します。認知的職務要求は、職務を遂行する際に必要とされる思考、問題解決、意思決定などの知的負荷や精神的努力の度合いを指します。
調査の結果、職務の自律性と認知的職務要求は、知識共有の頻度や有用性に正の相関(一方が増えれば、もう一方も増える関係)を示しました。また、これらの職務特性は、従業員が自律的動機づけを通じて知識隠蔽行動を抑制することにも関連していることがわかりました。
一方で、タスクの相互依存性が高い場合、外的規制を介して知識隠蔽行動を助長する可能性も指摘されました。外的規制とは、報酬や評価、上司からの監視、競争環境など、外部からの圧力やインセンティブによって行動が決まることを指します。例えば、知識共有がボーナスや昇進の基準になると、従業員は戦略的に知識を隠したり、選択的に共有したりする可能性があります。
特に、同僚から依存される状況では、従業員がプレッシャーを感じ、外的な動機づけに基づいて知識を隠そうとする傾向が見られました。この結果は、タスクの相互依存が必ずしも知識共有を促進するわけではないことを示唆しています。
実践的な含意として、職場環境をデザインする際には、従業員が自律的に知識を共有する動機を引き出す仕組みが有用です。具体的には、職務の自律性や認知的なチャレンジを提供し、目標設定に組み込み評価をすることで、知識共有を促進できるでしょう。
一方、タスクの相互依存性を適切に管理することも重要です。同僚間の過度な依存が外的規制によるプレッシャーを生み、知識隠蔽を誘発する可能性があるため、相互依存性のバランスを考慮した設計が求められます。
マネジメントへの応用として、リーダーは従業員に自己決定感を与える環境を作ることが効果的です。たとえば、意思決定の権限を委譲したり、認知的に刺激的なタスクを提供したりすることで、従業員の自律的な知識共有を促進できます。
また、知識共有の文化を醸成するために、成功事例を共有する場や報酬制度の整備も役立つでしょう。さらに、タスクの相互依存性が過剰にならないよう、業務の負荷や役割を適切に調整することで、知識隠蔽のリスクを低減できます。
チームの熟達雰囲気が高まると、知識隠蔽のイノベーションへの悪影響が減少する
従業員の革新的職務行動(Innovative Work Behavior: IWB)に影響を与える要因として、知識隠蔽、チームの熟達雰囲気、職務特性がどのように関係するのかを調査した研究があります[3]。革新的職務行動とは、従業員が組織や職場において新しいアイデア、プロセス、製品、またはサービスを生み出し、それを実行するための行動を指します。チームの熟達雰囲気とは、組織やグループ、教育環境において、個人やチームが学習や能力の向上、自己改善に焦点を当てた目標や価値観を重視する雰囲気や環境のことを指します。
スロベニアの中堅企業2社における従業員240名とその直属上司34名を対象に、調査を実施しました。この調査では、達成目標理論(Achievement Goal Theory: AGT)および職務特性理論(Job Characteristics Theory: JCT)の理論的枠組みを用いて、チーム、職務、個人レベルでの相互作用が革新的職務行動に与える影響を検討しました。
分析の結果、チームの熟達雰囲気が高い場合、知識隠蔽が革新的職務行動に与える負の影響が緩和されることがわかりました。ただし、この効果は、職務特性であるタスクの相互依存性や意思決定の自律性の水準によって変化することも示されました。
具体的には、高い意思決定の自律性または低いタスク相互依存性を特徴とする職務環境では、知識隠蔽が革新的職務行動に与える影響を軽減し、さらには逆転させる場合も見られました。
例えば、意思決定の自律性が高い環境では、従業員が自らの裁量で業務を進められるため、知識隠蔽が必ずしも業務の停滞を引き起こすわけではなく、むしろ個人の創造性を高める場合があります。自分の知識を戦略的に活用し、独自のアプローチを試す機会が増えることで、新しいアイデアや革新的な解決策が生まれる可能性があるのです。
一方で、意思決定の自律性が低く、タスクの相互依存性が高い状況では、知識隠蔽は革新的職務行動に対して負の影響を及ぼす傾向が強まることが明らかになりました。
この結果は、組織が従業員の革新的職務行動を促進するためには、職場の文脈や職務設計の重要性を考慮する必要があることを示唆しています。高い熟達雰囲気を醸成することに加えて、従業員に一定の意思決定の自由を与えたり、必要に応じてタスク相互依存性を調整したりすることで、知識隠蔽の負の影響を抑え、革新を支援する環境を整えることが有用です。
マネジメントへの応用としては、まずチーム全体の習得風土を高めるための施策が考えられます。具体的には、従業員の努力や学習成果を適切に評価し、成長志向の文化を育むことが重要です。また、職務設計の観点から、意思決定の自律性を高めることで、従業員に自発的な問題解決や創造的思考を促す環境を提供することが効果的です。
一方で、タスク相互依存性が過剰に高まることによるプレッシャーを緩和し、個人が独立して仕事を進められる余地を設けることも必要です。
さらに、知識隠蔽を行う従業員についても、完全に排除するのではなく、適切に対応することが求められます。そのような従業員に対しては、自律性の高い職務や個別タスクを与えることで、知識隠蔽が革新的職務行動に及ぼす負の影響を最小限に抑えるとともに、その従業員がイノベーションの源泉となる可能性を引き出すことが期待されます。
互いに協力し合う文化が、知識隠蔽行動を減少させる
職場における縄張り意識と知識隠蔽の影響を探る研究があります[4]。本研究は、アラブ首長国連邦の銀行および保険業界で働く従業員を対象に、198のチームリーダー、彼らの部下、そして上司からデータを収集し、実施されました。調査では、縄張り意識、知識隠蔽、タスクパフォーマンス、職場逸脱行動といった要素の関連性を、社会的交換理論、互酬性の規範、および心理的所有理論を理論的枠組みとして分析しています。
- 社会的交換理論: 人間関係は、互いの利益や報酬を交換することで維持されるとする理論。
- 互酬性の規範: 他者から何かを受け取った場合、それに見合う行為を返すべきだとする社会的ルール。
- 心理的所有理論: 人は、自分がコントロールできる対象に対して「自分のもの」という感覚を持つ傾向があるとする理論。
本研究では、縄張り意識が知識隠蔽を助長し、タスクパフォーマンスに悪影響を与える一方、対人的逸脱や組織的逸脱といった非生産的行動を増加させることが示されました。また、知識隠蔽がこれらの関係を媒介する役割を果たしていることも明らかにされています。この結果は、従業員間の相互不信が職場における悪循環を引き起こし、生産性や業務の質に大きな負の影響を与えることを示唆しています。
これらの知見には、重要な実践的な示唆が含まれています。まず、組織は従業員の縄張り意識を軽減し、知識の共有を促進する仕組みを導入することが有用です。例えば、知識の共同所有を奨励し、チーム全体の成果を重視する業績評価や報酬制度を取り入れることが考えられます。
また、物理的な壁を取り除いたオフィスレイアウトや共有スペースの活用は、従業員間のコミュニケーションを活性化し、信頼関係を築く助けとなるでしょう。
さらに、組織内の職務設計において、個々の独立性を重視するのではなく、相互依存的な職務構造を採用することも効果的です。このような環境は、従業員が互いに協力し合う文化を形成し、縄張り意識や知識隠蔽行動を減少させる可能性があります。加えて、人材を採用・育成する際には、誠実で協調性が高い人材を選び、職場での助け合いや協力を促すことが大切です。
マネジメントへの応用としては、リーダーや管理職が従業員間の相互信頼を高めるために、オープンなコミュニケーションを推進することが求められます。定期的なフィードバックセッションやワークショップの開催、心理的安全性を重視したリーダーシップスタイルの導入は、知識隠蔽の悪循環を断ち切る効果が期待されます。また、従業員が知識を共有することの重要性を認識できる教育プログラムやトレーニングも有用です。
許しの風土が強い職場では、知識隠蔽行動が抑制される
職場でのいじめが従業員の知識隠蔽行動に与える影響と、その背後にあるメカニズムを探る研究を紹介します[5]。本研究は、中国の技術系企業に勤務する研究開発従業員327名を対象に、2つの時点でデータを収集し、職場いじめ、感情的疲労、組織的同一性、知識隠蔽の関係を明らかにしました。
調査の結果、職場いじめは感情的疲労を引き起こし、従業員の組織的同一性を低下させ、それが知識隠蔽行動につながることが明らかになりました。組織的同一性とは、従業員が自身を組織の一員として認識し、組織の価値観や目標を自己のものと感じる心理的なつながりを指します。
また、感情的疲労と組織的同一性は、職場いじめと知識隠蔽の関係を連鎖的に媒介する役割を果たしていました。具体的には、まず職場いじめを受けた従業員は精神的ストレスが増加し、感情的疲労を感じやすくなります。感情的疲労とは、過度のストレスや感情的な負担によって、精神的に消耗し、エネルギーややる気が枯渇した状態を指します。
さらに、許しの風土という組織的要素が、職場いじめの悪影響を緩和することが確認されました。具体的には、許しの風土が強い職場では、いじめによる感情的疲労が軽減され、知識隠蔽行動の抑制に寄与することが示されています。
これらの知見には、いくつかの実践的な示唆が含まれています。まず、職場いじめの影響を軽減するために、組織は従業員の感情的疲労を適切にケアする仕組みを整備することが重要です。たとえば、従業員が心理的に疲弊した際には、カウンセリングやストレス管理のためのプログラムを提供し、心理的な負担を軽減する支援が有用です。また、定期的なフィードバックやポジティブな職務評価を通じて、従業員が組織内で重要な役割を果たしているという実感を得られるようにすることも効果的です。
さらに、従業員の組織的同一性を高める取り組みが必要です。チームの協力を促進するようなプロジェクトを設計し、相互理解や協力関係を築くことが、組織全体の一体感を向上させるでしょう。このような取り組みによって、従業員が組織への帰属意識を持つようになり、知識隠蔽行動が減少する可能性があります。また、リーダーは日常的な業務の中で相互尊重を奨励し、従業員間の信頼関係を構築するための活動を推進することが求められます。
最後に、許しの風土(職場でミスや対人関係のトラブルが発生しても寛容に受け入れ、互いに修復し合える環境や文化)の形成は、職場いじめの悪影響を軽減するために効果的です。職場では人間関係でお互いを思いやる姿勢を大切にし、従業員がストレスを軽減できる環境を整えることが大切です。具体的には、リーダーや管理職が率先して寛容性を示し、職場全体で公平性や透明性を重視する文化を築くことが必要です。このような風土が従業員のストレスを緩和し、知識共有を促進する土壌を形成します。
職場の礼節の欠如は情報の共有を阻害し、知識隠蔽を促進する
職場の礼節の欠如(Workplace Incivility: WIN)が従業員の無力な沈黙(Ineffectual Employee Silence: IES)にどのように影響を与えるかを明らかにした研究が注目を集めています[6]。従業員の無力な沈黙とは、従業員が自身の知識や意見が役立たない、または意味がないと感じて、意図的に発言や情報共有を控える行動を指します。
本研究では、合理化された知識の隠蔽(Rationalized Knowledge Hiding: RKH)と感情調整(Regulation of Emotion: ROE)の役割に焦点を当て、職場の礼節の欠如が従業員の無力な沈黙を悪化させるメカニズムを探りました。感情調整とは、自分や他者の感情を意識的にコントロールし、適切に管理することで目標や社会的要求に応じた行動を取る能力を指します。
資源保存理論(Conservation of Resources Theory: COR)と社会的交換理論(Social Exchange Theory: SET)を理論的枠組みとして採用し、インドにおけるIT分野の252名を対象とした調査を行いました。
調査の結果、職場の礼節の欠如は従業員の無力な沈黙を悪化させることが明らかになりました。従業員は職場の礼節の欠如によるストレスや資源の消耗を避けるため、沈黙という防衛戦略に頼る傾向があります。さらに、職場の礼節の欠如は情報の共有を阻害し、合理化された知識の隠蔽を促進することも確認されました。知識の隠蔽が進むことで、従業員の無能な沈黙がさらに悪化することが示されています。
一方、感情調整の高い従業員は職場の礼節の欠如の悪影響を和らげ、従業員の無力な沈黙を軽減することがわかりました。感情調整は、職場の礼節の欠如による精神的な疲れを和らげる効果的な方法であることが分かっています。
本研究の実践的含意として、組織は職場の礼節の欠如の緩和に向けた対策を講じる必要性があります。具体的には、従業員に対して市民的行動と非市民的行動の違いを認識させるための教育や研修プログラムを導入することが有用です。これにより、職場の礼節の欠如の発生を抑え、従業員の無力な沈黙や合理化された知識の隠蔽のリスクを低減できるでしょう。
また、感情調整のスキルを向上させる教育プログラムを提供することで、従業員が職場の礼節の欠如に対処しやすくすることが効果的です。感情を適切に管理できる従業員は、職場のストレスを乗り越え、健全なコミュニケーションを促進することが期待されます。
マネジメントへの応用としては、職場の礼節の欠如をゼロにするのは難しいものの、従業員同士で非礼な行動を行わないよう、組織全体でゼロ・トレランス・ポリシー(厳格対応方針)を確立することが求められます。また、職場の礼節の欠如の影響を軽減するためには、従業員が感情調整を高めるためのサポートが重要です。
たとえば、感情知能(Emotional Intelligence: EI)を測定する評価手法を採用し、感情調整の高い候補者を選抜して採用することが有用です。さらに、マネジメントは、従業員が知識を共有しやすい環境を整える必要があります。これにより、合理化された知識の隠蔽が抑制され、組織全体の効率性が向上するでしょう。
知識隠蔽は心理的安全性を低下させることで、従業員の成功を阻害する
知識隠蔽行動が職場での個人の成長や心理的安全性にどのような影響を及ぼすのかを明らかにした研究があります[7]。この研究では、心理的安全性が知識隠蔽と従業員スライビング(従業員の成功を示す指標)との関係を媒介する役割を果たし、さらに組織シニシズムがその影響を増幅させる可能性について検証しました。組織シニシズムとは、従業員が組織に対して不信感や否定的な感情を抱き、経営方針やリーダーシップに対して冷笑的・懐疑的な態度をとることを指します。
研究は、中国、ヨーロッパ、北米を中心に、異なる参加者層を対象に実施され、知識隠蔽が従業員スライビングに与える影響のメカニズムを明らかにしました。
本研究は、3つの段階で進められました。第一に、中国の一般就労人口214名を対象とした横断調査で、知識隠蔽が心理的安全性を低下させ、その結果、従業員スライビングを阻害することが確認されました。次に、ヨーロッパと北米から392名の社会人を対象とした2回のデータ収集により、これらの結果が再現されました。最後に、中国の3つの組織で働く205名を対象に、知識隠蔽の心理的影響をさらに検証しました。
調査の結果、知識隠蔽は心理的安全性を低下させることで、従業員スライビングを阻害することが示されました。心理的安全性が損なわれると、従業員は安心して意見を述べたり、知識を共有したりすることが難しくなり、それが職場での成長や活力を妨げる要因となります。また、組織シニシズムが強い職場では、知識隠蔽の悪影響がさらに顕著になることもわかりました。従業員が組織に対して冷笑的な態度を持つ場合、知識隠蔽の影響がより深刻化し、心理的安全性が一層低下する傾向があるのです。
本研究の実践的含意として、マネジャーは従業員の知識隠蔽を防ぐだけでなく、心理的安全性を高める環境づくりに努めることが重要です。具体的には、従業員が安心して知識やアイデアを共有できる職場文化を醸成することが求められます。そのためには、オープンで透明性の高いコミュニケーションを促進し、信頼を築くことが効果的です。また、組織シニシズムを抑えるために、従業員に対して誠実な対応を心がけ、職場環境の改善に取り組むことが重要です。
マネジメントへの応用としては、まず、知識共有を促進するための施策が挙げられます。これには、従業員同士が知識を交換する場を設けたり、知識共有の重要性を啓発するトレーニングを実施したりすることが含まれます。また、組織シニシズムを抑制するために、従業員の声を積極的に聞き入れ、公平性や透明性を重視した意思決定を行うことが効果的です。さらに、心理的安全性を高めるために、失敗を許容する文化を築き、従業員が挑戦しやすい環境を整えることも有用です。
知識の複雑さが増すほど知識隠蔽行動が強まる
最後に、組織内での知識隠蔽が組織パフォーマンスに及ぼす影響を明らかにした研究を紹介します[8]。この研究では、知識隠蔽の将来の結果や傾向を予測するための要因とその結果について調査し、知識隠蔽者(Knowledge Hiders: KH)と知識探索者(Knowledge Seekers: KS)の役割が、知識隠蔽の影響をどのように緩和または強化するかを分析しました。研究対象は多国籍企業9社に勤務する353名の従業員で、アンケート調査を基に検証しました。
調査の結果、知識隠蔽はプロジェクトチームのパフォーマンスや個人の創造性に負の影響を与えることが確認されました。また、これらの要素はさらに組織全体のパフォーマンスに波及し、悪影響を及ぼすことが示されています。具体的には、知識共有風土が高まると知識隠蔽が減少する一方、知識の複雑さが増すほど隠蔽行動が強まることが明らかになりました。。
この研究から得られる実践的な示唆として、組織内での知識隠蔽を軽減し、知識共有を促進するための施策の重要性が挙げられます。例えば、知識共有の文化を育むために、従業員が安心して意見や知識を共有できる信頼の風土を醸成することが有用です。
また、知識隠蔽の動機を減らすために、知識共有の重要性を明確に伝え、共有が個人やチームの評価向上につながる仕組みを構築することが効果的です。さらに、知識隠蔽者に対しては、一方的な排除ではなく、動機を理解し、適切なサポートや環境調整を行うことで、隠蔽行動を減少させることが期待されます。
マネジメントの観点からは、まず知識共有風土を高めるためのリーダーシップが求められます。リーダーは、従業員が協力し合い、知識を共有することで全体のパフォーマンスが向上することを示すとよいでしょう。
また、知識探索者を奨励する取り組みも有用で、彼らが他者の知識を効果的に活用し、組織全体の知識フローを改善することが促進されます。さらに、プロジェクトチームのパフォーマンスを向上させるために、職務設計の面で意思決定の自由度を高めたり、タスクの調整を行うことも重要です。
知識隠蔽を抑制する施策とその効果
知識隠蔽という行動は、組織内での信頼や文化、職務設計に深く影響され、またそれ自体が従業員の創造性やチームのパフォーマンス、さらには組織全体の成果に大きな影響を及ぼします。本コラムで紹介した複数の研究は、知識隠蔽が組織における重要な課題であり、その抑制と対応が組織の持続的成長において不可欠であることを示しています。
具体的には、信頼関係を基盤とした職場環境を構築することが、知識隠蔽を防ぐ鍵となります。従業員が安心して知識を共有できる環境を整備することで、心理的安全性が高まり、隠蔽行動が抑制される可能性が高まります。また、職務設計の面では、意思決定の自律性を高めることや、タスクの相互依存性を適切に管理することが有用です。これにより、従業員が自発的に知識を共有しやすい風土を育むことが期待されます。
さらに、知識隠蔽の背景には不信感や競争意識、心理的疲労といった複雑な要因があることを考慮すると、リーダーや管理職が果たす役割は非常に重要です。オープンで透明性のあるコミュニケーションを推進し、従業員同士の協力や支援を奨励することが、知識隠蔽の緩和に効果的です。また、職場全体での成功事例の共有や、知識共有を奨励するインセンティブ制度を導入することで、従業員が知識を共有する価値を実感できる環境を提供することが重要です。
知識は組織の競争力を支える最も貴重な資源の一つであり、その流動性を確保することが、組織の革新や発展を促進します。知識隠蔽を抑制するための施策は、単に隠蔽行動を減少させるだけでなく、従業員の成長や組織全体のパフォーマンス向上にも寄与します。今後も、知識を共有する文化を育み、信頼と協力を基盤とした職場づくりを目指すことが、企業にとっての重要な課題となるでしょう。
脚注
[1] Connelly, C. E., Zweig, D., Webster, J., & Trougakos, J. P. (2012). Knowledge hiding in organizations. Journal of organizational behavior, 33(1), 64-88.
[2] Gagné, M., Tian, A. W., Soo, C., Zhang, B., Ho, K. S. B., & Hosszu, K. (2019). Different motivations for knowledge sharing and hiding: The role of motivating work design. Journal of organizational behavior, 40(7), 783-799.
[3] Černe, M., Hernaus, T., Dysvik, A., & Škerlavaj, M. (2017). The role of multilevel synergistic interplay among team mastery climate, knowledge hiding, and job characteristics in stimulating innovative work behavior. Human Resource Management Journal, 27(2), 281-299.
[4] Singh, S. K. (2019). Territoriality, task performance, and workplace deviance: Empirical evidence on role of knowledge hiding. Journal of Business Research, 97, 10-19.
[5] Yao, Z., Zhang, X., Luo, J., & Huang, H. (2020). Offense is the best defense: the impact of workplace bullying on knowledge hiding. Journal of Knowledge Management, 24(3), 675-695.
[6] Ballekura, B., & Vilvanathan, L. (2023). When workplace incivility begets ineffectual employee silence-the role of rationalized knowledge hiding and regulation of emotion. Kybernetes.
[7] Jiang, Z., Hu, X., Wang, Z., & Jiang, X. (2019). Knowledge hiding as a barrier to thriving: The mediating role of psychological safety and moderating role of organizational cynicism. Journal of Organizational Behavior, 40(7), 800-818.
[8] Chatterjee, S., Chaudhuri, R., Thrassou, A., & Vrontis, D. (2021). Antecedents and consequences of knowledge hiding: The moderating role of knowledge hiders and knowledge seekers in organizations. Journal of Business Research, 128, 303-313.
執筆者
 樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
早稲田大学政治経済学部卒業、カリフォルニア州立大学MBA修了、UCLA HR Certificate取得、立命館大学大学院博士課程修了。博士(人間科学)。国家資格キャリアコンサルタント。ビジネスの第一線で30年間、組織と人に関する実務経験、専門知識で、経営理論を実践してきた人事のプロフェッショナル。通信会社で人事担当者としての経験を積み、その後、コンサルティングファームで人事コンサルタントやシニアマネージャーを務め、さらに銀行で人事部長などの役職を歴任した後、現在はFWD生命にて執行役員兼CHROを務める。ビジネスと学術研究をつなぐ架け橋となることを目指し、実践で役立つアプローチを探求している。