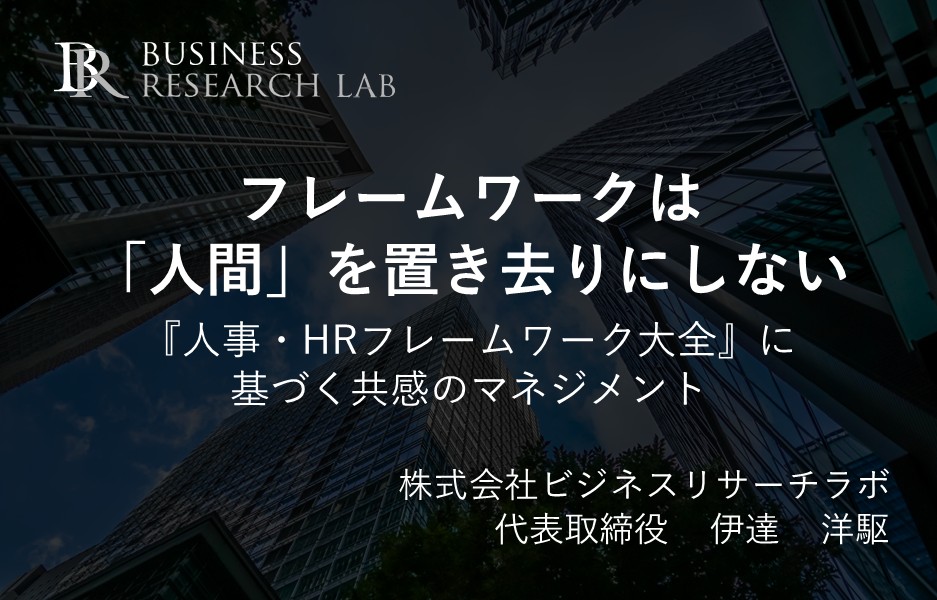2025年11月10日
フレームワークは「人間」を置き去りにしない:『人事・HRフレームワーク大全』に基づく共感のマネジメント
「人の心は、ロジックや型では割り切れない」「人事の問題はケースバイケースだ」。組織を率いる立場にある人なら、一度はそう感じたことがあるかもしれません。その感覚は、ある意味では合っていると思います。優れたリーダーが長年の実践で培ってきた勘や経験則は、組織を導く上で何物にも代えがたい価値を持ちます。しかし、その貴重な「感覚」や「経験」が、時として私たちを思わぬ落とし穴に導くことがあります。それらだけに頼るマネジメントが、知らず知らずのうちに組織の可能性を狭め、働く人々の心をすり減らしていないでしょうか。
この度、私が上梓した『人事・HRフレームワーク大全』が目指したのは、人を分析し、分類するための冷たい道具箱を作ることではありません。むしろ、その逆です。フレームワークという共通言語と客観的な視点を持つことで、私たちは、自身の経験という武器に、科学的な知見という新たな視点を加えることができます。それによって、一人ひとりの人間とより深く、真摯に向き合うことが可能になります。
本コラムでは、フレームワークがいかに私たちの人間理解を深め、より共感的で、より公正なマネジメントを実現する「血の通った知恵」となり得るのか、その可能性について述べたいと思います。
「感覚」頼りのマネジメントがもたらす残酷さ
経験や感覚だけに頼るマネジメントは、その意図とは裏腹に、無意識の「レッテル貼り」に陥ることがあります。「最近のAさんはやる気がない」「Bさんは協調性に欠ける」。こうした評価は、リーダーの経験に基づく直観から生まれるものかもしれません。しかし、その実態は、個人の内面を深く理解しようとするプロセスを省略した、ある種の思考停止とも言えます。
なぜA君は意欲を失っているのか。その背景にある構造的な問題、例えば過剰な業務負荷やキャリアへの不安、あるいは仕事そのものに意味を見出せないでいる状況から目を背けさせてしまいます。静かなメンバーを見て「意欲がない」と判断することがあるかもしれませんが、実際には、深く思考を巡らせてから発言するタイプであったり、会議の場よりも文章でのコミュニケーションを好む特性を持っていたりする可能性を見過ごしてしまいます。その結果、貴重な意見を吸い上げる機会を失い、本人の貢献意欲を削いでしまうのです。
リーダー自身が積み重ねてきた成功体験も、その輝きゆえに、時として視野を狭める一因となることがあります。「自分が若手の頃はこうやって乗り越えた」「このやり方が最も効率的だ」。その経験則は、特定の状況下では間違いなく有効だったことでしょう。しかし、価値観も働く環境も変化した現代において、その物差しは本当に有効でしょうか。
例えば、熾烈な個人競争の中で成果を上げてきたリーダーは、チーム内での協調や知識共有を軽視してしまうかもしれません。その結果、多様な個性を持つ部下に対し、自分という一つの基準を当てはめる行為は、その人の可能性の芽を摘んでしまうことにつながりかねません。経験は尊重されるべきですが、それが唯一の正解だと信じてしまうと、新たな可能性を見出す機会を失います。
経験則への過剰な依存は、結果的に組織から共感を奪うことにつながります。問題の本質を直視せず、個人を単純化して評価することは、一見すると迅速な判断に見えますが、長期的には組織の心理的安全性を損ない、活力を蝕んでいきます。
フレームワークはいかに「共感」を深めるか
どうすればこの「主観の罠」から抜け出し、経験をより豊かに活かすことができるのでしょうか。その一つの答えが、フレームワークの活用にあります。フレームワークは、捉えどころのない現象に構造と名前を与え、対話の糸口を生み出します。
例えば、「A君はやる気がない」というレッテル貼りの代わりに、本書で紹介する「心理的エンパワーメント」の視点から状況を捉え直してみます。この理論は、人の内発的動機づけが、仕事の「意味」、やり遂げる自信である「能力」、自分で決められる感覚の「自己決定」、周囲に影響を与えている実感の「影響力」という四つの要素からなると説明します。
この視点を持つことで、リーダーの思考は「A君はなぜ意欲がないのか」という個人への評価から、「A君の仕事において、これら四つの要素のどれが満たされていないのだろうか」という状況分析へと移行します。「仕事の意味は理解しているようだが、最近私が彼の業務プロセスに細かく口を出しすぎて、『自己決定』の感覚を奪っているのかもしれない」。このように考えることで、対話の質は変わります。個人を一方的に評価するのではなく、その人が置かれている状況を分析し、共に解決策を探るという姿勢が生まれます。
部下との関係性についても同様です。「どうも相性が悪い」という感覚的な言葉で片付ける前に、「LMX理論」の視点を借りることができます。この理論は、上司と部下の関係の質を、「愛着」「忠誠」「貢献」「専門的敬意」という四つの次元で捉えます。この視点を用いれば、「業務上の貢献は認めているが、一人の人間としての信頼関係、すなわち愛着を育むような対話が不足しているのかもしれない」「彼/彼女の専門性に対して、自分は十分な敬意を払えていただろうか」と、関係性をより深く、解像度高く見つめ直すことが可能になります。これは、感覚的な好き嫌いを越えた、意図的な関係構築への一歩となります。
フレームワークは、相手の行動の背景にあるメカニズムを理解するための補助線です。例えば、「衡平理論」を知ることで、ある社員の不満が、単なるわがままではなく、「自分の投入(努力や時間)とそこから得られる成果(報酬や評価)が、他者と比較して不公平だ」という切実な感覚から来ている可能性を理解できます。何が公正であるかは主観的な感覚ですが、この理論はその主観がどのような比較から生まれるかを教えてくれます。この「理解」が、共感の土台となります。
パーソナライズの道具としてのフレームワーク
フレームワークは、人を画一的な型にはめるためのものではありません。一人ひとりの内面がいかに多様であるかを科学的に示し、その多様性に応じた、きめ細やかなアプローチを可能にします。
全員に同じ目標、同じインセンティブを与えても、意欲を高める人もいれば、そうでない人もいます。「達成目標理論」は、人が「自身の能力を高めること」を重視するのか(熟達目標)、「他者との比較で優位に立つこと」を重視するのか(遂行目標)で、動機づけの源泉が異なることを教えてくれます。
リーダー自身の成功体験が「遂行目標」に基づいている場合、部下にも同じスタイルを求めるかもしれません。しかしこの視点があれば、部下との面談で「この仕事を通じて、どんなスキルを身につけたいですか(熟達)」「このプロジェクトで業界の注目を集め、ライバルに差をつけましょう(遂行)」といったように、一人ひとりの心に響く言葉を選び、目標設定をパーソナライズできるようになります。
キャリア形成においても、画一的な物差しは通用しなくなりました。「5年後、どうなっていたいですか」という問いに、誰もが明確に答えられるわけではありません。「計画的偶発性理論」は、キャリアが計画通りに進むものではなく、偶然の出会いや予期せぬ出来事をチャンスに変える力が、その人の職業人生を豊かにするという視点を提供します。
このフレームワークを知るリーダーは、部下のキャリアを固定的なゴールに導こうとするのではなく、新しい挑戦や部署外の人間との交流といった「良い偶然」が生まれる機会を意図的に設計しようとするでしょう。例えば、部下に普段接点のない他部署の会議への参加を促したり、社外の勉強会への参加を奨励したりする。そうした小さな働きかけが、本人のキャリアにとって予期せぬ転機をもたらすかもしれません。それは、個人のキャリアという予測不能な物語を尊重する、より人間的な育成のあり方です。
「キャリア・アンカー」という概念を用いれば、ある社員が専門性を追求することに価値を見出すのか(技術・職能別能力)、あるいは安定した環境で働くことを望むのか(保障・安定)といった、その人のキャリアの軸を理解する助けになります。管理職への昇進を打診した際に部下の反応が芳しくない場合、それは意欲の問題ではなく、彼/彼女のキャリアの軸がマネジメントとは異なる方向を向いているからかもしれません。
これらの例が示すように、フレームワークは人間理解の解像度を高めます。それによって、一人ひとりの違いを認識し、その個性を尊重したマネジメントを実践することが可能になります。
システムとしてのフレームワークがもたらす人間性
人間的な組織とは、ただ仲が良いだけの組織ではありません。「組織的公正」の理論が示すように、人は「何を得たか」という結果の公平性(分配的公正)だけでなく、「その結果がどのように決められたか」というプロセスの透明性(手続き的公正)を求めます。たとえ自分にとって望ましくない結果(例えば、希望の部署への異動が叶わない)であっても、その決定プロセスが一貫した基準に基づいており、偏見なく行われたと納得できれば、組織への信頼を維持しやすいものです。
リーダー個人の感覚としての「公平さ」だけでなく、誰もがそう感じられる仕組みがあること。これは、従業員一人ひとりに対する敬意であり、組織への信頼の基盤となります。フレームワークは、こうした公正な制度を設計するための指針を与えてくれます。
組織と人の間には、雇用契約書には書かれていない「暗黙の期待」が存在します。「この会社なら成長させてくれるはず」「困ったときは助けてくれるはず」。「心理的契約」という視点を持つことで、私たちは日々のマネジメントがいかに従業員の信頼や帰属意識に影響を与えているかに気づかされます。
例えば、「うちは家族のような会社だ」と日頃から伝えている組織が、業績悪化時に何の説明もなく一方的なリストラを行えば、その裏切りは単なる雇用契約の終了以上の深い傷を従業員に残すでしょう。フレームワークは、こうした組織と人の間の「見えない約束」を可視化し、より誠実な関係を築くための対話を促してくれます。
より賢慮に満ちた人間性へ
ここまで見てきたように、フレームワークは人を数字や記号に置き換えるためのものではありません。複雑で、時に矛盾を抱える「人間」という存在を、より深く、多角的に理解するための知的な視点を提供してくれるものです。
この視点を持つことで、私たちは自身の貴重な経験則を絶対視することなく、より客観的に状況を捉えることができます。安易なレッテル貼りを避け、感情的な対立を乗り越え、建設的な対話へと進むことができます。そして、一人ひとりの個性と尊厳を尊重した、人間的な組織を築くことができるはずです。
経験がもたらす直観に、科学がもたらす構造的理解が加わることで、私たちの判断はより賢慮に満ちたものになるでしょう。フレームワークは、答えそのものを与えてくれるわけではありません。しかし、それは私たちがより良い問いを立てることを助けてくれます。「私は部下を正しく評価できているか」から、「私は部下の動機づけの源泉を理解しているか」へ。その問いの変化が、マネジメントを進化させます。
私が上梓した『人事・HRフレームワーク大全』は、皆さんがより科学的で、同時に、より人間的なリーダーになるための招待状です。この756ページの思考の道具箱が、皆さんの現場に、そして皆さんが関わる人々の未来に、新たな光をもたらすことを願っています。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。