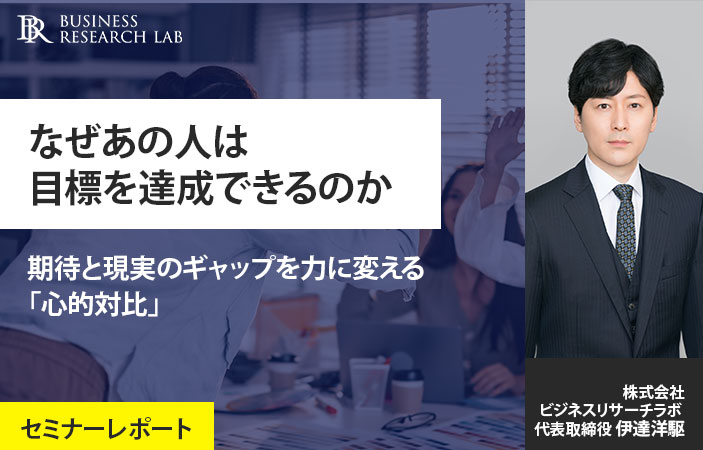2024年12月20日
なぜあの人は目標を達成できるのか:期待と現実のギャップを力に変える「心的対比」(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2024年12月にセミナー「なぜあの人は目標を達成できるのか:期待と現実のギャップを力に変える『心的対比』」を開催しました。
目標達成の新しい手法として、心理学研究の中で注目を集める「心的対比(メンタル・コントラスト)」。
この手法は、単に理想を思い描くだけでなく、それを妨げる現実の課題も同時に考えることで、行動計画の立案と実行を促進します。
本セミナーでは、心的対比の考え方から、それを組織の人材育成や目標管理に活用する方法まで、実践的な知見をお伝えします。
なぜポジティブ思考だけでは不十分なのか、どうすれば部下の目標達成をより効果的に支援できるのか、チームの生産性向上にどう活かせるのか。研究知見に基づいて、このような問いに答えていきます。
組織の目標達成力を高め、より効果的な人材育成を実現するための新しいアプローチを、ぜひこの機会に学んでいただければと思います。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
私たちは日々、様々な目標を立てて生活しています。仕事で成果を上げたい、健康的な生活を送りたい、資格を取得したいなど、願いは尽きることがありません。しかし、そうした目標の多くは途中で挫折してしまい、なかなか実現に至らないものです。
そのような中で、目標達成を効果的に支援する方法として注目を集めているのが「心的対比(メンタル・コントラスト)」という手法です。この方法は、目標を思い描くだけでなく、現実の課題も同時に考えることで、実践的な行動計画の立案を促します。
本講演では、心的対比がなぜ効果的なのか、どのような場面で活用できるのか、そして実践する際の注意点は何かなどについて、研究知見をもとに解説していきます。目標達成に悩む方々に、新しい視点と具体的なアプローチを提供できれば幸いです。
心的対比とは何か
心的対比は、望ましい未来と現在の状況を頭の中で意図的に比較することで、目標達成への具体的な行動を引き出す手法です[1]。
この手法では、まず自分が理想とする状態を鮮明にイメージします。例えば、健康的な体型を目指す場合、イメージする内容は人それぞれです。スポーツを楽しめる体力がついている姿かもしれませんし、好きな服が似合う体型かもしれません。大切なのは、その未来の自分の姿をできる限り具体的に思い描くことです。
次に、現在の自分の状況を見つめ直します。この時に重要なのは、理想の状態に至るまでの障害となっているものを認識することです。健康的な体型を目指す例で言えば、不規則な生活リズム、運動不足、間食の習慣など、目標達成を妨げている要因を洗い出します。これは単なる現状分析ではなく、理想の状態と比較しながら、そこに至るまでの障壁を明確にする作業です。
このように理想と現実を突き合わせることで、行動計画が浮かび上がってきます。例えば、毎朝6時に起きて30分ジョギングをする、職場では階段を使う、夜9時以降の飲食を控えるなど、理想に近づくための行動が見えてきます。これらの行動は、漠然と「運動しよう」「食事に気をつけよう」と考えるのとは異なり、いつ、どこで、何をするのかが明確になっています。
なぜ心的対比は効果的か
心的対比が効果的である理由は、何よりも強いエネルギーを引き出す点にあります。望ましい未来を思い描くだけの場合、一時的な高揚感は得られるものの、具体的な行動にはつながりにくいものです[2]。それに対して心的対比は、理想と現実のギャップを認識することで、そのギャップを埋めるためのエネルギーを生み出します。
研究によれば、心的対比を行うことで、人は身体的にも心理的にも活性化することが分かっています[3]。例えば、血圧の上昇や心拍数の増加といった生理的な変化が確認されており、これは体が行動に向けて準備態勢に入っていることを表しています。また、「体が温かくなった」「身体が軽くなった」「やる気が湧いてきた」といった感覚も報告されています。
このエネルギーの高まりは、パフォーマンスの向上という形で表れます。例えば、心的対比を行った後にプレゼンテーションを行った人は、声の大きさや話し方の明瞭さ、アイコンタクトの頻度などが改善され、聴衆からの評価も高くなることが確認されています。
心的対比のもう一つの重要な効果は、具体的で実行可能な行動計画を立てられることです。望ましい未来を思い描くだけでは、その実現のために何をすべきか、いつ行動を起こすべきか、どのような順序で進めるべきかといった点が不明確なままです。
しかし心的対比では、理想と現実のギャップを明確にすることで、そのギャップを埋めるために必要なステップが見えてきます。例えば、資格取得を目指す場合、現在の知識レベルと合格に必要な水準を比較することで、どの分野をどの程度学習する必要があるのか、そのためにはどのような教材をどのように活用すべきかといった計画を立てることができます。
さらに心的対比の重要な作用として、現状を「乗り越えるべき障害」として意味づける点が挙げられます[4]。例えば、忙しい毎日を送っている人が「時間がない」と感じている場合、それはそういう事実として認識されているに過ぎません。
しかし心的対比を行うことで、その「時間がない」という状況が「目標達成のために解決すべき課題」として再解釈されます。すると、朝型の生活に切り替える、通勤時間を活用する、スマートフォンの使用時間を制限するなど、時間を作り出すための対策を考えられるようになります。
心的対比は、目標達成に向けた支援を得やすくするという影響もあります。支援を必要とする状況を認識できるため、適切なタイミングで周囲に援助を求めることができます。例えば、勉強で困っている場合、「成績を上げたい」という願いと「理解できない箇所がある」という現実を比べることで、先生に質問するといった行動につながりやすくなります。
他者からの支援を得られると、目標達成の可能性は高まります。なぜなら、支援者からはアドバイスやフィードバックが得られるだけでなく、精神的な支えも得られるからです。また、支援者の存在自体が一種の動機づけとなり、目標達成に向けた行動を継続する力となります。さらに、支援者の経験から学ぶことで、より効率的な方法を見出したり、予期せぬ障害への対処法を知ったりすることもできます。
どういう場合に心的対比が用いられるか
研究によると、社会的責任を強く感じる状況では、人々は自然と心的対比を行う傾向が強まることが示されています[5]。重要な組織の意思決定に関わる立場にある場合、その決定が他者に与える影響を考慮して、望ましい結果と現状の課題を比較検討する傾向が強まります。
例えば、職場でプロジェクトのリーダーを務める場合、チームの成果に対する責任や期待が大きいことから、自然と心的対比的な思考が働きます。プロジェクトの成功イメージと現在の進捗状況を比較し、課題を洗い出し、必要な対策を講じようとするのです。
時間的な制約が厳しい状況も、心的対比が自然と行われやすい場面の一つです[6]。締め切りが迫った仕事や試験勉強などでは、限られた時間の中で最大の成果を上げる必要があるため、達成したい目標と現在の状況を比較し、残された時間をどのように使うべきか、優先順位をどのようにつけるべきかを考えるようになることが示されています。
例えば、「来週の金曜日までにレポートを完成させなければならない」という状況では、完成した理想的なレポートの姿と現在の作業進度を比較することで、時間配分を計画するといった具合です。
しかし、こうした社会的責任や時間的制約といったプレッシャーが存在しない日常場面では、心的対比は自然には行われにくいと言い換えることもできます。日常的な目標(例:運動習慣をつける、新しい趣味を始める)に対しては、人々は単に望ましい未来を思い描くだけで終わってしまう「インダルジング」や、現実の問題点だけに注目する「ドウェリング」といった思考パターン[7]を取りやすくなります。
これは、プレッシャーのない状況では、目標達成の失敗がもたらす影響が比較的小さいと認識されるため、理想と現実を意識的に比較検討する必要性を感じにくいためだと考えられています。例えば、「健康のために野菜を多く食べよう」という目標は重要ではあるものの、それを達成できなかった場合の即時的な影響は小さいため、目標達成に向けた行動計画を立てる動機が弱くなりがちです。
そのため、目標達成を目指す場合には、意識的に心的対比を行う必要があります。心的対比を意識的に活用することで、プレッシャーのない日常的な目標であっても、より効果的に達成することができます。
心的対比の活用どころ
心的対比の活用において注目すべきは、ポジティブ・フィードバックとの相乗効果です[8]。例えば、上司から「今回の進め方は良かった」と評価された際、その言葉を受け取るだけでなく、心的対比を行うことで、行動改善につながりやすくなります。
ポジティブ・フィードバックを受けた際の心的対比の活用方法は次のようなイメージです。
- その評価に値する理想的な状態をイメージします。例えば、「より複雑なプロジェクトを任されている自分」「チームのリーダーとして成果を上げている自分」といった姿です。
- 現在の自分の状態を客観的に見つめ直します。知識やスキルの不足、経験の浅さ、時間管理の課題など、理想の状態に至るまでの障害を認識します。
- これらを踏まえて行動計画を立てます。例えば、「毎週金曜日は30分専門書を読む」「月に1回は社外のセミナーに参加する」といった行動です。
また、目標設定の仕方も心的対比の効果を左右する要素です。目標があまりに大きすぎたり、達成までの期間が長すぎたりすると、行動に落とし込むことが難しくなります。例えば、「10年後に売上高を5倍にする」という目標は、現実との比較が難しく、行動計画を立てにくいものです。
そのような場合は、目標を小さな単位に分割することが効果的です。「今月の新規顧客を5社増やす」「既存顧客の購入頻度を10%上げる」といった目標なら、現状と比較しやすく、行動計画も立てやすくなります。目標を達成したら、次のステップとしてさらに高い目標を設定することで、徐々にレベルアップを図ることができます。
心的対比の実践場面
組織において部下の成長を支援する際、心的対比は効果的なツールとなります。例えば、部下との定期的な1on1ミーティングの場で、この手法を活用することができます。
- 部下に「半年後、1年後にどのような姿になっていたいか」を描いてもらいます。営業成績の向上、新しい技術の習得、リーダーシップの発揮など、部下自身が望む成長の姿を明確にします。
- その上で、現在の状況について率直に話し合います。例えば、「商談の場で顧客の潜在的なニーズを十分に引き出せていない」「新しい技術について基礎知識が不足している」「チームメンバーとのコミュニケーションが取れていない」といった課題を特定していきます。このプロセスでは、上司が一方的に課題を指摘するのではなく、部下自身が気づきを得られるような質問を投げかけましょう。
- 理想と現実のギャップが明確になったら、それを埋めるための行動計画を部下と一緒に考えます。「週に1回、ベテラン社員の商談に同行する」「毎朝30分、技術関連の書籍を読む」「チーム会議で積極的に発言する機会を作る」など、実行可能な行動を設定します。上司の役割は、この計画の実現可能性を確認し、必要なサポートを約束することです。
他方で、チームの生産性向上においても、心的対比は有効に機能します。
- チーム全体でミーティングを持ち、「理想のチームの状態」について議論を行います。例えば、「メンバー全員が互いの進捗状況を把握している」「問題が発生した際に迅速に対応できている」「アイデアが活発に出され、建設的な議論が行われている」といった姿を描きます。
- 続いて、現在のチームの状況を客観的に評価します。「情報共有が不十分で、重複作業が発生している」「問題の発見が遅く、対応に時間がかかっている」「慣習的な方法に固執し、イノベーションが起きにくい」といった課題を、チームメンバー全員で共有します。この際、批判や非難ではなく、改善のための建設的な議論となるよう、ファシリテーターが注意を払う必要があります。
- 理想と現実の差が明確になったら、チームとして取り組むべきアクションを具体化します。「朝会の実施による情報共有の徹底」「問題報告のフローの整備」「四半期に1回のアイデアソン開催」など、施策を決定します。その際、各施策の責任者を決め、実施状況を定期的にフォローアップする仕組みも併せて作ります。
このように、心的対比は個人の目標達成支援だけでなく、チーム全体のパフォーマンス向上にも活用できます。ただし、成功のカギは具体性にあります。理想の状態も、現実の課題も、そして行動計画も、できるだけ具体的に設定することで、実効性の高い改善活動につなげることができます。
心的対比の副作用と対策
心的対比は効果的な目標達成の手法ですが、いくつか注意すべき点があり、それぞれに対する対策が必要です。
まず、心的対比を頻繁に行いすぎることで、かえってストレスが高まる可能性があります。理想と現実のギャップを常に意識することは、時として精神的負担となります。特に、複数の目標に対して同時に心的対比を行うと、克服すべき課題が山積みになっているように感じられ、心理的な疲労を招くことがあります。
そこで、例えば、心的対比を行う目標を一度に1個に限定すると良いでしょう。また、定期的なリフレッシュタイムを設けて、意識的に目標から離れる時間を作ることも重要です。
心的対比によって明確になった課題に対して、必要以上に意識が向きすぎてしまう場合もあります。例えば、プレゼンテーションの場面で、「聴衆を引きつける話し方ができていない」という課題を強く意識するあまり、かえって不自然な話し方になってしまうかもしれません。
この対策として、課題への意識を一時的に手放す練習が有効です。例えば、本番の直前には課題について考えるのをいったん止め、その時々の状況に自然に対応することを心がけます。また、課題の改善に取り組む時間と、既存の強みを活かす時間とを意識的に分けることで、過度な意識集中を防ぐことができます。
心的対比を行う際のタイミングにも注意が必要です。例えば、重要な試験や商談の直前に心的対比を行うと、現実の課題が強く意識され、自信を失ってしまう可能性があります。このような場面では、むしろ自分の強みや過去の成功体験に焦点を当てる方が効果的かもしれません。
組織での活用においても注意点があります。上司が部下に心的対比を促す際、「理想の状態」を上司が一方的に設定してしまうと、部下の主体性や創造性が損なわれます。部下自身の考える理想像を十分に聴き、それを踏まえた上で組織としての期待値をすり合わせていく対話型のアプローチが必要です。
また、チーム全体で心的対比を行う場合、メンバー間で理想とする状態が異なることで、かえって対立が生まれる可能性もあります。個々のメンバーの理想像を共有し、その後でチームとしての共通目標を見出していくプロセスを設けましょう。
おわりに
本講演では、心的対比という目標達成の手法について、その仕組みや効果、実践方法を見てきました。望ましい未来と現実の状況を比較するという、一見シンプルなこの方法は、私たちの行動を変える力を持っています。
心的対比の特徴は、目標を思い描くだけでなく、現実の課題にも目を向けることで、実践的な行動計画を導き出す点にあります。また、社会的な責任や時間的な制約がある場面では自然と心的対比が行われやすい一方で、日常的な目標達成の場面では意識的に心的対比を活用する必要があることも分かりました。
さらに、個人の目標達成だけでなく、部下の育成やチームの生産性向上といった組織的な課題においても、心的対比は効果的なツールとなり得ます。1on1ミーティングやチームディスカッションの場で心的対比を活用することで、具体的で実効性の高い行動計画を立てることができます。
目標を達成するためには、願うだけでなく行動することが不可欠です。心的対比は、その願いを具体的な行動に変換するための方法と言えるでしょう。本講演で紹介した知見が、皆様の目標達成の一助となると嬉しいです。
Q&A
Q:目標が達成できない状況が続くと自己肯定感が下がってしまいます。心的対比を行う際に、モチベーションを保ちながら目標達成を目指すコツはありますか。
心的対比の特徴として、現実の課題に目を向けることがありますが、それだけでは疲れてしまう可能性があります。そこで、これまでの成功体験や自分の強みにも目を向けると良いかもしれません。例えば、自分の成長を振り返る時間を設けることで、小さな進歩を発見し、自己肯定感を維持しやすくなります。
また、理想となる目標をできるだけ細分化し、達成可能な単位に分解することで、着実に実行して前進しやすくなります。これらの方法を組み合わせることで、前向きに取り組むことができるでしょう。
Q:心的対比と自己効力感にはどのような関係性があるのでしょうか?
この関係性は、主に理想とする状態をどのように描くかによって変わってきます。心的対比は、理想とする状態を描き、それと現実を照らし合わせて行動に移るというプロセスです。
理想とする未来が達成可能なものであれば、現実と照らし合わせたときに「これは達成できそうだ」と考えられ、自己効力感が高めります。一方で、あまりに遠すぎる、あるいは高すぎる目標を立ててしまうと、現実と照らし合わせた際に「無理だ」と感じてしまい、自己効力感が低下する可能性があります。
Q:心的対比を行う際に、理想と現実のギャップが大きすぎて逆にやる気が失せてしまうことがあります。このような場合にどのように対処すればいいでしょうか。
中間目標を設定することが効果的です。例えば、3ヶ月後、半年後、1年後というように時間軸で区切り、段階的な成長のイメージを描いていきます。それぞれの段階でどのような状態になっていればよいのかを考えることで、現在何をすべきかが明確になります。
1年後の目標をいきなり掲げるのではなく、現実的に成長できる段階的なプロセスを構築することで、精神的な負担を減らし、やる気を失うリスクを軽減することができます。
Q:チーム全体で心的対比を行う際に、メンバー間で理想の状態について認識が異なることがあります。このような意見の相違をどのように調整すればいいですか。
重要なのは、それぞれのメンバーが描く理想像を否定せず、丁寧に傾聴することです。その上で、一見異なっているように見える理想像の中から共通点を探し、それをチームとしての共通目標として定めていくと良いでしょう。
また、認識が異なることは必ずしも悪いことではありません。むしろ、様々な視点を持つメンバーがいることで、目標達成に向けて多様なアプローチを考えることができます。特に行動計画を立てる段階では、異なる視点を持つことが有利に働く可能性があります。
Q:部下との1on1で心的対比を活用する際、部下が現状の課題を認識したがらない場合があります。このような場合、どう対話を進めればいいでしょうか。
現状や課題を直視するのは誰にとっても困難な場合があります。そこで、ネガティブな側面からではなく、部下の強みや成功体験などポジティブな側面から対話を始めてみましょう。例えば、「その強みをさらに活かすためには、どんなチャレンジが必要だと思いますか」というように質問を投げかけることで、徐々に現実に目を向けやすくなります。
また、上司自身の失敗体験や課題に直面した経験を共有することで、部下の心理的な抵抗を和らげることができます。
Q:心的対比を実践する際、完璧主義思考の強いメンバーが理想と現実のギャップにストレスを感じてしまうことがあります。このようなメンバーの特性に配慮しながら心的対比を活用するためのアプローチはありますか。
完璧主義傾向の強いメンバーに対しては、目標設定を工夫する必要があります。理想を最終目標として捉えるのではなく、方向性として設定することで、プレッシャーを軽減できます。また、達成基準を段階的に設定することも効果的です。それぞれの段階で成功体験を積み重ねることで、自信を育て、目の前の課題に取り組む意欲を高めることができます。
さらに、上司や同僚から進捗や現在の成果について客観的な評価をもらうことで、過度に高い目標設定を調整することができます。このように、他者の支援を得ながら、完璧主義傾向の強い人の心理的負担を軽減し、心的対比がより機能しやすい環境を作ることが重要です。
脚注
[1] Cross, A., and Sheffield, D. (2019). Mental contrasting for health behavior change: A systematic review and meta-analysis of effects and moderator variables. Health Psychology Review, 13(2), 209-225.
[2] Johannessen, K. B., Oettingen, G., and Mayer, D. (2012). Mental contrasting of a dieting wish improves self-reported health behaviour. Psychology & Health, 27(2), 43-58.
[3] Oettingen, G., Mayer, D., Timur Sevincer, A., Stephens, E. J., Pak, H. J., and Hagenah, M. (2009). Mental contrasting and goal commitment: The mediating role of energization. Personality and Social Psychology Bulletin, 35(5), 608-622.
[4] Kappes, A., Wendt, M., Reinelt, T., and Oettingen, G. (2013). Mental contrasting changes the meaning of reality. Journal of Experimental Social Psychology, 49(5), 797-810.
[5] Sevincer, A. T., Musik, T., Degener, A., Greinert, A., and Oettingen, G. (2020). Taking responsibility for others and use of mental contrasting. Personality and Social Psychology Bulletin, 46(8), 1219-1233.
[6] Sevincer, A. T., Tessmann, P., and Oettingen, G. (2018). Demand to act and use of mental contrasting. European Journal of Psychological Assessment, 34(5), 305-312.
[7] Oettingen, G., Stephens, E. J., Mayer, D., and Brinkmann, B. (2010). Mental contrasting and the self-regulation of helping relations. Social Cognition, 28(4), 490-508.
[8] Oettingen, G., Marquardt, M. K., and Gollwitzer, P. M. (2012). Mental contrasting turns positive feedback on creative potential into successful performance. Journal of Experimental Social Psychology, 48(5), 990-996.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。